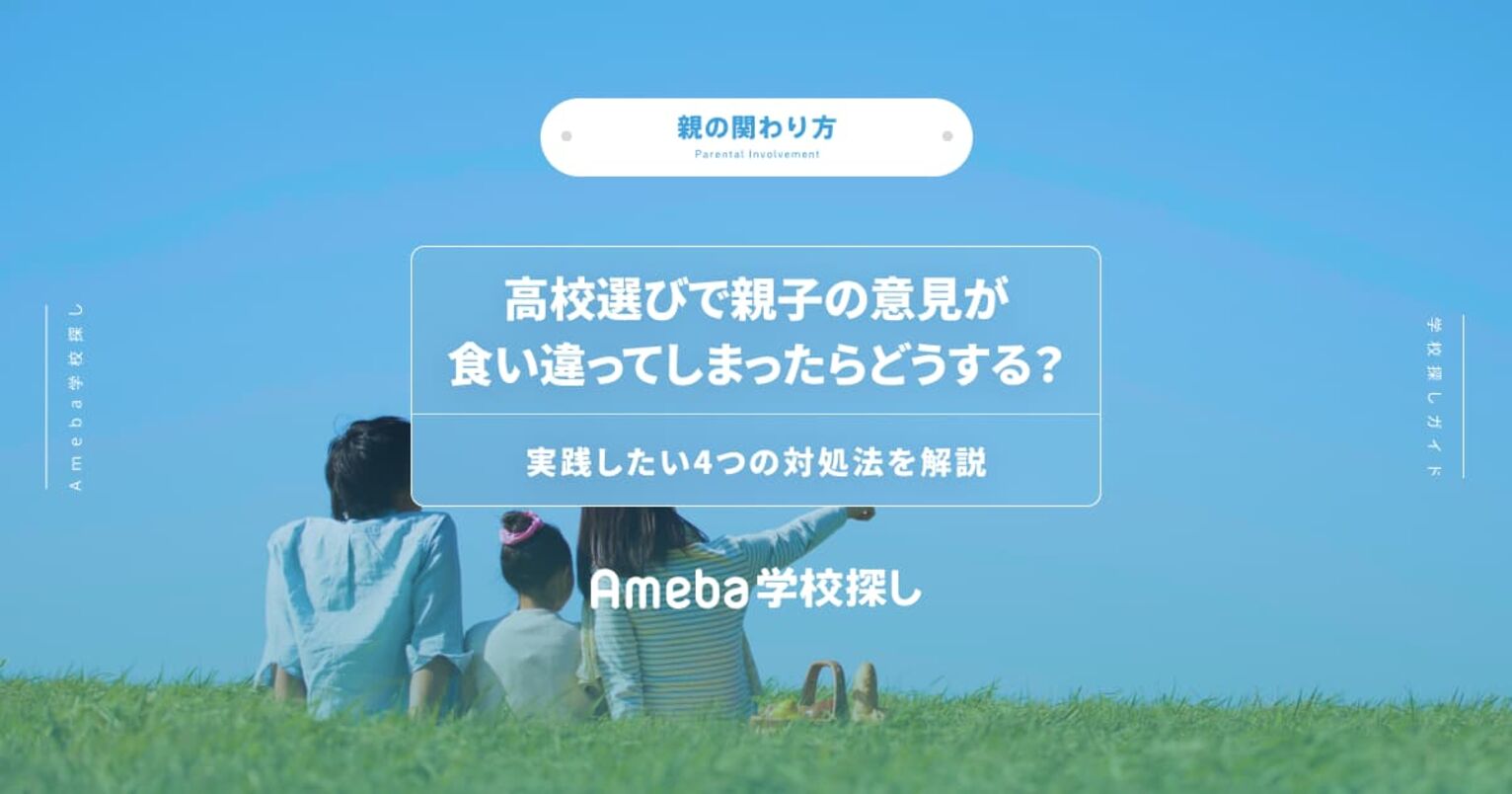高校選びは、これからの学びや人間関係、さらには将来の進路にもつながる重要なステップです。保護者としては「進学実績がよいか」「通学は安全か」など、さまざまな角度から慎重に検討してしまうものです。
一方で、お子さんは、「学校の雰囲気があいそう」「好きな部活動がある」といった、日々の生活の充実を重視することが多いようです。そのため、親子で意見がすれ違ってしまうことも少なくありません。
この記事では、親子で意見が食い違ったときに、前向きに話し合い、納得のいく高校選びをするための実際に役立つ4つの対処法を紹介します。
親子で高校選びの意見が割れてしまう原因を考える
高校を選ぶ場面では、親と子の考え方が一致しないことは珍しいことではありません。むしろ、ごく自然なことと言えるでしょう。
保護者としては、これまでの人生経験を踏まえて、なるべく将来に役立つ進路を選んでほしいという思いがあるものです。一方で、お子さん自身は、目の前の学校生活をどう過ごすかという視点を大切にする傾向があります。
意見を押し付けあうのではなく、それぞれの視点を比べてみると、お互いの考えがより見えやすくなります。
保護者が重視しやすいポイント
- 大学進学実績:希望の大学に進学できる学校か
- 通学の安全性:自宅から無理のない距離か
- 校風・雰囲気:ある程度の規律や落ち着きがあるか
- 費用面:家計への負担が現実的かどうか
お子さんが重視しやすいポイント
- 校風・雰囲気:自由で楽しそうか、制服に魅力を感じるか
- 部活動:好きな部活動があり楽しめそうか
- 友人関係:仲のよい友だちと一緒に通えるか
- 通いやすさ:自宅から近く通学が楽か
このように、親子それぞれの立場で見ているポイントが異なるため、意見が割れるのは当然ともいえます。大切なのは、その違いに気付き、お互いの考えを否定せずに受け止め合うことです。
高校選びで親子の意見が割れてしまったらどうする?4つの対処法

高校選びの場面では、保護者とお子さんが同じ方向を向くことができず、悩むことも多いものです。どちらが正しいというわけではなく、親子それぞれの思いがあるからこそ、ぶつかってしまうのです。
そんなときこそ、お互いの考えを尊重しながら冷静に向き合う工夫が必要です。ここでは、実践しやすい4つの対処法を紹介します。
- 話し合いの時間やルールを設ける
- お互いの考えを可視化・比較してみる
- その他の選択肢を探る
- 塾や学校など第三者に客観的な意見を求める
話し合いの時間やルールを設ける
親子の意見が食い違ったとき、大切なのは自分の主張を押し通すことではなく、納得のいく進路選びを一緒に考えることです。そのために、話し合いの「時間」や「ルール」を決めておくと、冷静に意見交換しやすくなります。
時間に区切りをつける
長時間ダラダラと話し続けると、お互いに疲れて建設的な意見交換ができなくなってしまいます。「まずは30分の間で、できるだけ話し合ってみよう」など、あらかじめ時間を区切っておくとよいでしょう。
話をさえぎらず最後まで聞く
お子さんが話している途中で口を挟むと、心を閉ざしてしまうことがあります。まずは傾聴し、「そう考えているんだね」と受け止める姿勢が信頼につながります。
人格を否定しない
「あなたはいつもこうだから」といった、過去の出来事やお子さんの人格そのものを否定する言葉は避けましょう。冷静に意見だけをやり取りすることが大切です。
一度で結論を出そうとしない
すぐに答えを出す必要はありません。意見がまとまらなければ、数日置いて改めて話すなど、クールダウン期間を設けるのも効果的です。
話し合いは説得の場ではなく、気持ちを分かち合う時間です。保護者の寄り添う姿勢が、お子さんの本音を引き出すきっかけになります。
お互いの考えを可視化・比較してみる
親子で高校選びについて意見がわかれるとき、その背景には「視点の違い」があります。感情のままに言い合ってしまうと、なかなか歩み寄れなくなってしまいます。
そこで役立つのが、考えを目に見える形に整理して共有することです。冷静に比較ができ、建設的な対話が進めやすくなります。
以下の3つのステップを参考に、親子で一緒に整理していきましょう。
①理由を書き出す
まずは、お子さん・保護者それぞれが「この高校をよいと思う理由」や「ここは避けたいと思う理由」を紙に書き出してみましょう。書くことで気持ちが整理され、お互いの考えが伝わりやすくなります。
②比較シートを活用する
次に、通学時間・校風・部活動・進学実績・学費といった具体的な項目を並べて表にまとめるのがおすすめです。視覚的に比較することで、好き嫌いだけでなく、条件の違いがひと目でわかります。
③優先順位を共有する
比較をしたうえで「何を一番大事にしたいか」を話し合ってみましょう。お子さんは「部活動を思い切りやりたい」、保護者は「進学実績や費用を重視したい」など、それぞれの優先順位が見えてきます。
こうして紙に書き出したり、シートで整理したりすることで、お子さんの思いもより具体的に伝わります。保護者としても受け止めやすくなり、前向きな対話につながっていきます。
その他の選択肢を探る
親子で希望が食い違ってしまったときは、無理にどちらかにあわせるのではなく、新しい可能性を一緒に探してみることも大切です。
意外な学校の候補が見つかり、お互いに気持ちが前向きになることもあります。以下のステップで、ほかの選択肢も探ってみましょう。
①希望条件を整理する
まずは、お子さん・保護者のそれぞれが大切にしたい条件を並べてみましょう。
たとえば「部活動に打ち込みたい」「通学が安心」「進学実績がよいこと」といった希望です。こうして整理するだけでも、お互いが大切にしている軸が見えてきます。
②第三、第四の候補校を探す
書き出した条件を見比べて、両方を満たす、または近い特徴を持つ学校を複数リストアップしてみます。「意外とこの学校なら両方の希望にマッチしそうだ」と気づくこともあります。
③新しい選択肢にも触れてみる
先入観を持たずに、これまで検討していなかった学校の説明会や文化祭に参加してみましょう。実際に足を運ぶと、雰囲気や生徒の様子から「ここなら安心して通えそう」と感じられる場合もあります。
新しい選択肢を探すプロセスは、親子で視野を広げるよいきっかけにもなります。お互いの希望を尊重しながら前向きに納得できる学校を見つけていきましょう。
塾や学校など第三者に客観的な意見を求める
親子だけでどれだけ話し合っても、なかなか結論が出ないことはよくあるものです。意見がすれ違ったままでは、お互いの思いが伝わらず、不満やモヤモヤが募ってしまうこともあるでしょう。
そんなときは、学校や塾の先生など、親でも子でもない立場の第三者に相談するという選択肢を考えてみてください。
たとえば、中学校の担任や進路指導の先生、塾の講師などに話してみるのもよいでしょう。進路に関する豊富な知識や、実際の進学データにもとづくアドバイスをしてくれます。
その際、「親子で意見がわかれてしまって」と正直に伝えることが大切です。それぞれの候補校について、第三者の冷静な視点で比較してもらうことで、新たな発見や選択肢が見えてくることもあります。
また、親子で一緒に相談に行くことで、同じ情報を共有し、話し合いのベースが揃います。外部の意見を取り入れることは、親子の対話を後押しし、より納得のいく進路選択につながります。
状況を悪化させてしまう親子のNG行動

高校選びについて話し合うなかで、保護者の「よかれと思って言ったこと」がお子さんの反発を招いてしまうことがあります。
反対に、お子さんの態度や言葉が、保護者を不安にさせてしまうこともあるでしょう。
ここでは、親子それぞれの立場で気を付けたい、状況を悪化させないために避けたいNG行動を具体的にご紹介します。
【親・保護者】のNG行動
高校選びにおいて、保護者としては「正しい道を選んでほしい」という思いからつい言い過ぎてしまうことも少なくありません。
しかし、その言動が結果的にお子さんの気持ちを遠ざけてしまうこともあります。ここでは、話し合いをスムーズに進めるために避けたいNG行動を3つ紹介します。
頭ごなしに否定する
「そんな高校はダメ」「考えが甘い」など、お子さんの希望を最初から否定してしまうと、心を閉ざしてしまう原因になります。まずは理由を聞き、「なるほどね」と一度受け止める姿勢が信頼関係につながります。
ほかの子と比較する
「〇〇ちゃんはもっと上の高校を目指しているのに」などとほかの子と比べることは、お子さんの自尊心を傷つけてしまいます。進路選びのモチベーションの低下にもつながりかねません。
兄弟姉妹や友人など、ほかの子と比較するのではなく、お子さん自身の気持ちやペースに向き合いましょう。
自分の世代の話を持ち出す
「自分の高校時代はこうだった」といった話は、今のお子さんには参考にならない場合が多く、反発されてしまうこともあります。過去の経験を押し付けるのではなく、今のお子さんの視点に立って話すことを意識しましょう。
保護者の言葉ひとつで、お子さんの気持ちは前向きになります。伝え方を工夫するだけで、前向きな話し合いにつながるでしょう。
【お子さん】のNG行動
高校選びの話し合いでは、お子さんの言動によってもすれ違いが生じることがあります。お子さん自身は強い思いを持っていても、伝え方や態度によっては正しく伝わらず、結果的に対立を深めてしまうこともあります。
ここでは、保護者が知っておきたい「お子さんが陥りやすい行動」とその背景を説明します。
話し合いを避ける・無視する
お子さんが「どうせわかってもらえない」と感じると、話し合いを避けたり、返事をしない態度をとることがあります。親からすると気持ちが見えず不安になり、「向き合ってくれない」と感じてしまうものです。
そんなときは感情的に責めるのではなく、「どうして話したくないの?」「何か不安なことがあるの?」と寄り添う姿勢を持ちましょう。お子さんと再び話すきっかけをつくりやすくなります。
理由を言わずに反発する
「この学校がいい」「ここは嫌だ」と結論だけを伝えてくる子も少なくありません。理由がわからないまま否定や主張を繰り返されると、親としても理解が難しく、説得や対話が進みにくくなります。
なぜそう感じるのかを丁寧に聞き出し、言葉にできるよう促してあげることが大切です。お子さんの理由を共有することで、お互いに冷静に話し合えるようになるでしょう。
このように、お子さんの態度には「伝えたい思いがあるのにうまく表現できない」という背景が隠れていることが多いものです。保護者がその点を理解し、受け止める姿勢を持つことで、前向きな進路選びにつなげられます。
悩んだら先輩親子の体験談も参考にしよう
お子さんの高校選びは、「これが絶対に正解」という答えはありません。だからこそ、親としても迷いや不安を抱えることは自然なことですし、すれ違いが起きるのも決して特別なことではありません。
そんなときに参考になるのが、すでに同じような経験をしてきた先輩親子の体験談です。実際に進路選びを乗り越えた家庭の声には、リアルな気づきや学びがたくさんあります。
身近なところでは、地域のママ友との会話やPTAでの情報交換が役立ちます。通学の雰囲気や学校生活の実際など、公式情報では得にくい声が聞けるからです。
さらに、ブログやSNSに投稿されたリアルな体験談から、新たな知識を得ることもできます。ただし、インターネット上の情報はあくまで個人の体験であり、すべての家庭に当てはまるわけではない点に注意が必要です。
先輩親子からの情報に触れることで、これまで見えなかった視点や思いがけない候補校に気づけることもあるでしょう。迷ったときには、そんな体験談を参考にしながら、納得できる判断につなげていきましょう。
親子で話し合い最適な高校選びを目指そう
お子さんの高校選びは、今後の学びや進路、そして社会に出た後の価値観にも関わってくる、大切な人生の分岐点です。
だからこそ、保護者としては「なるべくよい環境を選んであげたい」という強い思いがあるのは当然のことです。
一方で、お子さんも自分なりに「こんな高校生活を送りたい」という理想や夢を持っています。その思いがすれ違ったままだと、せっかくの進路選びが前向きに進めなくなってしまいます。
完璧な答えを見つけることよりも、「これなら一緒に頑張れる」と感じられる選択を積み重ねていきましょう。この記事でご紹介した対処法が、親子の大切な過程となり、お子さんにとって最適な高校を選びにつながることを願っています。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。