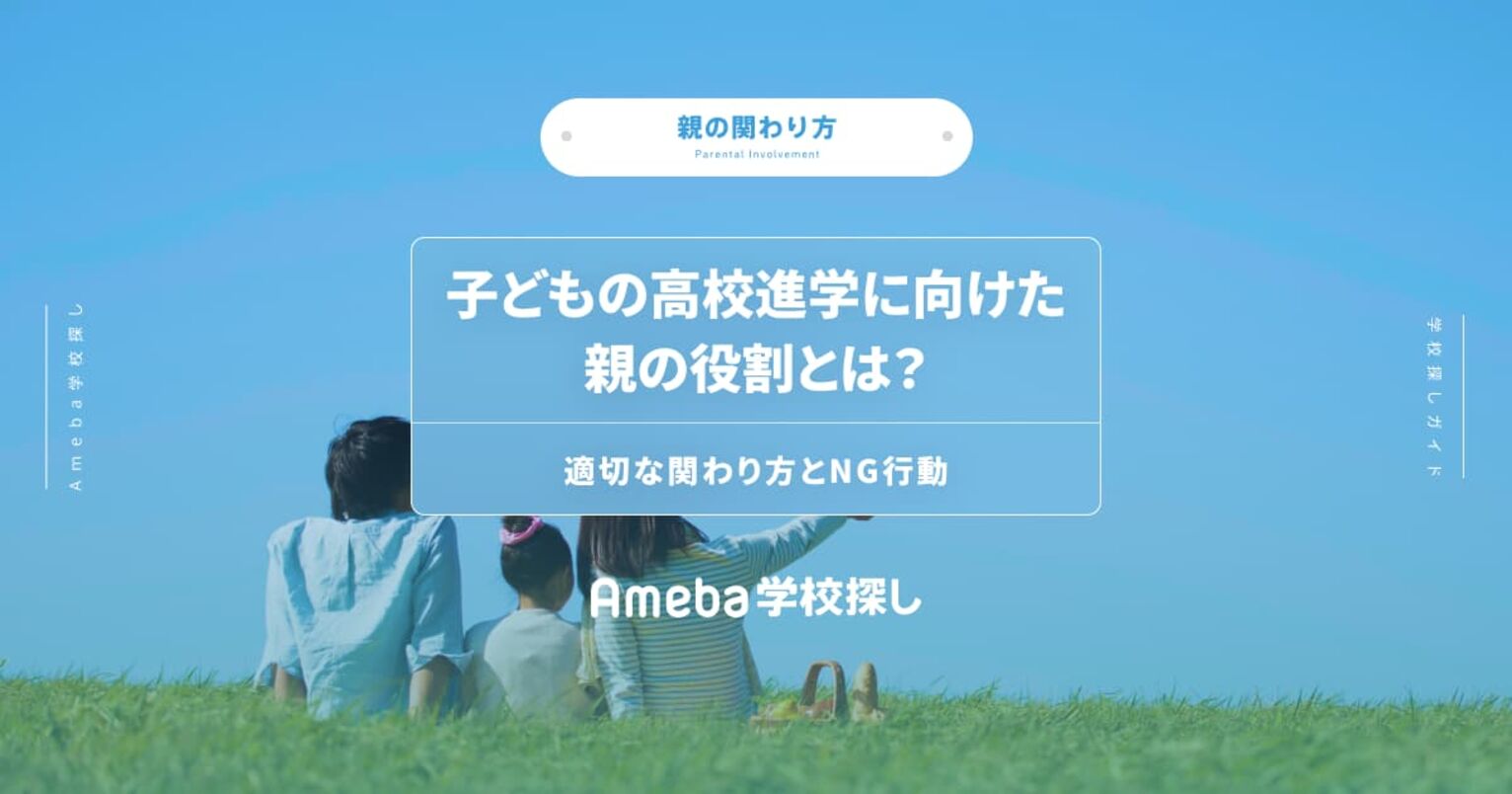中学生の子どもが高校進学を控える時期、親としてどのように関わればよいのか迷う方は少なくありません。思春期は自立心が芽生える一方で、将来への不安も抱えやすい時期です。親が干渉しすぎると反発を招き、放任しすぎると孤独を感じさせる恐れがあります。
大切なのは、子どもの意志を尊重しつつ、必要なサポートを適切な距離感で行うことです。
この記事では、高校進学や高校受験に向けて親が果たすべき役割を整理し、避けたいNG行動や伴走者として支えるコツを解説します。子どもが安心して進路を選び、自信を持って挑戦できるよう、本記事で一緒に確認していきましょう。
子どもの高校進学・高校受験において親が担うべき役割とは

高校進学に向けた親のサポートは、子どもにとって大きな支えになります。ただし、中学受験のように大きく介入する必要はなく、高校受験では子ども自身が主体的に考え、行動する力が求められます。
親は「管理者」ではなく「伴走者」として、子どもの意志を尊重しながら支えることが大切です。
親が担うべき役割
- 高校受験の仕組みを理解して共有する
- 進学先の条件を話し合う
- 学習環境を整える
- 子どもにあった学習方法を選ぶ
- 生活習慣・食習慣を整える
これらの取り組みによって、子どもは安心して受験に臨み、自信を持って挑戦する力を育むことができます。
次より、各サポートをどのように実践していくかを具体的に解説していきます。
高校受験の仕組みを理解して共有する
親がまずおこなうべきサポートは、高校受験の仕組みを正しく理解し、子どもと共有することです。制度を把握していないと、出願条件の見落としや準備不足といったリスクにつながります。
公立と私立では特徴が大きく異なるため、違いを整理しておくと安心です。
- 【学費】比較的安い
- 【カリキュラム】標準的
- 【施設】地域差あり
- 【入試日程】都道府県で統一
- 【学費】高め(※)
- 【カリキュラム】独自カリキュラム
- 【施設】充実している学校が多い
- 【入試日程】学校ごとに異なる
※奨学金制度を利用できる可能性あり
これらの違いを親子で確認し、それぞれのメリットとデメリットを理解することが第一歩です。
さらに、高校受験には一般入試のほか、推薦入試や特色選抜など多様な制度があります。推薦を希望する場合は、内申点や活動実績といった条件を早めに把握しておきましょう。
親子で整理しておくべきポイント
- 公立と私立の違いを理解し、メリット・デメリットを共有する
- 入試制度の内容や条件を確認し、必要な準備を早めにおこなう
- 内申点の重要性を伝え、授業態度や提出物も意識させる
- 受験スケジュールをカレンダーで可視化し、見通しを立てる
これらを意識して情報を共有すれば、子どもは安心して計画的に準備を進められます。親が情報整理の役割を担うことで、受験への不安も大きく軽減されるでしょう。
進学先の条件を話し合う
進学先を決める際は、偏差値だけに頼らず多角的な視点で学校を評価することが重要です。親は学校の特色や環境を理解し、子どもの希望と現実的な条件を照らし合わせながら一緒に検討しましょう。
学校選びで確認したいポイント
- 偏差値以外の判断軸を持つ
偏差値はあくまで目安です。校風や教育方針、カリキュラムの特色も考慮し、子どもにあった学校を選びましょう。 - 子どもの「好き」や「やりたい」を引き出す
「どんな高校生活を送りたいか」「どんな部活動に挑戦したいか」など、子どもの希望を聞き出して進路選びに反映させます。 - リアルな学校の雰囲気を確認する
オープンスクールや文化祭、学校説明会に親子で参加し、生徒や先生の雰囲気を肌で感じることが大切です。インターネットの情報だけではわからない要素を知ることができます。 - 通学時間や費用について具体的に話す
毎日の通学が負担にならないか、3年間でかかる費用を含めて現実的に計画しましょう。家計の状況も共有することで、納得感のある判断ができます。 - 卒業後の進路についても調べる
大学進学実績だけでなく、専門学校や就職など多様なキャリアを支援する体制が整っているかも確認しましょう。
親が情報を整理し、子どもと対話を重ねることで納得できる進学先を選びやすくなります。こうした話し合いは、受験への前向きな気持ちを高める力になります。
学習環境を整える
勉強の成果は環境によって大きく左右されます。どれだけ努力しても、集中できない雰囲気では力を発揮しづらいものです。親が少し工夫するだけで、子どもが安心して学習に取り組める空間を整えられます。
学習環境を整える際のポイント
- 集中できる場所を整える
部屋が狭くても問題ありません。大切なのは落ち着いて勉強できる場所を決めることです。漫画やゲームは視界から外し、気が散らない環境をつくります。 - スマホやタブレットのルールを決める
デジタル機器は便利ですが大きな誘惑のひとつです。「勉強中はリビングに置く」「夜は使用時間を制限する」といったルールを親子で決め、守れる環境を整えます。 - 家族全員で協力する
受験期は家庭全体のサポートも重要です。テレビの音を下げる、静かな時間を作るなど、小さな気遣いが子どもの集中力を支えます。 - 教材やプリントを整理する
必要な教材をすぐに取り出せる環境は効率を高めます。教科ごとにファイルを分けるなど整理整頓を手伝うことも、親の大切な役割です。
こうした工夫を積み重ねることで、子どもは自然と集中しやすくなり、学習効率も向上します。時には「今日は勉強しやすかった?」と声をかけ、環境が合っているか確認してあげるとさらに良いでしょう。
子どもにあった学習方法を選ぶ
受験勉強のやり方は一つではありません。塾に通う子もいれば、通信教材や自習で力をつける子もいます。親が押し付けるのではなく、子どもの性格や学習スタイルに合った方法を一緒に探すことが大切です。
子どもにあった学習方法を選ぶ際のポイント
- 複数の学習スタイルを比較する
集団塾、個別指導、家庭教師、オンライン教材など、さまざまな学習方法があります。メリット・デメリットを比較しながら、子どもに最もあう方法を見極めましょう。 - 子どもの性格を考慮する
競争環境でやる気が高まるタイプか、自分のペースで学びたいタイプかを見極め、その特性にあったスタイルを選びます。 - 体験授業で相性を確認する
気になる塾や教材は、必ず体験授業で相性を確認します。「わかりやすい」「楽しい」と感じられるかが継続できるかの大きなポイントです。 - 最終的な決定は子どもに任せる
親は情報提供とアドバイスに徹し、子どもが「自分で決めた」と感じられるようにすることが学習意欲を高めます。
子どもが「これなら頑張れる」と思える学習方法を見つければ、受験勉強は自然と前向きになります。親はそっと背中を押し、学習を支える伴走者であることを意識しましょう。
生活習慣・食習慣を整える
受験期は勉強時間ばかりに目が行きがちですが、実は生活リズムや食事内容も学力向上に欠かせない要素です。
夜更かしや朝食抜きは集中力を下げ、努力が成果につながりにくくなります。親が生活習慣と食習慣を整えるサポートをすることで、子どもは安定した体調を保ち、学習にも前向きに取り組めます。
生活習慣を整えるポイント
- 朝型の生活リズムを定着させる
入試本番にあわせ、毎日同じ時間に起きる・寝る習慣をつけると脳が活発に働きやすくなります。休日もリズムを崩さないよう見守りましょう。 - 適度な運動と休憩を取り入れる
長時間の勉強は疲れが溜まりやすいものです。軽い運動やストレッチを挟むと集中力が回復し、効率も上がります。気分転換に家族との会話も効果的です。 - 睡眠の質を高める
夜更かしや寝る前のスマホ使用は避け、深い眠りを確保しましょう。十分な睡眠は翌日の学習パフォーマンスの向上に大きく左右します。
とくに朝食は必ず摂るようにしましょう。短時間で食べられるおにぎりやスープ、ヨーグルトを用意すれば、午前中から集中して学習に臨めます。
栄養バランスと規則正しい生活が整えば、子どもは安心して力を発揮できるでしょう。親のちょっとした工夫が、受験期の大きな支えになります。
親のNG言動│「勉強しなさい」と言いたくなったら

受験期になると、親として「勉強しなさい」「遊んでばかりで大丈夫なの?」と声をかけたくなる場面が増えます。しかし、このような小言や命令は、一見正しいサポートに思えても逆効果です。子どもは「やらされている」と感じ、やる気を失ったり反発心を抱いたりする原因になります。
大切なのは、命令や干渉ではなく、子どもが自分から学ぼうと思える環境と声かけです。そのためには、避けるべき行動を理解し、接し方を意識する必要があります。
親がとくに注意すべきNG行動
- ほかの子や兄弟姉妹と比較する
- 勉強内容や進路に過度に口を出す
- 放任しすぎる・無関心になる
これらの行動は、子どもの自己肯定感や主体性を損なう大きな要因となります。次よりそれぞれの問題点と改善方法を詳しく見てきましょう。
ほかの子や兄弟姉妹と比較する
受験期に親がついやってしまうのが、「〇〇さんはもっと勉強している」「お兄ちゃんはあの高校に受かったのに」といった比較です。こうした言葉は一見励ましのようで、実は子どもの自己肯定感を大きく下げる原因になります。
比較され続けると、子どもは「自分は親に認められていない」「努力しても意味がない」と感じ、やる気を失ってしまいます。さらに、他人の評価ばかりを気にするようになり、主体的に行動する力が育ちにくくなります。
親が意識すべきは、他人との比較ではなく子ども自身の成長を認めることです。昨日より少し進歩した、課題に取り組んだ、といった小さな努力を評価する声かけが自信につながります。
言い換え例:努力を認める声かけ
- 「あなたはあなたのペースで頑張っているね」
- 「昨日より少し進んだね、いい調子だよ」
親が日々の頑張りを認めることで、子どもは安心感を持ち、自ら学び続ける力を伸ばしていけます。
勉強内容や進路に過度に口を出す
親が子どもの勉強や進路について強く口を出しすぎると、サポートのつもりがかえって逆効果になることがあります。必要なのは、助言と過干渉の境界を明確に理解し、子どもの主体性を尊重することです。
過干渉は、子どもに「親に支配されている」と感じさせ、モチベーションを低下させます。一方で、適度なアドバイスは、情報を整理し判断材料を与えることで子どもの自立心を伸ばします。
アドバイスと過干渉の違いを意識すれば、親のサポートは子どもの自信を育てる力に変わります。「信じて任せているよ」という姿勢を示すことで、子どもは安心して挑戦し、親子の信頼関係も深まります。
「勉強しなさい」と命令する
受験期になると、親はつい「勉強しなさい」と強い口調で言ってしまいがちです。しかし、この命令は子どもに「支配されている」という感覚を与え、反発心やストレスを引き起こします。
勉強が「やらされるもの」になってしまうと、やる気が削がれ、学習そのものを嫌いになる恐れがあります。
命令ばかりでは親子の会話も減り、信頼関係が崩れることさえあります。親が望む成果どころか、逆に距離が広がる原因になりかねません。
命令する代わりに、子どもの気持ちを尊重する問いかけを使いましょう。たとえば以下のような声かけが効果的です。
言い換え例:寄り添う声かけに変える
- 「調子はどう?」
- 「昨日より集中できているね」
- 「頑張っているのが伝わるよ」
このような寄り添う言葉は、子どもに安心感を与え、自分の意思で勉強に向かう意欲を引き出します。親がサポートしてくれていると感じれば、学習への姿勢も自然と前向きになります。
放任しすぎる・無関心な態度をとる
子どもの自主性を尊重するあまり、親が関わりを極端に減らしてしまうケースがあります。しかし、それが行き過ぎると「無関心」と受け取られ、子どもは孤独や不安を感じてしまいます。サポートと干渉のバランスが重要です。
「信じて任せる」という姿勢は、単に放っておくのではなく、「見守っているよ」という安心感を伝えることがポイントです。
たとえば「今日はどんな勉強をしたの?」「困ったことがあればいつでも相談してね」という声かけは、押し付けにならずにサポートの気持ちを示せます。親がそばで見守ってくれているとわかると、子どもは安心し、自ら努力する意欲を高めることができます。
親の役割は「管理者」ではなく「伴走者」である
高校受験は、子どもが自分自身の力で乗り越えていく大きな挑戦です。親が果たすべき役割は、結果を管理する立場ではなく、横で支え続ける伴走者になることです。
過干渉や命令は子どものやる気を削ぎますし、逆に無関心では安心感を失わせます。伴走者として大切なのは、子どもの意思を尊重しながら、必要なときにそっと手を差し伸べる姿勢です。
進路の話し合い、学習環境づくり、生活習慣のサポートといった取り組みは、親だからこそできるサポートです。さらに、声かけひとつでも子どもの気持ちは大きく変わります。「勉強しなさい」と命令するのではなく、「頑張っているね」「何か困ったことはある?」と寄り添う言葉が、安心感と自信を与えます。
親が信頼して見守ってくれていると感じれば、子どもは自らの力で前進し、受験という壁を乗り越える勇気を持てるでしょう。親は管理者ではなく、子どもの未来を共に支える伴走者であることを忘れないようにしましょう。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。