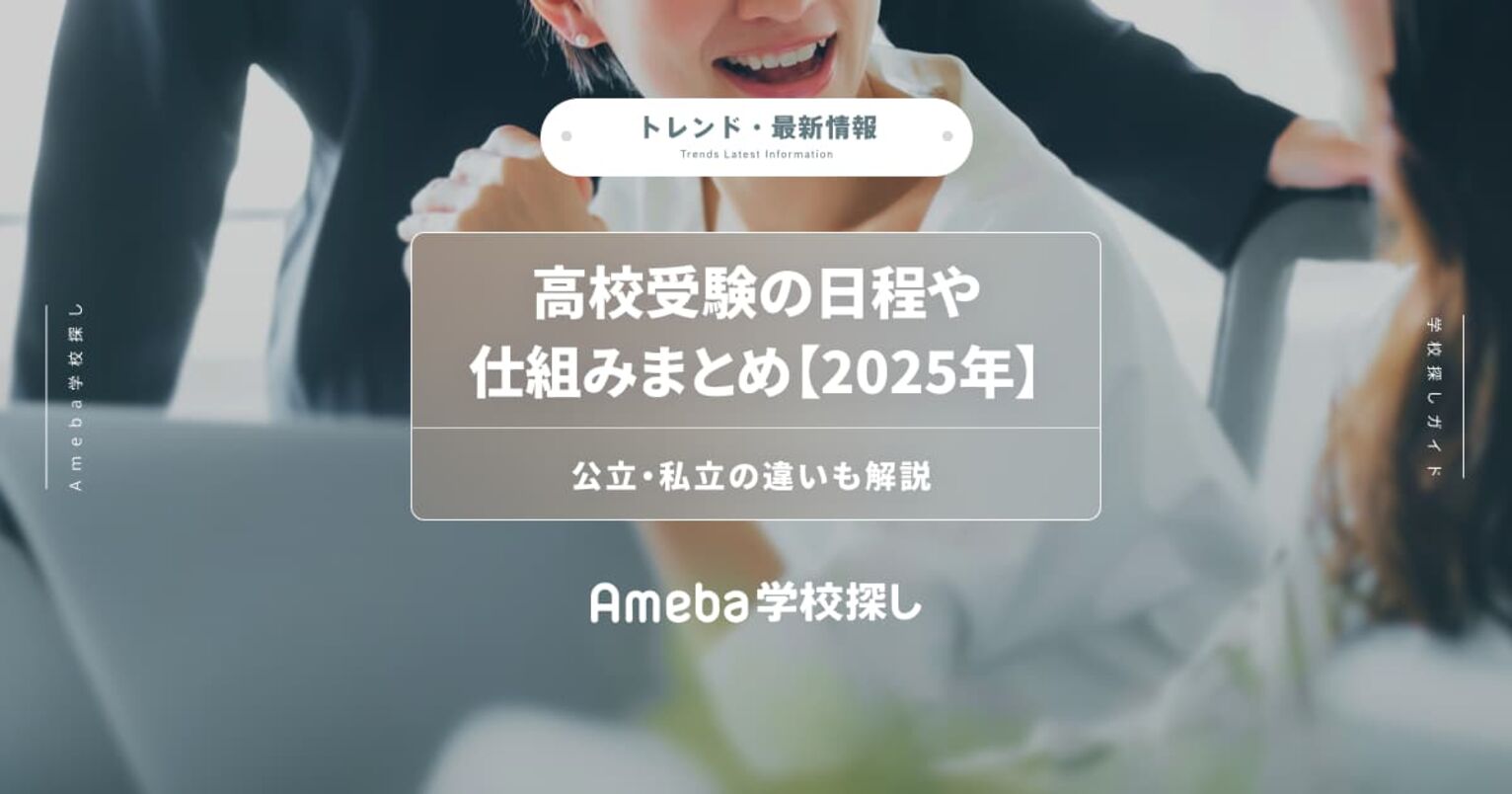高校受験は「公立」と「私立」で出願から発表までの流れや選抜方式が大きく異なります。
本記事では、2025年度入試(令和7年度)および2026年度入試(令和8年度)の最新情報を踏まえて、高校受験の日程や準備について詳しく解説します。
東京都・神奈川県・大阪府の具体例も交えながら、保護者の方にもわかりやすくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
※本記事の入試情報は2025年8月25日時点のものです。入試制度や日程は変更される可能性があるため、必ず各自治体・学校の公式サイトで最新情報をご確認ください。
- まずは公立・私立高校受験の全体像を把握しよう
- 公立高校の選抜の基本方針
- 私立は「学校ごと」、公立は「自治体で枠組み統一」
- 公立高校の受験の仕組み
- 推薦・特色等の選抜(学力検査以外を含む選抜)
- 一般選抜(学力検査)と志願変更
- 二次募集・追検査などの救済枠
- 私立高校の受験の仕組み
- 時期の目安と公式の窓口
- 受験方式の多様化(書類・面接・教科・実技・英語活用など)
- 入学手続きの期限と延納・返還の取扱いに注意
- 地域別・公立高校受験の日程【令和7・8年度公表分】
- 東京都(都立高校)
- 神奈川県(県立高校)
- 大阪府(府立高校)
- 高校受験準備の注意点
- 自治体ページで「最上位の告示」を確認する
- 私立は都道府県の取りまとめ&各校要項の二段構えで確認を
- 高校受験の用語解説
- 高校受験は各自治体・学校の公式サイトで最新情報を確認しよう
まずは公立・私立高校受験の全体像を把握しよう
高校受験制度は地域によって大きく異なるため、「うちの子の場合、どの選抜方法が向いているの?」「併願戦略をどう組み立てればいいの?」といった疑問を抱える保護者の方が少なくありません。
そこで、公立高校と私立高校の受験について、まずは全体像を理解することから始めましょう。
公立高校の選抜の基本方針
文部科学省の高等学校入学者選抜要項では、「多様な選抜方法を活用すること」が基本方針として示されており、これに基づき各都道府県が学力検査以外の評価方法や複数回の受験機会などを工夫して実施しています
つまり、お住まいの地域によって入試の仕組みが異なるということです。たとえば、学力検査と内申点の配分比率にも地域差があります。
東京都では学力検査と調査書の比重は7対3となっており、ほかの自治体では6対4や5対5といった配分を採用している場合もあります。
隣接する自治体でも大きく制度が異なるため、お住まいの地域の教育委員会公式サイトで最新の実施要項を確認し、志望校の所在地の制度も併せて調べることが重要です。
私立は「学校ごと」、公立は「自治体で枠組み統一」
高校受験で最初に理解しておきたいのは、私立高校と公立高校では「誰が入試制度を決めているか」がまったく違うという点です。
私立高校の場合、各学校が独自に決定します。試験日程、選抜方式、出願方法、合格発表、入学手続きの期限まで、すべて学校ごとに設定されています。
そのため、「A校は面接重視、B校は学力検査のみ、C校は実技試験あり」といったように、受験する学校ごとにまったく異なる準備が必要になります。
公立高校の場合、都道府県が大きな枠組みを決めて統一しています。「推薦選抜はいつ、一般選抜はいつ、二次募集はいつ」といった基本的な流れは県内で共通です。
もちろん学校ごとの特色はありますが、受験生や保護者にとってはわかりやすい仕組みになっています。
公立高校の受験の仕組み
公立高校の受験は、多くの都道府県で段階的に実施されています。一般的には「推薦・特色選抜→一般選抜→二次募集」という流れで進んでいきます。
推薦・特色等の選抜(学力検査以外を含む選抜)
推薦選抜は、「学力だけでは測れない生徒の資質や意欲を見る」選抜方法です。面接、作文、実技検査などを組み合わせて実施され、中学校長の推薦が必要となります。
東京都の場合では1月下旬に「推薦に基づく選抜」を実施します。各高校が面接、作文、実技などを組み合わせて選考し、具体的な日程は東京都教育委員会が毎年通知します。たとえば2026年度入試では、1月26日・27日に実施され、2月2日に合格発表がおこなわれる予定です。
推薦選抜を受けるためには、各高校が定める推薦基準(内申点や出席状況など)を満たし、中学校長の推薦を受ける必要があります。「推薦基準さえ満たせば合格」というわけではなく、人気の高校は一般選抜を上回る倍率になることもあります。
神奈川県の場合、「特色検査」として、学科の特色を活かした選抜を実施しています。これは一般的な推薦とは異なり、共通選抜とは別枠で設定される特別な選抜です。音楽科なら音楽の実技、国際科なら英語での面接といったように、学科の特性に応じた検査がおこなわれます。
大阪府の場合は「特別入学者選抜」として、2月中旬に実施されます。主に専門学科(音楽科、美術科、体育科など)が対象となり、それぞれの分野に特化した実技検査や面接が重視されます。
一般選抜(学力検査)と志願変更
一般選抜は、多くの受験生が利用する主要な選抜方法です。主に国語、数学、英語、理科、社会の5教科の学力検査を実施し、調査書(内申書)とあわせて合否を判定します。
東京都の場合、2月下旬に一般選抜(学力検査)を実施します。2025年度入試では2月21日に学力検査がおこなわれ、3月3日に合格発表がありました。学力検査と調査書の比重は7対3となっており、当日の試験結果が重要な要素となります。
東京都では推薦選抜と一般選抜の両方を受験することができるため、推薦で不合格になっても一般選抜で再チャレンジが可能です。また、一部の学校では分割募集を実施しており、前期・後期の2回に分けて募集をおこないます。
神奈川県の場合は、「共通選抜」として、学力検査、面接、必要に応じて特色検査を実施します。特徴的なのは、すべての受験生が面接を受けることです。2025年度入試では、学力検査が2月14日、面接・特色検査が2月17日〜19日に実施されました。
神奈川県では志願変更期間も設けられており、出願後に志望校を変更することも可能です。これにより、出願状況を見て最終的な志望校を決めることができます。
大阪府の場合、一般入学者選抜(全日制)を3月上旬に実施します。2025年度入試では3月12日に学力検査、3月21日に合格発表がおこなわれました。大阪府はほかの地域よりもやや遅い時期の実施となっています。
二次募集・追検査などの救済枠
公立高校では、一般選抜とは別に、特別な事情に対応するための制度が設けられています。
「二次募集」は、一般選抜の合格発表後に、定員に満たなかった学校でおこなわれる追加の募集です。人気の高い学校では定員が満たされるため二次募集は実施されず、比較的競争が少ない学校や定員割れした学校のみが対象となります。そのため、最初から二次募集を前提とした受験計画を立てるのは適切ではありません。
また「追検査」は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの病気、交通事故、家族の不幸など、やむを得ない事情で一般選抜を受験できなかった生徒のための代替試験です。
受験するためには医師の診断書や証明書類が必要で、事前または当日中に学校への連絡が求められるなど、厳格な条件が設けられています。
これらの制度の詳細な条件や手続き方法は、各都道府県の教育委員会の公式サイトで公表されていますので、必ず目を通しておきましょう。
たとえば神奈川県では、共通選抜の実施要項とは別に、追検査・二次募集に関する詳しい案内を公開しており、対象となる条件や必要な手続きがわかりやすく説明されています。
私立高校の受験の仕組み
私立高校の受験は、学校ごとに大きく異なる特色があります。公立高校のような統一的な制度ではなく、各学校の教育方針や校風を反映した独自の選抜がおこなわれているのが特徴です。
時期の目安と公式の窓口
私立高校の入試は、一般的に公立高校よりも早い時期に実施されます。これは、公立高校を第一志望とする受験生が併願校として私立高校を受験できるよう配慮されているためです。
都内の私立高校では、推薦入試が1月下旬、一般入試が2月上旬以降に設定されている学校が多くなっています。具体的には、推薦入試は1月22日以降、一般入試は2月10日以降に実施される学校がほとんどです。
東京都では「都内私立高校入学者選抜実施要項」として、都内すべての私立高校の基本的な入試情報を一覧にまとめて公開しています。この資料では、各校がどのような選抜方式を採用しているか、何人ぐらい募集しているかといった基本情報を効率的に比較検討できるでしょう。
ただし、この取りまとめ資料はあくまで「概要」です。具体的にどんな試験がおこなわれるのか、出願にはどんな書類が必要なのか、いつまでに手続きを完了すればよいのかといった詳細については、必ず志望校の募集要項を個別に確認してください。
このような都道府県の取りまとめ資料は、数多くある私立高校のなかから「子どもにあいそうな学校」を効率的に見つけ出すための第一歩として、保護者の方にとって非常に有用な情報源となります。
受験方式の多様化(書類・面接・教科・実技・英語活用など)
私立高校の魅力のひとつは、各学校の特色を活かした多様な受験方式が用意されていることです。従来の学力検査だけでなく、さまざまな能力や個性を評価する選抜がおこなわれています。
- 書類選考重視型:調査書や活動報告書などの書類を中心とした選考
- 面接重視型:個人面接やグループディスカッションを通じた人物評価
- 学力検査型:従来の3教科(英語・数学・国語)または5教科の筆記試験
- 実技検査型:音楽、美術、体育などの実技を重視した選考
- 英語4技能型:英検などの外部検定や英語面接を活用した選考
- 探究型:課題研究やプレゼンテーションを通じた思考力・表現力の評価
たとえば、国際教育に力を入れている学校では英語での面接やプレゼンテーションを実施し、芸術系の学校では実技検査を中心とした選抜をおこないます。
また、最近では思考力や課題解決能力を重視する学校も増えており、グループワークや課題レポートの提出を求めるケースも見られます。
このような多様な選抜方式は、文部科学省が推進する「多様な選抜方法の活用」という方針とも合致しており、お子さんの得意分野や特性を活かせる学校選択の幅が広がっています。
入学手続きの期限と延納・返還の取扱いに注意
私立高校の受験においてもっとも重要なのが、手続き期限の確認です。私立高校では合格発表日から数日以内、場合によっては翌日までに手続きを完了する必要がある学校もあります。
また、公立高校の合格発表まで入学金の納入を待ってくれる「延納制度」があるかどうかも事前に確認しておきましょう。この制度がない学校では、公立高校の結果を待たずに入学金を納めなければなりません。
さらに、入学を辞退した場合の入学金や授業料の返還についても学校によって規定が異なります。一度納めた入学金は返還されない学校が多い一方で、授業料については返還される場合があります。手続き方法についても、窓口への持参が必要な学校、郵送で済む学校、オンラインで完結する学校などさまざまです。
東京都の場合、多くの私立高校で「延納制度」を設けており、公立高校の合格発表まで入学金の納入を待ってくれます。しかし、制度の有無や具体的な条件は学校によって大きく異なるため、志望校を決める際には必ずこの点も確認しておくことが重要です。
とくに、複数の私立高校を受験する場合や、公立高校との併願を考えている場合は、それぞれの学校の手続き期限を一覧表にまとめるなど、スケジュール管理を徹底することが大切です。
「気がついたら手続き期限が過ぎていた」ということがないよう、カレンダーに記入しておくことをおすすめします。
地域別・公立高校受験の日程【令和7・8年度公表分】
公立高校の入試日程は、年度によって変更される可能性があります。また、学科や選抜方式によっても日程が異なる場合があるため、必ず各自治体の教育委員会公式サイトで最新の情報を確認してください。
ここでは主要な自治体の日程例をご紹介します。
東京都(都立高校)
東京都では推薦選抜と一般選抜の2回の受験機会があります。2026年度(令和8年度)入試の予定日程は以下の通りです。
- 推薦に基づく選抜
出願期間:2026年1月9日(金)〜16日(金)
検査実施日:2026年1月26日(日)・27日(月)
合格発表:2026年2月2日(日) - 一般選抜(学力検査)
出願期間:2026年1月30日(金)〜2月5日(木)
志願変更期間:2月12日(水)・13日(木)
学力検査:2月21日(金)
合格発表:3月2日(月)
東京都の特徴は、推薦で不合格になっても一般選抜を受験できることです。また、一部の学校では分割募集(前期・後期に分けた募集)を実施しており、より多くの受験機会が提供されています。
神奈川県(県立高校)
神奈川県では「共通選抜」として統一的な制度を採用しています。すべての受験生が面接を受けることが特徴です。
- 共通選抜
出願期間:2026年1月23日(金)〜1月29日(木)
学力検査:2026年2月17日(火)
面接・特色検査:2026年2月17日(火)・18日(水)・19日(木)
合格発表:2026年2月27日(金) - 二次募集
出願期間:2026年3月3日(火)・4日(水)
学力検査等:2026年3月10日(火)
合格発表:2026年3月19日(木)
神奈川県では志願変更期間が設けられており、出願後にほかの県立高校に変更することも可能です。これにより、出願状況を見て最終的な判断ができるという特徴があります。
大阪府(府立高校)
大阪府では複数の選抜機会を設けており、ほかの地域よりもやや遅い時期に実施されます。
- 特別入学者選抜
出願期間:2026年2月16日(月)〜17日(火)
学力検査:2026年2月19日(木)
実技試験または面接:2026年2月20日(金)・24日(火)のうち一日
合格発表:2026年3月2日(月) - 一般入学者選抜(全日制)
出願期間:2026年3月4日(水)〜6日(金)
学力検査:2026年3月11日(水)
合格発表:2026年3月19日(木) - 二次入学者選抜
出願期間:2026年3月24日(月)
面接:2026年3月25日(火)
合格発表:2026年3月26日(木)
大阪府の特別入学者選抜は、主に専門学科や総合学科が対象となり、学科の特色を活かした選抜がおこなわれます。一般入学者選抜では、府内統一の学力検査が実施されます。
※特別入学者選抜について、音楽科は別日程で、出願が2026年2月3日(火)〜2月4日(水)、視唱・専攻実技が2026年2月14日(土)、学力検査・聴音が2026年2月19日(木)におこなわれます。
高校受験準備の注意点
高校受験を成功させるためには、正確な情報収集と計画的な準備が欠かせません。とくに近年は制度変更が頻繁におこなわれているため、常に最新の情報をチェックする必要があります。
自治体ページで「最上位の告示」を確認する
公立高校の受験情報は、必ず都道府県教育委員会の公式サイトで確認することが鉄則です。塾や予備校、受験情報サイトの情報も参考になりますが、制度変更や日程変更は公式サイトで最初に発表されるため、「一次情報」を確認する習慣をつけましょう。
東京都、神奈川県、大阪府などでは、受験に関する情報を体系的に整理して公開しています。これらの自治体の公開形式は、ほかの地域の情報を調べる際の参考にもなります。
また、最近はオンライン出願を導入している自治体も増えているため、出願方法についても事前に確認しておくことが重要です。
とくに重要なのは、「実施要項」と呼ばれる正式な文書です。この文書には、選抜方法、配点、出願資格、実施日程などが詳細に記載されており、受験準備の基本となる情報が含まれています。
私立は都道府県の取りまとめ&各校要項の二段構えで確認を
私立高校の情報収集は、「都道府県の取りまとめ資料」と「各学校の募集要項」の両方を確認する「二段構え」のアプローチが効果的です。
まずは、都道府県の取りまとめ資料を確認。多くの都道府県では、域内の私立高校の入試情報を取りまとめた資料を公開しています。
たとえば東京都の「都内私立高校入学者選抜実施要項」では、各校の選抜方式、募集人数、試験日程の概要を一覧で確認できます。
この段階では、志望校候補の絞り込みや、大まかなスケジュールの把握をおこないます。
次に、各学校の募集要項で詳細確認。体的な試験内容、出願に必要な書類、入学手続きの期限、延納制度の有無などは、必ず各学校の募集要項で確認する必要があります。
同じ学校でも学科やコースによって入試制度が異なる場合があるため、注意深く確認することが大切です。また、併願制度、特待生制度、延納制度などの詳細についても、学校ごとに大きく異なります。
高校受験の用語解説
高校受験の情報を調べていると、聞き慣れない専門用語がたくさん出てきて戸惑うことがあります。「推薦選抜って何?」「内申点ってどう計算するの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、高校受験でよく使われる重要な用語について、わかりやすく解説します。
- 推薦選抜(公立)
学力検査だけでは評価できない生徒の資質や意欲を重視する選抜方法です。面接、作文、実技検査などを組み合わせて実施されます。
中学校長の推薦が必要で、各高校が定める推薦基準(内申点や出席状況など)を満たしている必要があります。
一般選抜よりも早い時期(多くは1月下旬)に実施され、合格すれば入学が確定します。 - 一般選抜(学力検査)
主要5教科(国語、数学、英語、理科、社会)の筆記試験を中心とした選抜方法です。
もっとも多くの受験生が利用する制度で、当日の試験結果と調査書(内申書)を組み合わせて合否を判定します。実施時期は2月下旬から3月上旬が一般的です。 - 特色検査/特別入学者選抜
学科や学校の特色を反映した特別な検査です。音楽科での演奏実技、美術科での実技制作、国際科での英語面接、理数科での理科実験など、各学科の専門性に応じた検査がおこなわれます。
実施時期は2月中旬から下旬が中心となっています。 - 併願制度
複数の高校を同時に受験できる制度です。私立高校では「併願優遇」として、一定の基準(主に内申点)を満たした生徒に対して合格しやすくする制度を設けている学校があります。
公立高校が第一志望の生徒が私立高校を「すべり止め」として受験する際によく利用されます。 - 内申点(調査書点)
中学校での成績や活動実績を点数化したものです。定期試験の成績だけでなく、授業態度、提出物の状況、部活動での活躍、生徒会活動、ボランティア活動なども評価対象となります。
地域によって、中学1年生から3年生まですべての成績を対象とする場合と、3年生のみを対象とする場合があります。 - 志願変更
出願後に志望校を変更できる制度です。多くの公立高校で採用されており、出願状況や倍率を見て最終的な志望校を決めることができます。変更期間は限定されており、一度だけ変更が可能な場合が一般的です。 - 延納制度
私立高校の合格者が、公立高校の合格発表まで入学金の納入を待ってもらえる制度です。
公立高校を第一志望とする受験生にとって重要な制度で、多くの私立高校で採用されていますが、条件や期限は学校によって異なります。
高校受験は各自治体・学校の公式サイトで最新情報を確認しよう
高校受験を成功させるためには、正確で最新の情報に基づいた準備が不可欠です。
公立高校の情報は、各都道府県の教育委員会が、推薦選抜から一般選抜、二次募集に至るまでの流れと詳細な日程を毎年公示しています。志願変更の期間や追検査の実施条件も公式に明記されているため、必ず確認しておきましょう。
また、私立高校は学校ごとに選抜方式、日程、手続き方法が大きく異なります。東京都のように自治体が取りまとめ資料を公開している地域もありますが、詳細は各学校の募集要項で個別確認が必要です。
志望校がなぜその選抜方法を採用しているのか、どのような生徒を求めているのかを理解することが大切です。また、制度変更や特別措置については、公式サイトで最新情報をこまめにチェックしましょう。
高校受験は、お子さんが充実した高校生活を送るためのスタートラインです。公立と私立の違いを理解し、お住まいの地域の制度を正確に把握することから始めて、個性を活かせる学校選びを心がけてください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。