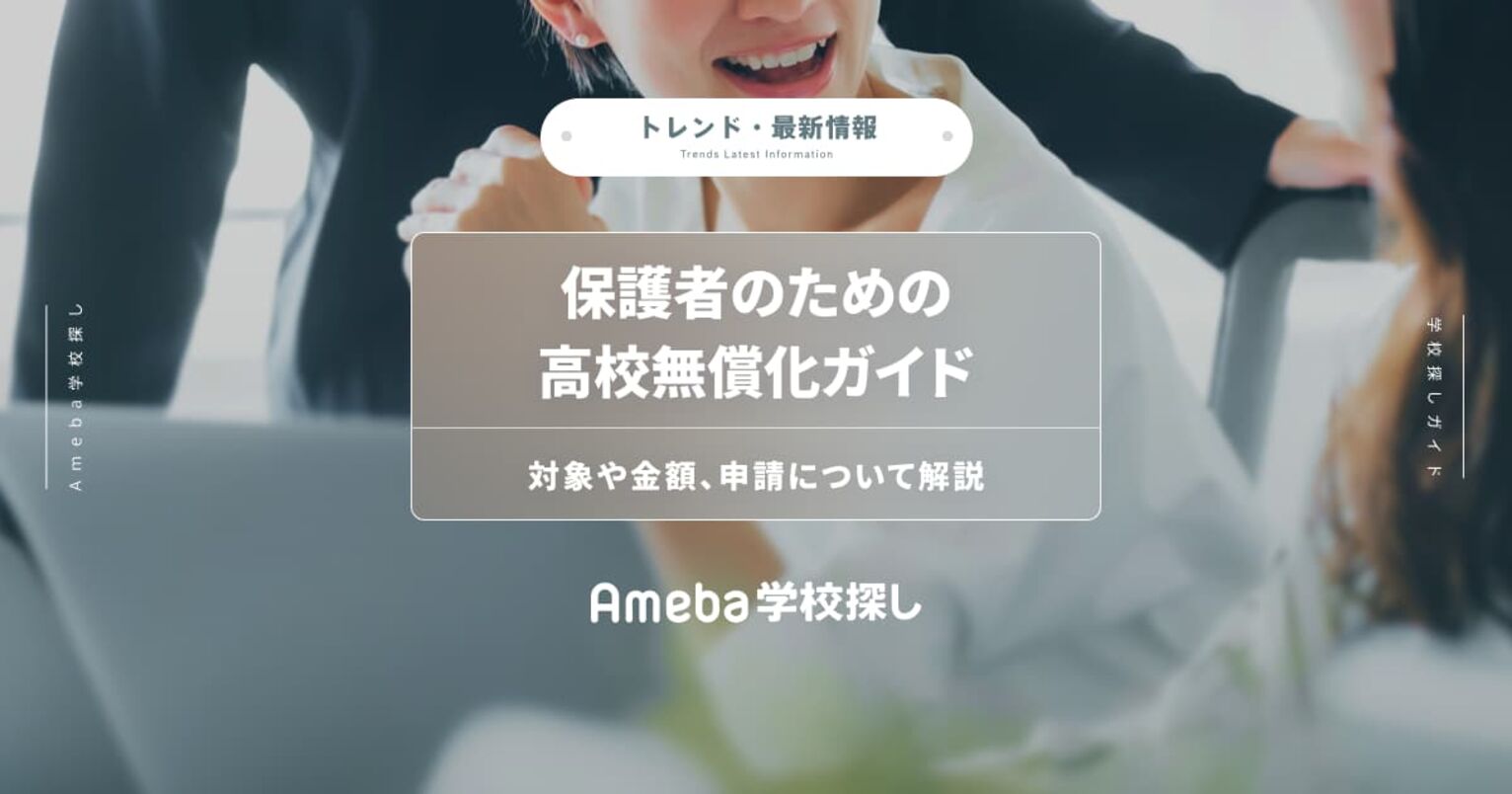2025年度より「高等学校等就学支援金」の所得制限の一部が撤廃され、さらに2025年度に限る移行措置である「高校生等臨時支援金」により、多くのの世帯で支援が受けられるようになりました。
2026年度以降も、支援の拡大が期待されています。ただし、「無償化」といっても支援対象は授業料のみで、入学金や教材費などは引き続き保護者負担となります。
本記事では、新制度の仕組みや支給額、申請方法から、各都道府県の上乗せ支援まで、保護者が知っておくべきポイントを最新情報に基づいて解説します。申請準備に役立つチェックリストも用意しましたので、ぜひ参考にしてください。
- 高校の無償化(就学支援金)とは?
- 制度の目的と対象となる学校
- 近年の制度変更と今後の動向
- いくら支給される?公立・私立・課程別に紹介
- 公立の基準額
- 私立の基準額と加算上限
- 2025年度は高校生等臨時支援金が実施されている
- 何が無償で、何が対象外?
- 「授業料のみ」が国の対象
- 授業料以外は「奨学給付金」を活用
- 申請の流れとスケジュール
- 年1回ではなく複数回判定
- e-Shienでオンライン申請できる
- 地域の「上乗せ支援」をチェックしよう
- 東京都の私立授業料は所得制限撤廃
- 各都道府県で支援制度が異なる
- ケース別Q&A
- 親権・同居状況が複雑なときは誰の所得で判定?
- 留年・転学・休学したら?
- 居住地と学校所在地が異なる場合
- 高校無償化によりすべての世帯で教育費負担の軽減が実現
高校の無償化(就学支援金)とは?
高校無償化とは、「高等学校等就学支援金制度」のことで、一定の条件を満たす家庭の高校生に対して、授業料相当額を国が支給する助成制度です。
この制度により、経済的な理由で高校進学を諦めることがないよう、教育機会の平等を図ることを目的としています。
制度の目的と対象となる学校
就学支援金は、高校などに通う生徒の授業料に充てるための国の給付で、返済は一切不要です。
対象となる学校は幅広く、国公私立の高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校1~3年、専修学校高等課程など、多様な教育機関が含まれています。
ただし、対象外となるケースもあります。既に高校等を卒業している場合や、標準修業年限(全日制3年、定時制・通信制4年)を超えて在学している場合は支給対象外となります。また、専攻科・別科の生徒や科目履修生、聴講生も対象外となるため注意が必要です。
この制度では、公立高校では授業料相当額が支給され実質無償となり、私立高校では授業料から一定額が差し引かれて家庭の負担が軽減されます。保護者の負担を軽減し、経済的な理由で進学が困難になることを減らし、教育機会を平等にすることが主な目的となっています。
近年の制度変更と今後の動向
2025年度から大きな変更が実施されました。公立高校の授業料については年収制限が撤廃され、すべての世帯で年額118,800円が支給されるようになり、実質完全無償化が実現しています。これまで年収約910万円以上の世帯は対象外でしたが、新たに「高校生等臨時支援金」として同額の支援が受けられるようになりました。
私立高校についても、2026年度からはさらなる無償化拡大が予定されています。世帯の収入に関係なく、私立高校などに対する授業料の無償化が全国的に進められる見込みで、現在の支給上限額39万6,000円から45万7,000円への引き上げと、所得制限の撤廃が検討されています(※)。これにより、多くの私立高校でも実質的な授業料無償化が実現する可能性が高くなっています。
※参照:文部科学省 高校無償化(令和7年度先行措置分)
いくら支給される?公立・私立・課程別に紹介
高校無償化の支給額は、学校の種類や課程によって異なります。2025年度からの制度変更により、公立高校はすべての世帯で実質無償化が実現し、私立高校についても段階的な支援拡充が進んでいます。ここでは、具体的な支給額を詳しく解説します。
公立の基準額
公立高校では、授業料相当額が支給され実質無償となります。全日制の場合は月額9,900円(年額118,800円)が基本額となっており、この金額は公立高校の標準的な授業料と同額に設定されています。
定時制の場合は月額2,700円、通信制では単位制を採用していることが多いため月額520円(1単位あたり)が支給されます。特別支援学校の高等部については月額400円が基準額となっています。
これらの金額は、それぞれの課程における標準的な授業料を基に設定されており、実質的に授業料負担がゼロになるよう調整されています。
2025年度からは、これまで年収約910万円以上の世帯では支給対象外でしたが、「高校生等臨時支援金」として新たに同額の支援が開始されました。これにより、所得制限が実質的に撤廃され、すべての世帯で公立高校の授業料は完全無償化が実現しています。
私立の基準額と加算上限
私立高校では、全課程で月額9,900円(年額118,800円)が基本額として支給されます。これに加えて、世帯の所得に応じて加算支給がおこなわれる仕組みとなっています。
世帯年収約590万円未満の家庭では、基本額に加えて上限年額396,000円(全日制の場合)まで加算支給されます。
つまり、基本額118,800円(年間)と加算額をあわせて、最大年額396,000円まで支援を受けることができます。多くの私立高校では、この金額で授業料がほぼカバーされ、実質無償化が実現しています。
ただし、学校の授業料がこの上限額を超える場合は、差額を保護者が負担する必要があります。私立高校の授業料は学校によって大きく異なるため、進学を検討する際は各学校の具体的な授業料を確認することが重要です。
2025年度は高校生等臨時支援金が実施されている
2025年度(令和7年度)は、制度拡充の移行期間として「高校生等臨時支援金」が新たに実施されています。これまで就学支援金の所得制限を超えていた世帯(年収約910万円以上)に対して、申請により授業料軽減が受けられる制度が整備されました。
この臨時支援金により、公立・私立を問わず年額118,800円が支給され、実質的に所得制限が撤廃されています。申請はオンライン申請システム「e-Shien」を通じておこなうことができ、学校からの案内に従って手続きを進めることになります。
さらに2026年度からは、私立高校の支援がさらに拡充される予定です。現在の上限額396,000円から457,000円(私立高校の全国平均授業料相当)への引き上げと、所得制限の完全撤廃が検討されており、より多くの家庭で私立高校の実質無償化が実現する見込みです。
何が無償で、何が対象外?
高校無償化といっても、すべての教育費が無料になるわけではありません。国の制度では「授業料のみ」が支援対象となっており、高校生活には授業料以外にもさまざまな費用がかかります。
ここでは、無償化の対象範囲と対象外の費用について詳しく解説します。
「授業料のみ」が国の対象
就学支援金制度による無償化の対象は、あくまでも授業料に限定されています。この制度では、国から都道府県や学校に支援金が支払われ、そのまま授業料に充てられる仕組みとなっています。
生徒や保護者が直接お金を受け取るわけではなく、授業料の負担が軽減される形で恩恵を受けることになります。授業料以外の教育費については、基本的に保護者の負担となります。
具体的には、入学金、教材費、制服代、交通費、学年費、修学旅行費、部活動費などは対象外です。これらの費用は学校や地域によって大きく異なりますが、とくに私立高校では授業料以外の諸費用が高額になる傾向があります。
文部科学省の令和5年度子供の学習費調査によると、公立高校でも年間約59万円、私立高校では年間約103万円の学習費がかかっており、このうち授業料が占める割合は一部に過ぎません。
したがって、高校無償化の恩恵を受けても、実際の教育費負担は相応にかかることを理解しておく必要があります。
授業料以外は「奨学給付金」を活用
授業料以外の教育費については、「高校生等奨学給付金」という別の制度で支援がおこなわれています。この制度は、主に住民税非課税世帯や生活保護受給世帯を対象に、教科書代、学用品費、通学用品費、修学旅行費などの費用を支援するものです。
奨学給付金は都道府県が実施主体となっており、支給額や要件は地域によって異なります。
文部科学省の基準では、生活保護受給世帯で年額3万2,300円程度、住民税非課税世帯では年額約15万2,000円程度が支給されますが、各都道府県で制度の詳細が異なるため、具体的な金額や条件は居住地の都道府県で確認する必要があります。
各都道府県の制度例として、首都圏から関西圏にかけての代表的な自治体をご紹介します。
- 東京都
「東京都私立高等学校等奨学給付金」として、生活保護世帯には年額52,600円、住民税非課税世帯には年額152,000円を支給。国公立高校と私立高校で異なる制度を設けています。 - 神奈川県
「神奈川県高校生等奨学給付金」により、県民税・市町村民税所得割額が非課税の世帯や生活保護受給世帯が対象となります。高等学校等専攻科に在学する生徒については年収約380万円未満まで対象を拡大しています。 - 千葉県
「千葉県私立高等学校等奨学のための給付金」により、生活保護世帯と住民税非課税世帯を対象に支援をおこなっています。申請は毎年度必要で、家計急変世帯への支援も実施しており、災害や失業などの外的要因による家計変化にも柔軟に対応しています。 - 大阪府
「大阪府私立高等学校等奨学のための給付金」として、生活保護受給世帯に年額5万2,600円、住民税非課税世帯には全日制・定時制で年額15万2,000円を支給しています。 - 兵庫県
「兵庫県国公立高校生等奨学給付金」として、住民税非課税世帯を対象に支援を実施しています。県内の公立高校に通う場合は学校経由、県外の国公立高校に通う場合は直接県への申請となります。
これらの給付金は返済不要の支援ですが、申請が必要であり、学校からの案内に従って手続きをおこなう必要があります。各都道府県によって申請時期や必要書類が異なるため、居住地の最新情報を必ず確認することが重要です。
申請の流れとスケジュール
高校無償化の支援を受けるためには、自動的に支給されるわけではなく、必ず申請手続きが必要です。申請のタイミングや方法を正しく理解して、期限内に手続きを完了させることが重要です。ここでは、申請の流れと具体的なスケジュールについて詳しく解説します。
年1回ではなく複数回判定
就学支援金の所得確認は、年1回ではなく複数回実施されます。新入生の場合は4月と7月の2回、在校生(2年生以上)の場合は7月の1回が基本的なスケジュールとなっています。
これは、保護者の所得状況に変化があった場合に適切な支給額を判定するためです。
4月の申請では、前年度の住民税情報を基に4月から6月分の支給額を決定します。その後、7月の申請では、最新の住民税情報(毎年6月ごろに確定)を基に7月以降の支給額を再判定する仕組みとなっています。
この仕組みにより、家計状況の変化に応じて適切な支援を受けることができます。
申請した月から支給が開始されるため、学校が定める期限を厳守することが極めて重要です。期限を過ぎてしまうと、本来受給できるはずの月分が支給されない可能性があります。
とくに新入生の4月申請は入学後すぐにおこなう必要があるため、入学前から必要書類の準備をしておくことをおすすめします。
e-Shienでオンライン申請できる
現在、就学支援金の申請は「e-Shien(イーシエン)」というオンライン申請システムを利用しておこなうことができます。このシステムは文部科学省が運営しており、24時間いつでもアクセス可能です(メンテナンス時を除く)。
従来の紙による申請も可能ですが、手続きの簡便性から多くの学校でオンライン申請が推奨されています。オンライン申請をおこなうには、学校から配布される「ログインID通知書」が必要です。このID通知書には専用のログインIDとパスワードが記載されており、これらを使ってe-Shienにアクセスします。
申請時にはマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された書類も必要となるため、事前に準備しておきましょう。e-Shienでは、申請の進行状況や審査結果をリアルタイムで確認することができます。
申請が完了すると「審査中」のステータスが表示され、審査が完了すると「認定」または「不認定」の結果が確認できるようになります。審査結果の詳細については、後日学校を通じて書面で正式な通知が届きます。文部科学省では、e-Shienの操作方法について詳細なマニュアルを提供しており、YouTubeの公式チャンネルでも動画解説を公開しています。
初めてオンライン申請をおこなう方は、これらの資料を参考にすることで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。提出先や締め切りは在学先の都道府県ごとに異なるため、学校配布の案内に従って正確に手続きをおこなってください。
地域の「上乗せ支援」をチェックしよう
国の就学支援金制度に加えて、各都道府県では独自の「上乗せ支援」を実施しています。これらの制度を併用することで、より大幅な授業料軽減を実現できる場合があります。
とくに私立高校の場合は、都道府県の制度によって実質無償化が実現するケースも多くなっています。
東京都の私立授業料は所得制限撤廃
東京都では2024年度(令和6年度)から、私立高校の授業料支援において所得制限を完全撤廃しました。これにより、保護者と生徒が都内に住所を有していれば、年収に関わらず私立高校の授業料負担を大幅に軽減することができるようになりました。
具体的には、国の就学支援金と都の「私立高等学校等授業料軽減助成金」をあわせて、都内私立高校の平均授業料相当額(年額最大490,000円)を上限として支援が受けられます。
多くの都内私立高校では、この金額でほぼ授業料が賄われるため、実質的な授業料無償化が実現しています。ただし、国の就学支援金と都の授業料軽減助成金は別々の制度のため、それぞれに申請が必要です。
申請時期は毎年6月20日ごろから7月31日までの期間で、オンラインでの申請が可能となっています。都の制度は、生徒が都外の私立高校に通学する場合や、進学のために都内から都外へ移住した場合でも対象となるため、幅広い世帯で活用できる制度となっています。
各都道府県で支援制度が異なる
都道府県ごとの支援制度は、対象要件や支給額が大きく異なります。一般的に、大都市圏では私立高校の授業料が高い傾向があるため、支援制度も充実している傾向があります。
一方で、地方では私立高校の授業料自体が比較的安価で、国の制度だけでも十分な支援効果が得られる場合が多くなっています。
代表的な例として、神奈川県では「私立高等学校等生徒学費補助金」があり、年収約750万円未満の世帯に対して国の制度に上乗せして支援をおこなっています。千葉県では「私立高等学校授業料減免事業補助」として、年収約590万円未満の世帯を対象に追加支援を実施しています。
これらの制度を活用するためには、保護者の居住地と生徒の在学先の両方で最新情報を確認することが重要です。
制度の詳細や申請方法は毎年更新される可能性があるため、各都道府県の教育委員会や私学担当部署のホームページで最新情報を確認し、学校からの案内にも注意を払うことをおすすめします。
ケース別Q&A
高校無償化の申請や支給に関して、保護者の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。複雑な家庭状況や特殊なケースについて、具体的な対応方法を解説します。
親権・同居状況が複雑なときは誰の所得で判定?
高校無償化の所得判定は、原則として生徒の親権者の所得でおこないます。両親がいる場合は2名の合算額が基準となり、共働き夫婦の場合も両親の所得を合計した金額で判定されます。
重要なのは、祖父母などの同居している家族がいても、親権者でなければその所得は算入されないということです。
保護者が離婚している場合は、実際に生徒を養育しているかどうかではなく、法的な親権者の所得を基準として判断されます。
たとえば、母親が親権者で生徒と同居しているが、実際の生活費は別居している父親が負担している場合でも、判定は親権者である母親の所得でおこなわれます。
親権者がいない場合の判定順序も明確に定められています。まず未成年後見人がいる場合はその方の所得、未成年後見人がいない場合は主たる生計維持者(原則として健康保険法の扶養者)、それもいない場合は生徒本人の所得で判定されます。
また、生徒が在学中に18歳に達して成年になった場合でも、それ以前に保護者であった方の収入により生計を維持している場合は、引き続き父母を生計維持者として取り扱います。
留年・転学・休学したら?
留年については、標準修業年限を超える在学期間は支給対象外となります。全日制高校では3年、定時制・通信制高校では4年が標準修業年限とされており、これを超えて在籍している場合は支援金の支給が停止されます。
単位制高校の場合は、74単位以上を履修済みの生徒は卒業要件を満たしているとみなされ、支給対象外となります。
転学の場合は、転学先でも継続して支給を受けることができますが、速やかな届け出が必要です。転学時に都道府県をまたぐ場合は、転学先の都道府県で新たに申請手続きをおこなう必要があります。また、保護者の転居により居住地が変わった場合も、変更届を提出することで支給が継続されます。
休学については、何も手続きをしなかった場合でも支援金の支給は継続されますが、支給期間(3年または4年)にカウントされてしまいます。
休学期間中に授業料が発生しない学校の場合は、支援金が実質的に無駄になってしまうため、学校に支給停止の申し出をおこなうことが推奨されます。復学時には再度申請することで支給を再開できます。
居住地と学校所在地が異なる場合
国の就学支援金制度は全国共通の制度のため、保護者の居住地と生徒の在学先が異なる都道府県でも、基本的な支給額に違いはありません。
しかし、申請実務や都道府県独自の上乗せ制度については、在学先の都道府県が所管することになります。
たとえば、東京都に住んでいる保護者の子どもが神奈川県の私立高校に通う場合、国の就学支援金は神奈川県を通じて申請しますが、東京都の「私立高等学校等授業料軽減助成金」については東京都に別途申請することができます。
このように、居住地と在学先それぞれの制度を併用できる場合があるため、両方の最新情報を確認することが重要です。
学校からの案内は在学先の都道府県の制度に基づいておこなわれるため、必ず学校の指示に従って手続きを進めてください。追加で利用できる制度がある場合は、各自治体の公式サイトで確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。
制度の詳細や申請方法は年度によって変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが大切です。
高校無償化によりすべての世帯で教育費負担の軽減が実現
高校無償化制度は、2025年度から大きく変わり、すべての世帯で教育費負担の軽減が実現されました。ここでは、制度の要点をまとめるとともに、申請に向けて確認すべきポイントをチェックリスト形式で整理します。
公立高校では年額118,800円、私立高校では最大年額396,000円が支給され、多くの場合で授業料の実質無償化が可能となっています。
ただし、支援対象は「授業料のみ」であることを理解しておくことが重要です。入学金、教材費、制服代、修学旅行費などは対象外となるため、これらの費用については別途準備が必要です。
授業料以外の教育費については「高校生等奨学給付金」があり、住民税非課税世帯を対象に支援が受けられます。
申請は入学後に学校を通じておこない、オンライン申請システム「e-Shien」を利用できます。各都道府県では独自の上乗せ支援も実施しているため、居住地の最新情報を確認することが重要です。
申請漏れや手続き遅れを防ぐため、以下のチェックリストを活用して準備を進めましょう。
- □学校からの申請案内を受け取り、締切日を把握した
→入学後すぐに学校から配布される申請案内をしっかりと確認し、提出期限を calendar に登録しておきましょう。 - □e-Shienのアカウント作成とマイナンバー書類を準備した
→オンライン申請に必要なログインIDは学校から配布されます。マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票などを準備してください。 - □課税標準額と調整控除を確認した(私立高校の場合)
→私立高校で支給額判定が必要な場合は、住民税課税標準額と調整控除額を住民税決定通知書などで確認しておきましょう。 - □居住地の上乗せ支援制度と奨学給付金の条件を確認した
→都道府県独自の支援制度について、居住地の教育委員会や私学担当部署のホームページで最新情報を確認してください。 - □変更事項(転学・保護者変更・家計急変)があれば速やかに届け出を準備した
→転学や保護者の変更、家計急変などがある場合は、速やかに学校に相談し、必要な手続きを確認しておきましょう。
高校無償化制度を適切に活用することで、家計の教育費負担を大幅に軽減し、お子さんの教育機会をよりよいものにしていきましょう。
※この記事は2025年9月時点の公表情報に基づいています。自治体の上乗せ制度や臨時支援の条件・申請期日は更新されるため、必ず在学先の案内と各自治体の最新ページをご確認ください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。