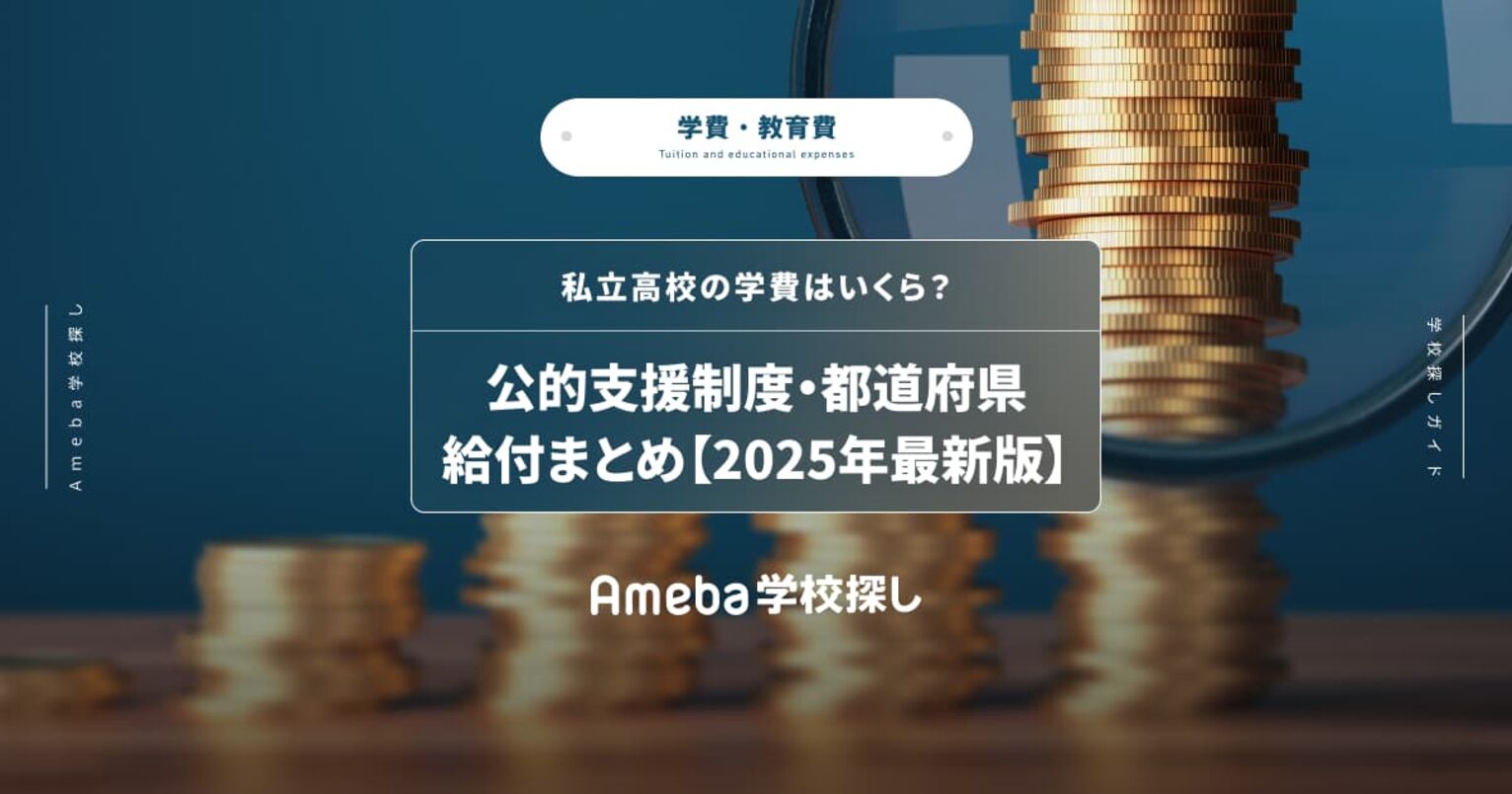お子さんの進学先に私立高校を検討すると、やはり気になるのが学費ではないでしょうか。「家計にとって大きな負担になりそう」と不安に思う方も少なくありません。
しかし、最近は国の制度や自治体の補助が充実してきており、費用の心配が少なくなる家庭も増えています。学費の目安や支援制度を知っておけば、安心して進学を考えることができるでしょう。
この記事では、私立高校にかかる費用の内訳、公立高校との違い、最新の支援制度の活用方法などをわかりやすくまとめました。お子さんの将来を見据えた学校選びの参考にしてください。
私立高校の学費はいくらかかる?【2025年最新データ】

「私立高校=学費が高い」と感じている・想像している方が多いのではないでしょうか。確かに、入学時や在学中に支払う費用は公立に比べると高くなる傾向があります。ただし、実際の金額には学校ごとに幅があり、負担額は一律ではありません。
入学金や授業料に加えて、施設費・教材費・PTA会費など、さまざまな費用がかかるのが私立高校の特徴です。さらに、寄付金など最初は見落としがちな費用もあります。
まずは、どのような項目があり、平均でどれくらいの金額がかかるのかを知っておきましょう。ここでは、私立高校の学費の内訳や、公立高校との違いについて詳しくご紹介します。
入学金・授業料・その他の費用の内訳
私立高校にかかる費用は、主に「入学時に必要な費用」と「在学中に毎年かかる費用」にわかれます。文部科学省の令和6年度(2024年度)の調査によると、私立高校(全日制)に通う場合、以下のような平均的な負担が見込まれます。
- 授業料:約45万7,300円
- 入学金:約16万5,900円
- 施設整備費等:約15万7,200円
- 合計(初年度):約78万円
まず、授業料は年間約45万7,300円かかり、まとまった出費となります。
続いて、入学時のみ必要な「入学金」は約16万5,900円で、多くの家庭が負担を実感しやすい金額です。さらに、施設整備費なども年間約15万7,200円かかり、授業料以外の大きな出費になります。
主な項目だけでも、私立高校に入学して最初の1年で支払う費用は平均で約78万円になります。また、PTA会費や寄付金(任意)、教材費などを含めると、実際はさらに出費が上乗せされる場合もあります。合計金額を考えると、私立高校に入学初年度に見込まれる総額は 70万円〜100万円程度を想定しておくと安心です。
※出典:文部科学省「令和6年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について」
公立高校との費用比較
「私立は公立の2倍ほどお金がかかる」と耳にされた方もいるのではないでしょうか。では、実際のところ私立と公立ではどのくらいの差があるのか見ていきましょう。
文部科学省が実施した「令和5年度 子供の学習費調査」によると、高校生1人あたりにかかる年間学習費の平均額は以下の通りです。
- 公立高校(全日制):約52万円
授業料は11万8,800円と比較的低め。教材費や行事費も抑えられる傾向 - 私立高校(全日制):約105万円
授業料は45万円前後で公立より高め。施設費や寄付金、修学旅行などの負担あり
※出典:文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」
このデータから見ても、公立と私立では年間の費用に大きな差があることがわかります。
とくに授業料の金額差が大きく、それに学校独自の施設費や教材費、行事費が加わることで差はさらに広がります。
ただし、ここで示されているのは支援制度を利用する前の金額です。実際には、国の就学支援金や自治体ごとの補助制度を活用することで、授業料の大部分が補助される家庭もあります。場合によっては「実質無償」に近い形になることも少なくありません。
公立と私立を比較するときには、単に公表されている数字だけを見比べないようにしましょう。支援制度を利用した後に残る「実際の負担額」を確認することが大切です。
制度の内容を正しく理解し、家庭の収入に応じた支援を把握することで、進学の選択肢はぐっと広がるでしょう。
私立高校の学費を軽減する国の支援制度
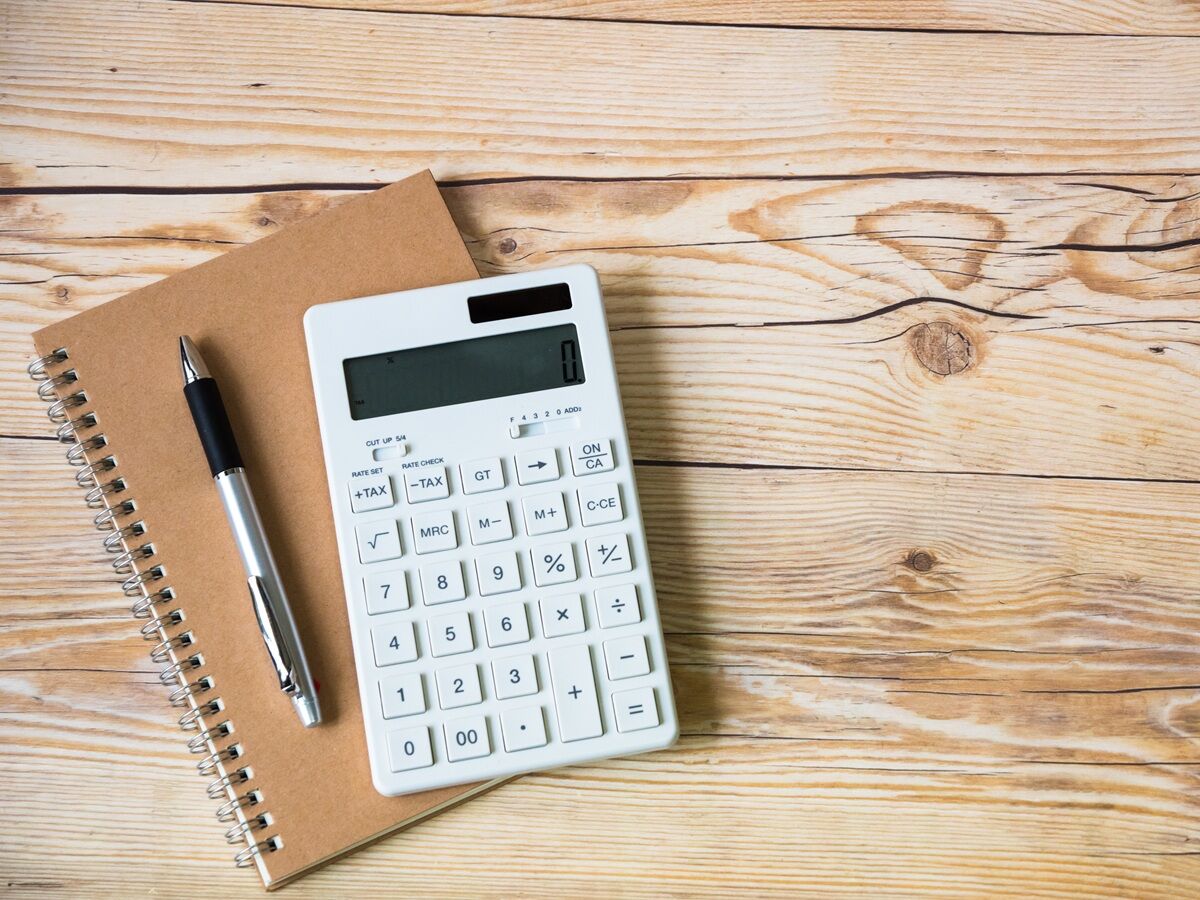
私立高校への進学を考えるうえで、大きな心配のひとつが学費の負担が心配という声は少なくありません。
しかし、そうした家庭を支えるために、国では「就学支援金制度」という補助制度が設けられています。
この制度は、一定の所得基準を満たす世帯を対象に、授業料の一部または全額を補助するしくみです。2026年度からは対象がさらに広がり、所得制限があった家庭でも実質的な負担を軽減できるようになる可能性があります。
ここでは、具体的にどのような条件で、どれくらいの金額が支給されるのかを詳しくご紹介します。支援制度を正しく理解し、私立高校という選択肢に前向きになれるよう、役立ててください。
高等学校等就学支援金
私立高校に通わせたいと思っても、やはり授業料の高さは気になるところです。そんな負担を少しでも軽くするために国が設けているのが「高等学校等就学支援金制度」です。
この制度の特徴は、補助金が保護者に直接支払われるのではなく、学校で納める授業料からそのまま差し引かれる点です。そのため「支給される」というより、結果的に毎月の納付額が減るという感覚に近いでしょう。
- 世帯年収の目安:約910万円未満
高等学校等就学支援金:授業料から最大39万6,000円減額 - 世帯年収の目安:約910万円以上
高校生等臨時支援金(物価高騰対策として令和7年度のみ):年額11万8,800円
この就学支援金は、年ごとに制度の内容が見直され、対象や補助額が拡大してきました。進学を検討するときには、最新の制度内容を必ず確認し、利用できる支援を取りこぼさないことが安心につながります。
私立高校の授業料が実質無償化に(年収目安による上乗せ支援)
これまで私立高校は、公立に比べて授業料の負担が大きいものとして考えられてきました。
しかし、令和8年度からは就学支援金制度がさらに拡充され、私立高校の授業料が「実質無償化」に近づくことが期待されています。新しい制度では、授業料に相当する額まで支援が引き上げられる見通しです。
これにより、従来は補助が不十分だった中間層世帯も対象が広がります。制度が実現すれば、家庭の収入に左右されず進学先を選びやすくなります。
制度の変化を整理すると、次のようにまとめられます。
- 令和8年度から授業料相当額まで支援を拡大
- 私立高校の授業料が実質的に無償化へ近づく
- 中間層や高所得層も支援対象に含まれる見込み
授業料がほぼゼロになる家庭も増え、家庭の経済状況に左右されず学校を選べる時代が近づいたといえるでしょう。
都道府県独自の給付・補助制度【2025年版】

国の就学支援金に加え、各都道府県でも独自の補助制度が設けられています。授業料の一部を上乗せで助成したり、入学金や教材費に対応する地域もあります。
対象となる世帯年収や金額は地域ごとに違いがあり、国の制度と併用できるケースも多いため、実質負担は大きく変わってきます。たとえば東京都や大阪府では、一定の条件を満たせば授業料がほぼゼロになったり、ほかの県でも独自の上乗せ補助がある場合があります。
ここでは、代表的な自治体の支援制度を取り上げ、それぞれの特徴や金額をわかりやすくご紹介します。
東京都の支援|私立高校授業料助成金
東京都では、独自の「私立高校授業料助成金」を設けています。国の就学支援金と組みあわせることで多くの家庭で授業料が実質無償化となり、授業料の心配を減らせる制度です。
- 対象:都内在住で、世帯年収の目安が約910万円未満
- 補助額:授業料を上限に、年間最大49万5,000円
- 利用効果:国の就学支援金と併用すれば授業料が実質ゼロになる家庭も多い
- 特徴:都市部特有の教育費の高さを考慮し、中間層まで幅広く支援
東京都ならではの手厚い助成は、お子さんの進学を前向きに選ぶ大きな後押しになっています。
大阪府の支援|私学授業料支援補助金
大阪府は全国のなかでも先進的に「授業料の無償化」に取り組んできました。国の就学支援金とあわせることで、公立高校とほぼ同じ負担で私立高校へ通える仕組みを整えています。
- 対象:府内在住の高校生
- 所得制限:2026年度からは所得制限を撤廃し、授業料が完全無償化される予定
- 補助額:年間最大63万円まで(授業料を上限として支給)
- 特徴:低所得世帯ほど手厚い補助があり、授業料が全額ゼロになるケースも多数
こうした取り組みによって、大阪府では「家庭の経済事情に左右されずに学校を選べる」環境が整いつつあります。
神奈川県の支援|私立高等学校等学費支援
首都圏で暮らす保護者の方のなかには「生活費も高いのに、私立高校の学費まで出せるか不安」という方も多いでしょう。神奈川県では、そうした家庭の負担を和らげるために、国の就学支援金に加えて利用できる独自の「私立高等学校等学費支援制度」を整えています。
- 対象:県内在住で、世帯年収が750万円未満・多子世帯で年収910万円未満
- 補助額:年収により年間最大46万8,000円(授業料を上限に支給)
- 国の制度との併用:国の就学支援金と組みあわせれば授業料が実質ゼロになる家庭も
- 特徴:中間層を含むさまざまな世帯が利用可能
公立とほとんど変わらない負担で私立を選べる可能性もあり、保護者にとって大きな安心材料になっています。神奈川県は毎年制度の見直しを行い、教育の機会が家庭の収入によって左右されないように取り組んでいます。
愛知県の支援|愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金
愛知県では国の就学支援金に加え、「私立高等学校等授業料軽減補助金」を実施しています。
- 対象:県内に居住する家庭で、課税標準額等に応じて判定
- 補助額:就学支援金と併せて年間で最大44万5,200円(学年や所得目安の段階あり)
- 入学金補助:所得に応じて初年度のみ最大20万円を補助
- 特徴:国の就学支援金と組みあわせることで、初年度の負担を大幅に軽減可能
入学金の補助があることで、制服代や教材費と重なる初年度を安心して迎えられます。愛知県の制度は、進学を後押しする現実的で心強い仕組みになっています。
そのほかの地域の取り組み・支援
私立高校の学費負担が不安なご家庭に向けて、全国の自治体でもさまざまな支援策が広がっています。ここでは、北海道・奈良県・兵庫県の事例をご紹介します。
制度は年度ごとに見直しがおこなわれるため、利用を検討する際には必ず最新の情報を確認するようにしましょう。
北海道の制度|私立高等学校等授業料軽減制度
北海道では、授業料の軽減に加えて、生活費を支える給付制度も整えられています。家計の状況に応じて学びやすい環境が工夫されています。
- 年収の目安:約590万円未満(世帯の所得に応じて段階的に設定)
- 補助額:世帯の所得に応じて、月額最大2,000円(年額約2万4,000円)を授業料に充当
- 奨学のための給付金:家計が急変した世帯などを対象に、教材費や通信費を補助
奈良県の支援|奈良県私立高等学校等専攻科修学支援金
奈良県では、国の補助に加えて県独自の支援策を展開しています。とくに専攻科や多子世帯への配慮が厚く、家庭の状況にあわせたサポートが特徴です。
- 授業料等軽減補助金:国の支援に加え、所得等に応じて県独自の補助を実施
- 専攻科修学支援金:国の就学支援金とあわせて、上限額は年間46万8,000円
- 多子世帯加算:兄弟姉妹が同時に在学する場合に追加支援あり
兵庫県の制度|授業料軽減補助金
兵庫県は、中間層の家庭にも手が届く補助制度を設けています。兄弟姉妹が多い家庭にも追加支援があり、幅広い層を支える仕組みになっています。
- 補助額:所得に応じて年間6万円〜12万円を補助
- 多子世帯加算:1万円を上乗せし、兄弟姉妹が多い家庭を支援
- 特徴:中間層の家庭も利用できる仕組みで、幅広い層をカバー
学費以外にかかる費用も確認しておこう

私立高校への進学を考えるとき、授業料や入学金といった大きな費用にまず目が向きがちです。しかし、実際には制服・教材・修学旅行費、さらには塾・習い事など、学費以外の出費も少なくありません。
とくに入学直後は制服や指定品の購入などで、まとまった費用がかかることが多く、想定以上の負担となるケースもあります。進学後に「思ったよりお金が必要だった」と慌てないためにも、どんな費用がかかるのかを把握しておくことが大切です。
この章では、入学初年度の支出や部活動・塾の費用など、授業料以外の負担について詳しく見ていきましょう。
制服・教材・修学旅行費
私立高校に進学すると、授業料以外にもさまざまな出費があります。とくに入学初年度は、制服や教材を揃えるための費用が大きくなります。
制服一式(冬服・夏服・体操服・指定靴などを含む)の費用は、一般的に5万円から10万円前後かかるといわれています。学校によってはさらに高額になることもあり、初年度の負担を重く感じる保護者の方も少なくありません。
教材費や学用品についても負担は大きく、文部科学省の調査では、私立高校で年間約7万4,600円という結果が出ています。教科書代だけでなく、実習用の材料費や副教材などが含まれるため、想像以上にかさみやすい部分です。
さらに、修学旅行の費用も見逃せません。私立高校の平均的な修学旅行費は約5万9,300円ですが、行き先や日程によって大きく変わります。海外修学旅行になると20万円から40万円程度かかるケースもあり、家計にとって大きな負担となることがあります。
このように、制服・教材・修学旅行などの費用は授業料とは別にかかるため、初年度の出費をしっかり見積もっておきましょう。
部活動や塾、習い事のコスト
高校生活では、授業料や教材費に加えて部活動や学習塾、習い事にかかる費用も無視できません。私立高校の場合は、学習環境が充実している分、活動の幅も広がり、結果として出費が大きくなることがあります。
まず部活動では、ユニフォームや楽器・道具の購入費用に加え、遠征や合宿があると、交通費や宿泊費が発生します。部の種類や活動の頻度によって負担額は大きく変わりますが、年間で数万円規模になるケースも珍しくありません。
さらに、学習塾や習い事に通う生徒も多く、これらは家計に大きな影響を与えます。文部科学省の調査によると、私立高校に通う生徒の「学校外活動費」は年間平均で26万4,000円にのぼります。これは塾や習い事、通学費などを含んだ金額で、公立高校に比べても高い水準です。
このように、部活動や塾・習い事の費用を考えると、授業料以外にも年間で20万円以上の負担がかかるのが一般的です。進学を検討する際には、学校外での活動費も含めて資金計画を立てておきましょう。
私立高校進学は支援制度を活用すれば負担は軽減する
私立高校の学費は、公立に比べるとどうしても高くなりがちです。ですが、国の就学支援金や各自治体の補助制度を組みあわせれば、授業料の多くがカバーされる家庭も少なくありません。
とくに近年は制度が拡充され、年収に応じて実質的に授業料がゼロになるケースも増えています。さらに入学金や教材費などに対応した補助をおこなう自治体もあり、条件にあえば負担をぐっと減らすことができます。
ただし、支援の内容や金額は毎年度見直されるため、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。学費以外にも部活動や修学旅行などの費用がかかることをふまえ、早めに全体の見通しを立てておくと安心です。
経済的な理由で私立をあきらめるのではなく、制度を上手に活用して、お子さんあった進路選びにつなげてみてください。
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。