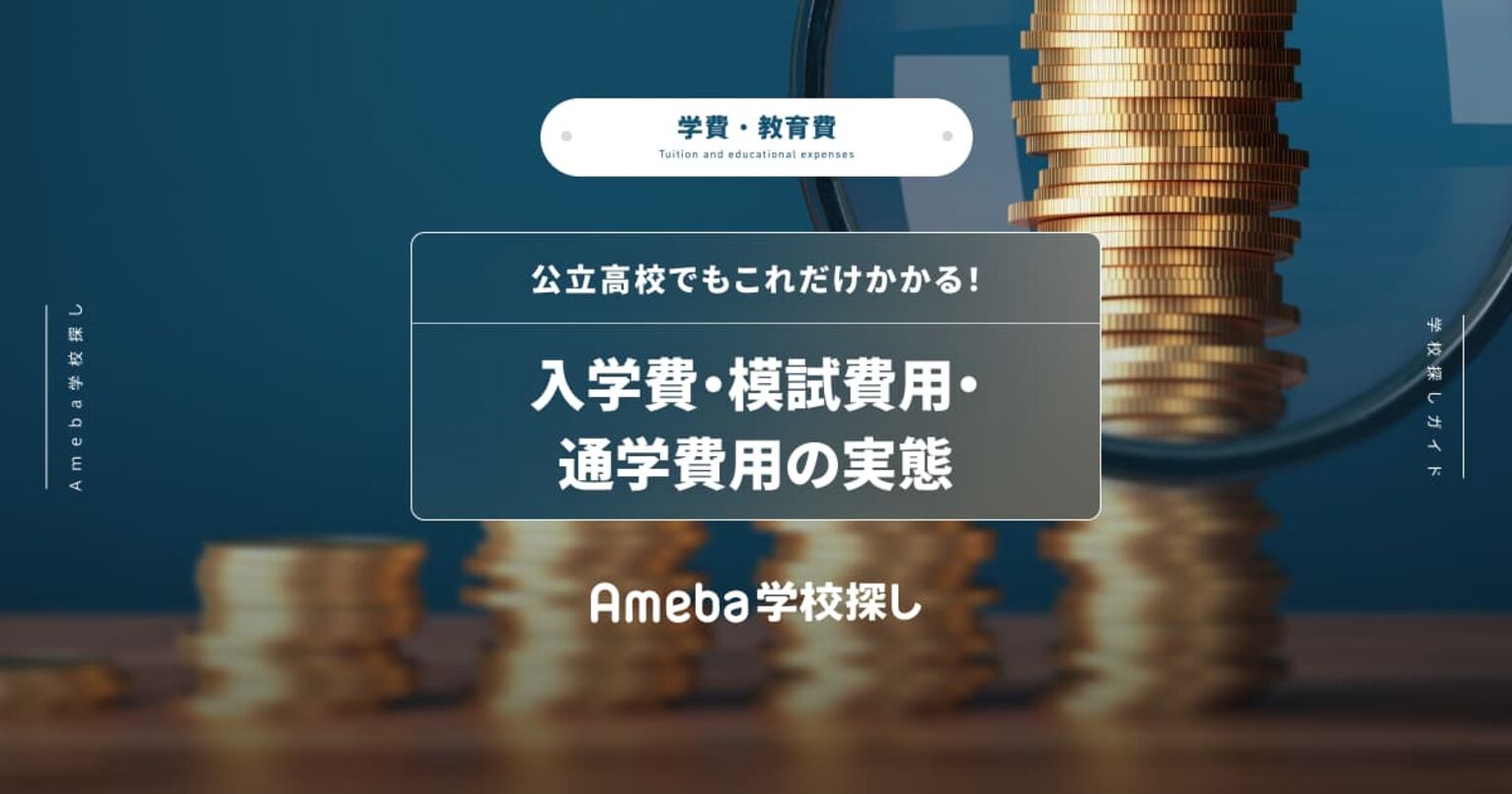「公立高校なら学費はほとんどかからないから安心」と思っていませんか? 実は、授業料が無償でも入学時にかかる費用や通学・模試代など、見落としがちな出費が意外と多いのが現実です。制服代だけでも4万~6万円、通学費は年間12万円以上かかることも珍しくありません。
この記事では、公立高校進学に際して実際にかかる費用を項目別に詳しく解説します。受験から入学、通学までの家計シミュレーションに役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
※この記事の情報は2025年8月時点のものです。各種制度や費用は変更される場合があるため、最新情報については必ず各学校や自治体の公式サイトをご確認ください。
入学時にかかる費用の実態

公立高校への合格通知を手にしたとき、多くの保護者が「これで教育費の心配も一段落」と安堵されることでしょう。確かに授業料は無償化制度により負担がありませんが、実は入学準備には思っている以上にまとまった費用がかかります。
「制服代くらいでしょ?」と考えていたら、予想以上の出費にびっくり……なんてことも珍しくありません。お子さんの新しい門出を安心して応援できるよう、入学時にかかる費用の内訳を詳しく見ていきましょう。
入学金や制服代、教材費の目安
まず必要になるのが入学金です。東京都立高校では5,650円、神奈川県立高校でも同程度となっています。金額としてはそれほど大きくありませんが、これはほんの序の口。本格的な出費はここからが本番です。
制服一式は、多くの保護者が「思ったより高い」と感じる項目です。文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、公立高校の通学関係費(制服・通学用品費・通学費の合計)は約9万8,000円となっており、このうち制服代は冬服上下・夏服上下・体操着・ジャージなどひととおり揃えると、4万円から6万円程度が相場となっています。
とくに女子の制服は、ブレザー・スカート・ブラウス・リボンやネクタイなど細かいアイテムが多く、思いのほか金額がかさみます。
「中学の制服よりずいぶん高いな」と感じられるかもしれませんが、高校の制服は一般的に生地や縫製にこだわりがあり、3年間しっかりと着用できる品質になっているためです。
教材関係では、教科書代・副教材費・実習費・芸術科目の道具代などで約6万2,000円。さらに、PTA会費・生徒会費・修学旅行積立金・学年費など、学校生活に必要な諸費用が約3万6,000円かかります。
これらすべてを合計すると、入学時だけで10万円から15万円程度の出費となります。「こんなにかかるとは思わなかった」という声をよく耳にするのも、この金額を見れば納得ですね。
学校指定品・部活動費も要チェック!
制服や教材以外にも、意外と多いのが「学校指定品」です。上履き、通学かばん、体育館シューズなど、「えっ、これも指定なの?」と驚かれる方も多いでしょう。学校によっては通学用の自転車まで指定の場合があり、これらの類だけでも5千円から1万円程度の出費になります。
とくに注意したいのが部活動関連の費用です。お子さんが「絶対にこの部活に入りたい!」と目を輝かせているとき、費用面で制限をかけるのは親としても心苦しいものです。
文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、公立高校の教科外活動費(クラブ活動・学芸会・運動会・芸術鑑賞会・臨海学校などの費用)は部活動以外の金額も含まれていますが、年間約4万9,000円 となっています。
部活動の費用は活動内容によって大きく異なるため、具体的な金額については事前に顧問の先生に確認しておくことをおすすめします。
たとえば、テニス部ならラケット・シューズ・ユニフォーム、吹奏楽部なら楽器(学校備品でない場合)、美術部なら画材セットなど、それぞれ専門的な道具が必要になります。
また、大会参加費・遠征費・合宿費なども年間を通じて発生する場合がありますので、年間1~5万円程度見込んでおきたいところ。
「入学してから考えよう」ではなく、学校説明会や体験入学の際に、気になる部活動の費用について遠慮なく質問してみてください。多くの学校では、保護者の負担を考慮して分割払いや中古品の融通など、配慮してくれるケースもあります。
通学費用は毎月の固定出費として捉えよう
入学時の一時的な出費も大きな負担ですが、それと同じくらい重要なのが毎月かかる通学費用です。「うちは公立だから大丈夫」と安心していると、3年間の累計でかなりの金額になることに後から気づくことも少なくありません。
とくに最近は、お子さんの希望する学科や部活動、進学実績を重視して高校を選ぶ家庭が増えているため、「近所の高校」ではなく「少し遠くても行きたい高校」を選択するケースが多くなっています。
定期代・交通費は自治体や通学距離で異なる
通学方法によって、月々の負担は大きく変わります。もっともお得なのは自転車通学で、定期代そのものはかかりません。ただし、雨具や自転車の整備費、万が一の修理代などは別途必要になります。
電車やバス通学の場合、月額5,000円~8,000円(片道30分圏内)が一般的です。しかし、乗り換えが必要だったり、私鉄とJRを組み合わせたりする場合は、月額1万円を超えることも珍しくありません。
「月1万円なら何とかなる」と思われるかもしれませんが、これが3年間続くと考えてみてください。年間12万円、3年間で36万円という計算になります。さらに、定期券の有効期限切れによる追加購入や、部活動の遠征などで別途交通費がかかることもあります。
地域による差も大きく、東京都では一定の通学費助成制度がありますが、神奈川県・千葉県・埼玉県では基本的に自己負担となります。お住まいの自治体にどのような支援制度があるかを事前に調べておくようにしましょう。
また、定期券は学割が適用されるとはいえ、成人の通勤定期と比べてそれほど大幅な割引があるわけではありません。高校3年間は保護者にとって教育費の山場でもありますので、通学費も含めて年間の教育費総額を把握し、計画的に準備を進めることをおすすめします。
通学ルートを決める際は、所要時間だけでなく費用面も含めて検討し、可能であれば実際に定期代を調べてから最終決定することで、入学後の「こんなにかかるとは…」という驚きを避けることができます。
公立でも「完全無償」ではない!支援制度のチェックを忘れずに

「公立高校は授業料無償だから安心」という認識は、確かに間違いではありません。しかし、「無償」なのは授業料だけであり、実際の高校生活には授業料以外にもさまざまな費用がかかることを理解しておく必要があります。
また、就学支援金にも条件があり、すべての家庭が対象になるわけではないことも重要なポイントです。制度をしっかりと理解し、利用できる支援は最大限活用しながら、万が一の場合の備えも考えておきましょう。
就学支援金と所得制限の関係
公立高校の就学支援金は、世帯年収の目安が910万円未満の世帯が対象となっています(※)。この「世帯年収」というのがポイントで、夫婦どちらか一方の収入ではなく、父母の収入を合算した金額で判定されます。
共働きが一般的な現在、片方が年収500万円、もう片方が年収450万円という場合、合算すると950万円となり、支援金の対象外になってしまいます。「うちはそんなに高収入じゃないのに…」と感じられる方も多いかもしれませんが、実は対象外になる可能性が高いのが現実です。
さらに注意したいのは、お子さんが高校に入学するころは、保護者の方も働き盛りの年代だということです。昇進や転職、副業の開始などで収入が増えることは決して珍しくありません。中学3年生の時点では支援金の対象内だったのに、高校2年生になったら対象外になってしまった、ということも起こり得ます。
就学支援金の対象外になった場合、年間約12万円の授業料負担が発生します。これは決して小さな金額ではありませんので、可能性がある場合は事前に準備をしておくことが大切です。
また、就学支援金でカバーされるのは授業料のみで、制服代・教材費・通学費・部活動費・修学旅行費などは別途自己負担となることも改めて確認しておきましょう。
※参考:文部科学省「高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット(概要版)」
自治体の助成制度の一部を紹介
国の就学支援金制度に加えて、各自治体では独自の支援制度を設けています。これらの制度は申請しなければ受けられないものが多いため、お住まいの地域にどのような制度があるかを積極的に調べることが重要です。
- 【東京都の取り組み】
東京都では「奨学のための給付金事業」により、非課税世帯に対して年額143,700円の給付をおこなっています。これは授業料以外の教育費(制服代・教材費・通学費など)を支援するもので、返済の必要がない給付型の支援です。 - 【大阪府の取り組み】
大阪府では「大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金」として、非課税世帯・生活保護世帯などを対象に、授業料以外の教育費を給付しています。低所得世帯の高校生の教育費負担軽減を目的とした制度で最大年額143,700円の給付が受けられます。 - 【大阪市の取り組み】
大阪市でおこなっている「大阪市奨学費」は大阪市在住、非課税世帯の高校生に対して、第1学年時には年額107,000円の教育費を支援する制度です。大阪府がおこなっている給付金の給付額を控除した金額が支給上限となります。 - 【堺市の取り組み】
堺市の「堺未来応援奨学金」は、非課税世帯などを対象に年額60,000円(国公立・私立で変動あり)程度を給付する制度です。申請は7月頃、オンライン申請可能となっています。
これらの制度に共通するのは、申請時期が限定されていることと、所得要件が細かく設定されていることです。「知らなかった」「申請を忘れた」で支援を受けられないのは非常にもったいないことです。
中学3年生の春頃から、進学予定先の自治体の支援制度について情報収集を始めることをおすすめします。学校からの案内だけでなく、自治体のホームページや広報誌もこまめにチェックし、申請時期を逃さないよう注意しましょう。
高校受験時にかかる見えない出費にも注意!
高校の費用について考えるとき、つい入学後のことばかりに目が向きがちですが、実は受験時にも相当な費用がかかります。とくに中学3年生になると、これまでとは桁違いの教育費が必要になることを覚悟しておきましょう。
「まだ受験まで時間があるから」と油断していると、いざというときに慌てることになりかねません。受験費用も含めた年間計画を立てておくことが大切です。
高校受験対策として欠かせないのが模擬試験です。V模擬・W模擬・神奈川全県模試など、地域によってメジャーな模試は異なりますが、1回あたり4,000円~5,000円というのが相場です。
模試は単なる腕試しではなく、志望校選択の重要な判断材料です。偏差値の推移を見ることで学力向上を実感できますし、志望校の合格可能性を客観的に把握することもできます。「今回はお金がもったいないから受けない」という判断は、受験戦略上あまりおすすめできません。
公立高校が第一志望であっても、多くの家庭では私立高校の併願受験を検討されます。「保険のため」「安心のため」という理由は十分理解できますが、私立高校の受験料は1校あたり2万円~3万円と高額です。
5校~6校を併願すると、受験料だけで10万円~18万円という計算になります。さらに、受験当日の交通費・宿泊費(遠方の場合)・昼食代なども含めると、併願受験の総費用は20万円を超えることも珍しくありません。
併願校を決める際は、本当にその学校に進学する可能性があるか、費用に見合った価値があるかを冷静に判断することが大切です。「みんなが受けるから」「塾の先生に勧められたから」だけで決めるのではなく、家計とのバランスも考慮しましょう。
最近では、多くの私立高校で「入学手続き時納入金の延納制度」を設けています。公立高校の合格発表まで支払いを待ってもらえる制度ですので、併願を検討している学校にはこの制度があるかどうかも確認してみてください。
高校無償化制度に頼りきらず、各家庭で準備をしておくことが大切
ここまで、公立高校進学に関わるさまざまな費用について紹介してきました。「公立なら安心」と思っていた方にとっては、予想以上に多くの出費があることに驚かれたかもしれません。
授業料は確かに無償ですが、それ以外の費用を合計すると、入学時の準備費用・3年間の通学費・受験関連費用などで、公立高校の場合でも総額20万円から30万円程度の出費が見込まれます。これは決して小さな金額ではありません。
大切なのは、これらの費用を「突然の出費」として捉えるのではなく、「予測できる必要経費」として事前に準備することです。中学2年生の段階から少しずつ準備を始めれば、家計への負担を大幅に軽減できます。
教育費は確かに大きな負担ですが、お子さんの将来への投資でもあります。高校3年間は、お子さんが大人になるための大切な準備期間。この時期を安心して過ごせるよう、保護者としてできる準備を整えておきたいもの。
今から少しずつ、できることから準備を始めてみてください。お子さんの輝かしい高校生活のために、一緒に頑張りましょう。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。