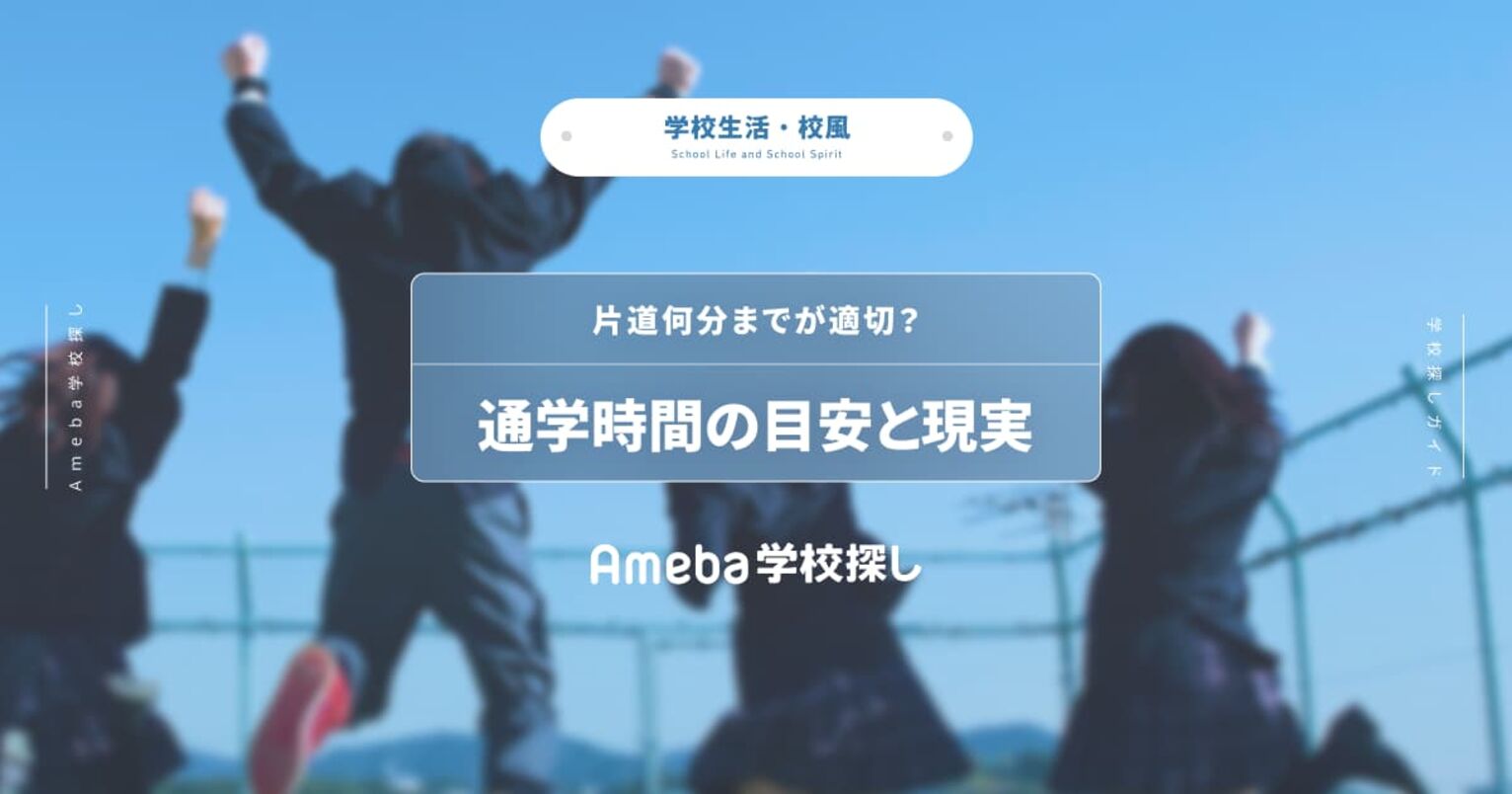お子さんの進学先を検討する際、「通学時間はどのくらいまでが適切なのか」という疑問をお持ちの保護者の方は多いのではないでしょうか。
実際に調べてみると、地域によって通学事情は大きく異なり、首都圏では長時間通学が一般的な一方、地方では比較的短時間で済むことが多いです。
また、中学生では自転車通学が主流になったり、大学生では一人暮らしか自宅通学かで状況がまったく変わったりと、学校段階によっても通学のあり方はさまざまです。
そこで本記事では、データをもとに、通学時間について後悔しない判断をするためのポイントを紹介します。お子さんの進学先選びの参考として、ぜひお役立てください。
学生のリアルな通学時間はどのくらい?

お子さんの進学先を決める際、ほかの学生がどのくらいの時間をかけて通学しているのか気になるところです。
実際のデータを見ると、学校段階によって通学時間には明確な違いがあり、地域による差も大きいことがわかります。まずは客観的な統計データから、現在の学生の通学事情を詳しく見ていきましょう。
【データで見る】中学生・高校生・大学生の平均通学時間

お子さんの進学を検討される際に気になるのが、実際の通学時間がどの程度なのかということです。各種調査データをもとに、学校段階別の通学時間を見てみましょう。
中学生の通学時間
中学生のお子さんの場合、多くは地域の公立中学校に通われることになります。小学校と同じように、住んでいる地域で通う学校が決まる「学区制」があるためです。
文部科学省が公表している東京学芸大学の全国調査(令和2年3月) によると、中学生になると通学手段が大きく変わります。小学生のころは「徒歩のみ」が半数以上でしたが、中学生では「自転車」が約半数(48%)と最も多くなります。
これは通学距離が少し延びても、自転車を使えるようになることで、小学校時代とそれほど変わらない時間で通学できることを意味しています。
そのため、私立中学校を選択される場合を除き、小学校時代からの通学時間に大きな変化がないお子さんが多いのが実情です。
※出典:東京学芸大学「小中高生の生活,健康・体力,学習に通常手段・時間が及ぼす影響ー発達段階別比較ー」報告書 より
高校生の通学時間
高校生になると、お子さんの希望や学力、将来の目標に合わせて学校を選べるようになるため、通学時間は一般的に長くなる傾向があります。
中学校では住んでいる地域で通う学校が決まっていましたが、高校では公立・私立を問わず、より広い範囲から学校を選択できます。そのため、学習内容や校風、部活動などを重視して、少し遠い学校を選ぶご家庭も多くなります。
参考として、総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」における通勤・通学時間データ(学生・社会人を含む全体)を見ると、地域による大きな違いがあることがわかります。
最も長いのは神奈川県で1時間40分、次いで千葉県及び東京都が1時間35分、埼玉県が1時間34分となっており、首都圏で長時間の通勤・通学が顕著です。
一方、最も短いのは山形県及び宮崎県で56分、次いで愛媛県57分などとなっており、都市部と地方部では大きな差があります。
この傾向は高校生の通学にも当てはまり、特に都市部では選択肢が多い分、通学時間が長くなる傾向が見られます。一方、地方では近隣に選択肢が限られているため、比較的短時間での通学となることが多いです。
※出典:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果 」
大学生の通学時間
大学生の通学時間は、住居形態によって大きく異なります。
京都医療科学大学が京都の大学生を対象に実施した2022年の調査では、自宅通学生の平均通学時間は1時間25分で、そのうち33%が1.5時間以上かけて通学していることが明らかになっています。これは高校生と比べても、かなり長時間の通学となっていることがわかります。
一方、一人暮らしの学生はその91%が大学から通学時間30分以内のところに住んでいるという対照的な結果も得られており、住居選択によって通学環境は大きく変わることがわかります。
大学生になると、進学と同時に一人暮らしを始める学生も多く、通学時間だけでなく住居選択も含めた総合的な判断が求められるのが特徴です。また、高校生までのように平日毎日通学するわけではなく、授業スケジュールによって通学頻度や時間帯が変動することも、大学生ならではの特徴といえます。
これらのデータは、お子さんの進学先選びの参考になりますが、最も大切なのはお子さん一人ひとりの体力や性格に合った選択をすることです。通学時間を有効活用できるお子さんもいれば、短時間通学で家庭学習に時間を充てる方がよいお子さんもいらっしゃいます。
お子さんと一緒に相談しながら、ご家庭に最適な選択をしていただければと思います。
※出典:京都医療科学大学「学生実態アンケート 」
通学手段による時間の違い
通学手段によっても、かかる時間や通学中の過ごし方が変わります。電車やバスを利用する生徒は長距離通学が可能な一方で、通学時間が長くなる傾向があります。ただし、座席を確保できれば読書や暗記など学習の時間に充てやすいという利点もあります。
一方、自転車や徒歩で通う生徒は短時間で移動でき、運動不足の解消や健康維持にもつながります。しかし、天候や季節に左右されやすく、雨具や安全対策が欠かせません。
通学時間が長いと大変?メリット・デメリットを徹底比較

お子さんの進学先を検討する際、通学時間が長くなることへの不安を感じる保護者の方は多いのではないでしょうか。確かに、通学時間が長いと負担が大きそうに思えますが、実は意外なメリットもあります。ここでは、長い通学時間だからこそ得られるメリットと、注意しておきたいデメリットを整理します。
時間がかかるからこそのメリット
通学時間が長いことを単純にマイナス面だけで捉える必要はありません。多くの学生や保護者が実感している、長時間通学ならではのメリットをご紹介します。
貴重な学習・読書時間に変わる
- 毎日の往復時間を、単語の暗記や読書など、まとまったインプットの時間として活用できることは大きなメリットです。電車やバス内では、参考書を開いたり、語学アプリを使ったり、読書に集中したりと、家庭では集中しにくい学習を効率的に進められます。
特に受験期においては、この通学時間が貴重な学習時間となり、1日2時間の通学なら年間で約500時間もの学習時間を確保できる計算になります。家庭で同じ時間を学習に充てるのは難しいため、通学時間の有効活用は大きなアドバンテージとなります。
思考を整理する一人の時間を持てる
- 学校と家の間の移動時間は、1日の予定を立てたり、学んだことを振り返ったり、将来について考えたりする貴重な「一人の時間」になります。現代の子どもたちは忙しく、ゆっくりと物事を考える時間が不足しがちですが、通学時間はそうした思考の時間を自然に提供してくれます。
また、学校モードから家庭モードへの切り替えの時間としても機能し、メンタル面でのバランスを保つのに役立ちます。
規則正しい生活リズムが身につく
- 電車やバスの時間に合わせて行動するため、自然と早寝早起きの習慣がつきやすくなります。決まった時間に起床し、決まった時間に家を出る生活リズムは、長期的な健康維持や学習効率の向上にもつながります。
また、時間管理能力も自然と身につき、社会人になってからも役立つスキルを早い段階で習得できることも大きなメリットです。
知っておきたい「デメリット」と心身への影響
一方で、長時間通学には注意すべきデメリットも存在します。これらを事前に理解しておくことで、適切な対策を講じることができます。
睡眠不足と学業成績への懸念
- 通学時間が長くなるほど睡眠時間が短くなる傾向があり、学業への影響が懸念されます。文部科学省の調査でも、睡眠時間と学習効果の関係が指摘されており、適切な睡眠時間の確保は学習面だけでなく、成長期のお子さんの健康面でも重要な要素です。
早朝の通学や部活動後の帰宅時間を考慮すると、1日の生活スケジュールが非常にタイトになり、十分な休息が取れなくなる可能性があります。
体力的な負担とストレス
- 特に満員電車での通学は、身体的な疲労だけでなく、精神的なストレスの原因にもなりえます。毎日の満員電車での通学は、大人でも疲労を感じるものですから、成長期のお子さんにとってはより大きな負担となる場合があります。
また、天候の影響を受けやすく、台風や大雪などの際には通学が困難になったり、遅刻の心配をしたりといった精神的な負担も生じます。
部活動や放課後の活動への制約
- 帰宅時間が遅くなるため、部活動や友だちとの交流、アルバイトなどの時間に制約が出てくる可能性があります。特に部活動に力を入れたいお子さんの場合、練習時間の確保や遠征への参加が難しくなることもあります。
また、友だち関係においても、放課後に一緒に過ごす時間が限られるため、学校外での交流が減る可能性も考慮する必要があります。
これらのメリット・デメリットを踏まえて、お子さんの性格や体力、将来の目標などを総合的に考慮することが大切です。通学時間の長さよりも、お子さんがその時間をどう活用できるかが重要なポイントとなります。
通学時間について後悔しないための判断基準

進学先を決める際、通学時間をどこまで許容するかは、多くの保護者の方が悩まれるポイントです。「この学校に行かせたいけれど、通学時間が心配」「子どもが希望しているけれど、毎日続けられるだろうか」といった不安をお持ちの保護者の方は実際に多くいらっしゃいます。
ここでは、後悔しない判断をするための具体的な基準をご紹介します。
①学習時間をしっかり確保できるか
お子さんの学習スタイルを考慮し、通学時間を活用しても目標とする学習時間を確保できるかシミュレーションしてみることが重要です。
まず、お子さんが1日にどのくらいの学習時間が必要かを明確にしましょう。学年や志望校、現在の学力レベルによって必要な学習時間は変わりますが、一般的な目安を参考に、ご家庭での学習計画を立ててみてください。
次に、通学時間中にどれだけ学習が進められるかを具体的に検討します。電車やバス内で集中して勉強できるお子さんなら、通学時間も貴重な学習時間として計算できます。一方、乗り物酔いしやすい、騒音が気になるといったお子さんの場合は、通学時間を学習時間としてカウントしない方が現実的です。
課題や予習・復習を通学時間中にどれだけ進められるか、具体的な計画を立ててみることをおすすめします。実際に体験入学や学校見学の際に、通学ルートを使って勉強してみると、より具体的なイメージが湧くでしょう。
②心と体の健康が維持できるか
通学は毎日のことですから、お子さんの心身の健康を最優先に考える必要があります。
まず、お子さんに必要な最低限の睡眠時間を把握し、それを確保できる範囲の通学時間かを検討してください。成長期のお子さんには、中学・高校生で8~10時間の睡眠が推奨されています。部活動や習い事の時間も考慮して、現実的な生活スケジュールを組み立ててみましょう。
満員電車が苦手、人混みでストレスを感じやすいなど、お子さんのストレス耐性も重要な判断材料です。通学ルートや時間帯を工夫することで負担を軽減できる場合も多いため、あわせて確認してください。朝の時間帯を少し早めたり、乗車位置を工夫したりすることで、快適性の改善が期待できます。
また、体力的な負担についても慎重に検討が必要です。お子さんの体力レベル、運動習慣、健康状態などを総合的に判断し、毎日の通学が過度な負担にならないか確認しましょう。
③災害時の動き方が想定できるか
近年、自然災害の頻発により、災害時の対応についても事前に検討しておくことが重要になっています。
大地震などの災害が発生すると、公共交通機関が停止し、保護者の迎えが必要になる場合があります。そのような状況でスムーズに行動ができるか、学校から自宅までの距離が現実的に迎えに行ける範囲かを確認しておきましょう。
災害時の避難場所、連絡方法、迎えに行くルートなどを家族で話し合い、お子さんも含めて全員が理解しておくことが大切です。また、学校の災害時対応方針についても事前に確認し、ご家庭の方針と照らし合わせて検討してください。
通学経路上に危険箇所がないか、代替ルートがあるかなどもあわせて確認しておくと安心です。
これらの判断基準を参考に、お子さんの個性や家庭の状況にあわせて、最適な選択をしてみてください。大切なのは、数字だけでなく、お子さんが毎日楽しく、安全に通学できるかどうかです。判断に迷ってしまう場合は、学校の先生やほかの保護者の方にも相談してみることをおすすめします。
賢い通学時間の使い方のアイディア
通学時間が長くなることが決まったら、その時間をいかに有効活用するかが重要になります。ただ漠然と過ごすのではなく、目的を持って通学時間を使うことで、お子さんの成長にとって大きなプラスになります。ここでは、多くの学生が実践している効果的な通学時間の活用方法をご紹介します。
スキルアップ・学習に費やす
- スマホアプリで勉強する
- 時事問題に触れる
- 音声コンテンツで学習する
通学時間を学習時間として有効活用することで、家庭での学習負担を軽減し、より効率的な学習サイクルをつくることができます。
現代では、スマートフォンアプリを活用して効率的に学習を進めることができます。英単語や古文単語、一問一答形式の問題アプリなどは、電車やバスの中でも手軽に取り組めます。短時間でも継続することで、着実に知識を積み重ねることができ、定期テストや受験対策にも大きく役立ちます。
特に暗記系の学習は、通学時間のような細切れ時間を活用するのに最適です。5分程度の短時間でも、毎日続けることで大きな学習効果が期待できます。
また、ニュースアプリで時事問題に触れ、社会への関心を高めることも有効な活用方法です。入試や就職活動でも時事問題は重要視されるため、日頃から社会情勢に関心を持つ習慣をつけることは将来に向けて大きなアドバンテージとなるでしょう。
また、ニュースを読むことで読解力や語彙力の向上にもつながり、国語力全体の底上げにも効果的です。
音声教材やポッドキャストを利用して、耳から語学や専門知識を学ぶことも効果的です。英語のリスニング力向上はもちろん、歴史や科学などの教養番組を聞くことで、幅広い知識を身につけることができます。
満員電車で本やスマートフォンを開くのが難しい場合でも、イヤホンがあれば学習を続けることができるため、通学環境を選ばない学習方法として多くの学生に活用されています。
リフレッシュ・趣味編
- 好きな音楽やラジオを聴く
- 読書する
- 動画コンテンツを観る
学習だけでなく、リフレッシュや趣味の時間として通学時間を活用することも、心の健康を保つ上で重要です。
好きなアーティストの音楽を聴いたり、ラジオ番組でリラックスしたりすることで、学校と家庭の間の切り替え時間として活用できます。朝の通学時間には気持ちを前向きにしてくれる音楽を、帰りの通学時間にはリラックスできる音楽を選ぶなど、時間帯に応じて使い分けることをおすすめします。
また、語学学習を兼ねて洋楽を聴いたり、英語のラジオ番組を聞いたりすることで、楽しみながら学習効果も期待できます。
電子書籍や文庫本で、普段読めないジャンルの本に挑戦することも素晴らしい活用方法です。小説、エッセイ、ビジネス書、自己啓発書など、学校の教科書とは違った分野の本を読むことで、幅広い知識や感性を養うことができます。
読書習慣は語彙力や文章力の向上にもつながり、将来の学習や仕事にも大きく役立ちます。通学時間を利用して読書習慣を身につけることは、長期的な成長にとって非常に価値のある投資といえるでしょう。
短い時間で楽しめるドラマやアニメ、教育系動画などのコンテンツを事前にダウンロードしておくことで、通学時間を楽しい時間に変えることができます。ただし、ダウンロード時間や通信量に注意し、適度な利用を心がけることが大切です。
また、語学学習系の動画や、将来の進路に関連する職業紹介動画なども、楽しみながら学べるコンテンツとしておすすめです。
通学時間の活用方法は、お子さんの興味や性格、学習スタイルによって大きく変わります。いくつかの方法を試してみて、お子さんに最も合った活用方法を見つけていただければと思います。大切なのは、通学時間を「ただの移動時間」ではなく、「成長のための時間」として捉えることです。
まとめ
お子さんの通学時間について考える際、多くの保護者の方が「どのくらいまでなら大丈夫なのか」という疑問をお持ちになるのは当然のことです。
今回ご紹介したデータを見ると、中学生から大学生にかけて通学時間は徐々に長くなり、地域によっても大きな差があることがわかりました。しかし、重要なのは時間の長さそのものよりも、お子さんがその時間をどう過ごし、日々の生活にどう影響するかということです。
長い通学時間は確かに負担になる場合もありますが、工夫次第では貴重な学習時間や自分と向き合う時間にもなります。一方で、睡眠時間や健康面への配慮も欠かせません。
大切なのは、数字だけで判断するのではなく、お子さんの体力や性格、ご家庭の状況を総合的に考えることです。「ほかの子はこれくらい通っているから」ではなく、「うちの子にとって無理のない範囲はどこまでか」を基準に考えていただければと思います。
進学は人生の大きな決断のひとつです。通学時間も含めて、お子さんが充実した学校生活を送れる選択ができることを心から願っています。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。