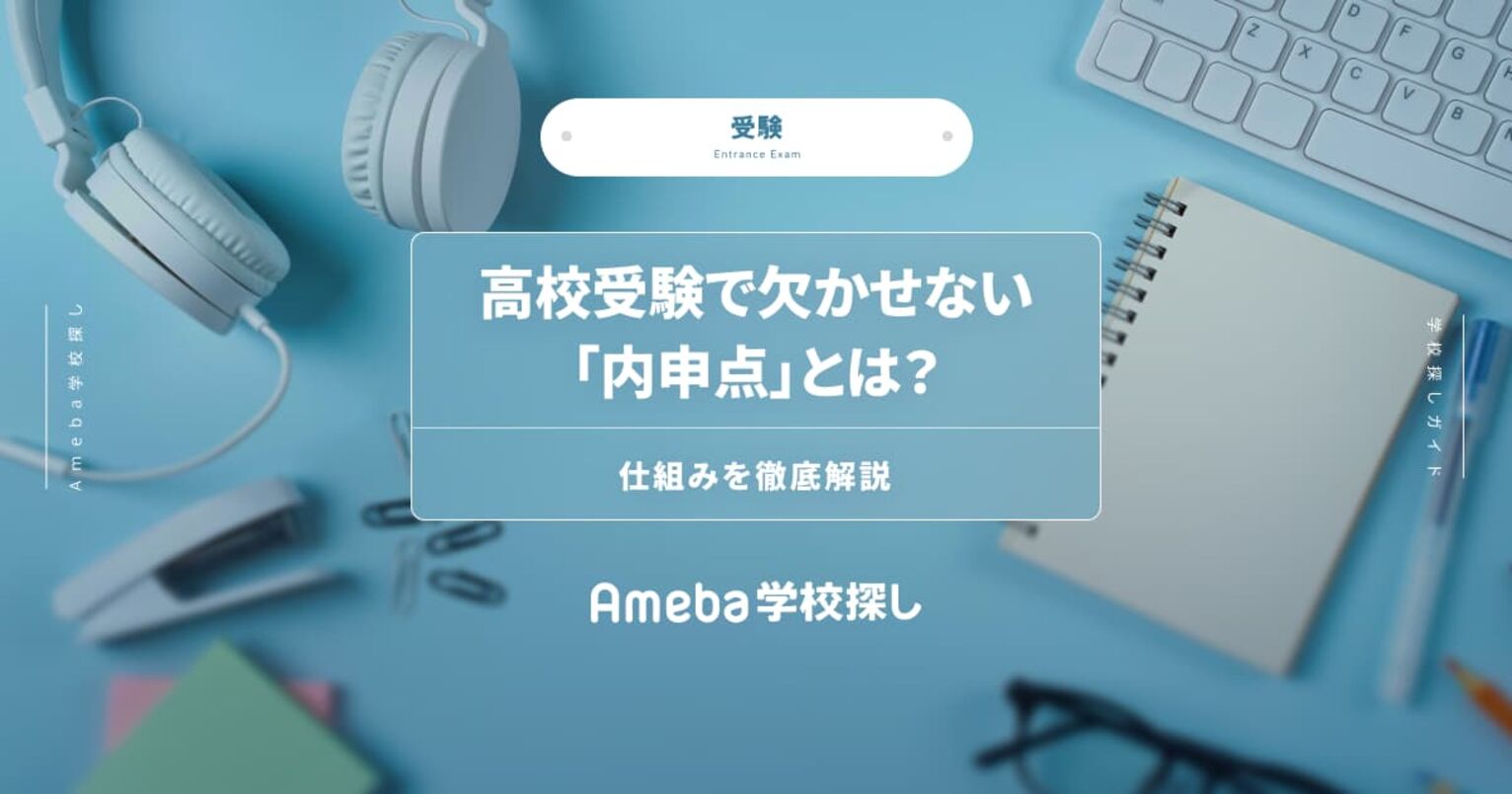高校受験を控えるご家庭でよく耳にする「内申点」。しかし、実際にどのように計算され、合否にどのような影響を与えるのか、わかりにくいと感じる保護者の方も少なくありません。
多くの公立高校では「学力検査点+内申点」を一定の比率で合算し、総合得点で合否が決まるため、どれだけ入試当日に高得点を取っても、内申点が極端に低いと合格が困難になるケースも存在します。
本記事では、内申点の基本的な意味から入試での扱われ方、さらにお子さんが今から取り組める対策までをわかりやすく解説します。
内申点とは?その基本的な意味
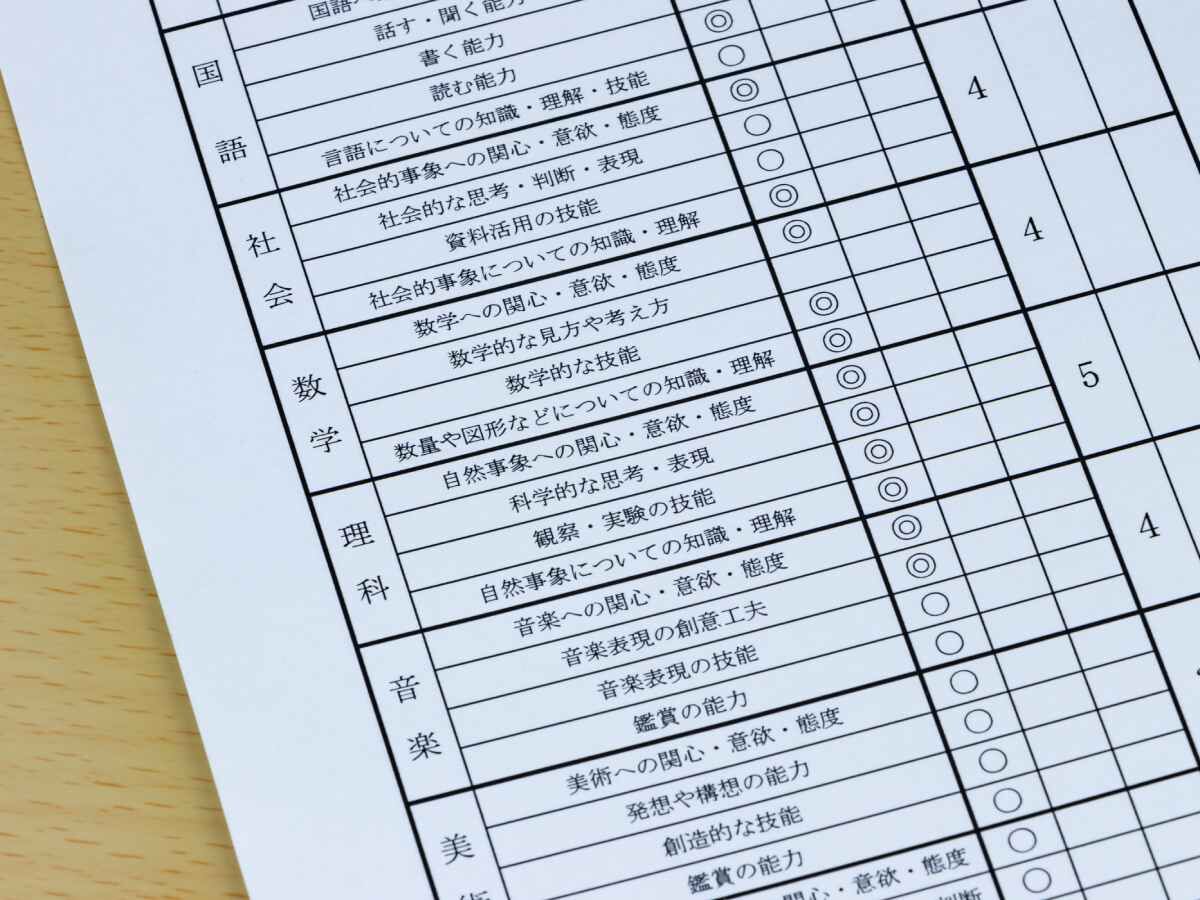
内申点の計算方法は、対象となる成績の時期や地域による違いを理解することが重要です。
多くの保護者の方が疑問に感じる「いつの成績が内申点になるのか」「なぜ地域によって制度が違うのか」といった基本的な仕組みについて、文部科学省の方針に基づいて詳しく解説します。
内申点は通知表の成績を数値化したもの
内申点は、正式には「調査書」に記載される各教科の評定を、各都道府県が定めた計算方法により点数化したものです。
調査書には各教科の成績をはじめ、学級・生徒会の委員経験、学校行事での活動状況、部活動や学校内外での活動実績、出欠日数など、学校生活全般について記録されています。
このうち「各教科の学習の記録」が内申点として数値化され、高校入試の合否判定において重要な役割を果たしているのです。
各教科の評定は「5・4・3・2・1」の5段階で記録され、国語・数学・理科・英語・社会の主要5教科に加え、音楽・美術・保健体育・技術家庭の実技4教科を含めた計9教科すべてが対象となります。
学力試験だけでなく、日頃の学習態度や提出物、授業参加なども評価対象になるため、日常的な努力が反映される点が大きな特徴といえるでしょう。
高校受験でなぜ内申点が重要なのか
公立高校では、入試当日の学力検査点と内申点を合算して合否が決まる仕組みになっています。
各都道府県の教育委員会が定める入学者選抜実施要項に基づき、「学力検査点+内申点」を各都道府県が設定した比率で評価する制度となっており、これにより受験生の総合的な学力と学習態度を評価しています。
多くの都道府県では「学力検査:内申点」が「7:3」や「6:4」といった比率で評価される傾向にありますが、具体的な比率は各都道府県や高校により異なるため、志望校の入学者選抜実施要項で必ず確認することが重要です。
どれだけ入試当日に高得点を取っても、内申点が極端に低いと合格が困難になるケースがあります。逆に内申点が高い場合、入試当日にプレッシャーを感じることなく、精神的な余裕を持って試験に臨むことができるでしょう。
内申点は、受験直前だけでなく、定期テストや日常の授業態度が長期的に影響を及ぼすため、中学校入学時から計画的な学習習慣を身につけることが重要です。
近年の高校入試では、上位校になるほど学力検査を重視する傾向もありますが、基本的には内申点と学力検査点の両方で総合的に判定されると捉えてよいでしょう。
内申点の計算方法と仕組み
内申点の計算方法は、全国共通ではなく、対象となる時期や計算式が地域によって異なります。多くの保護者の方が疑問に感じる「いつの成績が内申点になるのか」「なぜ地域によって制度が違うのか」といった基本的な仕組みについて、詳しく解説します。
いつの成績が対象になるのか
内申点の対象となる成績は、都道府県によって大きく異なることが特徴です。
多くの自治体では中学3年生の成績が重視されますが、地域により中学1年生から3年生まですべての成績が対象となる場合もあります。
もっとも一般的なパターンでは、中学3年生の成績(9教科・5段階評価)が内申点として扱われます。ただし、中学3年生の成績といっても、学年修了時の成績では高校入試に間に合わないため、実際には2学期末または後期中間時点の成績が採用されることになります。
一部の地域では中学1年生や2年生の成績も参考にされる場合があり、たとえば「中学1・2年生の成績も含めて総合的に評価」する仕組みを採用しています。このため、中学校入学時から継続的によい成績を維持することが重要になってきます。
成績の対象時期について詳しく知りたい場合は、お住まいの都道府県教育委員会の公式サイトで最新の情報をご確認ください。地域によって制度が異なるため、早めに正確な情報を把握しておくことが大切です。
地域による違い
内申点の計算方法や配点は、文部科学省の入学者選抜実施要項に基づきながらも、各都道府県の教育委員会が独自に定めているため、地域により大きな違いがあります。
たとえば東京都は「3年次の9教科評定合計」、神奈川県は「評定を得点に換算し、特色検査と組み合わせる」など、仕組みが違います。埼玉県や千葉県では中学1・2・3年生すべての成績が対象となり、学年ごとに重み付けをおこなう場合もあります。
このように同じ関東地方でも計算方法が大きく異なるため、志望校の制度を事前に確認しておくことが重要です。
各都道府県の教育委員会では、内申点の計算方法について詳細な資料を公開していますので、受験準備の早い段階で必ず確認することをおすすめします。
内申点の計算方法【地域別】
都道府県によって内申点の計算方法は大きく異なります。ここでは主要な地域の具体的な計算方法を詳しく紹介し、それぞれの特徴や注意点を解説します。
お住まいの地域の制度を正しく理解することで、効果的な対策を立てることができるでしょう。
【東京都】内申点の計算方法
東京都では、中学3年生2学期(または後期中間)までの成績のみを内申点として使用する制度になっています。東京都の内申点には「素内申」と「換算内申」の2種類があり、それぞれ異なる入試で使用されることが特徴です。
「素内申」とは、9教科(主要5教科と実技4教科)の評定をそのまま合計した数値で、満点は45点となります。これは主に推薦入試で使用されます。
一方「換算内申」は、主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)はそのまま合計し、実技4教科(音楽・美術・技術家庭・保健体育)は2倍にして計算する方式で、満点は65点となります。
たとえば、すべての教科で評定「3」を取った場合の換算内申は、主要5教科が15点(5教科×3点)、実技4教科が24点(4教科×3点×2倍)となり、合計39点となります。
都立高校の一般入試では、換算内申が300点満点に換算され、学力検査700点との合計1000点で合否が判定されます。内申点の配点比率は約3割となるため、日常の学習成果が入試結果に大きく影響することになります。
出典:東京都教育委員会「令和7年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」
【神奈川県】内申点の計算方法
神奈川県では、中学2年生と中学3年生の2年間の成績が内申点の対象となります。中学2年生の学年末9教科の評定をそのまま合計し、中学3年生の9教科の評定を2倍して合計する方式で、満点は135点となっています。
計算方法を具体例で説明すると、中学2年生でオール「3」、中学3年生でオール「4」だった場合、「2年生:27点(9教科×3点)+3年生:72点(9教科×4点×2倍)=合計99点」となります。この制度により、中学3年生の成績がより重視される仕組みになっています。
神奈川県の公立高校入試では、第1次選考で定員の90%、第2次選考で残りの10%を選抜します。
第1次選考では、内申点・学力検査・面接の結果を各高校が定めた比率で合算して判定され、多くの高校では「内申点4:学力検査4:面接2」の比率を採用しています。
特色検査を実施する高校では、「内申点3:学力検査5:面接1:特色検査1」のような配分になる場合もあります。
出典:神奈川県教育員会「令和8年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」
【埼玉県】内申点の計算方法
埼玉県では、中学1・2・3年生すべての成績が内申点の対象となります。各学年の9教科を5段階で評価し、3年間合計で135点満点(各学年45点×3学年)となる制度です。
ただし、多くの高校では中学3年生の成績により大きな重みをかける傾向があります。
埼玉県の公立高校入試では、学力検査500点満点と内申点を合算して総合得点で合否を判定します。内申点と学力検査の比率は原則として「学力検査:内申点=6:4」または「7:3」が一般的ですが、学校によって若干の違いがあります。
また、一部の学校では面接や実技検査が加わる場合もあります。
出典:埼玉県教育員会「令和8年度入学者選抜実施要項」
【大阪府】内申点の計算方法
大阪府では、原則として中学3年生の成績を内申点として使用しますが、特徴的なのは中学1・2年生の成績も段階的に重みをかけて計算することです。
中学1年生は2倍、中学2年生は2倍、中学3年生は6倍という比率で計算され、合計450点満点という他府県とは異なる大きな配点となっています。
大阪府の公立高校入試では、この内申点と学力検査を合算して合否を判定します。内申点の配点が非常に大きいため、日常の学習態度や定期テストの結果が合否に大きく影響する制度といえるでしょう。
普通科では「学力検査630点+内申点270点」のような配分が一般的ですが、学科によって比率が異なります。
出典:大阪府教育員会「令和8年度入学者選抜実施要項」
【兵庫県】内申点の計算方法
兵庫県では、中学3年生の成績のみを内申点として使用しますが、実技4教科により大きな重みをかけることが特徴です。
主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)は4倍、実技4教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)は7.5倍で計算され、合計250点満点となります。
この制度により、実技教科の重要性が非常に高く、主要5教科だけでなく実技教科にもバランス良く取り組むことが重要になります。
調査書点と学力検査点の比率は「学力検査:調査書=1:1」が目安とされており、特色選抜では面接や作文が加わる場合もあります。
出典:兵庫県教育員会「令和7年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱」
【奈良県】内申点の計算方法
奈良県では、中学3年生の評定を基本としつつ、2026年度入試からは制度変更が予定されています。新制度では中1・中2は「主体的に学習に取り組む態度」の3段階評価×9教科(27点満点×2年=54点)、中3は5段階評定×9教科×2倍(90点満点)で計算し、合計144点満点とされる予定です。
現行制度では、学力検査との比率は「学力検査:内申点=3:1」が一般的ですが、学校や学科によっては「2:1」などの比率が採用されることもあります。
制度変更により評価方法が大きく変わるため、受験予定の方は奈良県教育委員会の最新情報を定期的に確認することをおすすめします。
出典:奈良県教育員会「令和8年度奈良県立高等学校入学者選抜概要」
内申点を上げるために気を付けたいポイント

内申点を効果的に上げるためには、文部科学省が定める学習評価の3つの観点を理解し、それぞれに適した対策を講じることが重要です。単なるテスト対策だけでなく、日ごろの学習姿勢や取り組み方法について具体的に解説します。
- 定期テストを重視する
- 授業態度や提出物も評価対象
- 日々の積み重ねが結果を左右する
定期テストを重視する
定期テストの結果は評定に直結するため、内申点対策としてもっとも重要な要素のひとつです。文部科学省の学習評価に関する指針では、「知識・技能」の観点で主にテストの成績が評価されることが示されており、この部分が内申点に大きく影響します。
計画的に学習し、弱点科目は早めに補強することで定期テストで安定した成績を目指すことができます。テスト直前だけでなく、普段から授業ノートを整理し、小テストも大切にすることが重要です。
とくに、各教科で実施される小テストも評価の対象となるため、日頃の授業内容をしっかりと理解し、定着を図ることが求められます。
定期テストの準備においては、出題範囲を確実に把握し、教科書や授業プリント、ワークブックなどを活用して総合的な復習をおこなうことが効果的です。
また、過去の定期テストの傾向を分析し、重要なポイントを重点的に学習することで、効率的な対策が可能になるでしょう。
授業態度や提出物も評価対象
学習指導要領に基づき、学習評価は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から総合的におこなわれています。なかでも「主体的に学習に取り組む態度」は授業中の積極的な姿勢や提出物の状況を指し、評定に大きく影響します。
忘れ物をしない、期限を守る、授業で積極的に発言するといった基本的な行動が内申点に反映されるため、家庭での声かけも効果的です。また、提出物については、単に提出するだけでなく、丁寧に仕上げることも評価のポイントとなります。
文部科学省の指針では、「主体的に学習に取り組む態度」について、単なる挙手の回数や表面的な行動ではなく、よりよく学ぼうとする意欲を持って学習に取り組む態度を評価することが強調されています
そのため、授業中の質問や発言、課題に対する取り組み姿勢などが重要な評価要素となるのです。
日々の積み重ねが結果を左右する
内申点は一夜漬けで改善できるものではありません。文部科学省の学習評価に関する方針では、児童生徒の学習状況を継続的に把握し、「前の学びからどのように成長しているか、より深い学びに向かっているかどうかを捉えていく」ことの重要性が示されています。
小テスト、宿題、授業態度といった日常的な取り組みの積み重ねが、最終的な評定として内申点に反映されます。
とくに実技4教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)では、作品の完成度や実技の取り組み姿勢、授業への参加度などが総合的に評価されるため、すべての教科に対してバランス良く取り組むことが重要です。
また、中学校生活全般を通じて、学習に対する意欲や態度を持続させることが求められます。一時的な努力ではなく、継続的な学習習慣を身につけ、日々の授業を大切にする姿勢が、結果として高い内申点につながることになります。
学習内容の理解だけでなく、学習に向かう姿勢そのものが評価される仕組みを理解し、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵といえるでしょう。
内申点は高校受験の合否に大きく関わるため日ごろから対策しよう
内申点とは、日常の学校生活の努力を数値化したもので、高校受験の合否に大きな影響を与える重要な要素です。
文部科学省の入学者選抜実施要項に基づき、中学校での各教科の評定が点数化され、多くの公立高校では学力検査の結果と合算して総合的に合否が判定されます。
学力検査対策だけでなく、授業態度や提出物、定期テストへの取り組みも含めた総合的な対策が必要です
とくに平成29年の学習指導要領改訂により、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から評価がおこなわれるようになり、日常の学習姿勢がより重視されるようになりました。
内申点は一朝一夕で改善できるものではありませんが、継続的な努力により着実に向上させることができる要素でもあります。志望校の制度を早めに調べ、計画的に対策していくことが、お子さんの合格への近道となります。
※都道府県によって計算方法や対象学年が大きく異なるため、お住まいの地域の教育委員会が発行する最新の入学者選抜実施要項で詳細を確認することをおすすめします。
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。