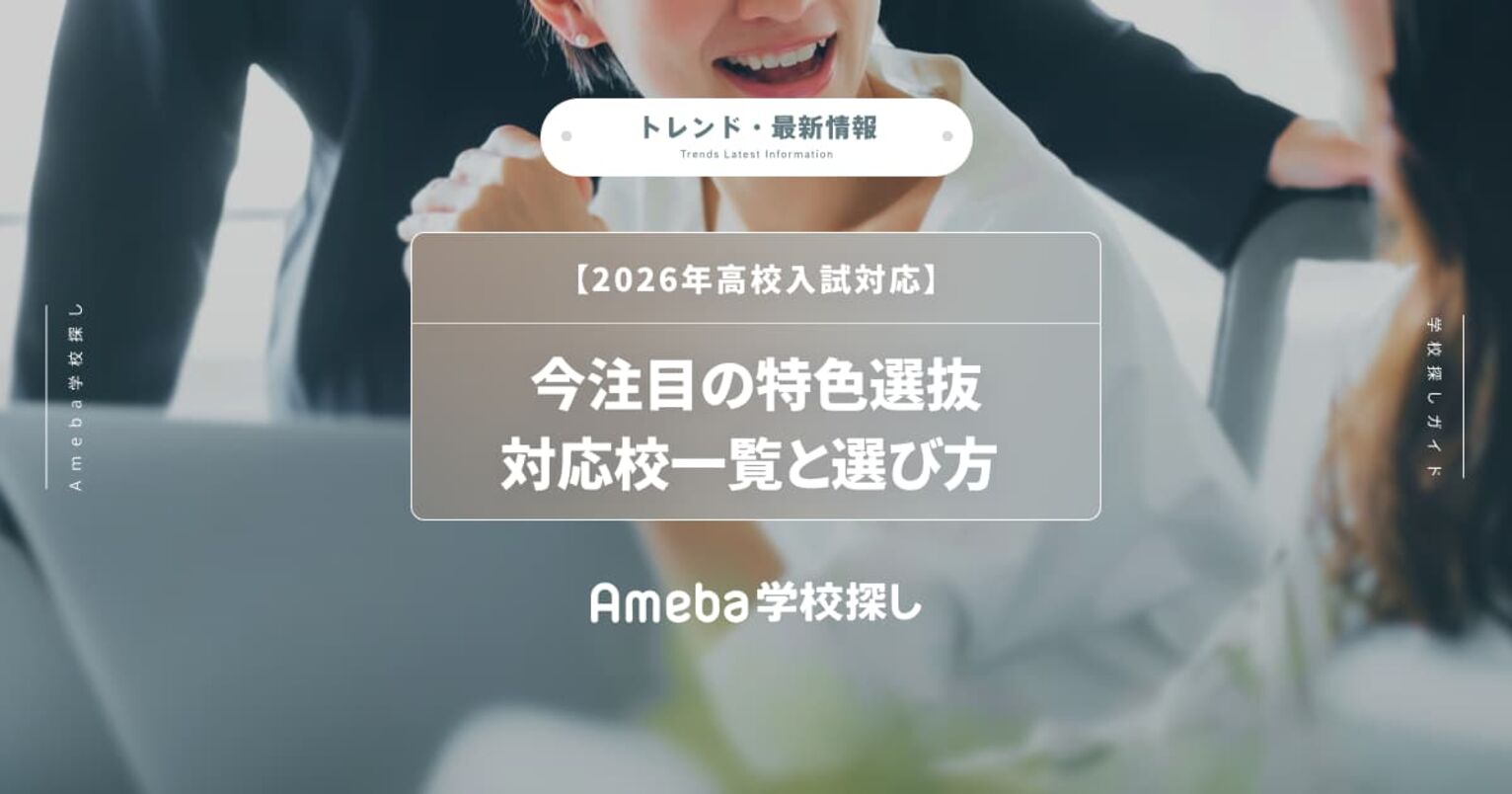2026年の高校入試では、これまでの学力検査だけでなく、思考力・表現力・主体性を評価する「特色選抜」を取り入れる学校が増えてきています。
特色選抜は、テストの点数だけでは測れないお子さんの個性や得意分野を活かせる絶好のチャンスです。ただし、地域や学校によって実施方法や評価のポイントが大きく異なるため、事前にしっかりと情報を集めておくことが大切になります。
本記事では、2026年入試で注目を集める特色選抜対応校をまとめて紹介するとともに、お子さんにぴったりの学校を選ぶためのポイントをわかりやすく解説します。
特色選抜とは?制度の基本を理解しよう
特色選抜は、従来の学力検査だけでは測れない受験生の多面的な能力を評価する入試制度です。
2026年度の高校入試においても、この制度を導入する学校が全国的に増加しており、お子さんの個性や得意分野を活かす新たな進路選択の機会として注目されています。
学力検査だけではない多面的評価
文部科学省の「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」において、多面的な評価の重要性が議論されており、この方針は高校入試にも反映されています。
特色選抜では、従来の学力検査に加えて、面接、作文、小論文、実技検査、プレゼンテーションなど多様な評価方法を組み合わせて実施されます。
学校推薦型選抜における評価方法の改善として、調査書などの出願書類だけでなく、各学校が実施する評価方法(小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテストなど)による評価が重視される方向性が示されており、高校入試においても同様の考え方が採用されています。
具体的には、暗記中心の知識を問う従来の試験とは異なり、与えられた課題に対して論理的に思考し、自分なりの解決策を提示する能力や、他者との協働において適切にコミュニケーションを図る能力などが評価されます。
これにより、学力だけでは測れない生徒の潜在的な可能性や人間性を発見することが可能になります。
導入の背景と目的
特色選抜導入の背景には、社会で求められる人材像の変化があります。
これからの社会では、AI技術の発達により定型的な作業は自動化される一方で、創造性、課題解決能力、コミュニケーション能力といった人間ならではの能力がより重要視されるようになっています。
また、中学生が偏差値だけで志望校を選ぶのではなく、各高校の教育方針や特色を理解した上で、自分の将来の目標や興味関心にあった学校を主体的に選択することを促す目的もあります。
これにより、入学後のミスマッチを防ぎ、より充実した高校生活を送ることができると期待されています。
各都道府県で入試制度は異なりますが、2026年度入試でも制度変更が予定されており、特色選抜の導入拡大もその一環として位置づけられています。
なお、埼玉県では2027年度の学力検査から、面接試験と特色試験が実施される予定であり、このような制度変更は全国的な傾向となっています。
【2026年高校入試対応】特色選抜対応校の一覧
2026年度の高校入試において、特色選抜を実施する学校は全国的に増加傾向にあります。地域ごとに制度の名称や実施方法は異なりますが、学力検査だけでは測れない生徒の多面的な能力を評価するという基本的な考え方は共通しています。
ここでは、主要地域での特色選抜対応校について、各校の特色ある取り組みとともに詳しくご紹介します。
【2026年高校入試対応】特色選抜対応校の一覧
2026年度の高校入試において、特色選抜を実施する学校は全国的に増加傾向にあります。地域ごとに制度の名称や実施方法は異なりますが、学力検査だけでは測れない生徒の多面的な能力を評価するという基本的な考え方は共通しています。
ここでは、主要地域での特色選抜対応校について、各校の特色ある取り組みとともに詳しくご紹介します。
東京都の注目校
東京都では令和8年度入学者選抜において、推薦に基づく選抜が実施されます。実施日は令和8年1月26日(月)・27日(火)で、合格発表日は令和8年2月2日(月)となっています。東京都の推薦入試は特色選抜の機能を果たしており、多様な評価方法が採用されています。
東京都立国際高校をはじめとする国際系学科では、グローバル人材育成のため英語面接や英語でのプレゼンテーションが実施されています。とくに都立国際高校の国際バカロレアコースでは入学者選抜も同様の日程で実施される予定で、国際的な視野を持つ生徒の育成に力を入れています。
理数系専門学科を持つ東京都立科学技術高校では、理数等特別推薦として科学分野の研究レポートに基づく口頭試問を実施しています。
この方式により、単純な知識の暗記力ではなく、探究心や論理的思考力、研究に対する真摯な取り組み姿勢が評価される仕組みとなっています。
晴海総合高校、つばさ総合高校、杉並総合高校、世田谷総合高校、町田総合高校、王子総合高校などの総合学科設置校では、生徒一人ひとりの多様な興味関心に対応するため、小論文や面接を中心とした選考をおこなっています。
これらの検査では、とくに将来への明確な目標意識と学習に対する強い意欲が重視されるポイントとなっています。
神奈川県の注目校
神奈川県では、共通問題及び共通選択問題を用いた特色検査実施校として、横浜翠嵐高等学校、柏陽高等学校、湘南高等学校、厚木高等学校、川和高等学校、希望ケ丘高等学校、横浜平沼高等学校など計18校の県立高校が指定されています。
これらの学校のなかでも、横浜翠嵐高等学校や湘南高等学校などの学力向上進学重点校では、とくに高度な思考力を問う特色検査が実施されます。
共通問題では数学的思考力や科学的分析力を、共通選択問題では人文・社会科学分野での論理的思考力や表現力を評価する内容となっており、大学入試改革を見据えた先進的な取り組みがおこなわれています。
これらの18校で組織する学力向上進学重点校連絡協議会では、グローバル時代に求められる資質・能力を育成し、国際社会で活躍するリーダーの養成に取り組んでいます。海外研修プログラムなども実施されており、単なる学力向上にとどまらない総合的な人材育成が図られています。
横浜国際高等学校では、国際バカロレアコースにおいて特色検査が実施され、国際的な視野と語学力を重視した選考がおこなわれています。
埼玉県・千葉県の注目校
埼玉県では、2027年度(令和9年度)の学力検査から、面接試験と特色試験が実施される予定です。令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の日程が公表されており、新制度導入に向けた準備が着実に進められています。
芸術総合高校では、音楽科・美術科・映像芸術科・舞台芸術科において、学力検査と調査書の加点に加えて、実技検査が実施されており、芸術への情熱と将来への明確な目標が評価されています。
千葉県では、「自己表現」を重視する学校設定検査を実施する高校が多く、2026年度入試では43校58学科で実施予定です。
幕張総合高校では総合学科の特色を活かし、生徒の多様な学習成果をプレゼンテーション形式で発表する「自己表現」検査が実施されており、コミュニケーション能力と創造性が重視されています。
関西圏の注目校
大阪府では、文理学科設置校の天王寺高校や大手前高校に加えて、一部専門学科やグローバル系学科でも特色選抜が実施されています。
グローバル系学科では、住吉高校の国際文化科、水都国際高校のグローバル探究科において、英語でのプレゼンテーションや異文化理解に関する論述問題が出題され、国際的な視野と語学力が重視されています。
専門学科では、大阪府教育委員会の実施要項により、工業に関する学科の一部(建築デザイン科、インテリアデザイン科、ビジュアルデザイン科など)、音楽科、美術科、体育に関する学科において特別選抜が実施され、各分野の専門性と創造性を評価する検査がおこなわれています。
兵庫県では、理数科や総合科学科を設置する学校でも複数志願選抜制度の下で特色検査が実施されています。
加古川東高校の理数科では、数学と理科の発展的内容に関する思考力検査が実施され、科学的探究力と論理的思考力が評価されています。また、小野高校の科学探求科でも、理数分野の課題解決能力を問う検査がおこなわれ、将来の科学技術人材としての資質が重視されています。
奈良県では、奈良高校・郡山高校・高田高校・畝傍高校といった「進学教育重点校」をはじめ、作文や面接を課す学校があります。
特色選抜を実施する専門学科や総合学科、普通科の一部コースにおいて、学力検査に加えて学校独自検査・面接・実技検査から各校が選択して実施しており、探究活動や課題解決能力を評価する傾向が強まっています。
これらの検査では、地域の課題を題材とした論述問題や、社会問題への提案力を問う面接が実施され、実社会で活躍できる人材の育成が重視されています。
特色選抜対応校を選ぶときのポイント
特色選抜対応校を選ぶ際には、お子さんの個性や能力、将来の目標にあわせて慎重に検討することが重要です。
単に偏差値や知名度だけで判断するのではなく、学校の教育方針や選抜方法が、お子さんの特性と合致しているかを多角的に判断する必要があります。
子どもの適性を重視する
文部科学省が示す学力の3要素「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」のうち、特色選抜ではとくに思考力・判断力・表現力が重視されます。そのため、論理的に物事を考えることが得意で、自分の意見を明確に表現できるお子さんに適しています。
思考力は、さまざまな資料から必要な情報を整理して自分の考えをまとめる過程や、社会的な事象から見出した課題を多面的・多角的に考察する過程、自然の事象を目的意識を持って観察・実験し科学的に探究する過程などを通じて育まれます。
こうした探究的な学習活動に興味を持ち、積極的に取り組めるお子さんは、特色選抜での評価が期待できるでしょう。
一方で、決められた問題を正確に解く能力に長けているお子さんや、集中して知識を蓄積することが得意なお子さんの場合は、従来の学力検査を重視する一般入試のほうが力を発揮しやすい場合もあります。
お子さんの学習スタイルや得意分野を客観的に把握し、それに適した選抜方法を選択することが重要です。
学力検査との比率も考慮する
特色選抜を実施する学校でも、学力検査と特色検査の配点比率は学校によって大きく異なります。学力検査を重視する「学力重視型」から、特色検査の配点を高く設定する「多面的評価重視型」までさまざまなパターンがあります。
文部科学省では、基礎的・基本的な知識・技能の習得と、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成を両輪として重視しています。
そのため、どちらか一方だけに偏るのではなく、バランスの取れた学習が求められています。学力検査の配点が高い学校を選ぶ場合は、特色検査の対策に加えて従来の学力向上にも継続的に取り組む必要があります。
逆に、特色検査の配点が高い学校では、面接や小論文、実技検査などの対策により多くの時間を割く必要があります。お子さんの現在の学力レベルと今後の学習計画を考慮して、最適な配点比率の学校を選択しましょう。
学校の実施内容を確認する
同じ特色選抜でも、学校や学科によって実施される検査の内容は大きく異なります。作文重視、面接重視、小論文重視、実技重視など、各校の教育方針や求める生徒像に応じて多様な評価方法が採用されています。
各教科で育まれた力を、実社会のさまざまな場面で活用できる汎用的な能力に育てていくためには、各教科間の内容事項についての相互の関連付けや、教科横断的な学びをおこなう「総合的な学習の時間」などの取り組みが重要とされています。
そのため、特色選抜では単一教科の知識だけでなく、複数の分野を関連付けて考える能力が求められることが多くなっています。
志望校の特色検査の具体的な実施内容については、各校の公式サイトや募集要項で詳細に公表されています。過去の検査問題や面接の観点、評価基準なども可能な限り確認し、お子さんが準備すべき内容を早めに把握することが大切です。
また、学校説明会や体験入学などの機会を活用して、実際の教育活動を見学し、学校の雰囲気や教育方針を直接確認することをおすすめします。
特色選抜に向けた対策や準備するポイント
特色選抜で合格するためには、従来の暗記中心の学習だけでなく、思考力・判断力・表現力を育成する準備が必要です。
2026年度入試に向けて、お子さんの能力を効果的に伸ばすための具体的な対策と準備のポイントを紹介します。
作文・小論文の練習
特色選抜では、作文や小論文が重要な評価要素となっており、文部科学省の言語活動の充実に関する指導方針では、「自らの考えを深め、他者とコミュニケーションをおこなうために言語を運用するのに必要な能力」の育成が重視されています。
論理的思考力と表現力を身につけるためには、日常的な言語活動の充実が欠かせません。
作文・小論文対策として、まず新聞記事や時事問題を題材にした要約練習から始めることをおすすめします。与えられた文章の要点を整理し、自分の言葉で表現する能力は、特色選抜で求められる重要なスキルです。
文部科学省の指導事例でも、各教科で習得すべき学習の基本語彙を整理して明確にし、論理や情緒に関する語彙を豊かに身につけることが思考力を高めることにつながるとされています。
なお、東京都教育委員会では、過去の推薦入試で実施された小論文・作文のテーマを公表しており、これらは特色選抜の対策にも活用できます。
テーマは「持続可能な社会」「多様性と共生」「科学技術と人間」など現代社会の課題を扱ったものが多く、普段から社会問題に関心を持ち、自分なりの考えを持つことが重要です。
面接対策
面接は、受験生の人間性や学習意欲、主体性を評価する重要な機会です。文部科学省の方針では、知的活動(論理や思考)等の基盤といった言語の果たす役割を踏まえて、言語活動を充実することが求められており、面接はその実践の場となります。
面接対策の基本は、自己PRと志望動機を明確に言語化することです。「なぜその高校を志望するのか」「高校でどのような学習をしたいのか」「将来の目標は何か」といった質問に対して、具体的な根拠とともに論理的に答えられるよう準備しましょう。
文部科学省では、思考・判断したことを説明、論述、討論等といった言語活動等を通じて表現する能力の重要性を指摘しており、面接はまさにこの能力を発揮する場面です。
また、模擬面接を通じて実際に話す練習を重ねることも重要です。家族や先生との対話を通じて、自分の考えを相手にわかりやすく伝える技術を磨きましょう。
神奈川県の特色検査では面接も実施されており、調査書や学力検査では測りとることが難しい総合的な資質・能力や特性などを評価する重要な要素となっています。
探究活動や部活動経験を活かす
特色選抜では、中学校での探究活動や部活動での経験が高く評価される傾向があります。
文部科学省では、各教科間の内容事項についての相互の関連付けや、教科横断的な学びをおこなう「総合的な学習の時間」などの取組が重要とされており、これらの学習経験は特色選抜で大きなアピールポイントとなります。
探究活動については、テーマ設定から調査・分析、まとめ・発表まで一連のプロセスを通じて身につけた能力を具体的に説明できるよう整理しておきましょう。
「どのような課題を見つけたのか」「どのような方法で調査したのか」「どのような結論に至ったのか」「その学びをどう活かしたいのか」といった観点から振り返ることが大切です。
部活動経験についても、単に「頑張った」という抽象的な表現ではなく、「チームワークを重視し、後輩指導を通じてリーダーシップを発揮した」「技術向上のために独自の練習方法を考案し実践した」など、具体的な行動と成果を言語化できるよう準備しましょう。
これらの経験は、文部科学省が重視する「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な証明となります。
特色選抜は子どもの強みや特性を活かせる高校を選ぼう
特色選抜は、学力だけでなく多面的な力を評価する入試方式であり、2026年入試では対応校がさらに拡大すると見込まれています。
従来の偏差値中心の選択から、お子さんの個性や得意分野を活かした進路選択の時代へと変化しています。早めに対応校の情報を把握し、お子さんの適性や強みを生かせる選択肢を検討することが大切です。
各都道府県で実施される特色選抜は、面接、作文、実技検査、自己表現など多様な評価方法を通じて、生徒の潜在的な可能性を発見する機会となっています。
学力検査対策に加え、作文や面接などの準備を積み重ねることで、合格の可能性が広がります。とくに、中学校での探究活動や部活動での経験、将来への明確な目標意識は、特色選抜において高く評価される要素となります。
お子さんの個性と可能性を最大限に発揮できる高校選びのため、各学校の教育方針や特色検査の内容を詳しく調べ、学校説明会や体験入学にも積極的に参加してみてください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。