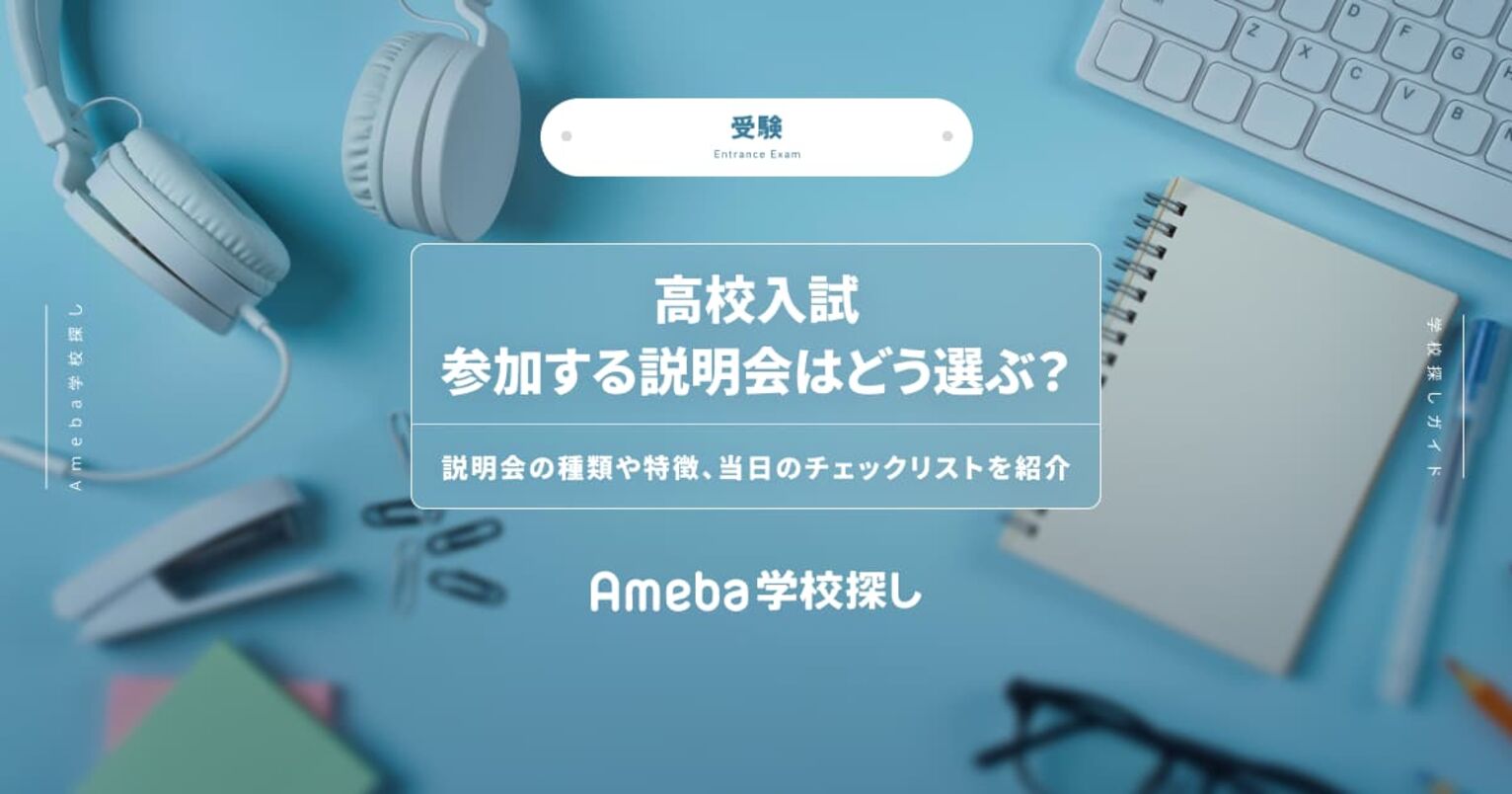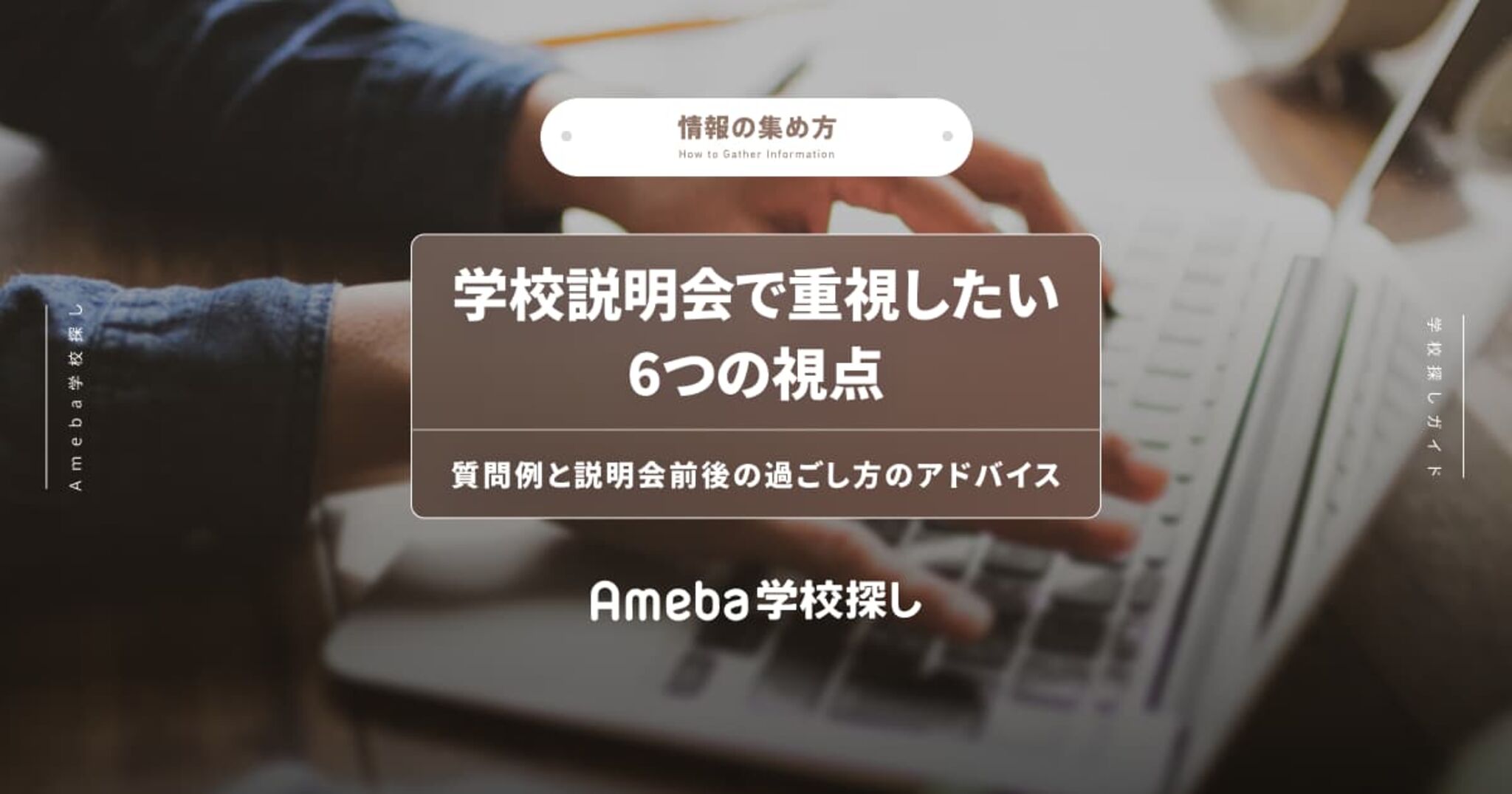高校入試を控えたご家庭では、「どの学校説明会に参加すればよいのか」「種類ごとの違いがわからない」と悩む方もいるでしょう。
学校が独自に実施する説明会、授業や部活動を体験できるオープンスクール、複数校を比較できる合同形式のイベントなど、内容や得られる情報はそれぞれ異なります。限られた時間の中で効率よく参加するためには、早めに計画を立て、志望校選びの軸を整理しておくことが大切です。
説明会の特徴を把握し、準備のステップや当日の確認ポイントを押さえておけば、学校選びに納得感を持てるだけでなく、お子さんの進路に対して安心して判断できるようになります。
高校の説明会の種類と特徴

高校の説明会といっても、学校が主催するものだけではありません。合同説明会やオープンスクール、個別相談会など複数の形式があり、それぞれで得られる情報や体験の質が異なります。違いを理解しておくことで、目的に応じた説明会に効率よく参加できるようになります。
- 学校主催:教育方針・校風・入試制度など詳細を把握できる
- 合同説明会:複数校を短時間で比較できる
- オープンスクール:授業や部活動を体験できる
- 個別相談会:成績や内申を踏まえた具体的な相談が可能
たとえば、志望校がまだ定まっていない場合は合同説明会で幅広く情報を集め、気になる学校が見つかったら学校主催の説明会で詳しく確認します。
さらに、お子さんが実際の授業や部活動に触れて「自分にあうかどうか」を体感できるのはオープンスクールならではの利点です。そして最終的に、出願や併願を決める段階で個別相談会を活用すると、より具体的な受験準備が進めやすくなります。
このように、説明会は種類によって役割が異なり、受験の進み具合に応じて使い分けることが重要です。
説明会に参加する計画の立て方
高校説明会は、行き当たりばったりで参加するのではなく、あらかじめ計画を立てて臨むことで限られた時間を最大限に活用できます。
どの学校の説明会に出るのかを整理し、志望校を決めるまでの流れを意識して参加すれば、情報を無駄なく集められるだけでなく、比較検討もしやすくなります。準備を整えておけば、後から振り返るときにも判断基準が明確になり、候補校を絞り込む際に大いに役立つでしょう。
- ① 学校選びの軸・方針を定める
- ② 候補となる学校をリストアップする
- ③ 説明会に参加するスケジュールを立てる
学校選びの軸・方針を定める
高校説明会に参加する前に、まず整理しておきたいのが「学校を選ぶ基準」です。判断の軸を持たずに説明会へ行くと、どの学校も魅力的に見えてしまい、かえって迷ってしまうことがあります。あらかじめ方針を固めておけば、限られた時間のなかで確認すべき点を効率よくチェックできます。
- 学力レベル(子どもの成績に見合うか、挑戦校にするか)
- 通学時間(毎日の負担にならないか)
- 普通科か専門学科か(将来の進路とのつながり)
- 大学進学指導の方針(国公立重視か、推薦枠が豊富か)
- 校風(自由な校風か、規律を重んじるか)
- 部活動(取り組みたい競技や文化活動があるか)
- 施設・設備(図書館やグラウンド、ICT環境など)
これらの条件は家庭によって優先度が異なります。たとえば、大学進学を強く意識する家庭では進学実績や指導体制を重視するでしょう。一方で、子ども本人の学校生活の充実を第一に考える場合は、部活動や校風を中心に判断することもあります。
重要なのは、こうした要素を保護者の視点だけで決めるのではなく、子ども自身の意見を聞きながら一緒に優先順位をつけることです。進学後の3年間を安心して過ごすためにも、事前に「自分たちはどんな学校を望んでいるのか」を共有しておくことが、説明会を有意義に活用する第一歩になります。
候補となる学校をリストアップする
学校選びの基準を定めたら、次は候補校をリストアップしていきます。すべての説明会に参加する必要はなく、段階や目的に合わせて優先順位をつけることが大切です。ここでのポイントは「広く集めてから絞り込む」ことです。最初から数校に限定してしまうと比較の幅が狭まり、思わぬ選択肢を逃す可能性があります。
代表的なケースごとに、適した説明会を整理すると次のようになります。
- 志望度が高い:学校主催+個別相談会
入試制度や進学実績を詳しく確認できる
- 志望校が未定:合同説明会
複数校を一度に比較し、候補を広げられる
- 適性・雰囲気重視:オープンスクール
授業や部活動を体験し、校風を感じ取れる
- 保護者の理解を深めたい:学校主催説明会
教育方針や学校の姿勢をしっかり把握できる
候補を出す段階では、まず合同説明会やオープンスクールに参加して学校の雰囲気や全体像を知るのがおすすめです。そのうえで、志望度が高まった学校には学校主催の説明会や個別相談会に参加し、具体的な情報を深掘りすると効率的です。
こうした流れを意識すれば、候補校を無理なく整理でき、説明会の参加に優先順位をつけやすくなります。
説明会に参加するスケジュールを立てる
候補校をリストアップしたら、次は年間の受験スケジュールに合わせて説明会の予定を組み立てていきます。内申点の確定や模試、出願時期など大きな行事を意識しながら逆算して計画することが大切です。行き当たりばったりで参加してしまうと、肝心の学校を見逃す可能性があるため注意が必要です。
- 夏〜秋:合同説明会
幅広く候補校を知り、比較の材料を集める - 秋〜冬:学校主催説明会・個別相談会
志望校を絞り込み、具体的な出願準備に活用
スケジュールを立てるときは、模試の日程や部活動の予定も含めて家庭内のカレンダーにまとめておくと安心です。
また、人気のある学校の説明会や個別相談会は早めに予約が埋まるため、情報公開後すぐに申し込むよう意識しましょう。計画を前もって立てておくことで、受験準備を無理なく進められ、親子で落ち着いて学校選びができるようになります。
説明会に参加するときのポイント

説明会は単にパンフレットに載っている情報を補う場ではなく、実際に足を運ぶことでしかわからない学校の雰囲気や、先生方の姿勢を直接確かめられる貴重な機会です。生徒の様子や施設の雰囲気も含めて体感できるため、進学後の生活を具体的にイメージしやすくなります。
こうした機会を十分に活かすには、事前に確認したい観点を整理しておくことが大切です。準備をして臨めば、当日の限られた時間を有効に活用し、より多くの情報を持ち帰ることができるでしょう。
- お子さんと学校の相性を確認する
- 学校生活や部活動についても確認する
- 学校側の姿勢も確認する
- 当日のチェックリスト
お子さんと学校の相性を確認する
高校説明会では、成績や入試制度などの情報に目が行きがちですが、実際に通うのはお子さん自身です。したがって、学校との相性を確認することがとても大切です。説明会での先生方の話し方や在校生の雰囲気は、その学校の空気感を映し出しています。
保護者が「よい学校だ」と感じても、子どもが居心地の悪さを覚える場合もあります。反対に、校舎や授業の雰囲気が子どもの好奇心を刺激し、「ここで学びたい」と感じることも少なくありません。
相性を確認する際は、子どもがどう感じたかをしっかり聞き取り、家庭で共有することが欠かせません。高校生活は3年間と長く、学力だけでなく日常生活の快適さも大きな影響を与えます。説明会を「あうかどうかを見極める場」として意識すると、進学後のミスマッチを防ぎ、より納得感のある進路選びにつながります。
学校生活の雰囲気や部活動についても確認する
高校生活は勉強だけでなく、友人関係や部活動など日常の過ごし方によって充実度が大きく変わります。説明会は、こうした生活面を知る貴重な機会でもあります。学校全体の雰囲気や、生徒がどのように活動しているかを意識して見ることが大切です。
- □ 生徒の表情や会話から、学校全体の雰囲気を感じ取れるか
- □ 部活動の種類や活動実績、練習の雰囲気は子どもに合っているか
- □ 施設や設備が部活動にどの程度充実しているか
これらを事前にリストアップして参加すると、当日に見落としが少なくなります。とくに部活動は、入学後の学校生活の満足度に直結する要素のひとつです。説明会で得られる学習面の情報とあわせて、生活面の印象もきちんと記録しておくとよいでしょう。
学校側の姿勢や対応力も確認する
説明会では学校の教育方針や入試制度などの情報に目が向きがちですが、同じくらい大切なのが学校側の姿勢です。どれほど立派な方針を掲げていても、説明する先生やスタッフの態度に誠実さがなければ、実際の学校生活にも不安を感じてしまうものです。説明会は学校の「顔」が見える場であり、受験生や保護者に対する対応力を測る絶好の機会といえます。
- □ 質問に対して誠意をもって答えているか
- □ 説明内容がわかりやすく、整理されているか
- □ 生徒や保護者への接し方に温かさや安心感があるか
こうした観点をチェックしておくと、単にデータや実績だけではわからない「教師の人間的な魅力」を感じ取ることができます。
入学後は先生方と長く関わっていくため、対応力や人柄は子どもの学校生活に直結します。パンフレットやウェブサイトでは伝わらない部分を確かめるためにも、説明会の場で学校側の姿勢を見極めることは欠かせません。
当日のチェックリスト
高校説明会に参加する際は、限られた時間のなかで効率よく情報を集めることが大切です。そのためには、事前に確認したい項目をリスト化して持参すると安心です。漠然と話を聞くだけで終わらず、気づいたことをメモして比較できるようにしておきましょう。
- □ 全体説明:教育理念、進学実績、カリキュラム、入試基準
- □ 施設:教室やトイレの清潔さ、図書室の蔵書、体育館や食堂の環境
- □ 生徒の様子:挨拶や表情、服装、先生との距離感
- □ 通学:自宅からのアクセス、駅からの距離、周辺環境
- □ 個別相談:成績を踏まえた具体的な質問ができるか
これらを一通り確認しておけば、学校の表面的な情報だけでなく、日常生活や学習環境のリアルな部分まで把握できます。説明会当日は子どもが感じた印象も一緒に記録しておくと、後で複数校を比較するときに役立ちます。
高校説明会は候補を絞り参加スケジュールを立てよう
高校説明会は、学校の教育方針や進学実績だけでなく、校風や部活動の雰囲気を実際に確かめられる貴重な場です。パンフレットや数値データだけではわからない部分を体感することで、子どもにあう学校を見極めやすくなります。
種類ごとの特徴を理解し、参加する説明会を計画的に選ぶことが大切です。合同説明会で幅広く情報を集め、学校主催説明会や個別相談会で詳細を確認する流れを意識すると効率的です。さらにオープンスクールでは、授業や部活動を通して「ここで学びたい」と思えるかどうかを子ども自身が実感できます。
最終的な判断で重視すべきなのは、保護者の視点ではなく子どもの気持ちです。学校側の説明や施設面だけで決めるのではなく、実際に過ごす本人が安心して学べるかどうかを確認しましょう。親子で印象を共有しながら候補を絞っていけば、納得のいく学校選びにつながります。
計画を立てて積極的に説明会に参加することは、受験準備をスムーズに進めるだけでなく、高校生活をより充実させる第一歩となります。
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。