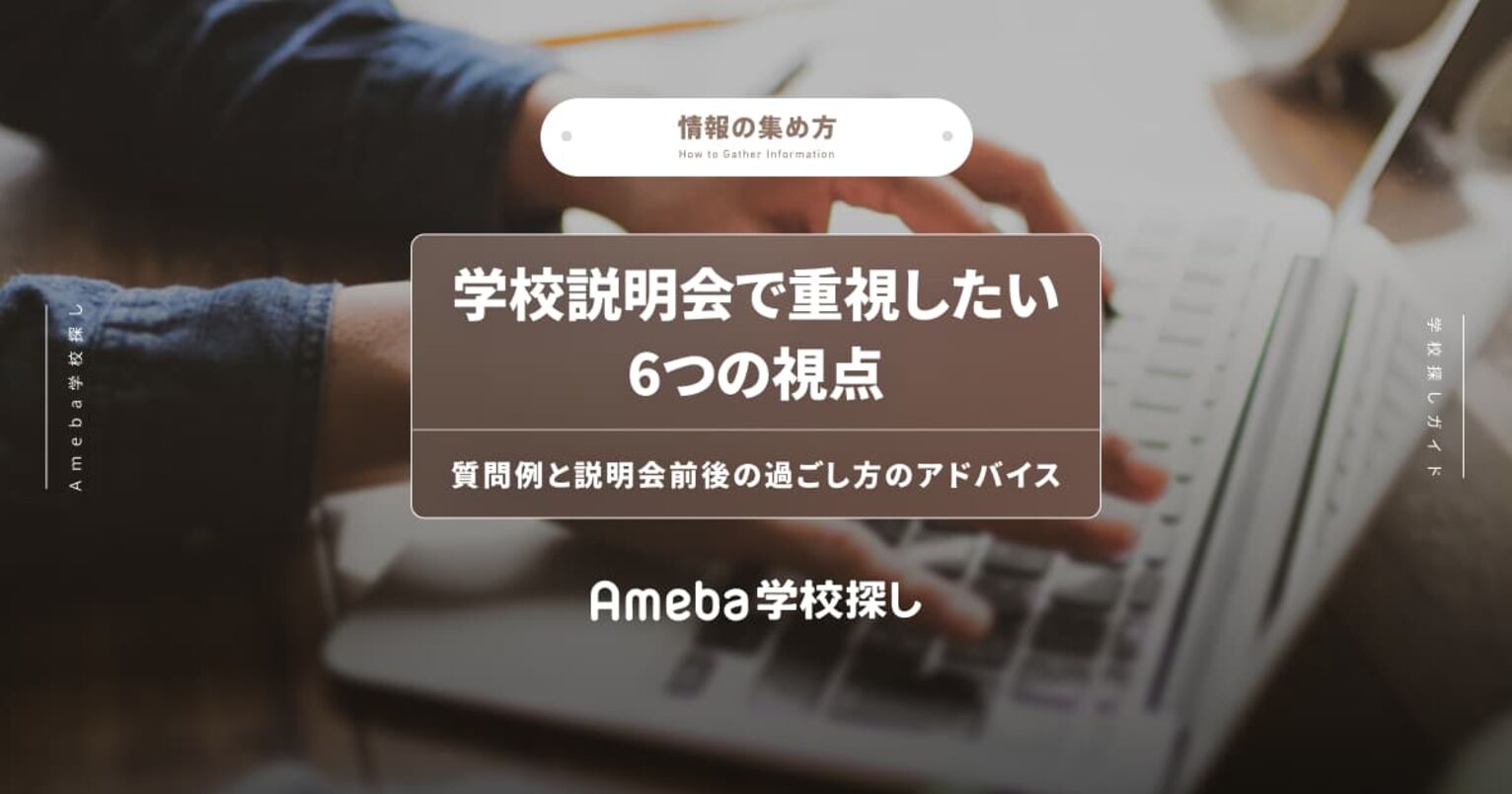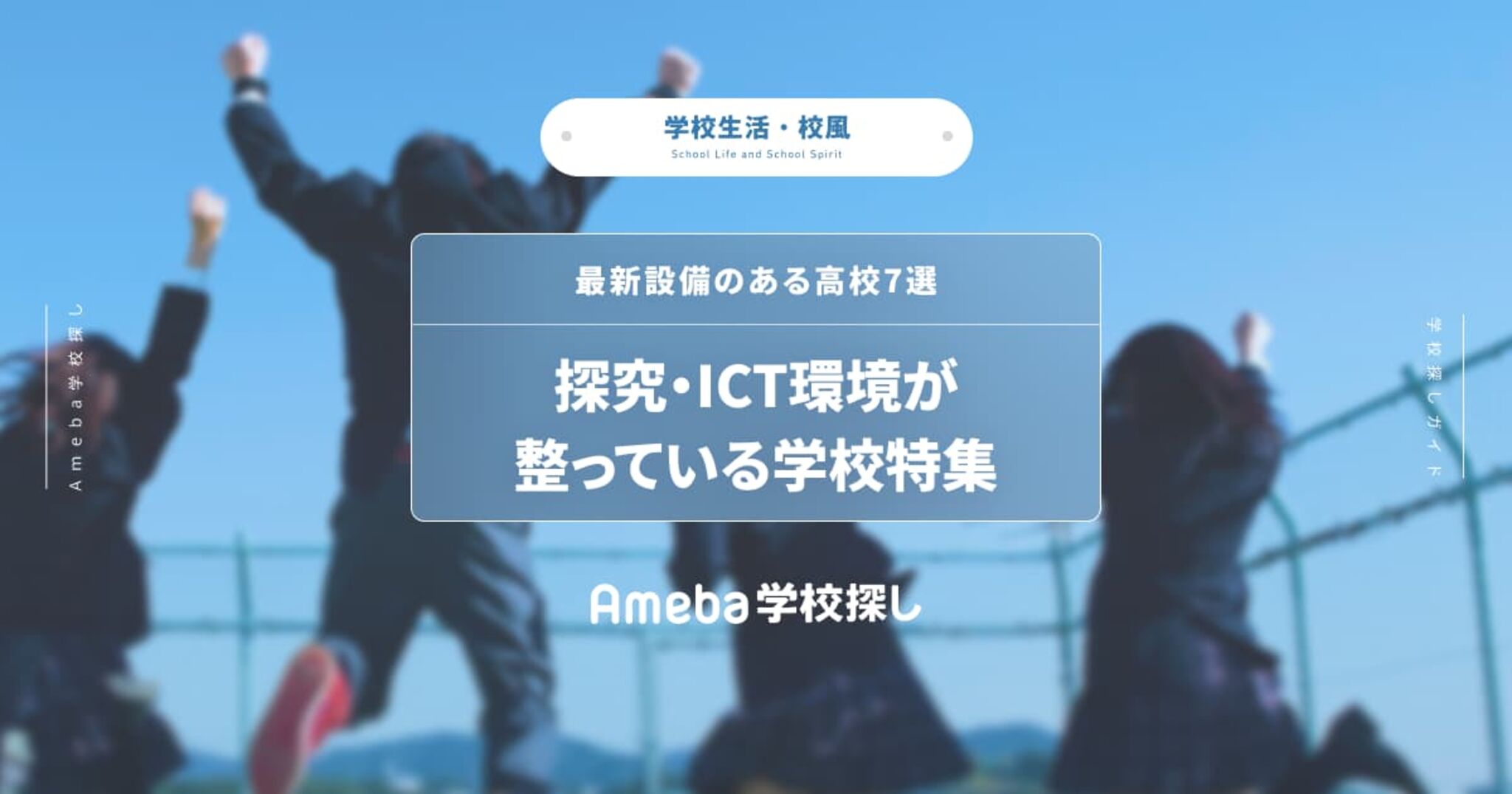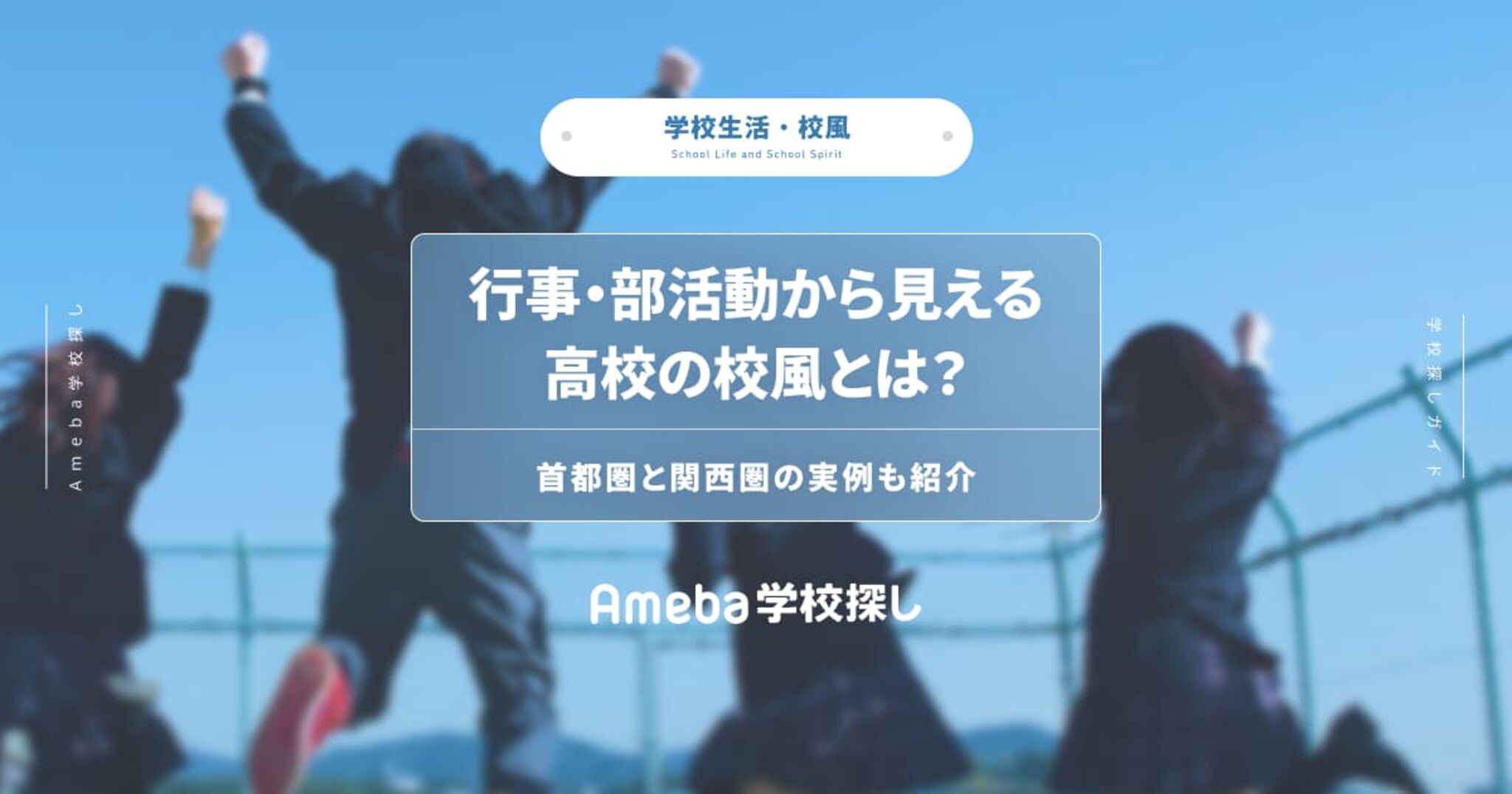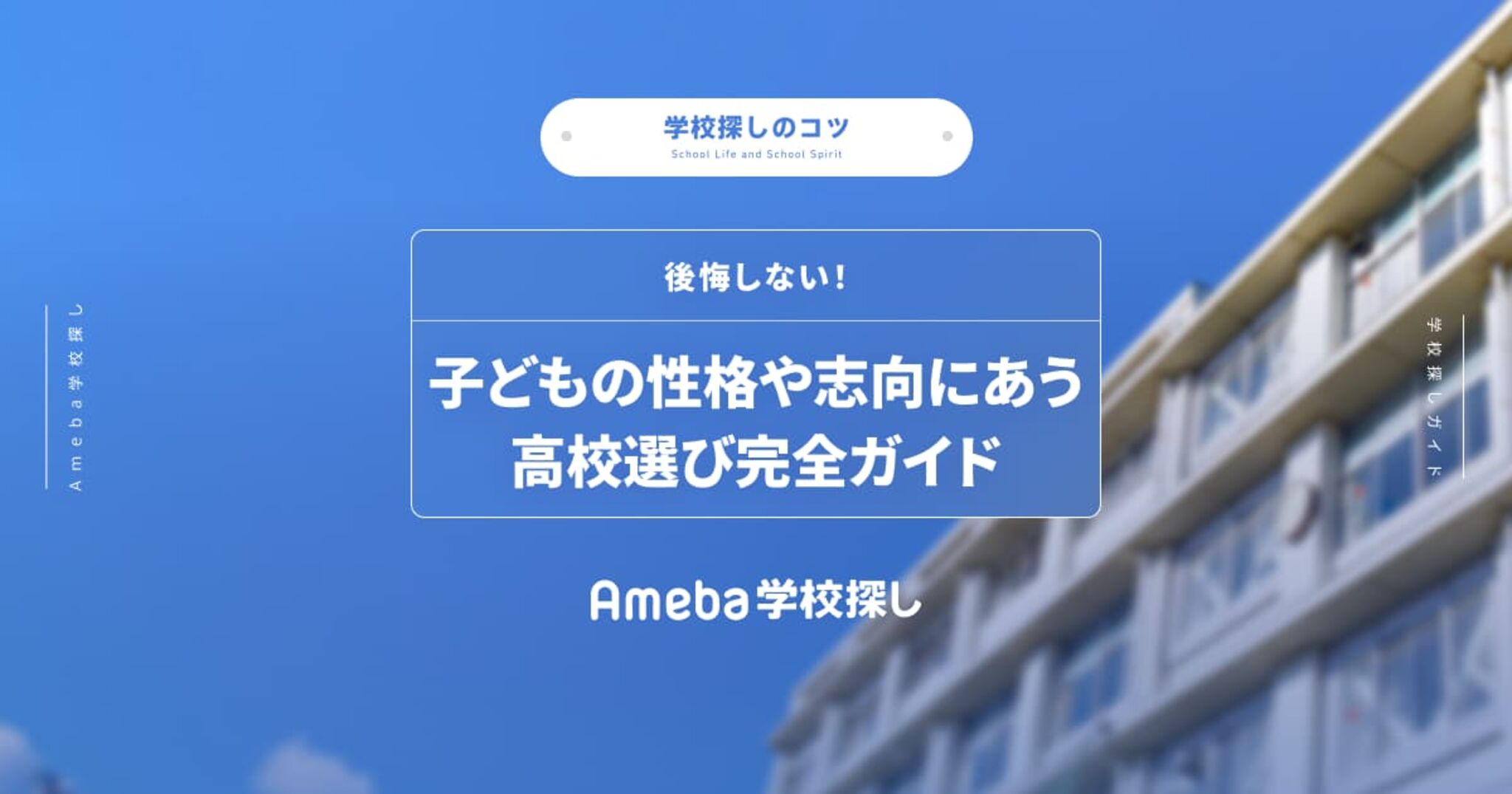お子さんにあう学校を選びたいけれど、「何を基準に判断すればいいのかわからない」と迷っていませんか。
学校説明会は、その答えを見つけるための大切な場です。学校の雰囲気、先生や在校生の様子など、パンフレットや公式サイトではわからない「日常の顔」に触れることができます。限られた時間を有意義にするためには、事前の準備や当日の視点がポイントになります。
この記事では、説明会前後に押さえておきたい行動や質問例をまとめましたので、お子さんにぴったりの学校を選ぶ参考にしてください。
学校説明会はなぜ重要?参加する意味を確認する

学校選びを進めるうえで、説明会への参加は欠かせないステップです。公式サイトなどで得られる情報は多くありますが、それだけでは学校のすべてを知ることはできません。
とくに学校の空気感や日常の雰囲気は、実際に訪れて初めて感じ取れるものです。学校説明会は、そうしたリアルな情報に触れる絶好の機会です。
また、先生や在校生の「生の声」を聞けることも大きなポイントです。教育方針や授業の進め方について、資料ではわからない現場の視点が見えてきます。生徒自身が学校生活をどう感じているかを知ることで、より明確
なイメージが持てるようになるでしょう。
さらに、保護者とお子さんが同じ場で話を聞くことにより、感じたことや気づきを自然に共有できます。家庭での進路の話し合いも、実体験に基づくものになるため、現実的で前向きな対話につながります。
資料だけでは見えてこないことを知るためにも、学校説明会にはぜひ足を運んでおきましょう。
【事前準備】情報収集と家庭内のすり合わせを忘れない
学校説明会は、先生や在校生と直接触れあえる数少ない機会です。しかし準備をせずに参加すると、話を聞くだけで終わってしまい、「なんとなく良さそう」といった曖昧な印象しか残らないこともあります。
有意義な時間にするためには、下調べをしたり、親子で意識を共有しておくことが重要です。
こうした準備を意識しておくだけで、説明会の見え方や気づきが大きく変わります。それぞれのポイントについて見ていきましょう。
学校の基本情報を調べる
説明会の前に、まずは公式サイトやパンフレットなどで基本的な情報を把握しておくことが大切です。
教育方針・コースの種類・1日のスケジュール・部活動など、あらかじめ確認できる内容を整理しておきましょう。また、入試情報・学費・通学手段・制服のデザインなども、しっかり確認しておくことが大切です。
当日は、基本情報を踏まえてより深い質問をしたり、実際の印象を確かめることができます。こうした事前の情報収集が、説明会を受け身で終わらせず、主体的に参加する姿勢にもつながっていきます。
どのような学校に通いたいのか家庭内で話し合う
学校の情報をリサーチした後は、ご家庭で改めて「何を重視して学校を選びたいのか」を話し合ってみましょう。
たとえば、学習指導のスタイルを重視するのか、部活動や学校行事の充実度を大切にするのかによって、視点は変わってきます。また、「一人ひとりにあわせた指導」「カリキュラムの幅広さ」など、具体的な希望を整理しておくことが大切です。
家庭内で方向性を共有しておけば、説明会での見学や質問の内容もぶれずに済みます。優先順位を明確にしておくことで、当日の印象をより的確に比較でき、参加後の振り返りにも役立ちます。
質問したい事柄を考える
説明会に参加する前に、「当日、何を聞きたいか」を整理しておくとよいでしょう。公式サイトだけではわからなかったことや、気になっていることをメモしておくと、慌てずに済みます。
たとえば、「授業以外で学習サポートは受けられますか?」といった質問は、実際の学校生活をイメージするのに役立ちます。
また、お子さんがどういう教育を受けたいかという視点から考えてみるのもおすすめです。たとえば、「海外で語学研修はありますか?」など、興味のある内容に深く踏み込んで聞いてみるとよいでしょう。
ほかにも、「いじめなどがあったときの対応はどうしていますか?」といった、不安を解消するための質問も大切です。率直な質問にはしっかり答えてくれる学校かどうかを見極めるひとつの判断材料にもなります。
質問を準備しておくことで、説明会をより有意義に活用でき、参加後の満足感も高まります。
【説明会当日】チェックするべき6つのポイント

説明会当日は、学校の雰囲気や考え方を直接感じ取れる貴重なチャンスです。限られた時間のなかで必要な情報をしっかり得るためには、「何を見たいか」「何を知りたいか」を意識しておくことが大切です。
たとえば、校長先生が語る教育方針は、学校全体の方向性や指導の特徴を知る大切なヒントになります。また、在校生の様子や校内の雰囲気を見れば、普段の生活をどんな空気感のなかで送っているのかが伝わってきます。
以下では、説明会当日にぜひチェックしておきたい6つのポイントをご紹介します。
説明会当日にチェックしたい6つのポイント
それぞれのポイントについて質問例も交えながら、当日にすぐ役立つ内容を解説していきます。気になることを事前に確認しておき、説明会の内容をより深く理解する機会にしていきましょう。
①教育方針・カリキュラム
学校がどんな教育を大切にしているかは、説明会でしっかり確認しておきたいポイントです。ここでは、当日チェックしておきたい視点と質問例をご紹介します。
教育理念が伝わってくるか
校長先生や担当の先生の話から、学校が大切にしている考え方が感じ取れるかどうかに注目してみましょう。また、先生の言葉や表情、在校生への接し方などから、教育理念が日常に根付いているかが伝わってきます。
授業の雰囲気はどうか
授業見学ができる場合は、積極的に参加しましょう。生徒が楽しそうに授業を受けているか、発言の様子や教室の雰囲気などから、学ぶ環境を肌で感じることができます。
特色あるプログラムがあるか
探究学習やICT教育、語学研修など、学校ごとに力を入れている取り組みに注目しましょう。プログラム内容と、それに取り組む生徒の姿を知ることで、学校の教育の方向性がよりはっきり見えてきます。
学習サポートは充実しているか
習熟度別の授業や補習・自習時間の確保、質問しやすい雰囲気があるかも大切な視点です。
「勉強についていけないときにどんなサポートがあるか」なども確認しておきましょう。
- 「探究学習では、どのようなテーマに取り組んでいますか?」
- 「英語はネイティブの先生がいらっしゃいますか?」
- 「学力に不安がある生徒には、どんなフォローをしていますか?」
②リアルな学校生活の様子
説明会では、資料だけではわからない学校の「日常」に触れることができます。とくに生徒や先生のふるまい、校内の雰囲気からは、リアルな学校生活が垣間見えますので注視してみましょう。
生徒の表情やあいさつから感じ取る
校内ですれ違う在校生の様子は、学校全体の雰囲気を知る手がかりになります。明るい表情で気持ちよく挨拶してくれるかどうかも、日頃の指導や人間関係の表れといえるでしょう。
先生と生徒の関係性はどうか
説明会では、先生と生徒が自然に言葉を交わしている場面が見られることもあります。距離が近すぎず遠すぎず、信頼関係が感じられると安心です。
校則が生活にどう影響しているか
服装や頭髪などの校則がどの程度あるか、それが日常生活のなかでどう運用されているかにも注目しましょう。生徒たちがのびのびとしているかを観察することで、学校の柔軟さや風通しのよさも見えてきます。
いじめへの対応が明確か
いじめが起こらないような雰囲気づくりはもちろん、もしものときの対応も重要です。「何かあったとき、どう対応するか」という基本的な流れについても把握しておくことが大切です。
- 「休み時間や放課後は、先生と気軽に話せますか?」
- 「学校内でスマートフォンは使用できますか?」
- 「いじめなどが発生した場合の対応について教えてください」
③進路指導や合格実績
高校や中高一貫校を選ぶうえで、進路指導の方針や実績は気になるポイントのひとつです。合格者数などの数字だけでなく、「どのような進路サポートがおこなわれているか」にも目を向けてみましょう。
実績の「中身」に注目する
難関大学の合格者数だけでなく、現役進学率や指定校推薦の枠、進学先の学部・学科の傾向などをチェックしましょう。どのような進路を選ぶ生徒が多いのかを見ることで、教育の方向性が見えてきます。
進路指導の体制は整っているか
大学進学に限らず、専門学校・看護や医療系の進路・就職など、多様な選択肢に対応している学校もあります。個別の面談体制や進路ガイダンスの機会など、支援の仕組みを確認してみてください。
- 「指定校推薦や総合型選抜に向けたサポートはありますか?」
- 「夏期講習や冬期講習などはありますか?」
- 「大学以外の進路を希望する生徒には、どのようなサポートがありますか?」
④学校の施設や設備の快適さ
毎日通う場所だからこそ、学校の施設や設備はとても大切です。学習環境によって勉強への取り組みやすさが変わりますし、生活空間の快適さも学校生活の満足度につながります。ぜひ細かいところまでチェックしてみましょう。
学習環境は整っているか
教室が明るく清潔か、机や椅子は使いやすいかを確認してみましょう。図書館の蔵書数や自習スペースの利用しやすさも、学習意欲に大きく関わります。
ICT環境は充実しているか
Wi-Fiが安定して利用できるか、一人一台の端末をどのように活用しているかを確認しましょう。オンライン授業や課題提出の方法など、実際の運用例を聞いてみると参考になります。
生活空間の使いやすさ
食堂のメニューや価格、利用しやすさは毎日の生活に直結します。また、トイレが清潔かどうかも意外と重要なチェックポイントです。
その他の施設や安全面
体育館やグラウンドの広さ、部活動に必要な設備が整っているかも確認しましょう。さらに、通学路の安全性や周辺環境についても見ておくと安心です。
- 「自習室や図書館は、放課後どのくらい利用できますか?」
- 「学校内に文具などを買える購買施設はありますか?」
- 「端末やWi-Fiは、授業でどのように活用されていますか?」
⑤学費
学校を選ぶ際には、学費の確認も大切です。授業料だけでなく、制服代・教材費・積立金・寄付金など、実際にはさまざまな費用がかかります。説明会では「総額」で考える視点を持ち、年間を通じてどのくらい必要になるのかを把握しておきましょう。
授業料以外にかかる費用を把握する
制服や教材の購入費、修学旅行の積立金などは、学校によって大きく差があります。あらかじめ確認しておくことで、後から思わぬ出費に驚くことを避けられます。
経済的なサポートの有無
奨学金や特待生制度、兄弟姉妹が通う場合の優遇措置などが用意されている学校もあります。利用条件や申請の流れを知っておくと、安心して進学を検討できます。
- 「授業料以外で、年間どのくらいの費用がかかりますか?」
- 「初年度にかかる費用はどのくらいですか?」
- 「奨学金や特待生制度はどのような条件で利用できますか?」
⑥部活動や課外活動
学校生活をより充実させる要素として、部活動や課外活動も欠かせません。勉強との両立が可能かどうか、活動内容や雰囲気がお子さんにあっているかを見極めてください。
部活動の雰囲気や両立のしやすさ
活動日数や時間などは、学校生活の満足度につながるポイントです。見学ができる場合は、生徒が楽しんで活動しているかを観察してみましょう。
通学を含めた生活リズムの確認
部活動や課外活動に取り組む場合、通学との両立も大切です。実際の通学時間帯に電車やバスの混雑具合を確かめておくと、日々の生活リズムをイメージしやすくなります。
学校行事の盛り上がり
文化祭や体育祭、修学旅行など、行事の内容には学校の個性が表れます。生徒自身が企画・運営している行事が多い学校では、主体性や協調性を育む経験につながります。
- 「部活動と勉強の両立について、先生はどのようにサポートされていますか?」
- 「文化祭などは受験生でも見学できますか?」
- 「学校行事は生徒がどのくらい企画や運営に関わっていますか?」
【説明会後】情報を整理して学校を比較する材料にする
説明会に参加しただけで終わらせてしまうと、せっかくの機会を活かせないまま、曖昧な記憶で終わってしまう可能性があります。当日感じたことや得られた情報を整理し、次の行動へつなげていくことが大切です。
ここでは、説明会後に取り組みたい4つのアクションをご紹介します。
説明会で得た情報を整理する
まずは、配布資料や自分で取ったメモを見返し、印象に残ったことを書き出しておくとよいでしょう。「よかった点」と「気になった点」を整理しておくと、後で検討する際に役立ちます。
ほかの学校と比較する
複数の学校に参加した場合、それぞれの良さや違いがわかりにくくなることがあります。同じ観点で比較すると、お子さんにふさわしい学校が見つけやすくなります。
次の行動を考える
「説明会に参加して終わり」ではなく、体験授業や個別相談など、次のイベントへの参加につなげてみましょう。気になる学校があれば、追加の説明会やオープンスクールに足を運ぶのもおすすめです。
志望校を選ぶ
整理と比較が終わったら、志望校を具体的に絞り込んでいきます。保護者とお子さんが同じ情報を共有しながら話し合うことで、納得のいく選択につながります。
学校説明会は「こだわり」を持って臨もう!
学校説明会は、単に情報を集めるだけの場ではありません。お子さんが将来通う学校を、保護者自身の目で確認できる貴重な機会です。
そのためには、事前に情報を集めて家庭で話し合い、当日チェックしたいポイントや質問を整理しておくことが大切です。また、説明会後には感じたことを振り返り、他校と比較して次のステップにつなげましょう。
「ここだけは大事にしたい」という視点を持ちながら参加することで、学校選びはより納得感のあるものになります。お子さんと一緒に学びの場を見極め、安心して進学への一歩を踏み出してくださいね。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。