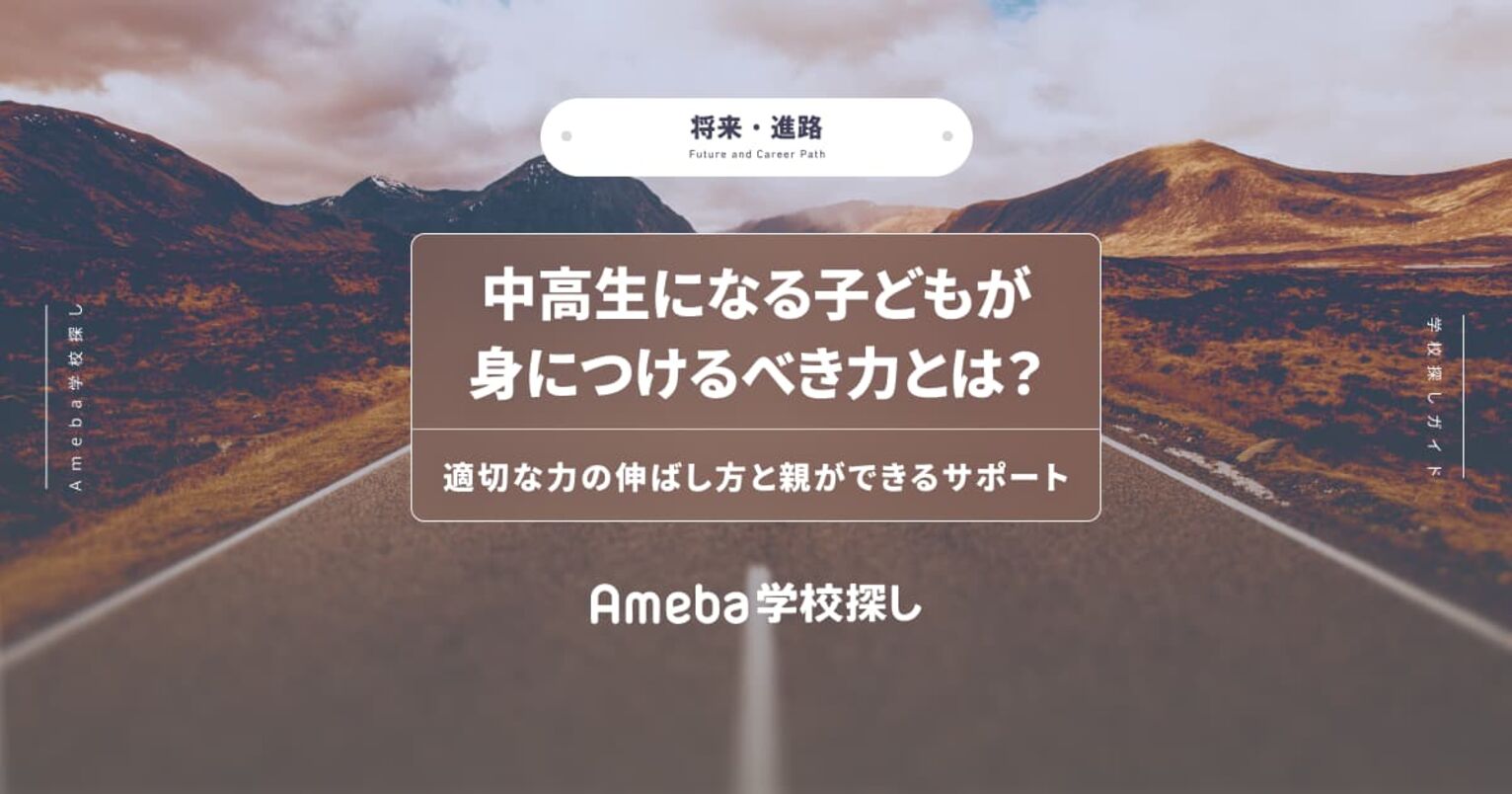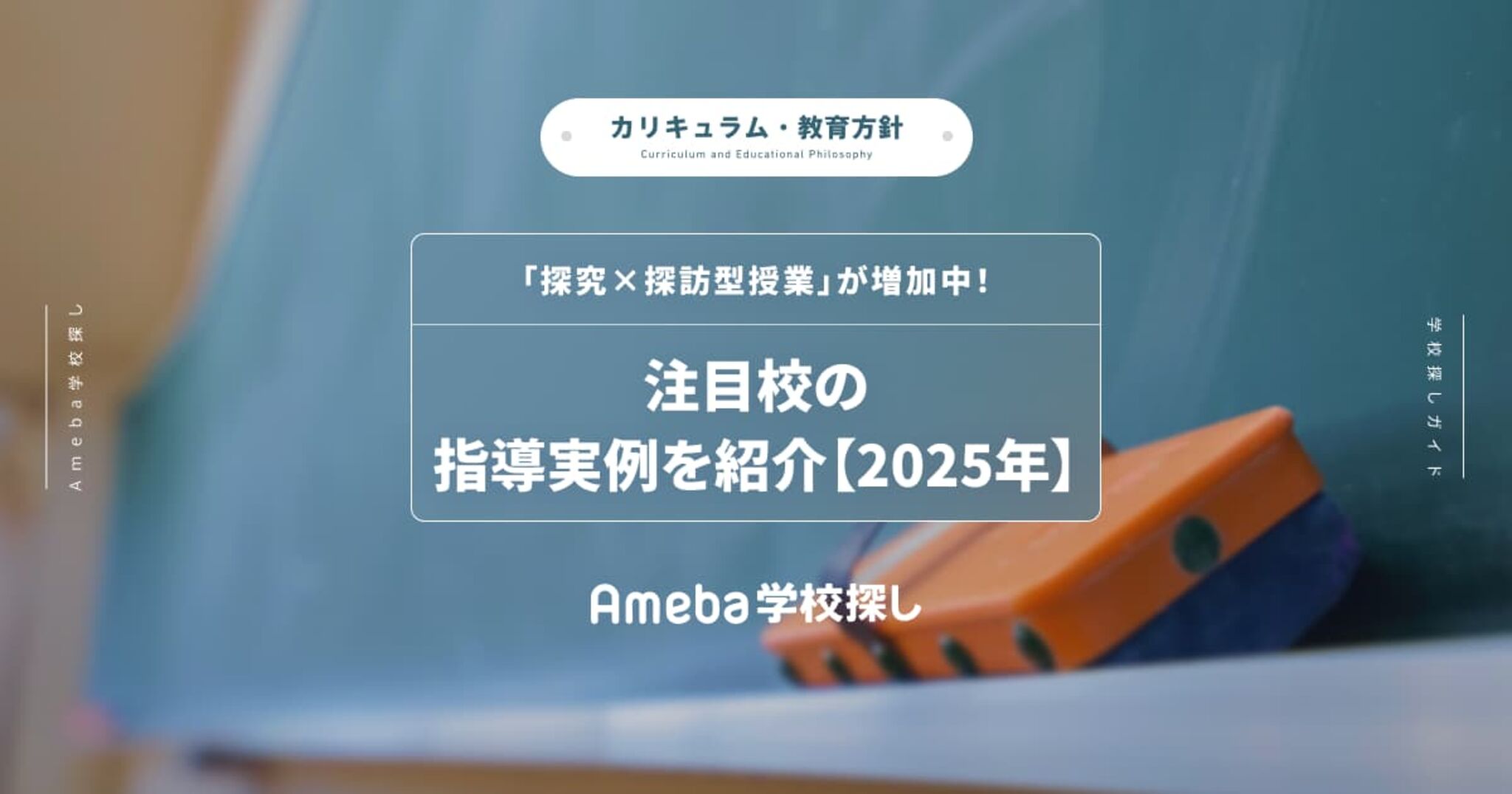小学生から高校生まで子どもを育てる保護者にとって、「どのような力を身につけさせればいいのか」は悩みの種になりやすいテーマです。
とくに中学や高校を選ぶ際には、学校ごとに特色が異なり、判断基準がわかりにくいこともあります。進路を考えるうえで大切なのは、「今後どのような力を伸ばしてほしいのか」「どの学校ならその力を育めるのか」という視点です。
この記事では、現在の教育環境を踏まえ、中高生に必要とされる力と適切な伸ばし方、さらに親ができる具体的なサポートについて解説します。
これからの時代、中高生の子どもが身につけるべき力とは
社会が大きく変化する中で、中高生には従来の「学力」だけではなく、多様な力が求められるようになっています。
文部科学省が定める学習指導要領でも「知識を活用し、自ら学びを深めること」「他者と協働して課題を解決すること」などが強調されています(※)。
こうした力は将来の進学や社会生活の基盤となるため、保護者としても早い段階から意識しておくことが安心につながります。
※文部科学省「学習指導要領」
具体的に身につけるべき力
これらは学校の授業や探究活動だけでなく、家庭での関わりや日常生活の中でも少しずつ育まれていきます。
親がこうした観点を理解しておくことで、子どもの成長に寄り添いながらサポートする道筋が見えてきます。
思考力・判断力・表現力
現在の教育方針では、知識を覚えるだけでなく、自ら考え、判断し、表現する力が重視されています。文部科学省の学習指導要領でも「知識の活用」「多角的な見方」「表現を通じた理解」が柱とされ、正解がひとつではない課題に対応する力が求められています。
この力は学習や成績だけでなく、人間関係や進路選択にも直結します。情報をそのまま受け取るのではなく、自分で解釈して判断する力は、社会に出ても欠かせません。
保護者は「考えをまとめられるか」「人前で意見を言えるか」と不安になることもありますが、家庭で「どう思う?」「なぜそう考えたの?」と問いかけるだけでも十分です。小さな会話の積み重ねが、子どもの大きな自信へとつながります。
自ら考え探究する力
学習指導要領では「探究的な学び」が重視され、自ら問いを立て、調べ、考え、答えを導き出す力が求められています。知識を受け取るだけでなく、問題意識をもって学びを広げる姿勢が大切です。
中高生にとっては、進路を考えるうえでもこの探究の姿勢が役立ちます。理科の実験や地域の課題調査などを通じて、主体的に学ぶ経験を積むことができ、単なる知識習得を超えて「考え抜く力」を育てられます。
保護者は「子どもが課題を見つけられるだろうか」と不安に思うかもしれませんが、家庭で「どう思う?」「調べてみたら?」と声をかけるだけでも十分です。日常の中で小さな問いかけを積み重ねることで、安心して探究心を深められる環境が整っていきます。
コミュニケーション能力
中高生の時期は、友だちや先生、先輩後輩との関わりを通じて精神面でも大きく成長する時期です。しかし「自分の気持ちを言葉にできない」「相手の意見を受け止められない」といった不安を抱える子どもも少なくありません。
将来を見据えると、社会で必要とされるのは知識だけではなく、他者と協力しながら物事を進める力です。だからこそ、中高生のうちにコミュニケーション能力を育むことが重要になります。
以下は、身につけるべき具体的な要素を整理したものです。
- 意味:自分の考えを整理し、相手にわかりやすく伝える
- 将来の活かし方:プレゼンや面接で自信をもって話せる
- 意味:相手の言葉を受け止め、理解しようとする姿勢
- 将来の活かし方:人間関係のトラブルを防ぎ、信頼関係を築く
- 意味:意見を出し合いながら合意点を見つける
- 将来の活かし方:チームで成果を出す社会人スキルにつながる
たとえば、「うちの子は人前でしっかりと話せるだろうか」と心配になるのは当然ですが、過度に心配する必要はありません。
家庭内で日常的に会話の機会をつくり、子どもの言葉をしっかり聞くことが、何よりのサポートになります。相手に理解してもらえた経験の積み重ねが、子どもに自信を与え、自然とコミュニケーション能力を育んでいきます。
物事をやり抜く力
中高生は、学習や部活動、人間関係の構築などを通して多くの挑戦機会に直面します。その中で「無事に達成することができるだろうか」と不安になる保護者もいるでしょう。しかし、子ども自ら困難に向き合い、粘り強くやり遂げた経験は将来の大きな支えになります。
社会で求められるのはいわゆる「正解」だけでなく、失敗しても工夫を重ね続ける姿勢です。受験勉強や部活動、学校行事、友人とのコミュニケーションなどで努力を積み重ねることは、忍耐力や責任感を育てます。
その過程を見守る保護者として、「最後までやり抜いたね」「こういう努力ができたのは素晴らしいことだね」と努力の過程を認めることが大切です。結果にこだわらず努力を評価する声かけが、子どもに安心と自信を与え、粘り強さを育む第一歩となります。
情報を正しく活用する力
インターネットやSNSの普及によって、中高生は膨大な情報に触れるようになりました。その中には正しい情報もあれば、誤解を招く内容や偏った意見も含まれています。
情報をそのまま信じて行動すると、学習や人間関係に影響することもあるため、適切に見極めて活用する力が求められています。
保護者としては「子どもが間違った情報に流されないか」と心配になるものです。こうした不安を和らげるには、家庭で具体的な確認の仕方を共有することが効果的です。
情報に対して意識しておきたい観点
- 広告と記事の違いを見分ける練習をする
- SNSの拡散情報は一次情報と照らし合わせる
- 動画や画像の加工・編集の可能性を考慮する
- 自分に必要な情報かどうかを一度立ち止まって判断する
「出どころの確認・複数情報源の比較」といった基本に加え、日常的に意識できる具体的な行動指針を持つことが大切です。意識を高め共に実践することで、子どもも自然と情報リテラシーを高めていけるでしょう。
子どもの力を伸ばす方法
中高生に必要な力を伸ばす方法に悩む保護者は少なくありません。学校の指導に任せてよいのか、家庭や習い事で補うべきか、不安になることもあるでしょう。
学校教育に限らず、日常生活や課外活動も学びの場であることをあらためて認識し、子どもの力を伸ばす方法を検討しましょう。
子どもの力を伸ばす具体的な方法
力を伸ばせる学校に通う
学校ごとに、教育方針やカリキュラム、力を入れている点は異なります。探究学習の深さや授業の進め方、施設や設備の充実度などによって、子どもがどのような力を重点的に伸ばせるかは変わってきます。
保護者が「本当にこの学校で大丈夫だろうか」と不安になるのは当然のことです。そのため、納得できるだけの情報を集めて判断することが大切です。
学校の公式サイトや資料の確認、説明会への参加を通して、実際の教育方針や学習環境を見極めることが大切です。子どもにあった環境を見つけることで、学びを支える安心感につながります。
課外活動や習い事をする
学校以外の活動も、子どもの力を伸ばす大切な要素です。部活動や地域活動、習い事を通じて、表現力や創造力、やり抜く力などを育むことができます。ただし「どの活動を選べばよいか」「無理なく続けられるか」と悩む保護者も多いでしょう。
【代表的な活動と育まれる力】
- スポーツ系:体力・協調性・粘り強さ
- 文化系:表現力・創造力・自身
- 学習系:思考力・探究心・論理的思考
- 地域活動・ボランティア:社会性・責任感・主体性
課外活動や習い事は、結果を出すことだけが目的ではありません。子どもが「続けたい」と思える活動を見つけることが、子どもの成長を支える第一歩になります。
日常生活のなかで子どものために親ができること
子どもの力を伸ばすには、学校や習い事だけでなく、家庭での日常の関わり方がとても大切です。保護者にとっては「どのような声かけをすればいいのか」「どのように子どもと接すればよいのか」と迷うことも多いでしょう。
日常生活の中で意識できる工夫を知ることで、不安を安心に変えながら子どもの成長を支えることができます。
家庭でのコミュニケーションを工夫する
子どもが人との関わり方を学ぶ最初の場は家庭です。日常の会話や家族とのやりとりは、表現力や聞く力を育てる基盤となります。中高生になると自分から学校のことを話さなくなることもあるため、保護者が意識して声をかけることが重要です。
「今日はどうだった?」「楽しいことあった?」といった問いかけや、子どもの話を最後まで聞く姿勢は安心感を与え、自分の意見を言葉にする自信を育てます。保護者として「人前で話せるだろうか」と不安になることもありますが、家庭で小さな成功体験を積むことが第一歩です。
その積み重ねが学校や社会での自信につながり、将来のコミュニケーション能力を支える力になります。
結果だけではなく過程をほめる
子どもが努力したときに、つい注目してしまうのは「テストの点数」や「大会での成績」といった成果です。しかし結果ばかりを意識させると、子どもは「成果を出さなければ認めてもらえない」と感じ、挑戦を避けるようになってしまいます。とくに中高生の時期は、努力が必ず結果につながるとは限らないため、過程を評価する姿勢が支えになります。
たとえば「最後まで取り組めたね」「工夫してやり方を変えられたね」と声をかければ、努力の価値を実感できるでしょう。たとえ結果が伴わなくても「自分を見守ってくれる人がいる」という安心感が、次の挑戦へ進む力になります。
保護者が日常で過程を認めるようにすると、子どもは成長を前向きに捉えられるようになります。努力そのものに意味を見いだせれば、自信や粘り強さが養われ、将来の学習や人間関係に大きな力となるでしょう。
子どもに多くのことを体験させる
本や授業での学びも大切ですが、実際に体験することでしか得られない学びがあります。自然に触れたり、美術館や博物館を訪れたりと、五感を通じて得られる経験は、子どもの探究心を刺激し、学びの幅を広げます。
保護者にとっては「どんな体験をさせればよいのか」と迷うこともありますが、いくつかの観点を意識すれば安心して選択できます。
【代表的な体験の種類とそこで育まれる力】
- 自然体験(登山・キャンプ)など:忍耐力・協調性・探究心
- 文化体験(美術館・博物館)など:表現力・知的好奇心
- 社会体験(ボランティア、地域活動など:責任感・社会性・主体性
- プログラミング・科学教室など:論理的思考力・創造力
こうした体験は、必ずしも特別な場を用意しなくても構いません。休日の散歩や地域イベントでも十分に学びにつながります。親が「子どもにとって新しい刺激になるか」を意識することが、安心して成長を支える第一歩です。
子どもの興味関心を否定しない
子どもが新しいことに興味を示したとき、保護者の反応はその後の姿勢に大きな影響を与えます。たとえば「そんなことに時間を使っても意味がない」と否定的に言われてしまうと、挑戦する意欲をなくし、好奇心を狭めてしまうこともあります。
一方、「面白そうだね!」「やってみたらどう?」と受け止めてもらえると、自分の関心を大切にしてよいのだと感じ、主体性が育ちます。
中高生になると、親から見ると一見役に立たないように思えることに関心を持つこともあります。しかし、それが将来の進路や人間関係につながる可能性も少なくありません。安心して挑戦できる環境を整えることこそが、子どもの探究心を伸ばし、自信につながります。
保護者にとっては「この先の役に立つのか」と心配になるのは自然なことです。ただ、その気持ちを抑えてまずは子どもの思いを尊重することが、安心して成長を支える大きな力になります。
親子で考える時間を増やす
子どもの思考力や判断力を伸ばすには、親が答えを与えるだけでなく、一緒に考える時間を持つことが大切です。
「どう思う?」「なぜそう考えたの?」と問いかけることで、自分の考えを整理し表現する練習になります。日常の小さな出来事を題材にするだけでも十分に効果があります。
意識したいポイント
- 食事のときに話題を共有する
- 日常の出来事を一緒に考える題材にする
- 子どもの意見を最後まで聞く
安心して意見を言える雰囲気が家庭にあると、子どもは「自分の考えを大切にしてよい」と実感できます。その積み重ねが自信となり、学びを深める姿勢へとつながるでしょう。
安心して子どもの成長を見守るために
中高生には、思考力や探究心、コミュニケーション能力、やり抜く力、情報を見極める力など、これからの社会を生きるために欠かせない力が求められています。これらは学校教育に限らず、家庭での会話や日常体験、習い事を通じても育てられます。
保護者が「本当にこのやり方で大丈夫だろうか」と不安になるのは自然なことですが、その気持ちはわが子の成長を真剣に考えている証拠でもあります。学校や課外活動を活用しつつ、家庭で小さな体験を重ねることで、子どもは安心して力を伸ばしていけます。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。