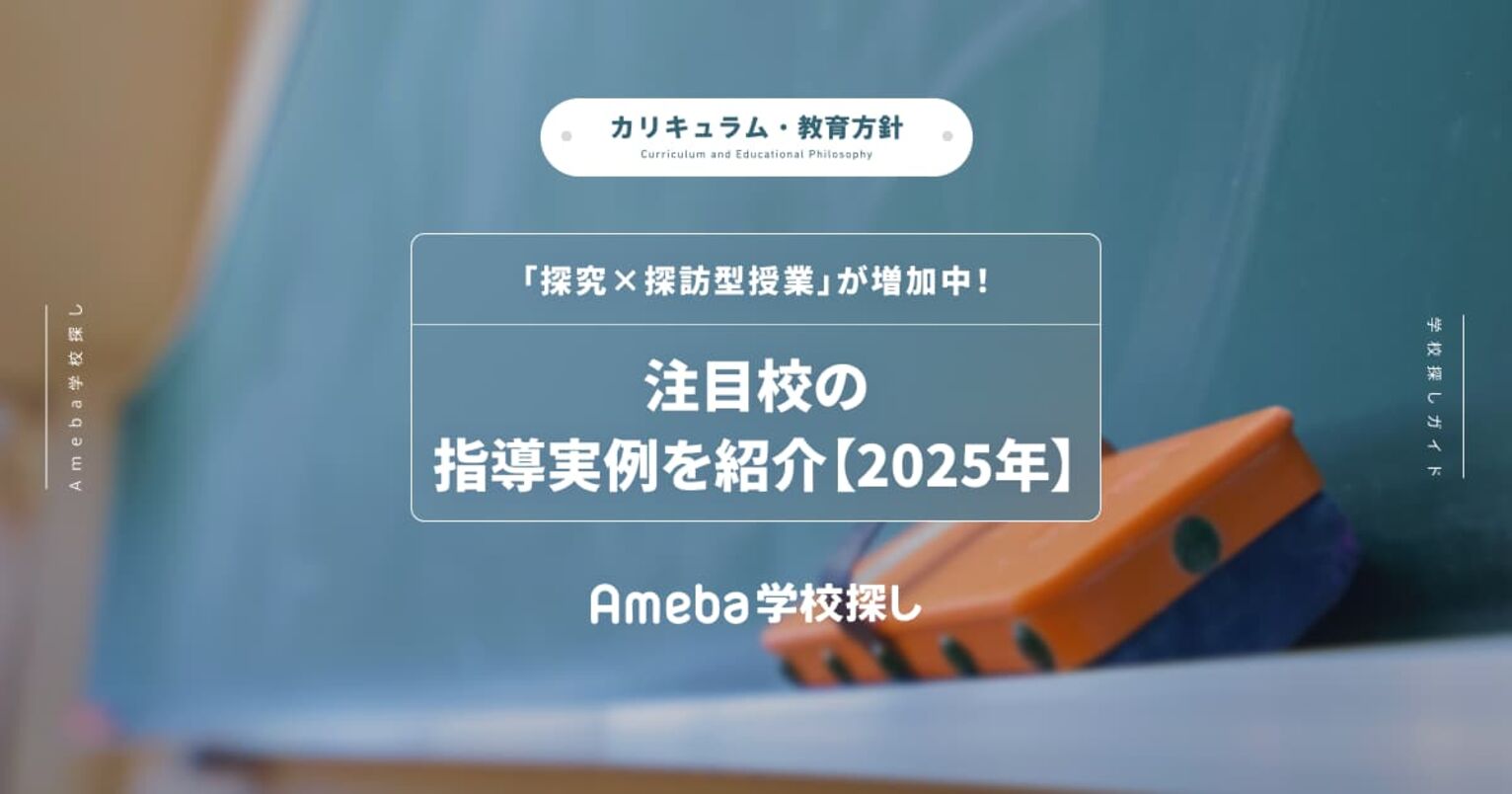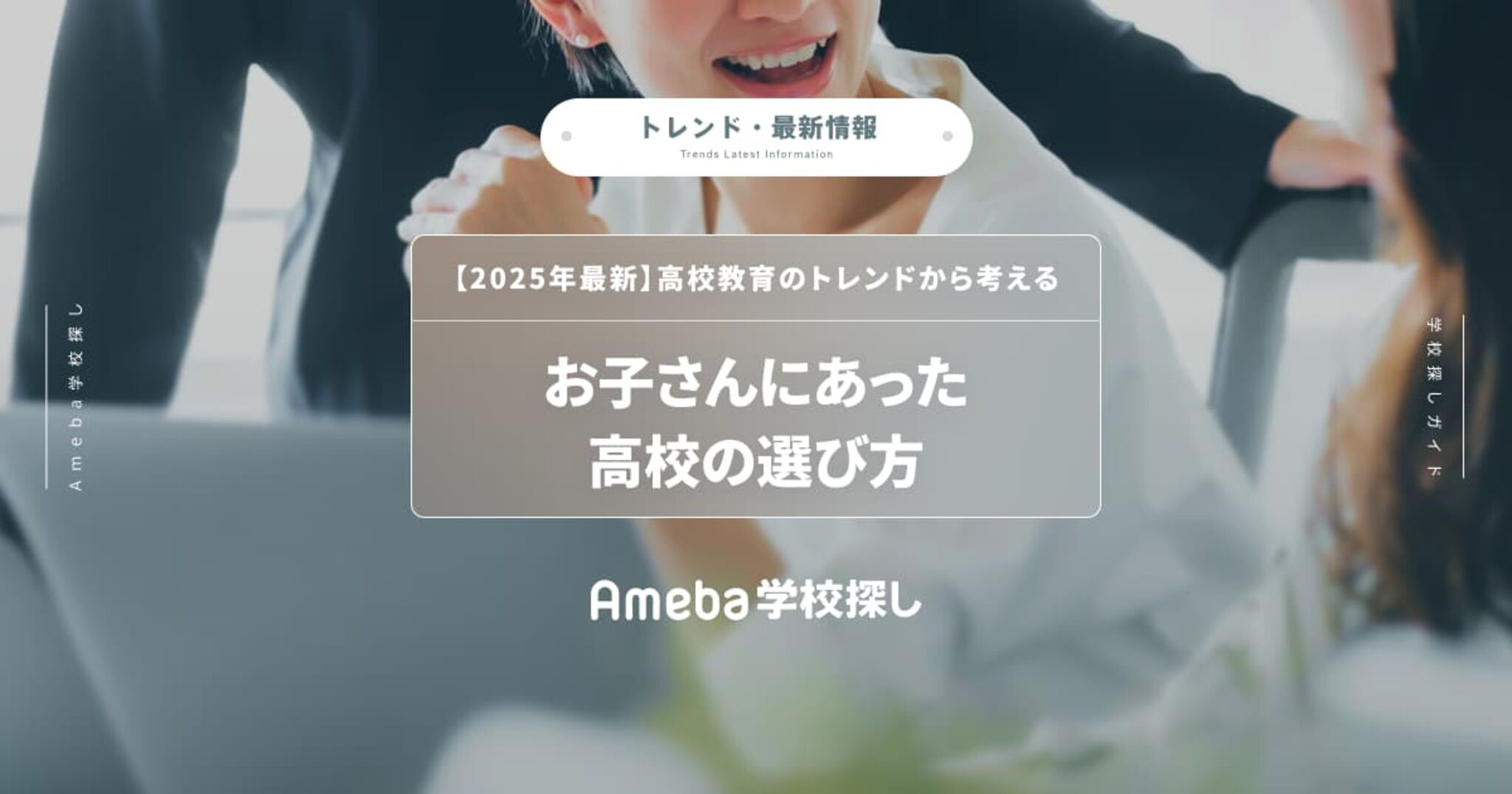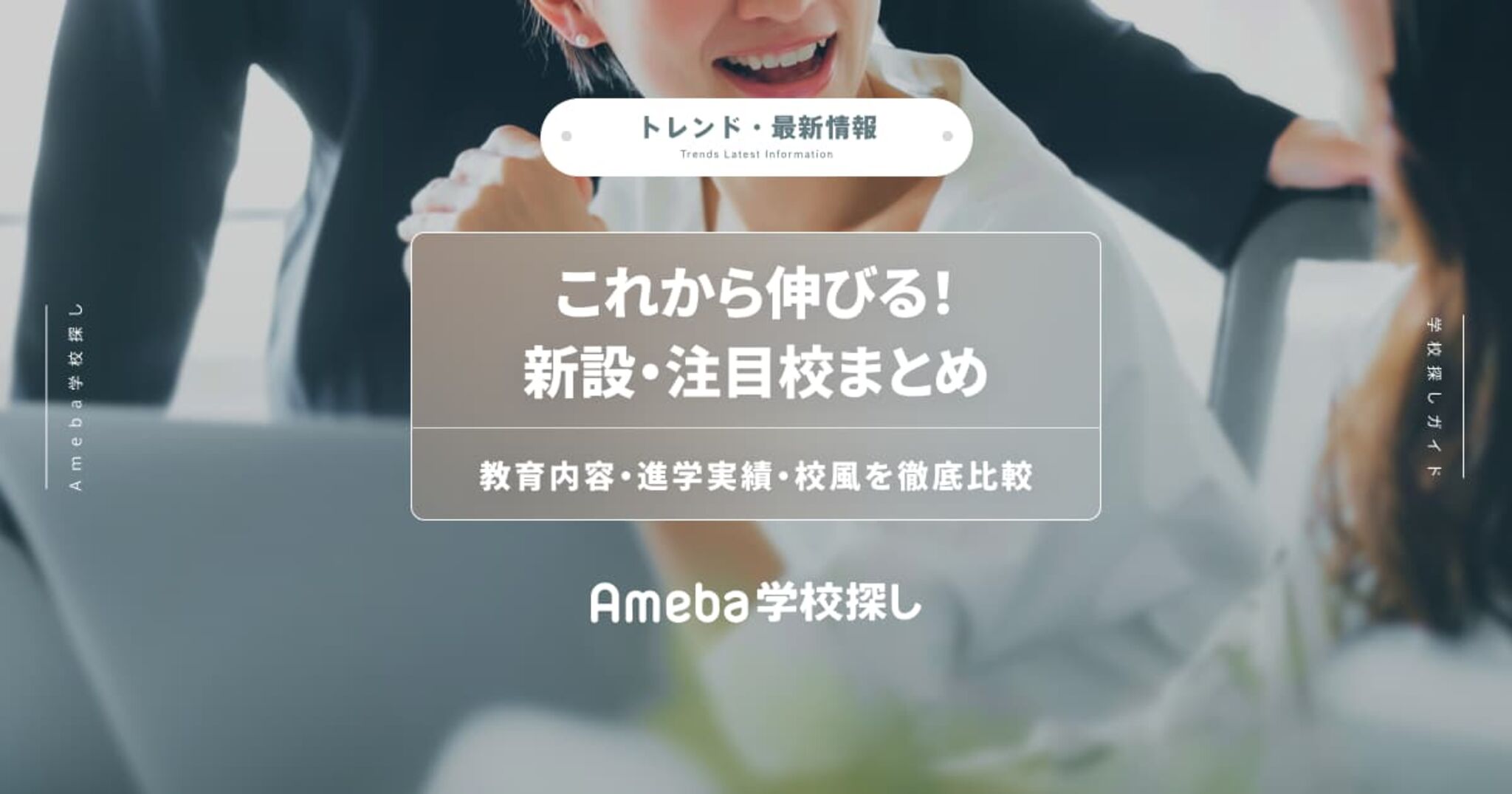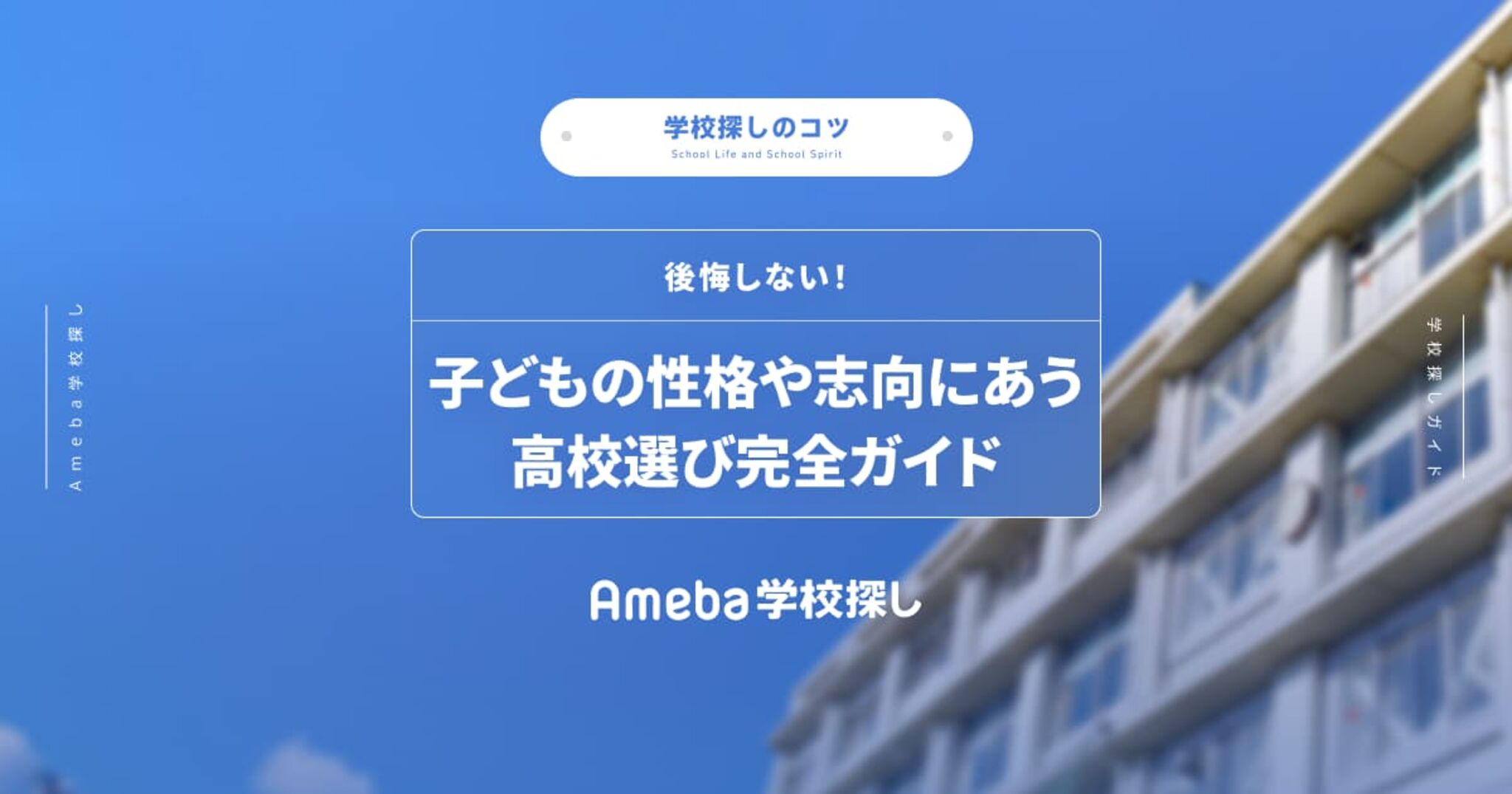ここ数年で高校の「総合的な探究の時間」が本格化し、さらに「探訪(フィールドワーク)」を組み合わせた授業スタイルが注目されています。
従来の座学中心の授業とは異なり、地域・企業・大学との連携を通じて生徒たちが主体的に課題を設定し、現地調査や発表をおこなう探究学習が全国の中学・高校で広まりつつあります。
2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」により、現在では全国の高校でこうした実践的な学びが当たり前となっています。そのため、お子さんの進学先を選ぶ際に、どの学校がより充実した探究学習を提供しているかを検討されている保護者の方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では最新データとともに、実際に「探究×探訪型授業」に取り組む中学・高校の先進事例を詳しく紹介します。学校選択の参考として、ぜひご活用ください。
- そもそも「探究×探訪型授業」とは?
- 「探究×探訪型授業」の流れ・進み方
- 「探究×探訪型授業」が注目されている理由
- 探究学習の最新動向【2025年】
- 高校で必修化された「総合的な探究の時間」の現状
- 探究×探訪の組み合わせで学びが深化
- 「探究×探訪型授業」注目校の実践事例を紹介
- 新渡戸文化中学・高等学校「スタディツアー」(東京)
- 和洋九段女子中学校・高等学校「総合探求・PBL型授業」(東京)
- 三田国際科学学園中学校・高等学校「サイエンス探究」「社会課題探究」(東京)
- 大阪女学院中学校・高等学校「総合探究」(大阪)
- 立命館守山中学校・高等学校「文社探求」「理数探求」(滋賀)
- 関西学院千里国際中等部・高等部「知の探究」(大阪)
- 学校探しで保護者が見るべきポイント
- 学校説明会・パンフレットで「探究内容」の記載有無を確認する
- 「探究×探訪」プログラムの設計と発展性を見る
- 子どもの興味関心との相性を整理する
- 「探究×探訪型授業」は子どもが主体的に学びを深めることができる
そもそも「探究×探訪型授業」とは?

「探究×探訪型授業」とは、生徒が自ら問いを立てて学びを深める「探究学習」と、実際に現地に足を運んで体験する「探訪学習(フィールドワーク)」を組み合わせた授業スタイルのこと。
文部科学省が推進する「主体的・対話的で深い学び」の代表例として、全国の中学・高校で導入が進んでいます。わかりやすくいえば、「自分で調べ、考え、現場で確かめる学び」です。従来の教科書や資料だけで完結する授業とは大きく異なり、生徒が実社会とつながりながら学習を進めることが最大の特徴といえます。
探究学習とは興味のあるテーマについて、自ら疑問をもち、資料やデータを集めて考察・発表する学習方法です。たとえば「地域の観光資源を活かすには?」というテーマで、統計データや先行研究を調査し、仮説を立てて検証するプロセスを重視します。
探訪学習(フィールドワーク)は、実際に現地に行き、見たり聞いたり体験しながら学ぶ学習方法です。観光地や企業を訪問し、関係者にインタビューをおこなったり、現地調査を実施したりして、リアルな情報を収集します。
「探究×探訪型授業」の流れ・進み方
では、この探究学習と探訪学習を組み合わせた「探究×探訪型授業」は、実際にどのような流れで進められるのでしょうか。一般的なプロセスを紹介します。
- ①【探究フェーズ】テーマ設定・事前調査
生徒が関心をもつテーマを設定し、文献調査やインターネット検索により基礎情報を収集します。この段階で仮説や調査の視点をまとめ、探訪での確認事項を明確にします。 - ②【探訪フェーズ】現地見学・調査
企業訪問、地域活動への参加、大学研究室見学など、実際に現地に赴いて体験的な学習をおこないます。事前調査で立てた仮説を現場で検証し、新たな発見や気づきを得ることが目的です。 - ③【探究フェーズ】調査結果の分析・発表
探訪で得た情報と事前調査を総合して分析をおこない、レポートやプレゼンテーションにまとめます。ほかの生徒や教師、ときには地域の方々に向けて発表し、振り返りを通じて学びを深化させます。
従来の講義型授業では、教師が知識を一方的に伝達することが中心でしたが、探究×探訪型授業では生徒が学習の主体となります。
また、教室内で完結する学習ではなく、地域社会や実社会とのつながりを重視し、より実践的で応用可能な学びを提供することが特徴です。
「探究×探訪型授業」が注目されている理由
「探究×探訪型授業」が全国の学校で注目されているのは、従来の暗記中心の学習では身につかない、これからの社会で必要とされる力を養えるからです。
具体的に身につく4つの力として、次のようなものが挙げられます。
- ①課題発見力・問題解決力
生徒が自ら問いを立て、情報を収集・分析する過程で、現代社会に必要な課題発見力が育まれます。答えのない問題に取り組むことで、複雑な状況を整理し、解決策を考える力が身につきます。 - ②コミュニケーション力・プレゼンテーション力
現地でのインタビューや調査活動を通じて、初対面の大人とも適切にコミュニケーションを取る力が養われます。また、調査結果を他者にわかりやすく伝える発表スキルも向上します。 - ③社会とのつながりを実感できる学習意欲
教室を飛び出して実社会に触れることで、学習内容が「自分ごと」として捉えられるようになります。これにより、従来の受動的な学習姿勢から、能動的な学習姿勢への転換が期待できます。 - ④将来の進路選択に活かせる体験
企業や大学との連携を通じて、さまざまな職業や研究分野に触れる機会が得られます。早い段階から社会の多様性を知ることで、より具体的で現実的な進路選択が可能になります。
近年の大学入試では、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜の重要性が増しており、これらの入試では探究活動の経験が重視される傾向にあります。
文部科学省「令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」(令和6年11月27日発表)によると、令和6年度入試では総合型選抜・学校推薦型選抜による入学者数が、大学全体で31万3,069人(全入学者の約51%)に達しており、探究学習の成果を活用できる入試機会が大幅に拡大しています。
とくに探究×探訪型の学習経験は、志望理由書や面接において具体的なエピソードとして活用でき、受験生の個性や学習意欲をアピールする材料として有効です。
また、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」(前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力)の育成にも、探究×探訪型授業は有効とされています。実際に多くの企業が、新卒採用において「主体性」「課題解決力」「コミュニケーション力」を重視しており、これらの力を在学中に育める教育プログラムへの関心が高まっています。
このような社会的背景から、探究×探訪型授業を導入する学校は年々増加傾向にあり、保護者の学校選択の際の重要な判断材料のひとつとなっています。
探究学習の最新動向【2025年】
2025年度を迎え、探究学習は新たな段階に入っています。高校での「総合的な探究の時間」必修化から3年が経過し、全国の学校では試行錯誤を重ねながら、より実践的で効果的な探究プログラムが確立されつつあります。
とくに地域や企業との連携を活かした「探訪型授業」の導入により、生徒たちの学びは教室を超えて大きく広がっています。
高校で必修化された「総合的な探究の時間」の現状
2022年度より高校で導入された「総合的な探究の時間」は、新学習指導要領で必修化されたため、2025年度の実施率はほぼ100%となっています。
この科目は従来の「総合的な学習の時間」から名称変更されただけでなく、内容も大幅に刷新されました。
もっとも大きな変化は、生徒が「課題を解決する」だけでなく「課題を発見する」ことに重点が置かれるようになった点です。
これにより、教師が与えたテーマについて調べる学習から、生徒自身が興味関心に基づいて問いを立て、その解決に向けて主体的に取り組む学習へと大きく転換しています。
探究×探訪の組み合わせで学びが深化
地域や企業と連携したフィールドワーク(探訪型授業)は、実践的な学びだけでなく、探究テーマの発見の場としても重要な役割を果たしています。
従来の教室内での学習では見つけることが困難だった「リアルな課題」に直接触れることで、生徒たちの問題意識が格段に高まることが全国の実践事例から明らかになっています。
また、民間の教育支援団体による探究活動発表の場も充実してきており、たとえば教育と探求社主催の「QUEST HEROES」では、中高生が研究成果を大学関係者や他校と共有する機会が設けられています。
こうした外部発表の機会が増えることで、生徒たちの探究活動に対するモチベーションも高まり、今後も探究活動の場はさらに発展していくことが期待されています。
2025年度の探究学習には新しい動向が見られます。AI技術を活用した情報収集・分析により、より効率的な探究活動が可能に。また、SDGs(持続可能な開発目標)をテーマとした探究活動が全国的に広がり、地球規模の課題を地域の問題として捉え直す学習が実践されています。
さらに、大学との連携が密接になり、大学教員による指導や研究室での探究活動など、専門的で高度な学習機会が拡充され、学びの深化が加速しているのが特徴です。
「探究×探訪型授業」注目校の実践事例を紹介

全国の中学・高校では、それぞれの教育方針や地域特性を活かした独自の「探究×探訪型授業」を展開しています。ここでは、とくに先進的な取り組みをおこなっている首都圏・関西圏の学校の実践事例を紹介します。各校の特色ある取り組みを、学校選択の参考にしてください。
新渡戸文化中学・高等学校「スタディツアー」(東京)
新渡戸文化中学・高等学校では、従来の修学旅行を再構築し、生徒が自ら目的地を選び、行程・調査企画をおこなう「スタディツアー形式」を導入しています。この取り組みは、授業だけでなく旅行そのものを「探究の時間」とする独自の試みとして注目されています。
スタディツアーでは、生徒たちが事前に興味のあるテーマを設定し、そのテーマに関連する地域を訪問先として選択。地域の産業、歴史、文化など、さまざまな分野から生徒の関心に応じたテーマが選ばれ、現地での体験的な学習がおこなわれています。
従来の受動的な旅行体験から、生徒が主体的に学習目標を設定し、現地での学びを深める能動的な体験へと転換しているのが特徴です。旅行後には、調査結果をまとめて発表することで、探究学習の一連のプロセスを完結させています。
和洋九段女子中学校・高等学校「総合探求・PBL型授業」(東京)
和洋九段女子中学校・高等学校では、「総合探究」という独自カリキュラムを通じて、生徒が課題設定から現地調査、発表まで一貫しておこなう探究学習を実践しています。
同校の特徴的な取り組みとして、地域企業・NPO・大学などと連携したプロジェクトベースの学習を展開。「つながる学び~Connected School~」をテーマに、世界標準のリベラルアーツ教育を背景とした実践的な学習がおこなわれています。
探訪例としては、地域の社会課題解決プロジェクト、企業連携活動、NPO団体での社会貢献プログラム、大学研究機関での学習体験などがあります。生徒たちは現地を訪問し、関係者へのインタビューや現地調査を実施、課題分析から具体的な改善提案の作成・発表まで、実社会と直結した学習をおこなっています。
また、全教科でPBL(Problem Based Learning:問題解決型学習)を取り入れており、生徒たちは自分たちで問いを立て、チームでよりよいものを創り上げる過程を重視した授業を実践しています。
三田国際科学学園中学校・高等学校「サイエンス探究」「社会課題探究」(東京)
三田国際学園中学校・高等学校は、2025年4月より「三田国際科学学園」に校名を変更し、サイエンス教育により一層力を入れることを表明しています。同校はICT活用と英語教育で先進的な取り組みをおこないながら、探究型学習を教育の中心に据えています。
「サイエンス探究」では、生徒たちが科学的な疑問を出発点として、仮説設定から実験・検証まで本格的な研究活動をおこないます。
とくに注目されるのは、企業の研究所や大学の研究室との連携プログラムです。生徒たちは実際の研究現場を訪問し、研究者から最新の研究手法を学ぶとともに、自分たちの研究テーマについてアドバイスを受ける機会が設けられています。
「社会課題探究」では、現代社会が直面するさまざまな課題について、多角的な視点から分析・検討をおこないます。たとえば、環境問題をテーマにしたグループは、環境保護団体や環境関連企業を訪問し、理論と実践の両面から問題を捉える学習をおこなっています。
大阪女学院中学校・高等学校「総合探究」(大阪)
大阪女学院中学校・高等学校では、国際協力・環境問題・ジェンダーなど、現代的課題をテーマとした探究学習を実践しています。同校の教育の特徴は、グローバルな視点を重視した学習活動にあります。
同校では建学以来、国際理解教育に力を入れており、生徒たちは世界の多様な文化や課題について深く学ぶ機会が豊富に設けられています。
現代社会が直面するさまざまな問題について、多角的な視点から分析・検討をおこなう授業を展開。国際機関の見学、NGO・NPO団体での活動体験、大使館や領事館への訪問、国際会議の傍聴、海外研修での現地調査などの探訪活動を通じて、地球規模の課題を身近な問題として捉える力を育んでいます。
立命館守山中学校・高等学校「文社探求」「理数探求」(滋賀)
立命館守山中学校・高等学校では、「立命館グローバル・イノベーション探究」を柱として、大学・企業・地域と連携した本格的な探究学習を展開しています。
「文社探求」では、地域の歴史・文化・社会問題を中心とした探究活動をおこなっています。生徒たちは地域の自治体や文化施設、NPO団体などを訪問し、地域が抱える課題と解決策について実地調査を通じて学習していきます。
「理数探求」では、理系分野の高度な研究活動をおこなっており、定期的に大学や企業の研究施設への訪問を実施。生徒たちは最新の研究設備を実際に見学し、研究者から直接指導を受けながら、自分たちの研究テーマを深化させています。
たとえば、環境科学に興味をもつ生徒は、琵琶湖の水質調査をテーマに、滋賀県の環境科学研究センターと連携した長期的な研究プロジェクトに参加しています。
同校の探究学習は、立命館大学との連携により、大学レベルの研究手法や論文作成技術も学ぶことができ、高大接続の観点からも充実したプログラムとなっています。
関西学院千里国際中等部・高等部「知の探究」(大阪)
関西学院千里国際中等部・高等部は国際バカロレア(IB)認定校として、リサーチ型の探究活動を教育の中核に位置づけています。
「知の探究」では、IBプログラムの特徴である厳密な研究手法に基づいた探究学習を実施。生徒たちは、地域調査から国際的な課題まで幅広いテーマを選択し、1年以上にわたって継続的な研究活動をおこないます。
同校の特徴的な探訪学習として、海外研修や国際機関へ訪問などグローバルな探訪学習が挙げられます。たとえば、国際関係に興味をもつ生徒は、国連機関や国際NGOの現地事務所を訪問し、国際協力の現場を直接体験する機会が提供されています。
学校探しで保護者が見るべきポイント
多彩な授業を展開する学校が増え、学校選びで迷うことの多い昨今。どのような点に注目すれば子どもにあう学校を見つけられるのか、悩んでいる保護者の方も多いことでしょう。
そこで、ここでは学校説明会や見学の際に確認すべき具体的なチェックポイントを紹介します。これらの視点で学校を見ることで、お子さんにぴったりの教育環境が見つかるはずです。
- 学校説明会・パンフレットで「探究内容」の記載有無を確認する
- 「探究×探訪」プログラムの設計と発展性を見る
- 子どもの興味関心との相性を整理する
学校説明会・パンフレットで「探究内容」の記載有無を確認する
まず最初に確認すべきは、学校が探究学習にどの程度力を入れているかを示す具体的な記載があるかどうかです。学校説明会のプレゼンテーションやパンフレット、公式サイトで以下のキーワードが具体的に触れられているかをチェックしましょう。
確認すべきキーワード
- 「総合的な探究の時間」の具体的な実施内容
- 「フィールドワーク」や「現地調査」の事例
- 「PBL(Project Based Learning)」の実践例
- 「高大連携」や「企業連携」の具体的なパートナー
単にキーワードが記載されているだけでなく、実際の活動内容が具体的に説明されているかが重要です。たとえば、「地域の〇〇企業と連携し、生徒が実際に商品開発提案をおこないました」といった具体的なエピソードが紹介されているかを確認してください。
PBL(Project Based Learning)とは問題解決型学習や課題解決型学習と訳される学習方法のひとつです。生徒が自ら課題を見つけ、その解決策をグループで検討・実践することで、思考力や応用力、表現力、情報リテラシーなどを身につけることを目的としています。
また、学校説明会では「どのような企業や団体と連携しているか」「年間何回程度の探訪活動があるか」「生徒一人当たりの発表機会はどの程度か」といった具体的な質問をすることで、学校の取り組みの充実度を把握できます。
「探究×探訪」プログラムの設計と発展性を見る
探究学習の質を判断するためには、プログラムがどの程度体系的に設計されているかを確認することが重要です。以下の観点から学校の取り組みを評価してみてください。
探究活動が年間を通じてどのように計画されているかを確認しましょう。具体的なスケジュールが示されている学校は、探究学習に対する取り組みが本格的である可能性が高いです。
また、単発的な見学ではなく、継続的な関係性を築いている連携先があるかを確認してください。たとえば、「〇〇大学の研究室と3年間継続して共同研究をおこなっている」「地域の△△商工会議所と定期的な意見交換会を実施している」といった長期的な連携は、より深い学びを提供している証拠といえます。
さらに、生徒の探究成果が学校外でも発表されているかも重要な指標です。地域のコンテストへの参加、大学主催の発表会での受賞歴、行政機関への政策提案など、校外での活動実績があるかを確認してみてください。
子どもの興味関心との相性を整理する
何よりもっとも重要なのは、学校の探究プログラムがお子さんの興味関心と合致しているかを確認することです。
お子さんが関心を持ちそうな分野での探究活動が実施されているかを確認しましょう。理科・環境分野が好きなお子さんには「環境問題」「科学技術」をテーマとした探究例があるか、社会や歴史に興味があるお子さんには「地域史」「国際理解」といったテーマでの活動があるかをチェックしてください。
探究活動の経験が将来の進路選択にどのように活かされるかも重要な観点です。大学進学時の総合型選抜での活用事例や、卒業生の進路実績なども参考になります。
これらのポイントを総合的に検討することで、お子さんにとって最適な「探究×探訪型授業」を実施する学校を見つけることができるでしょう。
「探究×探訪型授業」は子どもが主体的に学びを深めることができる

探究×探訪型授業は、単に調べる学習を超えて、地域連携や外部連携を通じて生徒が学習を「自分ごと化」する教育スタイルです。
従来の受動的な学習とは大きく異なり、生徒自身が興味関心に基づいて課題を発見し、現地での体験を通じて深く考え、解決策を模索する一連のプロセスを重視しています。
保護者の方が候補の学校を選択される際は、探究内容の具体性、実践方法の充実度、発表機会の多様性を確認してください。複数の学校を比較検討し、実際に見学や説明会に参加することで、お子さんに最適な教育環境を見つけることができるでしょう。
最新の取り組み状況や詳細な情報については、各学校の公式サイトや学校説明会でご確認ください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。