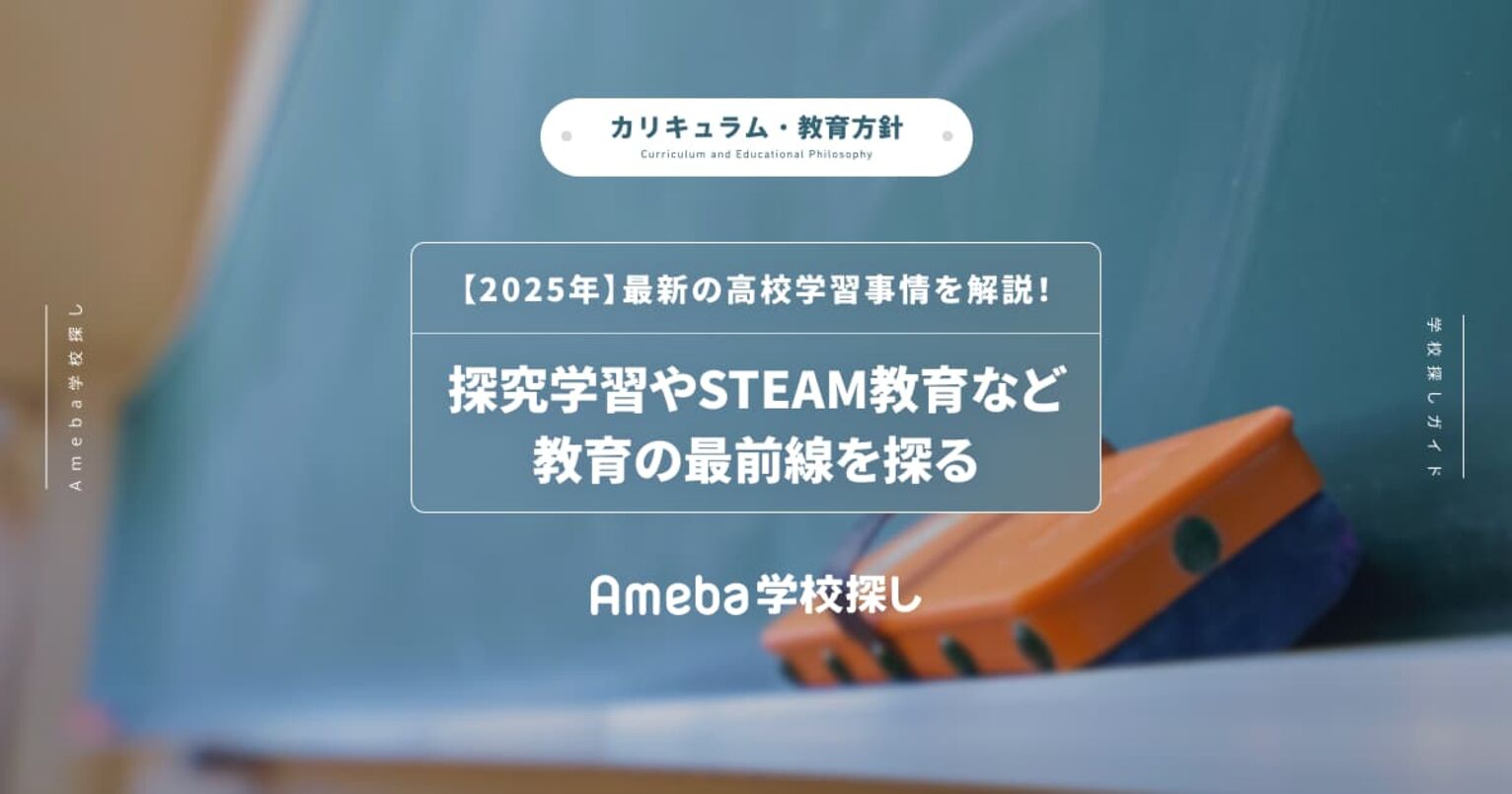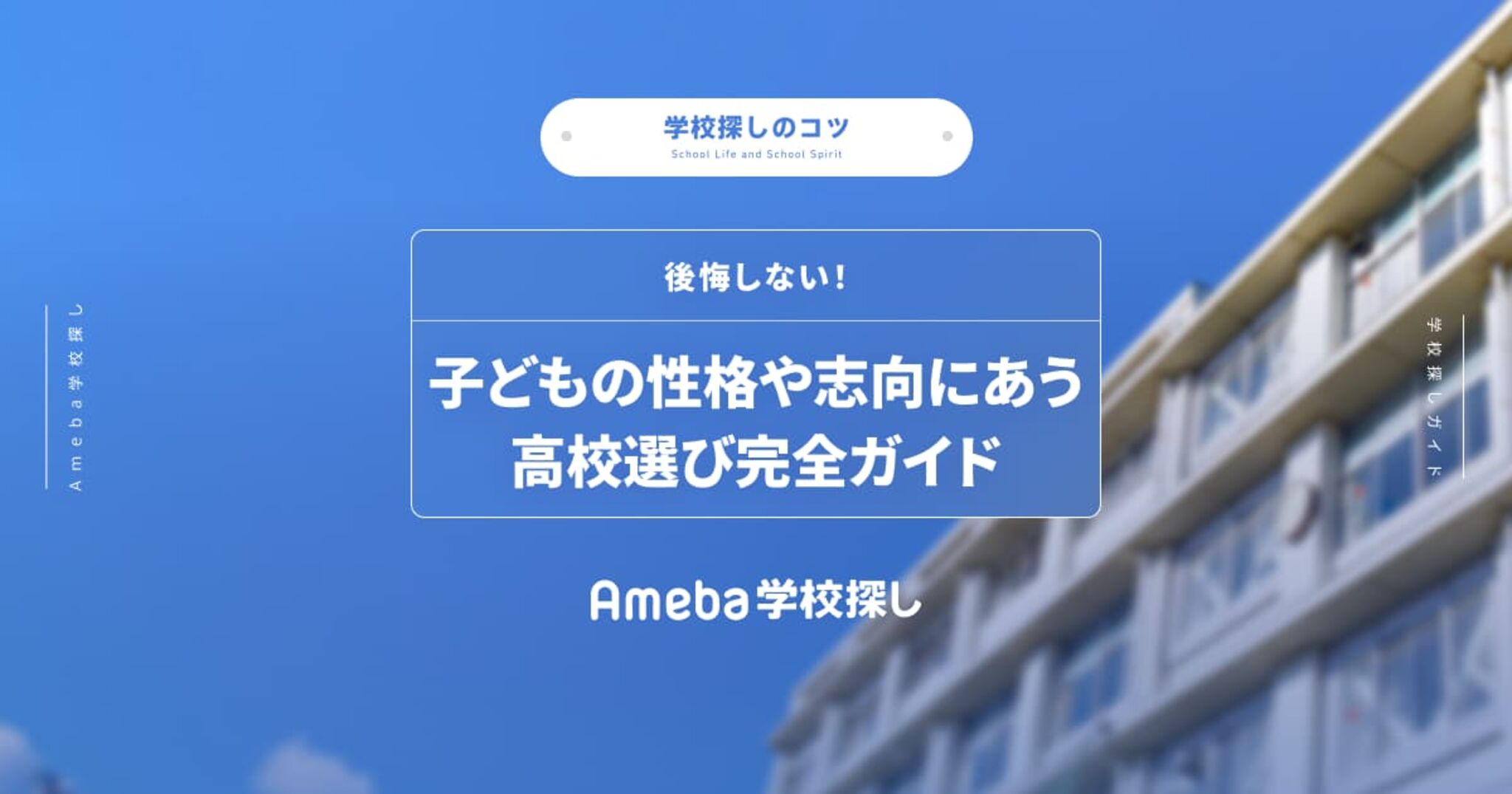高校は「偏差値」や「進学実績」だけで評価される時代から大きく変わりつつあります。2025年現在、多くの高校では知識の暗記に偏った授業から、思考力・表現力・課題解決力を育てる学びへとシフトしています。
ICT端末の活用、主体性を育む探究学習、教科横断型のSTEAM教育など、新しい取り組みが急速に浸透し、生徒一人ひとりの力を伸ばす環境が整備されています。
そこで、この記事では最新の授業スタイルと教育改革の実態をわかりやすく解説し、保護者が今知るべき学びの最前線をお届けします。
- 今、高校の学びは大きく変わっている!保護者が知るべき教育改革の背景
- 2022年度から始まった新学習指導要領
- 変化する大学入試制度と社会が求める人材像
- 主体性を育む「探究学習」とは?
- 「総合的な探究の時間」とは
- 高校ではどんな探究活動がおこなわれている?
- 探究学習が大学入試や将来に与える影響
- 高校教育に浸透しつつある「ICT教育」と、その先の「STEAM教育」とは?
- 高校でのICT環境と情報活用能力
- 教科の枠を越えて創造する「STEAM教育」という新しい学び方
- わが子にあう学校の選び方
- ①まずは公式サイトで基本情報をチェック
- ②「教育方針」「カリキュラム」ページを確認する
- ③「総合的な探究の時間」に関するページを確認する
- 今後の高校教育はどうなる?数年先の展望
- Society 5.0時代に求められる教育とは
- 知っておきたい教育のトレンド一覧
- まとめ
今、高校の学びは大きく変わっている!保護者が知るべき教育改革の背景

高校教育は近年、大きな変化を迎えています。2022年度から始まった新学習指導要領では、「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」を重視。暗記中心から、主体的に考え、対話し、表現する学びへと進化しました。
そして、この学びを経験した生徒が2025年春に初めて高校を卒業します。
大学入試も総合型や推薦型など、多様な力を評価する制度が広がっています。保護者はこうした変化を理解し、お子さんの成長を支える視点を持つことが大切です。
2022年度から始まった新学習指導要領
2022年度から高校に導入された新学習指導要領は、高校教育を大きく変えました。これまでの「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」「学んだことをどう活用するか」を重視しています
新学習指導要領のポイント
- 学び方の改革:「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」を推進
- 重視する力:暗記だけではなく、思考力・判断力・表現力を育成
- 評価とのつながり:探究活動やプレゼンなど、生徒の主体性を評価する流れが進む
- 2025年入試への影響:この指導要領で学んだ生徒が、2025年春に大学入試へ挑む最初の世代
このような学びの変化を理解しておくことで、保護者は子どもの日々の授業スタイルを把握しやすくなり、家庭での声かけやサポートにも活かせます。
変化する大学入試制度と社会が求める人材像
大学入試制度は、ペーパーテストだけでは測れない「思考力」「主体性」「課題解決力」といった力を重視する方向へ変化しています。
代表的な例
- 総合型選抜や推薦型選抜の拡大
- 面接・小論文・探究活動の成果による多角的評価
- ポートフォリオ提出で思考プロセスを可視化
- 課題発見と協働を重視し、自分で問いを立てて協力しながら解決へ導く力
加えて、今はAIやグローバル化が進み「予測困難」なVUCA(ブーカ)時代です。このような時代に求められる力とは、情報を判断し、仮説を立て、柔軟に対応する能力です。これは学校での探究学習とも自然につながります。
こうした現状を理解すれば、保護者の方も「何を大切に学んでほしいか」がより見えるようになります。
主体性を育む「探究学習」とは?

高校で導入された探究学習は、生徒が自ら課題を設定し、調査・分析・発表のプロセスを通じて、学び方そのものを身につけることを目指す授業です。
主な探究学習方法
- 毎週1〜2時間、教科横断型で学ぶ
- 卒業まで105〜210時間(3〜6単位)が必修
- 問いを立て、調べ、分析し、発表するプロセスを経験
- 暗記ではなく、思考力・判断力・表現力・協働力を育む
探究学習はただの授業ではなく、子どもの学びの基盤を築く機会です。日々の授業スタイルや取り組みを知ることで、家庭でも子どもを自然に支えられるようになります。
たとえば「今日は探究でどんなことを調べたの?」とさりげなく声をかけるだけでも、子どもの学びを温かく見守る姿勢になります。
「総合的な探究の時間」とは
2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」は、かつての「総合的な学習の時間」から進化した内容で、生徒自身が課題を設定し、調査・分析・表現する一貫した学びのプロセスを通じて、主体性や問題解決力を育む授業です。
特徴とねらい
- 教科を横断した学び
教科の枠を超えて、現実社会の課題に取り組む設計です。 - 問いを立て、調べ、表現する主体的なプロセス
探究の4ステップ(課題設定→情報収集→整理分析→まとめ・表現)を全員が経験します。 - 必修であること
多くの高校で週1〜2時間、1年〜3年次を通じて実施され、卒業まで合計105〜210時間が確保されています。
- 主体性・自律性:自分の関心からテーマを設定し学びを進める
- 問題発見・分析力:社会や身近な環境から問いを立て、それを深める
- 表現力・伝える力:発表や資料作成を通じて自分の主張を伝える
- 協働・創造性:仲間と協力しながら探究の質を高めることも多い
この授業は、子どもが能動的に学び方を身につける大切な時間です。
家庭でも「今日はどんな問いを立てたの?」と投げかけるだけで、自然と探究学習の振り返りが生まれ、自信が育まれます。
暗記から「問いを立てる力」を育む学習へ
高校の探究学習では、生徒が自分の関心をテーマにし、問いを立てて「考え・調べ・まとめ・伝える」プロセスをじっくり体得します。
週1〜2時間の授業で、教師は教えるのではなくサポート役に徹し、生徒同士による議論や情報整理を中心に進められます。
学びの目的
- 「問いを作り、自分で調べ、考え、表現する」プロセスを経験すること
- 覚えること以上に、自ら学ぶ力を育む構成となっていること
このように、生徒が自分の関心を出発点にして学びを進めるスタイルは、暗記中心の授業とは明らかに異なります。
探究学習の3つのプロセス「課題設定→情報収集・整理分析→まとめ・表現」
高校で展開される探究学習は、以下の一連のプロセスに沿って進められます。これを通じて、自ら考え行動する力が自然と身につきます。
探求学習の3つのプロセス
- ① 課題設定:問いを見つける
生徒自身が興味・関心や社会問題から、「なぜそうなるの?」「どうすればもっと良くなる?」と、自分なりの問い(テーマ)を見つけます。この主体的な問いの立て方こそが、探究学習の出発点です。 - ② 情報収集・整理分析:深掘りする
図書館の書籍、インターネット、インタビュー、フィールドワークなど多様な手段で情報を集めます。その後、集めた情報を分類・比較・分析し、「何が言えるのか」を考えまとめていきます。 - ③ まとめ・表現:学びを伝える
分析した内容をレポートやスライド、ポスターなどにまとめ、クラスや学年全体で発表します。他者との質疑応答や交流を通じて、考えがさらに深まります。
高校ではどんな探究活動がおこなわれている?
2022年度に必修化された「総合的な探究の時間」は、高校教育における学びの転換点です。「何を学ぶか」だけでなく、「どう学ぶか」「どう活かすか」を重視する探究スタイルが広がっています。
探究学習の主なスタイル
- 地域課題解決型:地域住民や自治体と連携し、身近な社会課題を探究
- グローバル/SDGs型:国際問題や持続可能をテーマに、国内外と連携した学び
- 研究型(学術探究):自らの興味を深め、論文や研究発表を目指す探究
以下でそれぞれのタイプを代表する高校事例を取り上げ、実際にどのような学びがおこなわれているのか紹介します。
事例①地域課題の解決に挑むフィールドワーク型
まず「地域課題解決型(フィールドワーク型)」の代表校を紹介します。
代表校:島根県立隠岐島前高等学校(地域共創科)
- 地域共創DAYを導入し、週に1日丸ごと地域のリアル現場で探究するカリキュラムを実施。
- 地元の漁業協同組合や観光協会と協働し、地元産品のブランド化や観光資源の発掘、移住促進SNS施策などを実践。
- 1期生卒業時点で、大学総合型選抜等により20名中15名が難関国立大学などに進学する成果も出ています。
このような実践を通じて、生徒は地域への愛着や当事者意識を育むことができ、教育として成果の出る環境が整っています。
事例②SDGsや国際問題に取り組むグローバル型
続いてグローバル型の代表校を紹介します。
代表校:静岡県立浜松開誠館高等学校(グローバル教育推進校)
- 「気候マーチ」プロジェクト
生徒2名の発案によって始まり、学校全体へ拡大された「気候マーチ」は、生徒が市中心部で気候危機のメッセージを掲げて行進し、市長に提言書を提出する活動です。最初は少人数からのスタートでしたが、今では400人規模となり地域社会にも大きな影響を与えています。 - SDGsを「自分ごと化」して学ぶ
生徒自身が自らの行動を通じて民主的に考え、声を上げ行動することで、SDGsを自分の生活に結びつけて深く理解する機会となっています。
このように、浜松開誠館高校は、SDGsを探究活動の核に据えて生徒主体の行動を重視し、地域や社会への責任感を育む学びを展開しています。
事例③興味をとことん追求する論文・研究型
最後に論文・研究型の代表校を紹介します。
代表校:京都市立堀川高等学校(探究科)
- 週2時間×1.5年間の探究基礎カリキュラム
「HOP・STEP・JUMP」の3段階構成で、疑問の発見から調査・仮説の検証、論理的思考の訓練、最終的に個人研究としてまとめ上げる緻密なプログラムです。 - ゼミ形式と多層的サポート体制
各10名程度の少人数ゼミで教員2名+大学院生などがティーチングアシスタント(TA)として関与。専門性の高いサポートを受けながら、主体的に研究を進められます。
京都市立堀川高等学校は、1999年に人文探究科と自然探究科の「探究科」を設置し、日本初期から探究教育を推進。
堀川高校の探究科では、好きな問いにじっくり向き合い、自分の言葉で考えをまとめる力が育まれます。親としては何より、「子どもが自分らしく探究を楽しめる学びの環境」であることが魅力ではないでしょうか。
探究学習が大学入試や将来に与える影響
探究活動で作成したレポートや発表資料は、大学入試で大きな武器になります。とくに総合型選抜や推薦入試では、それらをポートフォリオとして提出することができ、「主体的に学び取った経験」として評価される点が強みです。
さらに、面接では「なぜそのテーマを選んだのか」「どのような困難をどう乗り越えたのか」といった質問に答える場面があり、ここで主体性や思考力、問題解決力が深く見られます。
探究活動は学力だけでなく、子どもの「学びの姿勢」そのものを伝える機会となります。推薦や面接、書類審査でも、自信を持って語れる経験があることは大きな価値となります。
総合型選抜・学校推薦型選抜で評価される「探究の成果」
総合型選抜や学校推薦型選抜では、学校での探究活動の成果が重く評価されます。とくに、探究の成果をまとめたポートフォリオは重要な自己アピールの材料となります。
評価されるポイント
- ポートフォリオとして提出し、自分らしい学びの軌跡を示せる
探究テーマ、取り組んだプロセス、得られた気づきや成果をまとめた記録で、独創性や主体性を大学側に具体的に証明できる資料です。 - 面接では探究のプロセスが深掘りされる
面接官からは「なぜそのテーマを選んだか」「困難をどう乗り越えたか」といった問いがあり、その対応を通じて主体性・思考力・問題発見能力などが評価されます。
探究活動は、入試対策に留まらず、「学びへの姿勢そのもの」を伝える重要な機会です。大学側に「あなたらしさ」をアピールする決定打となるでしょう。
社会で必須となる課題解決能力の土台作り
高校での探究活動で身につく、「課題発見→情報収集・分析→企画立案→表現」のプロセスは、仕事や地域活動などで求められる課題解決力そのものです。
これらのスキルは、21世紀型スキルと呼ばれ、企業や大学でも高く評価されており、批判的思考・協働力・柔軟な判断力が重視されます。
育まれる力の例
- 問題解決力と批判的思考:情報を分析し、結論を導く思考力が自然と身につきます。
- コミュニケーション・協働力:共同調査や発表を通じて、相手に伝え協力する力が育まれます。
探究学習は、子どもが「自分で考え行動する習慣」を育む絶好の機会です。
その経験を見守りながら、家庭でも問いかけや対話の機会を増やしてあげることで、将来にわたって役立つ力が自然に根づきます。
高校教育に浸透しつつある「ICT教育」と、その先の「STEAM教育」とは?

近年、高校教育ではまずICT教育の基盤整備が進み、そしてその延長線上に「探究×創造」を重視するSTEAM教育の導入が進んでいます。
簡単にいうとICT教育は、オンライン環境を活かした学びの「基盤」を整えており、STEAM教育はその基盤を活かし、「自分で考え、創り出せる学び」に進化させる次のステージということです。
高校でのICT環境と情報活用能力
GIGAスクール構想により、高校にも「生徒一人ひとりに端末」が行き渡り、授業や家庭での学びがスムーズに連携するようになりました。
ICTを「使う」から、「考えて使う力」へと進化しつつある学びの現場を紹介します。
具体的な活用例
- 1人1台端末の整備が急速に進行
端末の整備は全国の学校でほぼ完了し、教室だけでなく家庭や教室外の学びにも活用できる環境が整いつつあります。 - 授業でのクラウドツール活用が定着
Google Classroom や Microsoft Teams によって、資料共有・課題提出・グループ学習が自然にオンラインでもおこなわれています。 - 情報モラルから「デジタル・シティズンシップ」へ教育の転換
従来の情報モラル教育では制限が中心でしたが、今は児童生徒が自律的にICTを活用し、社会で責任ある行動ができる力を育てる「デジタル・シティズンシップ」が重視されています。
教科の枠を越えて創造する「STEAM教育」という新しい学び方
STEAM教育は、S・T・E・A・Mを横断して学びをつなぎ、実社会の課題解決や価値創造に結び付ける学びです。以下で詳しく見ていきましょう。
なぜ今STEAM教育が注目されるのか?
STEAM教育は、Science(科学)・Technology(技術)・ Engineering(工学)・ Arts(芸術・リベラルアーツ)/・Mathematics(数学)を横断的に学ぶアプローチです。
AIやIoTで課題が複雑化する今、1つの教科だけでは解けない現実の課題に向き合うため、文系・理系の枠を越えた統合的な視点が求められています。
ねらいは、教科で得た知識を実社会の問題発見・解決に結び付け、論理的思考力と創造性の両方を育てて新しい価値を生み出せる人材を育成することです。
STEAM教育の具体例
STEAM教育では、たとえばロボット制御のプログラミング、統計データの視覚的デザイン化(インフォグラフィック)、3Dプリンターを使った日用品の自作など、理科・技術・工学・芸術・数学の要素を組み合わせた実践的学びがおこなわれます。
わが子にあう学校の選び方
高校は、偏差値や通学距離だけで選ぶ時代ではありません。 子どもが伸ばしたい力や将来の目標にあう教育方針を持つ学校を見極めることが大切です。
学校の選び方
- まずは公式サイトで基本情報をチェック
- 「教育方針」「カリキュラム」ページを確認する
- 「総合的な探究の時間」に関するページを確認する
①まずは公式サイトで基本情報をチェック
学校選びの第一歩は、各高校の公式サイトをじっくり確認することです。公式サイトには、学校案内や行事予定、部活動紹介、入試情報など、パンフレット以上に詳しい最新情報が掲載されています。
とくに今回のテーマに沿って見るべきポイントは、学びの特色や教育方針が具体的に表れているページです。理念やスローガンだけでなく、その内容を裏付ける取り組みや成果が記載されているかどうかが重要になります。
②「教育方針」「カリキュラム」ページを確認する
学校選びでは、その学校がどのような教育を大切にしているのかを知ることが欠かせません。公式サイトの「教育方針」や「カリキュラム」のページには、その学校の方向性や授業の特色が集約されています。
注目したいキーワード
- 探究
- ICT
- STEAM
- 主体性
- 課題解決
これらの言葉が単なるスローガンとして並んでいるだけではなく、実現するための具体的なプログラムや授業内容が明記されているかが重要です。
たとえば、探究学習なら実際のテーマや活動例、ICT活用なら使用しているツールや授業風景が写真付きで紹介されていると、より信頼性のある情報といえます。
こうした情報をもとに、学校の教育が自分の子どもの学び方や将来像にあっているかを判断できます。
③「総合的な探究の時間」に関するページを確認する
「総合的な探究の時間」は、学校の特色や教育の深さを知るうえで重要な指標になります。
公式サイトでは、過去の探究テーマや生徒の活動報告が掲載されていることが多く、それらを見ることで学校の取り組み姿勢やレベル感が分かります。
チェックしたいポイント
- 生徒が過去に取り組んだ探究テーマや発表内容が具体的に掲載されているか
- 発表会の様子や、生徒が作成したポスター・論文などの成果物が閲覧できるか
- 大学や企業、地域団体と連携した探究活動が行われているか
これらの情報から、単なる課題発表にとどまらず、社会とつながる学びが実現しているかを見極められます。外部連携が豊富な学校ほど、実践的で質の高い探究学習をおこなっている可能性が高く、進学やキャリア形成にも良い影響を与えます。
今後の高校教育はどうなる?数年先の展望
Society 5.0や教育改革の進展により、高校教育は知識の暗記から、変化に対応し価値を創造する力の育成へと移行しています。探究学習や教科横断型プロジェクトが増え、AIやICTを使った個別最適化学習も広がっています。
デジタル教科書や生成AIの導入で、音声・動画・双方向教材を活用した多様な学びが可能に。さらに、オンライン交流や海外研修などで、多文化理解と国際的なコミュニケーション力を養う機会も増えています。
Society 5.0時代に求められる教育とは
Society 5.0は、IoTやAIなどの先端技術を活用して経済成長と社会課題の解決を両立する未来社会の構想です。この社会では、単なる知識習得だけでなく、変化の激しい環境に適応し、新しい価値を創り出す力が重要になります。
高校教育もその方向にシフトし、探究的な学びや課題解決型の授業が増えています。生徒は多様な情報を分析・統合し、自分なりの答えを導き出す力を磨く必要があります。また、教科間の壁を越えて学ぶ機会が増えることで、文理を融合した総合的な視野が育まれます。
【求められる力の例】
- 課題解決力:社会課題や地域の問題をテーマに、調査・企画・提案をおこなう
- 情報活用力:データ分析やICTツールを使って情報を整理・発信する
- 創造力:複数分野を組み合わせ、新しいアイデアやサービスを考案する
- 協働力:異なるバックグラウンドを持つ人と意見を交わし、共通の目標を達成する
知っておきたい教育のトレンド一覧
高校生活は3〜5年続くため、入学時点での教育方針や学びの環境は卒業時の力に直結します。ここでは、今後注目される教育のトレンドを一覧で整理します。
【注目される教育のトレンド】
- デジタル教科書の本格導入
音声や動画が埋め込まれた教材で学び、AIが学習データを分析して個別最適化を実現 - AI活用の広がり
課題解決や文章作成のサポートなど、AIを効果的に使いながら批判的思考や倫理観も育成 - 教科横断型プロジェクト
文系・理系の枠を超えた協働学習が増加し、実社会とつながる課題解決型学習が推進 - グローバル教育の強化
オンライン交流や海外研修を通じて、多文化理解と国際的なコミュニケーション能力を習得
これらの動きは、単なる教育方法の変化にとどまらず、生徒一人ひとりの将来設計にも影響します。学校選びの際は、こうしたトレンドを踏まえて、わが子の成長にあう環境を見極めることが大切です。
まとめ
高校の学びは、2022年度の新学習指導要領で「どう学び、何ができるか」を軸に、必修の「総合的な探究の時間」が中核になりました。
大学入試も総合型・推薦型を中心に多面的評価へ進み、探究のポートフォリオや面接でのプロセス説明が強みになります。またGIGAスクールで整った1人1台端末の基盤の上でSTEAMの教科横断学習が広がり、AI・IoT時代に必要な論理性と創造性を育てる環境が整い始めています。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。