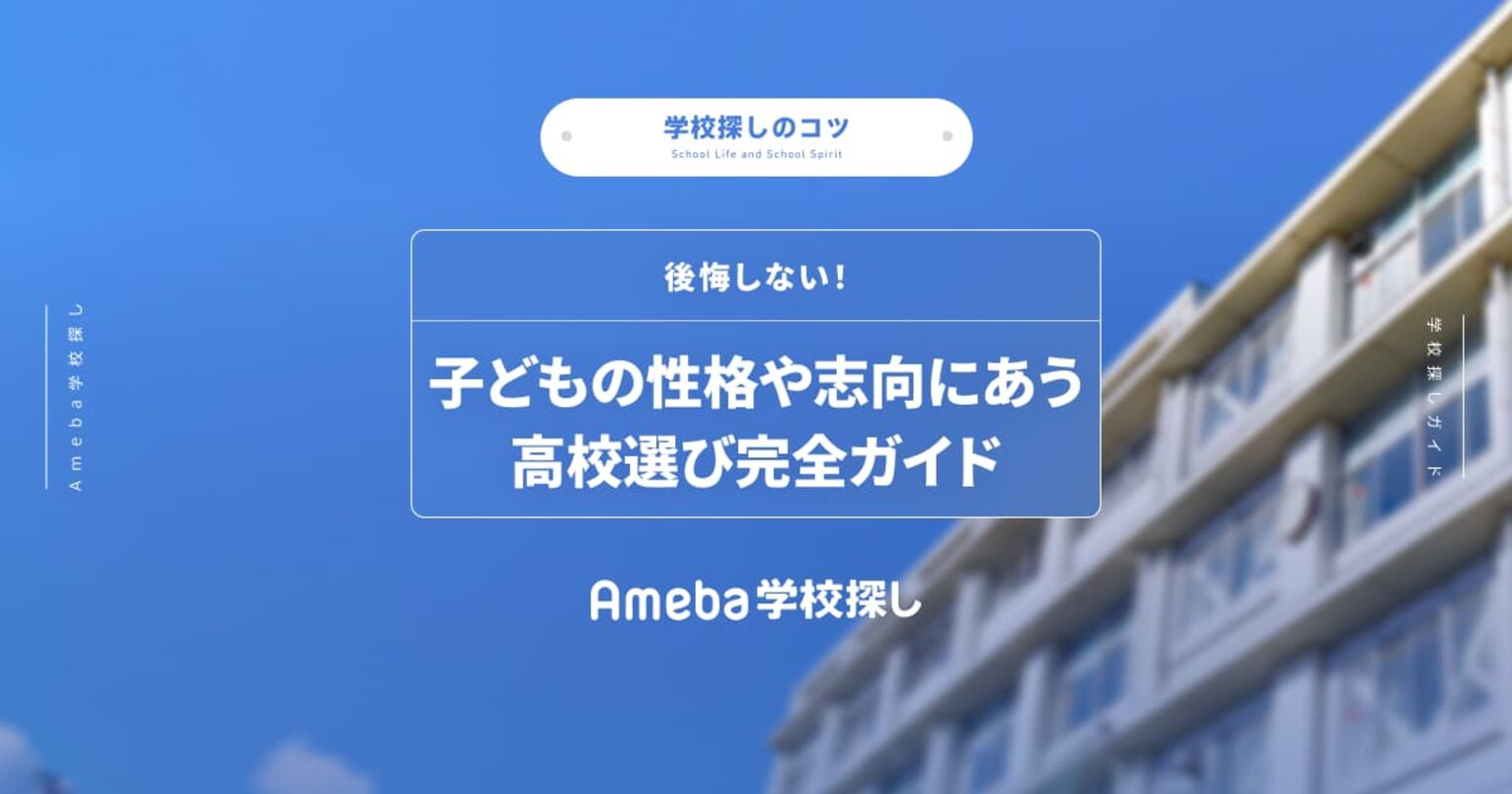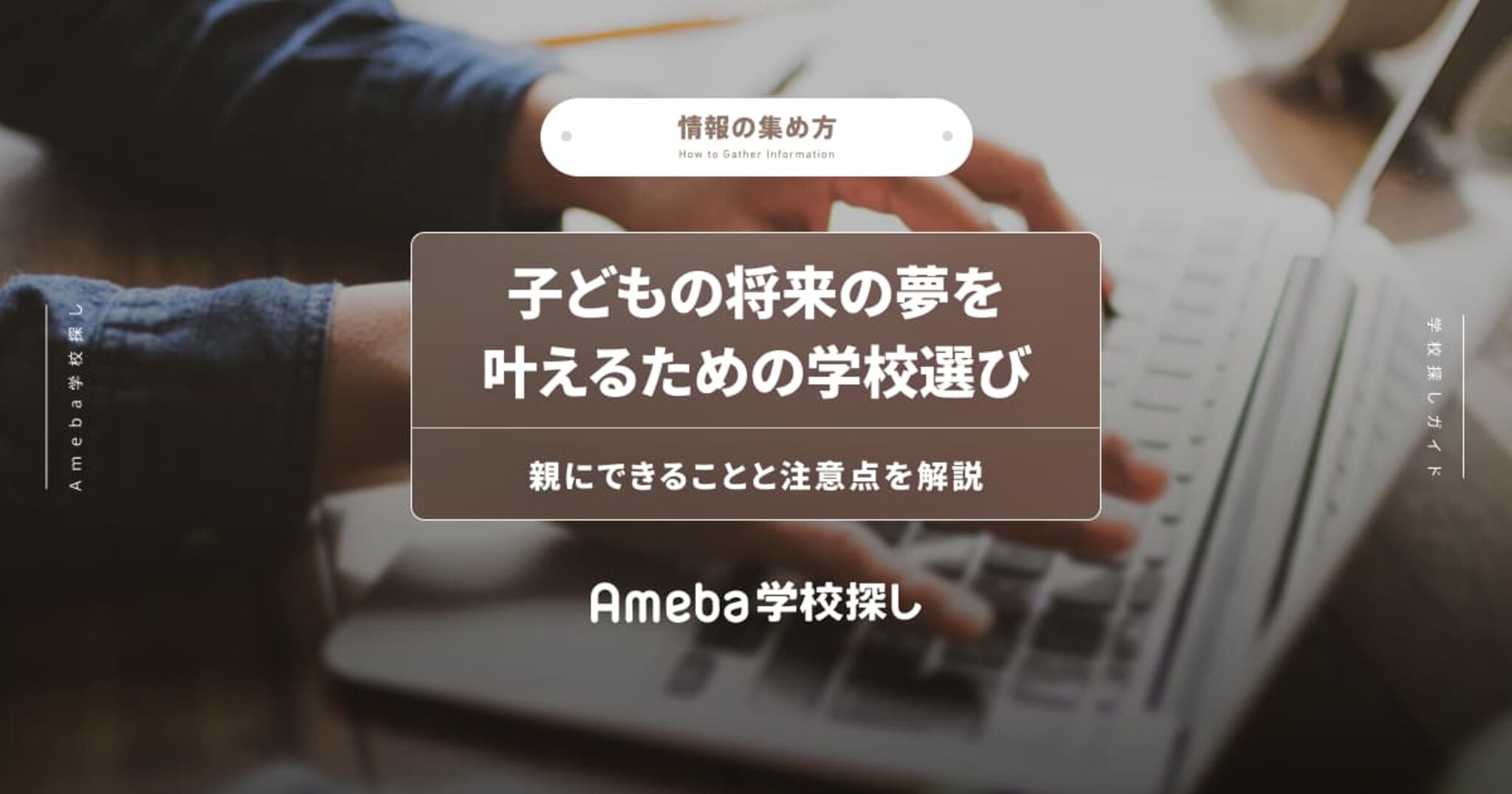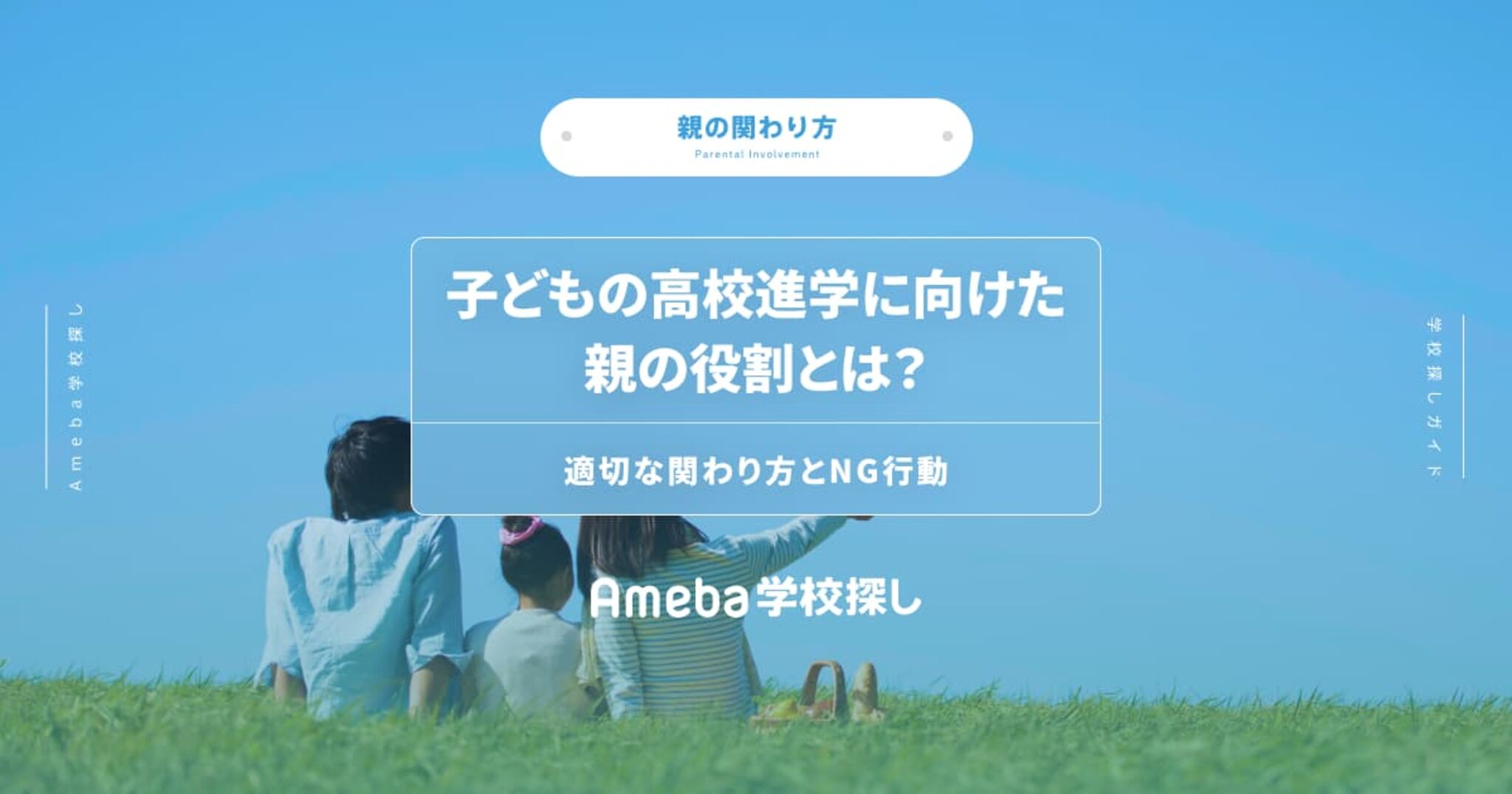「うちの子にはどんな高校があうんだろう?」「偏差値だけで選んで大丈夫かな…」
中学3年生のお子さんを持つ保護者のみなさん、高校選びで悩んでいませんか?進路決定の時期が近づくにつれて、不安が大きくなるのは当然のことです。
偏差値や立地のよさだけで選んでしまい、入学後に「思っていた学校と違った」と後悔するケースは決して珍しくありません。大切なのは、お子さん一人ひとりの性格・志向・将来の夢に本当にあった学校を見つけることです。
本記事では、「どんな高校がどんなタイプの子にあうのか」という視点から、高校の種類や選び方のポイントを具体的に解説します。お子さんが自分らしく成長し、充実した高校生活を送れる学校選びの参考にしてください。
※本記事は2025年7月時点の情報に基づいて作成されています。高校の制度や入試制度は変更される場合がありますので、最新の情報については各学校や教育委員会の公式サイトでご確認ください。
- まずは高校の種類と特徴を知ろう
- 公立高校と私立高校の特徴を理解しよう
- 全日制・定時制・通信制の違いを把握しよう
- 子どもの性格・志向をもとにした高校の選び方
- ①内向型・外向型など性格にあわせて選ぶ
- ②将来像や興味から逆算して選ぶ
- 【子どものタイプ別】おすすめの高校
- 【勉強が好き・大学進学志望】の子どもにあう高校
- 【マイペース・個性重視型】の子どもにあう高校
- 【人間関係が心配・学校生活に不安がある】子どもにあう高校
- 子どもにあう高校を選ぶために見学・説明会でチェックすべきポイント
- ①授業・先生・生徒の関わり方を見る
- ②子どもの表情・反応を観察する
- 子どもの高校選びにおける親の関わり方
- ①親の希望を押しつけすぎない
- ②定期的な対話で価値観をすり合わせる
- 子どもの意見を尊重し、総合的に判断して最適な高校を選ぼう
まずは高校の種類と特徴を知ろう

高校選びを始める前に、まずは高校にはどのような種類があるのかを整理しておくことが大切です。設置者による分類、学習時間による分類など、それぞれに特徴があります。
お子さんにあった高校を見つけるために、基本的な知識から確認していきましょう。
公立高校と私立高校の特徴を理解しよう
高校は設置者によって「公立高校」と「私立高校」に大きく分けられます。それぞれに明確な特徴があるため、ご家庭の教育方針や経済状況も含めて検討することが重要です。
公立高校の特徴
学費負担の軽減:高等学校等就学支援金制度により、世帯年収に応じて授業料の支援が受けられます。年収590万円未満の世帯では授業料相当額(年額118,800円)が支給され、実質的な負担軽減が図られています。
地域密着型の教育:地元の中学校から多くの生徒が進学し、地域とのつながりが強い特徴があります。
学力別に多様な選択肢:進学指導重点校から職業系専門学科まで幅広い選択肢が用意されており、生徒の進路希望に応じた教育が提供されています。
学習指導要領に基づく教育:文部科学省の学習指導要領に沿った標準的なカリキュラムが実施されています。
私立高校の特徴
独自の教育理念:建学の精神に基づいた特色ある教育を実施し、各校の個性を活かした教育活動が展開されています。
多様なコース制:特進コース、国際コース、スポーツコースなど目的別の選択が可能で、生徒の個性や進路希望に応じた専門的な教育が受けられます。
充実した施設・設備:最新の設備や専門的な施設を備えている場合が多く、教育環境の充実が図られています。
きめ細かい指導:少人数制や習熟度別授業など、個別対応が充実した指導体制が整備されています。
学費について:私立高校の学費は学校により大きく異なります。なお、私立高校においても高等学校等就学支援金制度の対象となり、世帯年収に応じた支援が受けられます。年収590万円未満の世帯では年額396,000円を上限として支援金が支給されます。
全日制・定時制・通信制の違いを把握しよう
学習時間帯による分類も重要な選択要素です。文部科学省では、生徒の多様なニーズに応じた高等学校教育の提供を推進しており、全日制だけでなく、定時制や通信制も制度の充実が図られています。
全日制高校の特徴
平日の日中に授業をおこない、3年で卒業する最も一般的な高等学校です。部活動、学校行事、生徒会活動など、学習指導要領に基づく教科指導と特別活動が組織的に実施されています。
同年代の生徒との協働的な学習を通じて、社会性やコミュニケーション能力の育成が図られ、大学進学、就職など多様な進路に対応した系統的な進路指導がおこなわれています。
定時制高校の特徴
勤労青少年などの学習機会を確保するため、夜間など特別の時間に授業をおこなう課程です。近年は昼間部や多部制を設置する学校も増加しています。
働きながら学ぶ生徒のほか、全日制高校になじめなかった生徒、高校教育を受ける機会を逸した者など、多様な学習者を受け入れています。標準修業年限は4年ですが、学習状況に応じて3年での卒業も可能です。
通信制高校の特徴
レポート(添削指導)、スクーリング(面接指導)、テスト(試験)により単位を認定する課程です。生徒の自学自習を基本とし、レポート作成を通じて学習内容の理解と定着を図ります。
近年はインターネットを活用した授業も実施され、学習の利便性が向上しています。不登校を経験した生徒、芸術・スポーツ活動に重点を置く生徒、社会人など、さまざまな事情を持つ学習者の教育機会確保に重要な役割を果たしています。
文部科学省では「すべての生徒が安心して学ぶことができる魅力ある高等学校づくり」を推進しており、これらの多様な学習形態は、生徒一人ひとりの個性や能力、進路希望に応じた教育機会の提供を目的としています。
お子さんの学習スタイルや生活状況に最も適した教育課程を選択することで、充実した高校生活を送ることが期待されます。
子どもの性格・志向をもとにした高校の選び方

高校の種類を理解したら、次に重要なのはお子さん自身の特性を把握することです。同じ学校でも、性格や学習スタイルによって感じ方は大きく異なります。
お子さんが3年間を充実して過ごせるよう、性格や志向にあった学校選びのポイントを見ていきましょう。
①内向型・外向型など性格にあわせて選ぶ
お子さんの性格と学校の校風があっているかは、高校生活の満足度に大きく影響します。性格的な特徴を理解して、お子さんがストレスなく過ごせる環境を選びましょう。
内向的な性格のお子さんには、落ち着いた校風で集中できる学習環境が整った学校が適しています。少人数制のクラスで一人ひとりに丁寧な指導が受けられる環境や、質問しやすい雰囲気で個人のペースを尊重してくれる学校を選ぶとよいでしょう。
図書館や自習室が充実していて、一人で集中して学習できるスペースがあることも重要です。学校行事も強制参加ではなく、参加方法を選択できる配慮があれば安心です。
外向的な性格のお子さんには、学校行事や部活動が盛んでエネルギッシュな雰囲気の学校が向いています。委員会活動やボランティア、地域連携など多様な交流機会があり、グループ学習やディスカッションを取り入れた授業が充実している学校がおすすめです。
生徒会活動や行事の実行委員など、リーダーシップを発揮できる場があることで、お子さんの持つ力を最大限に発揮できるでしょう。
ただし、内向的・外向的という分類は目安であり、お子さんの個性は一人ひとり異なります。「うちの子は内向的だから静かな学校」と決めつけるのではなく、お子さん自身がどのような環境で力を発揮できるかを一緒に考えることが大切です。
②将来像や興味から逆算して選ぶ
お子さんの将来の夢や興味のある分野が明確な場合は、それに向けた準備ができる高校を選ぶことで、より充実した高校生活を送れます。
大学進学を希望する場合は、希望する大学や学部への合格実績を確認し、受験に必要な科目の授業時間数や内容が充実しているかをチェックしましょう。
進路相談や模試、進学説明会などのサポート体制も重要です。近年の大学入試では探究活動など主体的な学習も重視されているため、そうした機会が豊富な学校を選ぶとよいでしょう。
専門分野への興味が強い場合は、理数系、国際系、芸術系など特化したコースが設置されているかを確認してください。実験室や語学室、音楽室などの専門設備の充実度、在学中に取得できる資格や検定、大学や企業との連携プログラムの有無も重要な要素です。
職業系の進路を考える場合は、実際の職場に近い環境での実践的な学習ができる学校がおすすめです。求人開拓や面接指導、インターンシップなどの就職サポート、就職に有利な資格取得支援があることを確認しましょう。
地域企業との協力関係があれば、より具体的な職業イメージを持てます。
将来の目標が明確でないお子さんも多いですが、それは問題ではありません。高校生活を通じてさまざまな経験をしながら将来の方向性を見つけられるよう、幅広い選択肢を提供してくれる学校を選ぶこともひとつの方法です。
お子さんの意見を聞きながら、一緒に最適な学校選びを進めていきましょう。
【子どものタイプ別】おすすめの高校

お子さんの性格や志向を理解したところで、具体的にどのような高校があうのかを見ていきましょう。ここでは代表的な3つのタイプ別に、おすすめの高校の特徴を紹介します。
ただし、お子さんの個性は一人ひとり異なるため、あくまで参考として捉え、最終的にはお子さん自身の気持ちを最優先に考えてくださいね。
【勉強が好き・大学進学志望】の子どもにあう高校
学習意欲が高く、将来は大学でさらに専門的な勉強をしたいと考えているお子さんには、進学実績が豊富で受験対策が充実した学校が適しています。
進学校と呼ばれる学校では、大学受験に向けた体系的なカリキュラムが組まれており、3年間を通じて計画的に学力向上を図ることができます。
私立の特進コースや公立の進学指導重点校では、難関大学への合格実績も豊富で、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら学習に取り組める環境が整っています。
また、近年注目されているのが、探究型学習や課題研究の時間が充実した学校です。これらの学校では、単に知識を詰め込むだけでなく、自分で課題を設定し、調べ、考え、発表するという主体的な学習を通じて、大学での学びに必要な思考力や表現力を身につけることができます。
このような経験は、推薦入試やAO入試でも高く評価されることが多く、志望大学への道筋を広げてくれます。
ただし、進学校を選ぶ際は、お子さんが勉強だけでなく部活動や学校行事も楽しめるかどうかも確認しておきましょう。バランスの取れた高校生活で、人間的な成長も期待できます。
【マイペース・個性重視型】の子どもにあう高校
自分のペースで学習したい、個性を大切にしたいと考えているお子さんには、緩やかな校風で生徒の自主性を尊重する学校がおすすめです。
総合学科や単位制高校では、従来の普通科とは異なり、お子さんの興味や将来の目標に応じて科目を選択できる柔軟なシステムが特徴です。
たとえば、文学に興味があるお子さんは国語系の科目を多く選択し、将来は保育士になりたいお子さんは家庭科や心理学関連の科目を中心に学ぶことができます。このような学校では、一人ひとりの興味や適性に応じた学習ができます。
さらに、芸術系、スポーツ系、IT系など専門分野に特化したコースを設置している学校も増えています。音楽や美術に才能があるお子さん、スポーツで特技を持つお子さん、プログラミングや情報処理に興味があるお子さんなどは、こうした専門コースで自分の得意分野を伸ばしながら、同時に一般的な教養も身につけることができます。
これらの学校では、生徒の個性を尊重し、多様な価値観を認める校風が一般的です。お子さんが「自分らしさ」を大切にしながら成長できる環境です。
【人間関係が心配・学校生活に不安がある】子どもにあう高校
中学校で人間関係に悩んだ経験があったり、大きな集団での生活に不安を感じたりするお子さんには、きめ細かいサポート体制が整った学校を選ぶことが大切です。
少人数制を採用している学校では、先生と生徒の距離が近く、一人ひとりの状況をしっかりと把握してもらえます。困ったときにも相談しやすく、お子さんのペースにあわせた指導が受けられます。カウンセリング体制が充実している学校では、学習面だけでなく精神面でのサポートも期待できます。
不登校の経験があるお子さんや、従来の学校システムに馴染みにくいお子さんには、通信制高校やサポート校という選択肢もあります。
これらの学校では、登校日数を調整できたり、個別指導を中心とした学習スタイルを取ったりすることで、お子さんの状況に応じた柔軟な対応が可能です。通信制高校でも全日制と同じ高校卒業資格を取得できるため、将来の進路選択に制限はありません。
フリースクールと連携している学校や、多様な学習スタイルを認めている学校では、お子さんが安心して学べる環境づくりに力を入れています。
どのタイプのお子さんにも共通していえることは、学校選びの際は必ず実際に足を運んで、校風や先生方の雰囲気を確認することです。お子さんと一緒に見学に行き、お子さん自身がどう感じるかを聞いてみてください。
子どもにあう高校を選ぶために見学・説明会でチェックすべきポイント

どんなに詳しく情報を集めても、実際に学校を見学しなければわからないことがたくさんあります。パンフレットやウェブサイトでは伝わらない学校の雰囲気や、お子さんとの相性を確認するために、積極的に学校見学や説明会に参加しましょう。
①授業・先生・生徒の関わり方を見る
学校見学で最も重要なのは、実際の授業の様子を観察することです。先生が一方的に話す講義形式なのか、生徒との対話を重視した双方向の授業なのかを確認してください。
お子さんが積極的に発言するタイプなら参加型の授業が適しており、じっくり考えるタイプなら個人の思考時間を大切にする授業スタイルが適しています。
先生と生徒の関係性も重要な観察ポイントです。先生が生徒の名前を覚えて個別に声をかけているか、生徒が気軽に質問できる雰囲気があるかを見てみましょう。
生徒同士の関係性も見逃せません。クラスの雰囲気が和やかで、お互いを尊重し合っているか、多様な個性が受け入れられているかを観察してください。
②子どもの表情・反応を観察する
保護者の評価も大切ですが、それ以上に重要なのはお子さん自身がその学校をどう感じるかです。校舎に入った瞬間のお子さんの表情に注目しましょう。明るい表情になっているなら、その学校の雰囲気に好感を持っています。
授業見学中に熱心に授業を見ていたり、「面白そう」といった反応を示したりする場合は、その学校の教育内容がお子さんの興味にあっている証拠です。
見学後はお子さんと感想を話し合う時間を設け、「どの場面が印象に残った?」といった質問で率直な気持ちを聞いてみてください。
「なんとなく落ち着く」「この雰囲気が好き」といった直感的な反応も重要な判断材料です。気になる学校があれば、文化祭や体験授業など別の機会にも足を運んでみることをおすすめします。
子どもの高校選びにおける親の関わり方
子どもが高校を選ぶ際、保護者はどこまで介入すればよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。ここでは、子どもの高校選びにおける親の関わり方について紹介していきます。
①親の希望を押しつけすぎない
「我が子にはよい高校に進学してほしい」という親心は自然で大切な気持ちです。しかし、その思いが強すぎると、お子さんに自分の価値観を押しつけてしまうことがあります。
「偏差値の高い学校なら将来安心」といった考えに固執するのではなく、お子さんの適性や希望と一致しているかを確認することが何より大切です。
たとえば、お子さんがスポーツに打ち込みたいのに勉強一筋の進学校を勧めることは、可能性を狭めてしまいます。
大切なのは、お子さんの個性や適性、そして本人の気持ちを第一に考えることです。お子さんが自分らしく成長できる環境を一緒に見つけることが、親として最も大切な役割です。
②定期的な対話で価値観をすり合わせる
高校選びは一度で終わりではありません。お子さんの成長とともに考え方や興味も変化するため、定期的な対話を重ねながら、お互いの価値観をすり合わせることが重要です。
中学1・2年生のころから、将来について気軽に話し合う習慣を作ってみてください。対話で最も大切なのは、お子さんの意見をまず受け止めることです。たとえ現実的でないと感じても、「そう考えているんだね。どうしてそう思ったの?」と興味を示してください。
対話では、お子さんの自主性を育てることが大切です。さまざまな選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを理解し、自分なりの判断基準を持てるようサポートしましょう。迷った際は、専門家に相談することも有効です。
子どもの意見を尊重し、総合的に判断して最適な高校を選ぼう
高校選びは重要な決断ですが、偏差値や世間体だけで判断するのではなく、お子さん一人ひとりの個性や将来への想いを大切にした選択をすることが何より大切です
現在の高校選びは「偏差値重視」から「子どもらしさを軸にした選択」の時代へと変化しています。お子さんが自分らしく成長できる環境を見つけることが重要です。
お子さんにとって最適な高校とは、必ずしも偏差値の高い学校ではありません。毎日楽しく通学でき、興味や関心を深められ、将来への希望を育てられる学校こそが真に価値ある選択となります。内向的なお子さんには落ち着いた環境の学校を、外向的なお子さんには活発な交流機会が豊富な学校を選択しましょう。
そして保護者の方は「進路を押しつけない、けれどしっかりと寄り添う」姿勢を心がけてください。お子さんの意見を尊重しながら、必要な情報提供やアドバイスをおこない、自信を持って選択できるようサポートしましょう。
学校見学や説明会は、お子さんが将来をイメージし、主体的に選択する力を育てる絶好の機会です。お子さんの表情や反応を大切にし、直感も含めた総合的な判断で本当にあう学校を見つけましょう。
もし迷いや不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。中学校の進路指導の先生、各高校の相談窓口、教育相談機関など、さまざまなサポート体制が整っています。
お子さんが自分らしく学び、充実した高校生活を送れる学校選びを、ぜひ一緒に進めてください。きっと最適な道が見つかるはずです。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。