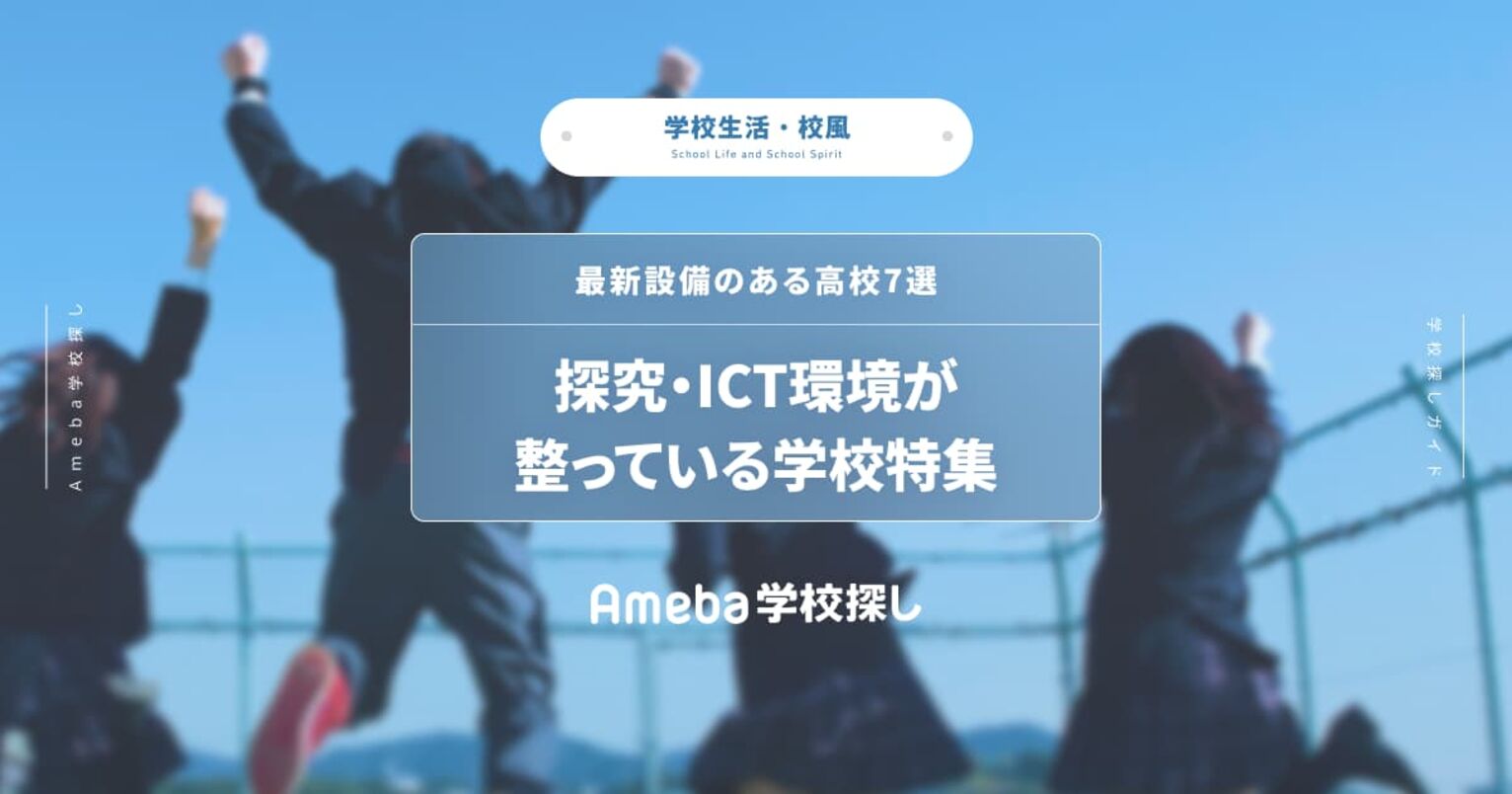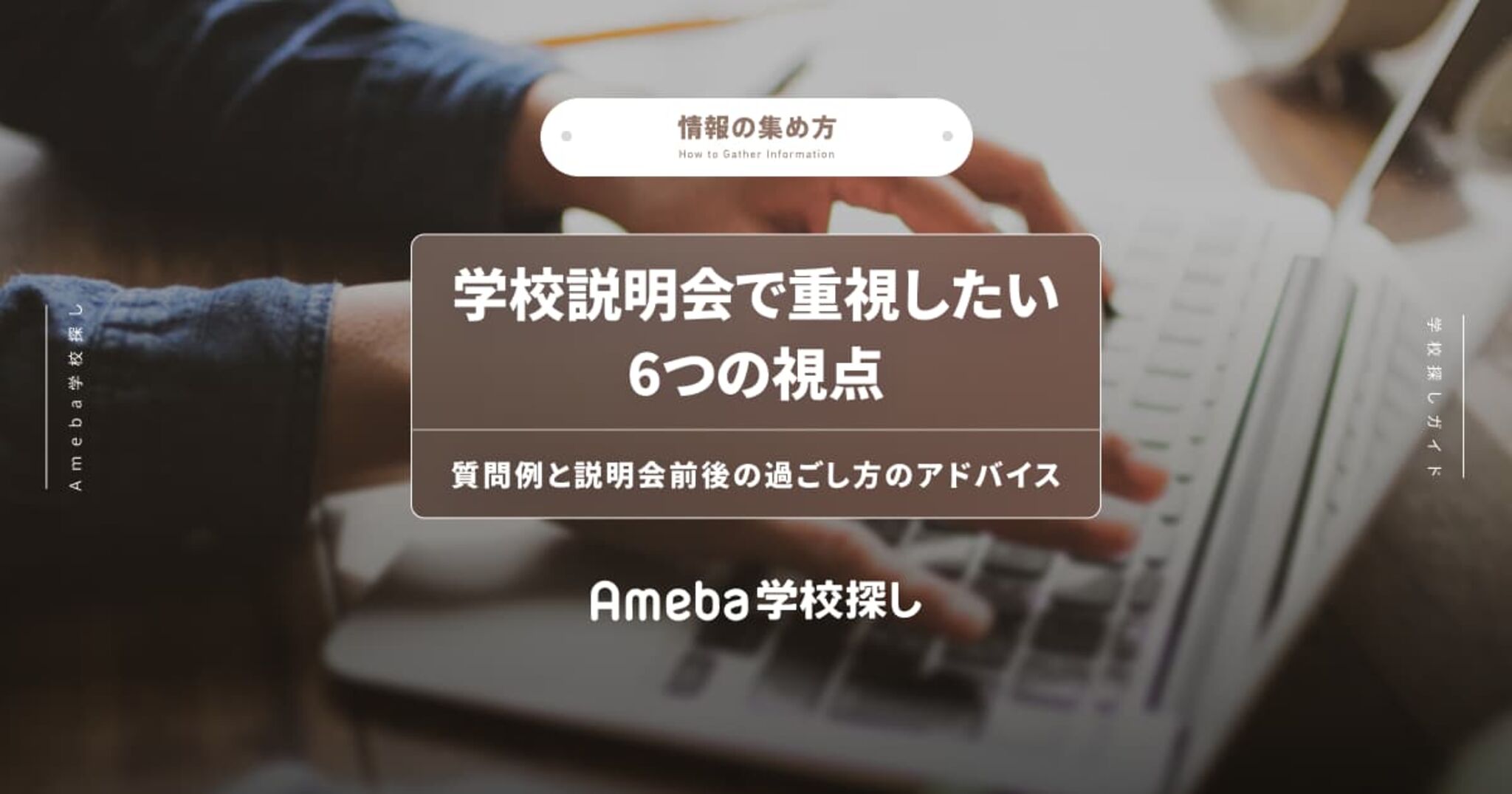大学入試で問われる「思考力」や「表現力」「主体的な学び」への対応が本格化し、設備投資=学びの質に直結する時代になりました。
1人1台端末、クラウドLMS、ラーニングコモンズ、メイカースペース、サイエンスラボなど、最新設備のある教育環境で学ばせたい、という保護者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本特集では、最新設備が充実し、「授業→探究→発表」の循環を生む高校を首都圏・関西圏から厳選して紹介します。見学時の着眼点や質問例など保護者がすぐに役立つ情報も紹介しますので、ぜひご覧ください。
※本記事の学校情報は2025年8月25日時点のものです。最新情報については各学校の公式サイトでご確認ください。
- 高校の選定基準と見学時に確認したいポイント
- 選定基準
- 見学時のチェックポイント
- 【首都圏】最新設備×探究・ICTが強い高校4校
- 広尾学園高等学校(東京都)
- 三田国際科学学園高等学校(東京都)
- 工学院大学附属高等学校(東京都)
- 開智日本橋学園高等学校(東京都)
- 【関西圏】最新設備×探究・ICTが強い高校3校
- 関西学院千里国際高等部(大阪府)
- 立命館守山高等学校(滋賀県)
- 京都先端科学大学附属高等学校(京都府)
- 【説明会・面談用】"設備が学びを変えるか"を見抜く質問例
- 授業での具体活用
- 評価と発表
- 運用と安全
- 家庭における準備と確認すべきポイント
- 初期費用・維持費の目安を確認する
- 家庭でのICTリテラシー
- 無理のない通学動線
- 最新設備の高校は学びの循環を生む設計かどうかを見極めよう
高校の選定基準と見学時に確認したいポイント

最新設備を備えた高校を選ぶ際には、単に機器があるかどうかではなく、その設備が子どもの学びにどのように活用されているかを見極めることが重要です。
設備の充実度だけでなく、それが子どもの日常的な学習にどのような効果をもたらしているかを確認することで、価値のある学校選びができるでしょう。
選定基準
今回紹介する高校の選定では、以下の3つの基準を重視しました。
- カリキュラム実装:探究/PBL/STEAMが時間割と評価に組み込まれている
└単発のイベントではなく、通常の授業として探究学習やプロジェクト型学習が実施され、成績評価の対象となっていることを確認しています。 - ICT常時運用:1人1台端末・学校Wi-Fi・LMS・電子図書/デジタル教材の日常運用
└特別な授業だけでなく、日常的にICT機器が活用される環境があることを重視しています。ネットワーク環境の安定性やトラブル対応体制も含めて、お子さんが安心して学習に集中できる環境を提供している学校を選定しました。 - 空間の学習化:ラーニングコモンズ、スタジオ、制作・実験ラボなど学びの動線設計
└従来の教室だけでなく、さまざまな学習スタイルに対応できる空間設計を重視しています。グループワークから個人研究、発表活動まで、お子さんの学習の流れにあわせて柔軟に使える空間がある学校を選んでいます。
見学時のチェックポイント
学校見学の際には、以下の点を重点的に確認することをおすすめします。
設備がどの授業で、どの単元で使われ、どんな成果物が出ているか
見学時には、具体的にどの科目のどの単元で最新設備が活用されているかを質問してみましょう。
過去の生徒作品や研究成果を見せてもらうことで、お子さんがその学校で実際にどのような学びを体験できるかを具体的にイメージできます。
発表機会(学内外)と評価ルーブリックの有無
探究活動の成果を発表する機会がどの程度設けられているか、また評価基準が明確になっているかを確認しましょう。
外部コンテストへの参加実績や学会発表の機会があることは、お子さんのモチベーション向上にもつながります。
教員のICT運用力(研修・校内ルール)、端末トラブル対応体制
最新設備があっても、それを指導する教員のスキルが追いついていなければ効果的な学習はできません。
教員研修の実施状況や、端末トラブル時の対応フローを確認することで、安心してお子さんを任せられる環境かどうかを判断できます。
放課後の自習/制作/探究スペースの開放状況
授業時間以外にも設備を利用できるかどうかは、お子さんの主体的な学びを支える重要な要素です。
開放時間や利用ルール、安全管理体制についても確認しておくとよいでしょう。
【首都圏】最新設備×探究・ICTが強い高校4校
首都圏では、都心部の立地を活かした学外連携や、充実した設備投資により、高度な探究学習を実現している高校が多く見られます。
それぞれの学校が独自の特色を活かしながら、お子さんの可能性を最大限に引き出す教育環境を整えています。
広尾学園高等学校(東京都)
広尾学園高等学校は、医進・サイエンスコースを中心とした理系教育に定評があり、最新の実験設備と充実したICT環境を誇っています。
同校の6階「サイエンス・ストリート」に並ぶ3つの専門サイエンスラボでは、最先端の機器・設備を活用した本格的な研究活動が展開されています。
中学段階の「理数研究」から高校での本格的な研究まで、未知なる問題にアプローチする術を学びながら、医師・研究者として必要な科学的視点・思考法・マインドを養成します。
「知る」「進む」「拡げる」の3段階ステージで構成された6年間の研究活動では、内発的な知的好奇心を原動力として独創性のある研究に取り組みます。
中高の枠にとらわれない高い専門知識・技術を身につけながら、世界を見据えた新規性のあるテーマを追究し、科学者と同様に最新かつ信憑性の高い情報を収集・吟味する力を育成しています。
見学の際は、6年間を通した研究活動の成果展示を見てみましょう。授業・研究活動・中高大・産学連携の3本柱による教育活動、それを支える英語教育・ICT教育の取り組みにより、医師・研究者としての本質的なマインドを同時に育成している実績を確認できます。
三田国際科学学園高等学校(東京都)
三田国際科学学園高等学校は、Apple社の認定を受けるなど、ICT教育の先駆的な取り組みで注目を集めています。
Apple Distinguished School認定校として「BUILD」理念を実践。動画・3D・プログラミングによる創造活動が日常化した同校では、「自由な発想をかたちにする」をテーマに、ICTを学びのパートナーとして位置づけています。
生徒たちは1人1台のタブレット端末やノートパソコンを活用し、動画制作、音楽制作、アニメーション、3Dモデリング、プログラミングなど幅広いクリエイション活動を通じて、自分のアイデアを具現化する力を身につけているのです。
学校全体で無線環境を整備し、STEP1(個人での情報収集・思考構築)、STEP2(生徒同士の意見交換・リアルタイム共有)、STEP3(グループ討論を経た結論導出・プレゼンテーション)という段階的な学習プロセスが確立されています。
Wi-Fiを介した資料共有により、授業中のコミュニケーションが活性化し、多様な考えに触れる機会が豊富にあります。
見学時には、生徒によって組織されるBUILD委員会の活動に注目してください。ICT活用推進と将来的な規制ゼロ環境を目指し、生徒自らがルールやモラルについて問題提起し改善策を実践しています。
また、情報授業や最先端ICT企業との連携による特別講座でのプログラミング教育により、単なる利用者から創造者への転換を促す取り組みについても確認されることをおすすめします。
工学院大学附属高等学校(東京都)
工学院大学附属高等学校は、大学との連携を活かした実践的なSTEAM教育と充実したICT環境で高い評価を得ています。
併設する工学院大学の研究室と連携し、高校生のうちから本格的な研究活動に参加できる機会を提供しています。ロボット工学、AI開発、環境工学など、最先端の研究分野に触れることで、お子さんの進路選択の幅が大きく広がります。
校内のMake RoomとFabスペースには、3DプリンターやiMac、Adobe Creative Cloudが設置され、アイデアを実際に形にする体験ができます。生成AIを使いこなすだけでなく、情報の選択・活用・倫理的判断力を育てる実践的な指導がおこなわれています。
CADソフトを使った製品設計から3Dプリンターでの試作まで、ものづくりの一連の流れを体験できるカリキュラムがあり、放課後にはプログラミングやマインクラフト、動画制作などの専門班でスキルを磨くことが可能。
見学の際は、大学研究室との連携プログラムの具体的な内容や、Make Room・Fabスペースの安全管理体制について詳しく聞いてみましょう。放課後の利用時間や指導体制、ICT環境の活用方法についても確認しておくと安心です。
開智日本橋学園高等学校(東京都)
開智日本橋学園高等学校は、都心の立地を活かした探究学習と、先進的なICT活用で注目されています。
Googleアカウントを活用したクラウドベースの学習管理により、探究活動の記録と振り返りが効率的におこなわれています。チームでの共同編集機能により、リアルタイムでの意見交換や資料作成が可能になり、探究の質が大幅に向上。
東京都心という立地を活かし、企業や自治体、大学などでの調査や活動を継続的に実施しています。
英語教育は、「使う」ことを念頭に置いてカリキュラムや環境を整えており、実用に耐える英語を学ぶ機会を学習者に提供し、英語をコミュニケーションツールとして活用していく探究的な学びを実践しています。
見学時には、探究活動の年間計画と評価基準について詳しく説明を受けることをおすすめします。これまでの学外連携の実績や、生徒が実際におこなったプロジェクトの成果物も確認してみてください。
【関西圏】最新設備×探究・ICTが強い高校3校
関西圏では、国際的な教育プログラムと最新設備を組み合わせた独自の教育を展開している高校が目立ちます。
地域の特色を活かしながら、グローバルな視点での学びを重視した教育環境が整っています。
関西学院千里国際高等部(大阪府)
関西学院千里国際高等部は、国際バカロレア(IB)プログラムと充実したICT環境により、グローバル人材の育成に取り組んでいます。
多国籍な環境の中で、生徒たちは日常的に英語でのディスカッション、エッセイライティング、プレゼンテーションに取り組み、IBプログラムが重視する批判的思考力と表現力を同時に身につけています。
図書館を中心とした学習空間は、単なる図書館を超えて、探究活動の拠点として機能し、授業もおこなわれる多機能なコモンズとしての役割を果たしています。
加えて、Google for Educationを基盤とした先進的なICT教育により、LMS(学習管理システム)の運用が学習の前提となっています。
デジタルツールを駆使したプレゼンテーションやエッセイ作成が日常的におこなわれるなかで、学習の記録、省察、再設計という継続的な学習サイクルが生徒の学習スタイルに定着しているのが特徴です。
見学時には、IBプログラムの内部評価システムとICT機器活用の具体的な対応関係、そして英語での発信力を育成する発表会の記録とアーカイブシステムに注目してみましょう。
立命館守山高等学校(滋賀県)
立命館守山高等学校は、理数系教育に特化した設備と地域密着型の探究学習で注目を集めています。
高校生からPCとタブレットの2台活用を導入。探究学習では、ICTを活用してドローンを使った農業研究や、AIを活用したファッション診断Webサイト開発など、実社会の課題解決に取り組むプロジェクト型学習を展開しています。
放課後自習室「TERAKOYA」では、メンターのサポートのもと、生徒が自分で計画を立てて主体的に学習を進められる環境を提供。
立命館大学との連携により、大学レベルの研究設備を活用した探究活動や、企業との交渉を含む実践的なプロジェクト学習を通して、研究から発信までの一連のプロセスを体験できます。
見学時には、1人2台環境に対応した600×600サイズの正方形机や最新のICT設備を確認してください。生徒が制作した動画作品、プログラミング作品などの展示から、お子さんがどのような創造性を発揮できるかイメージできるでしょう。
京都先端科学大学附属高等学校(京都府)
京都先端科学大学附属高等学校は、校名変更とともに設備投資を積極的におこない、STEAM教育の充実を図っています。
校名変更を機に、Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsを統合したSTEAM教育を本格導入。併設大学だけでなく、地域企業との連携により、実社会の課題解決に取り組むプロジェクトが実施されています。
見学の際は、放課後の設備利用体制について詳しく聞いてみてください。生成AI利用に関する学校独自のガイドラインについても確認しておくとよいでしょう。
【説明会・面談用】"設備が学びを変えるか"を見抜く質問例
学校説明会や個別面談の限られた時間のなかで、その学校の設備がお子さんの学びにどのような効果をもたらすかを見極めるための、保護者が学校説明会で使える、やや掘り下げた具体的な質問例を紹介します。
授業での具体活用
実際の授業でどのように最新設備が活用されているかを確認することは、お子さんの日常的な学習環境を理解する上で重要です。
- 「英語や理科など実技を伴う教科では、端末やラボを使った学習はどのようにおこなわれていますか?」
この質問により、ICT機器や実験設備が単なる補助ツールではなく、学習の中核として活用されているかどうかがわかります。 - 「PBL(プロジェクト型学習)の際、端末で作成する成果物の形式(動画・スライド・レポートなど)はどう決まりますか?」
探究学習の成果物がワンパターンではなく、課題や生徒の特性に応じて柔軟に設定されているかを確認できます。 - 「端末使用の割合は、教室内での授業時間のうち何割程度を占めますか?」
ICT機器が日常的に活用されているか、それとも特別な時だけ使用されているかを把握できる重要な質問です。
評価と発表
探究学習や最新設備を使った学習の成果がどのように評価され、発表の機会が提供されているかを確認することは、お子さんのモチベーション維持に直結します。
- 「探究活動の評価は、発表内容だけでなく調査プロセスや協働性も点数化されていますか?」
結果だけでなく、取り組みの過程や他者との協働を重視する評価制度があるかどうかは、お子さんの総合的な成長を支える重要な要素です。 - 「学外発表は、地域イベント・学会・オンライン発表など、どの場で実施されますか?」
校内だけでなく、外部での発表機会があることは、お子さんの社会性や表現力の向上につながります。 - 「1年間での発表回数は学年ごとに決まっていますか?また全員が発表機会を得られますか?」
発表機会が一部の優秀な生徒だけでなく、すべての生徒に公平に提供されているかを確認することが重要です。
運用と安全
最新設備を安全かつ効果的に運用するための体制が整っているかどうかは、お子さんが安心して学習に集中できるかどうかに大きく影響します。
- 「端末が故障した場合、修理期間中は貸出端末を利用できますか?」
故障やトラブル時のサポート体制は、ICT教育の継続性に直接関わる重要な要素です。 - 「生成AI利用の際、出力内容の信頼性検証方法はどのように指導されていますか?」
生成AIの教育利用が進むなか、その適切な使用方法についての指導体制を確認することは重要です。 - 「情報モラル教育は年度の初めだけですか、それとも定期的(たとえば学期ごと)に実施されていますか?」
デジタル社会で必要な倫理観を身につけるための継続的な教育体制があるかどうかを確認できます。
上記のような質問をすると、学校のICT・探究活動の実態がかなり明確になります。
家庭における準備と確認すべきポイント
最新設備を備えた高校への進学を検討する際には、学校選び以外にも家庭で準備しておくべきポイントがあります。
事前に確認し備えることで、お子さんがスムーズに新しい学習環境に適応できるでしょう。
初期費用・維持費の目安を確認する
最新設備を活用した教育には、従来の教育費に加えて追加の費用が発生することが一般的です。
授業料だけでなく、端末購入・管理費、アプリ/クラウド利用料、実験消耗品・制作材料費、課外プログラム参加費などを確認しておきましょう。
家庭でのICTリテラシー
学校でICT教育を受けるお子さんをサポートするためには、家庭でも基本的なICTリテラシーを身につけておくことが重要です。
著作権・出典・AI利用の基礎知識を身につけ、家庭内の端末ルールを決め、ポートフォリオの見守り方法など、ICTリテラシーの向上を図りましょう。
無理のない通学動線
最新設備を活用した探究学習では、放課後の活動や休日の研究活動が充実している学校が多く見られます。
そのため、放課後の自習・制作・部活動まで見越した動線と最終下校時刻、自学スペースの使い勝手を確認しておきましょう。
最新設備の高校は学びの循環を生む設計かどうかを見極めよう
最先端の設備は見栄えではなく、学びの循環を生む設計かどうかを見極めることが大切です。
「設備→授業→成果物→発表→振り返り→再設計」が回っているか、その循環を時間割・評価・校外機会で後押ししているか、この2点を軸に、気になる学校をぜひ現地まで足を運び比較してください。
設備の使われ方が、わが子の探究力・表現力・進路の幅を決めます。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。