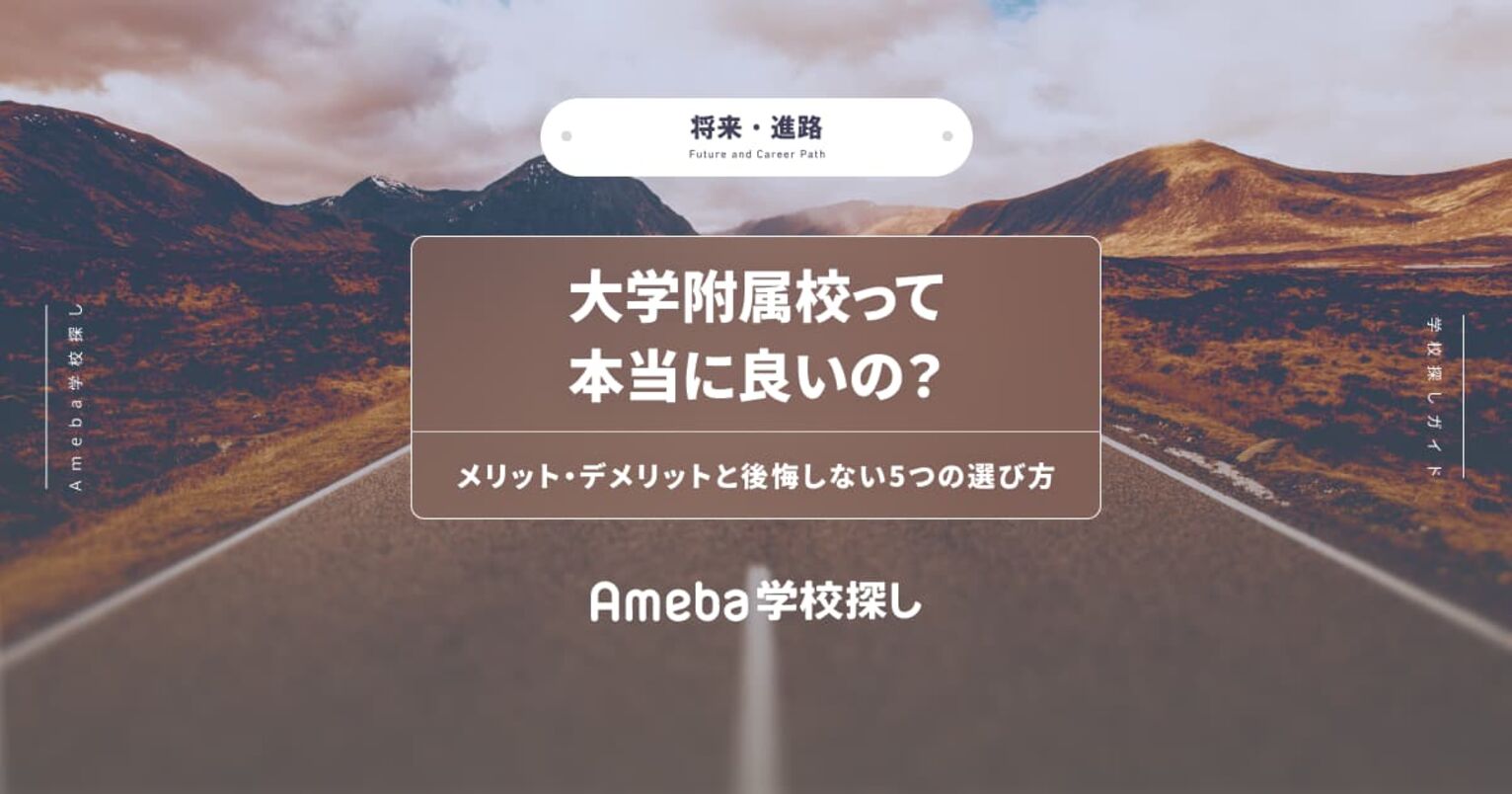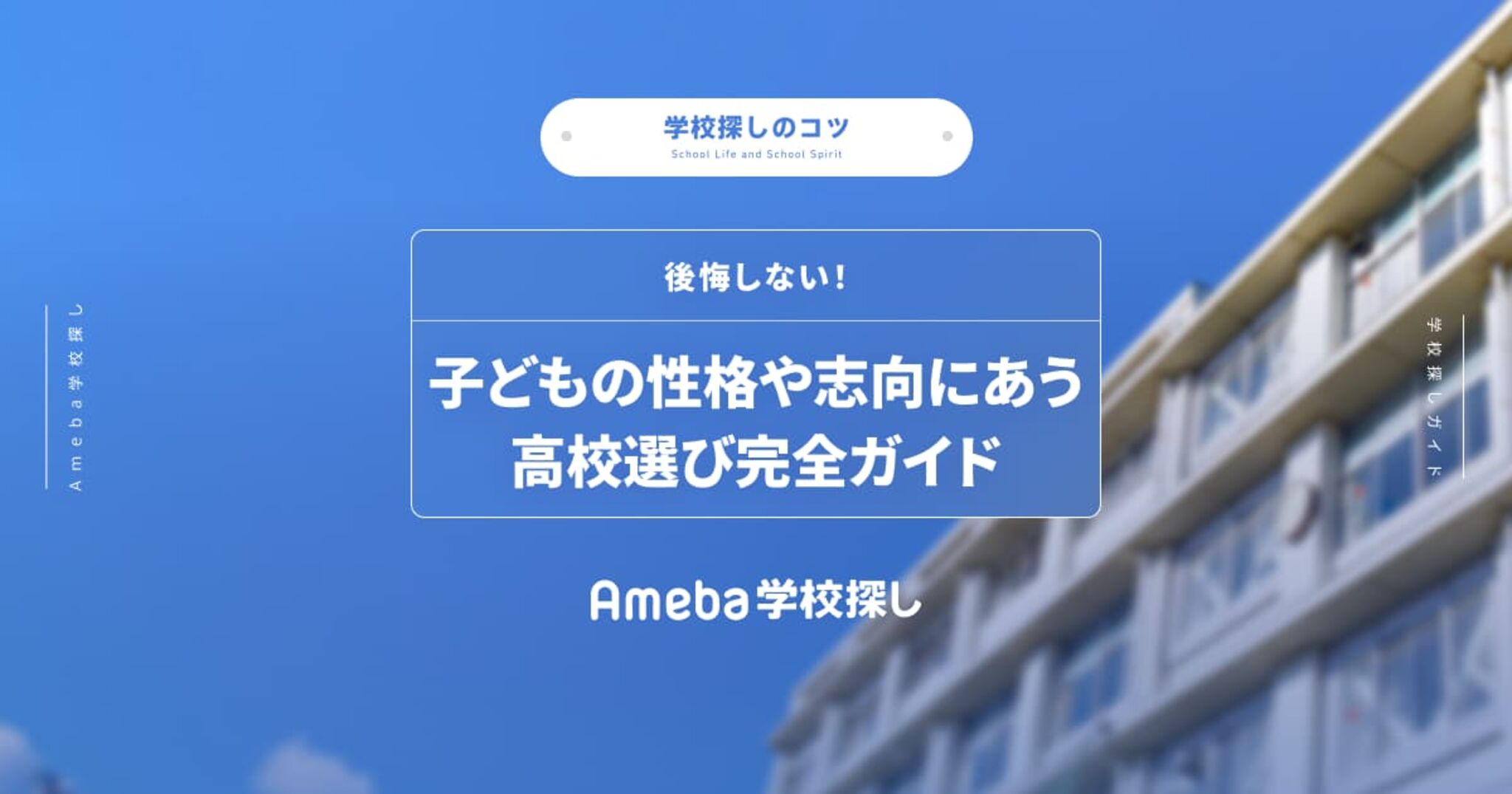大学附属校は、内部進学の安心感や大学資源を活用できる魅力から、中学受験や高校受験で注目を集めています。一方で、学部の配分や進学条件、学費や校風は学校によって大きく異なり、入学後に「想像と違った」と感じてしまうリスクもあります。
本記事では、大学附属校の基本的な特徴から、通うことで得られるメリットと注意すべきデメリットを整理し、後悔を防ぐための選び方や代表的な学校の特徴までをまとめました。
家庭の価値観やお子さんの希望と照らし合わせながら、最適な進路を見極める参考にしてください。
大学附属校の特徴をおさらい

そもそも大学附属(付属)校とは、大学が設置または系列化した中学・高校で、内部進学制度を備えている点が特徴です。多くは成績や生活態度など一定の基準を満たすことで大学へ進学できますが、進学枠や学部配分は学校ごとに異なり、人気学部では競争も生じます。
入学時は募集枠が限られ大学ブランドへの期待も重なるため、志願者が集まりやすく難易度も学校や年度によって差があります。内部進学の安心感は魅力ですが、基準や学部決定の仕組みを事前に確認し、家庭の方針と子どもの興味にあうかを見極めることが大切です。
私立大学附属校と国立大学附属校の違い
同じ「附属校」でも、私立と国立では目的や制度設計が異なります。進学の安心感を優先するのか、自由度の高い探究環境を重視するのかで、家庭に合う選択は変わります。保護者の方が不安に感じやすい点として考えられるのは、内部進学の基準や入学できる学部の人数配分、外部受験の扱いです。
まずはそれぞれの全体像を、以下の表で確認してみましょう。
- 【設置目的】教育研究と実践の場としての性格が強い
- 【内部進学】運用や基準は学校ごとに幅がある
- 【入試・募集】適性や多様性を重視する傾向がある
- 【学びの特色】自由度の高い探究や実験的な学びが展開される傾向がある
- 【設置目的】一貫教育と大学資源の活用を軸に運営
- 【内部進学】進学枠と基準を比較的明確に示している
- 【入試・募集】大学ブランドと連動した選抜になりやすい
- 【学びの特色】高大連携や独自プログラムが充実している傾向がある
上記は私立大学附属校と国立大学附属校のおもな違いをまとめたものですが、受験を検討する場合は、最新の公式資料で内部進学の基準、希望学部の決め方、外部受験の扱いなどを調べておきましょう。
大学附属校に通うメリット・デメリットとは

大学附属校は、併設大学への内部進学が可能という安心感により、多くのご家庭で受験の選択肢として検討されています。教育改革や入試制度の変化への不安を抱える中、こうした「進路の安定性」が注目されているようです。なお、附属校の人気は統計的に右肩上がりの傾向にありますが、それぞれの家庭の方針に応じて慎重に判断することが大切です。
まずは、受験負担や高大連携による学びの機会、希望学部への到達可能性、家計への負担、校風との相性を同じ基準で比べて検討することが大切です。
不安が残るときは、家庭で重視したい点を2〜3個に絞りつつ、大学附属校に通うメリットとデメリットを確認しておきましょう。
大学附属校に通うメリット
まずは、大学付属校のメリットを紹介していきます。
それぞれの項目について解説していきます。
原則として大学受験が不要である
大学附属校の大きな利点は、原則として一般入試を経ずに附属大学への進学を目指せる点です。
受験対策にあてる大量の時間や模試のスケジュールに縛られにくく、探究学習や部活動、資格取得、芸術・スポーツといった興味関心ごとに時間を割くことができます。内部進学には成績や日頃の学習態度などの基準が設けられる場合がありますが、興味関心に沿った活動のペースを保ちやすいことは心身の負担軽減につながります。
高大連携の教育を受けられる
高大連携とは、高大連携とは、中学校や高校と大学が協力し合い、生徒が大学の教育資源を活用しながら学べる仕組みのことです。
大学の図書館や研究室、教授陣の特別講義に早い段階から触れられる点は大きな魅力です。最先端の知と日常の授業が結び付き、知的好奇心が刺激されて学習意欲の持続に役立ちます。高大連携の例として、以下のものが挙げられます。
- 【授業・学問】出張講義・特別講座・合同カリキュラム
- 【研究・探究】研究室参加・共同発表
- 【施設・課外】大学図書館・施設の利用・大学行事への参加
早稲田実業学校高等部、慶應義塾高等学校、明治大学付属明治、立命館宇治、関西学院高等部などが参考の学校として有名です。
一貫した教育理念に基づき学びを深められる
大学まで見据えると、7〜10年に渡り同じ考え方で学びを積み上げやすい点が大きな利点です。人間形成の時期だからこそ、独自に体系化されたカリキュラムに沿って力を段階的に伸ばせます。
- 7〜10年の一貫性
- 学年間で評価観点の共通化
- 探究・行事の連続性
教育理念とお子さんの性格との相性が気になる場合は、家庭で大切にしたい価値観を3つに絞り、学校の教育目標の言葉と照らし合わせます。日々の時間配分に置き換えられるかを確かめると、入学後のミスマッチを減らせます。
深い人間関係を築きやすい
同じ仲間と中高の多感な時期を重ねることで、互いの得意や弱さまで理解した関係が育ちやすいです。行事や部活動、探究の共同作業が積み重なるほど、相談し合える土台が強まり、大学進学後も支え合えるつながりに発展しやすくなります。
関係が固定化することに不安を感じる方がいるかもしれません。学校の授業以外に、部活動やボランティア、地域イベントなどから1つ挑戦することを家庭で決めておくと効果的です。そして学期ごとに「誰とどんなことに取り組んだか」を親子で振り返ることで、活動の幅を広げながら学びを深めていけます。
他大学への進学にも挑戦できる
多くの附属校では、附属大学への推薦権を保持したまま他大学を受験できる制度があります。高校生活で新しい目標が見つかったときにも挑戦の余地が残されている点は安心材料です。
ただし、学校によっては他大学を受験する場合に推薦による内部進学ができなくなることもあるため、制度の違いには注意が必要です。いずれの場合も、希望を実現するには学内で安定した成績を維持することが欠かせません。挑戦の幅とリスクの両面を理解し、子どもの意欲や目標と結び付けて具体的に検討することが大切です。
大学附属校に通うデメリット
附属校には内部進学の安心感や高大連携といった大きな魅力がありますが、同時に気をつけたい点も存在します。
家庭で重視する価値観やお子さまの性格とあわなかった場合、入学後に「想像と違った」という後悔につながることも少なくありません。そこで、ここからは代表的なデメリットを5つに分けて紹介します。
それぞれ詳細を解説します。納得のいく進路選びにつなげましょう。
中だるみのリスクがある
大学受験を回避できるという安心感は大きなメリットですが進学がほぼ保証されている状況では、日常の勉強に力を入れなくても進学できるという油断が生まれやすくなります。
結果として、授業や宿題を漫然とこなし、将来必要な基礎学力や計画性を身につけ損なう恐れがあります。こうした「中だるみ」を防ぐには、学期ごとに達成可能な目標を設定し、部活動や探究活動とバランスをとりながら学習習慣を維持する工夫が欠かせません。
進路選択の幅を狭めてしまう可能性がある
附属校は内部進学を前提としているため、早い段階で進路が固定されやすいという側面があります。中学や高校の時点で「この大学に進む」と決めてしまうと、成長とともに興味や適性が変わった場合に進路を柔軟に変更しにくくなります。結果として「もっと別の大学や学部に挑戦したかった」という後悔につながることもあります。
後悔しない進路選択のためには、以下の点をあらかじめチェックしておくのが理想です。
- 附属大学にどの学部・学科が設置されているか
- 内部進学以外の進路を選べる割合や条件
- 高校段階で進路希望を変更できる柔軟性の有無
- 他大学を受験した場合に推薦権を保持できるか
これらを確認しておけば、進路の選択肢をどこまで広げられるか、反対にどこで制約がかかるかを具体的にイメージしやすくなります。
希望する学部に進めない可能性がある
附属校では、必ずしも希望する学部に進学できるとは限りません。多くの場合、高校での成績順に進学先が決まり、特に人気の高い学部は競争が激しくなります。内部進学であっても「努力すれば必ず希望が叶う」とは言い切れず、成績や評価の積み重ねが重要です。
- 学部決定に使われる成績の範囲(評定・科目・順位)
- 過去の学部配分で人気学部の倍率や競争度合い
- 希望が叶わなかった場合の進路フォローの有無
こうした観点を事前に確認しておくと、「内部進学だから安心」という思い込みを避け、より現実的に学び方を考えることができます。
学費が高い傾向がある
大学附属校は、一般的な私立進学校と比較しても学費が高めに設定されている場合が多いです。初年度に120万〜150万円程度かかる学校も少なくなく、大学まで通うと総額はかなり大きな負担になります。
さらに、制服や教材費、課外活動費など見えにくい支出も積み重なります。教育への投資としては価値がありますが、家計への影響を冷静に見極めることが欠かせません。
- 入学金・授業料・施設費の初年度合計額
- 高校3年間+大学4年間を合わせた総額の見通
- 制服・教材・課外活動費など追加費用の有無
- 奨学金や分納制度など家計支援の仕組み
費用を事前に把握することで「払えなくなったらどうしよう」という不安を減らせます。家庭の教育資金計画と照らし合わせ、無理なく続けられるかを検討することが重要です。
外部受験する場合のサポートが薄い可能性がある
大学附属校は内部進学を前提にしているため、外部受験を希望する生徒へのサポート体制が十分ではない場合があります。模試や受験対策講座の機会が限られていたり、進路指導が内部進学を中心に設計されていたりすることも珍しくありません。
そのため、外部受験を目指す際には塾や予備校に頼らざるを得ず、家庭の負担が増えることがあります。内部進学と異なる道を選びたい場合には、早い段階から学習環境を整える必要がある点を理解しておくことが大切です。
後悔しない大学附属校の5つの選び方

大学附属校には安心感や魅力がある一方で、進学条件や学部配分、学費、校風など注意すべき点も多くあります。メリットだけに目を向けて選んでしまうと、入学後に「思っていたのと違う」と後悔するケースも少なくありません。
そこで、家庭で優先すべき視点を整理しながら、附属校を検討する際に確認しておきたい5つのポイントを紹介します。
これらを踏まえて比較すれば、メリットとデメリットを家庭の基準で見極めやすくなり、納得感のある進路選びにつながります。
①附属校に通いたい理由を掘り下げる
大学附属校には内部進学の安心感や大学資源に触れられる魅力がありますが、「大学受験を避けたいから」という理由だけで選んでしまうと、入学後にモチベーションを保てず後悔する可能性があります。
学校選びの出発点は、お子さんがどのような中高生活を送りたいかに置くことが大切です。
- なぜ附属校を希望するのか
- 受験回避以外に求める価値はあるか
- 中高生活で大切にしたい体験や学びは何か
こうした視点を具体的に言葉にしておくと、学校説明会や見学での情報を取捨選択しやすくなり、附属校が本当にあっているかを冷静に判断できます。
②大学の学部や研究内容・就職実績についても調べる
附属校を選ぶということは、その先の大学をある程度選ぶことと同じ意味を持ちます。中学受験であれば7年後、高校受験であれば4年後の進路を決めることになるため、大学にどのような学部・学科が設置されているのかを事前に把握しておくことは欠かせません。
また、研究分野の特色や教育方針が子どもの関心とあっているかを確認することも重要です。さらに、卒業生の進学や就職の実績を調べることで、附属校での学びが将来のキャリア形成にどう結び付いているかを具体的にイメージできるようになります。
③内部進学や外部受験の条件・サポート体制を確認する
大学附属校と一口に言っても、内部進学の条件や外部受験への対応は学校ごとに大きく異なります。内部進学では一定の成績基準や出席状況が求められる場合が多く、希望する学部に進むには学内での努力が欠かせません。
また、外部受験を認めている学校でも、内部進学の推薦権を失うケースやサポート体制が十分でないケースがあり、進学校に比べると受験指導が手薄になりやすいのが実情です。附属校を検討する際には、この内部進学と外部受験の両方の条件をしっかりと確認しておくことが、後悔を防ぐ大きなポイントとなります。
④中学・高校の教育が魅力的なものか吟味する
大学に進学できる安心感に注目が集まりがちですが、実際に子どもが過ごすのは中学・高校の6年間です。この期間の教育内容や校風が合わなければ、学びや生活に違和感を抱く可能性があります。授業の方針や部活動、行事の位置づけを確認し、学校生活の雰囲気を具体的にイメージすることが大切です。
- 【教育方針】学校の理念と子どもの性格が合うか
- 【校風】落ち着いた雰囲気か、自由度が高いか
- 【部活動】活動の種類や実績、学習との両立しやすさ
- 【行事】生徒主体の活動や国際交流の有無
- 【施設】図書館・実験室・運動施設などの充実度
表の観点をもとに学校見学や説明会で情報を集めると、日常の生活に無理なく馴染めるかを具体的に判断しやすくなります。
⑤子どもの意志を尊重する
大学附属校の進学先を検討する際、保護者が学校の魅力を感じていても、最終的に通うのはお子さん自身です。親の判断だけで進学先を決めてしまうと、入学後に壁にぶつかったとき「親に言われて選んだ学校だ」という不満につながりかねません。
だからこそ、文化祭や学校説明会には必ず一緒に足を運び、子どもが自分の目で見て「ここで学びたい」と感じられるかを確かめることが大切です。本人が心から納得して進学先を選べたとき、学習や部活動への意欲が高まり、困難を乗り越える力にもつながります。
大学附属校14選を紹介

大学附属校といっても、校風や進学制度は大きく異なります。ここでは代表的な附属校を3つのカテゴリに分けて紹介します。
この3つを比較して見ていくことで、附属校と一口にいっても多彩な選択肢があることがわかり、ご家庭の優先軸にあった学校を見つけやすくなります。
おもな私立大学附属校9選
私立大学の附属校は、内部進学率が高く、大学の教育資源を活用できる点が大きな魅力です。校風や特色は学校ごとに異なり、学習環境や行事、進学制度にそれぞれの個性があります。代表的な学校を以下に挙げます。
主な私立大学附属校
これらの学校は、いずれも大学までの道が見通しやすく、安心感のある進学環境を提供しています。ただし、内部進学の条件や学部の配分は学校ごとに異なるため、校風とあわせて見学や説明会で確かめておくことが大切です。
慶應義塾高等学校(神奈川県)
慶應義塾高等学校は、伝統的に「自主自立」を重んじる自由闊達な校風で知られています。生徒一人ひとりの主体性を尊重し、自ら学び、自ら考える姿勢を育てる環境が整っています。大学の教授陣による高度な授業やプログラムが実施されている点も大きな魅力で、高校段階から専門的な知識や大学レベルの講義に触れることができます。
- 校風:自主性を尊重する自由闊達な雰囲気
- 学び:大学教授陣による質の高い授業やプログラム
- 強み:卒業後も続く強固な人的ネットワーク
学びの自由度が高く、学習面だけでなく人間関係や社会性を重視するご家庭に適しています。内部進学率の高さに加え、幅広い分野で活躍する卒業生ネットワークに支えられることで、将来のキャリア形成にもつながりやすい環境です。
早稲田大学本庄高等学院(埼玉県)
早稲田大学本庄高等学院は、自然豊かな広大なキャンパスを誇り、落ち着いた環境で学びを深められる学校です。全寮制ではありませんが、寮を利用できる制度があり、仲間と共に生活を送りながら人間関係を築けるのが大きな特徴です。学業だけでなく日常生活を通じて自立心や協調性を育てやすい点も魅力です。
- 環境:自然豊かな広大なキャンパスでのびのび過ごせる
- 生活:寮生活を通じた人間関係形成と自立心の育成
- 進学:約100%という圧倒的な内部進学率
学力面だけでなく、生活そのものを教育の一部として重視するご家庭に適した学校です。自然に囲まれた環境で落ち着いて学びたい、仲間とともに成長できる人間関係を築きたい、そして確実に大学進学を見通したい、そうしたニーズを満たす選択肢となります。
明治大学付属明治中学校・高等学校(東京都)
明治大学付属明治は、落ち着いた学習環境の中で学業に集中できる点が大きな魅力です。都心に位置しながらも静かな校風を維持しており、生徒が安心して学べる環境が整っています。
また、部活動が非常に盛んで、学習と部活動を両立する「文武両道」のスタイルを実現しやすい学校です。
- 学習環境:落ち着いた雰囲気で学業に集中しやすい
- 部活動:多様で活発、文武両道を目指せる環境
- 進学:高い内部進学率と大学からの信頼
勉強に専念しながらも部活動や課外活動を通じて幅広い経験を積みたいお子さまに適しています。将来的に大学進学を見据えつつ、バランスのとれた中高生活を送りたいというご家庭にとって有力な選択肢となるでしょう。
青山学院中等部・高等部(東京都)
青山学院中等部・高等部は、都心に位置しながらも落ち着いた学習環境が整っている点が特徴です。キリスト教に基づく人間教育を大切にしており、生徒一人ひとりの人格形成に力を注いでいます。
また、国際交流にも積極的で、留学生との交流や海外研修の機会も用意されています。
- 学習環境:都心にありながら静かで落ち着いた雰囲気
- 教育理念:キリスト教に基づく人間教育を重視
- 国際交流:留学や海外研修など国際的な経験を積める
- 校風:自由な雰囲気の中で個性を尊重
勉強だけでなく人間的な成長や国際感覚を身につけたいお子さまに適しています。内部進学の安心感を持ちながら、多様な経験を重ねられる点は家庭にとっても魅力です。
中央大学附属中学校・高等学校 (東京都)
中央大学附属中学校・高等学校は、内部進学率が約9割と非常に高く、安定した進学環境が整っている点が大きな特徴です。
安心感のある進学制度に加え、推薦権を保持したまま他大学の受験に挑戦できる柔軟な制度が用意されており、生徒の進路選択に幅を持たせています。
- 進学制度:約9割が中央大学へ内部進学可能
- 外部受験:推薦権を保持したまま他大学受験に挑戦できる
- 学校生活:生徒主体の学校行事が活発
中央大学という安定した進学先を見据えつつ、より高い目標を持った場合に外部受験へ挑戦できる点は大きな強みです。内部進学と挑戦の両立を希望する家庭にとって、有力な選択肢の一つとなるでしょう。
日本大学高等学校・中学校(神奈川県)
日本大学高等学校・中学校は、全国的に見ても規模の大きな附属校の一つで、幅広い進路選択肢が整っている点が特徴です。
内部進学を通じて日本大学の多様な学部へ進めるため、専門分野を深めたい生徒にとって安心感があります。また、進学目標が明確に設定されており、学習意欲を高める仕組みが充実しています。
- 進路:幅広い学部への進学が可能
- 学習:明確な進学目標を設定しやすい仕組み
- 学校生活:部活動が盛んで文武両道を実現しやすい
多様な進路を見据えながら、自分の関心分野を模索したい生徒に適しています。特に、学習と部活動を両立させたい家庭にとって、日本大学高等学校・中学校は安心して選べる環境です。
関西大学第一中学校・高等学校(大阪府)
関西大学第一中学校・高等学校は、スポーツの名門校として知られ、多くの競技で全国レベルの実績を残しています。部活動を通じて培われる忍耐力や協調性は、学業や人間関係にも生かされやすい環境です。
- 学校生活:スポーツの名門校として高い実績
- 進学:高い内部進学率を誇る
- 教育理念:学力と人間教育を両立
スポーツに力を入れたいお子さんや、仲間と切磋琢磨しながら人間的に成長してほしいと願う家庭にとって、非常に魅力的な学校です。大学進学の安心感と、豊かな人間形成の両方を重視したい場合に有力な選択肢となります。
関西学院中学部・高等部(兵庫県)
関西学院中学部・高等部は、国際性豊かな校風が大きな特徴で、自由な探究学習を通じて生徒一人ひとりの個性を伸ばす教育を行っています。美しいキャンパス環境の中で、自主性を育みながら幅広い学びに触れられるのも魅力です。
内部進学制度を通じて関西学院大学へ進学できる安心感があり、同時に社会で活躍するための基盤を整える教育方針が徹底されています。
- 校風:国際性を重視し、多様な価値観を尊重
- 学び:自由な探究学習を推進
- 環境:美しく整備された学習環境
多様な視点を持ちながら学び、自分の興味を自由に追究したいお子さまに向いています。国際的な経験を重ねながら、確実に大学進学も見据えられる点で、将来の可能性を広げたいご家庭に適した選択肢といえるでしょう。
立命館中学校・高等学校(京都府)
立命館中学校・高等学校は、先進的な理数教育や国際教育に力を入れており、多様な学びのコースが整備されています。探究的な授業を通じて「自ら考え、行動する力」を育むことを重視し、生徒の主体性を最大限に引き出す環境が特徴です。
- 教育:先進的な理数教育と国際教育に注力
- 学び:多様なコース設定で個性に合わせた選択が可能
- 校風:探究心を重視し、生徒の主体性を育成
理数分野や国際的な学びに強い関心を持つお子さまにとって、特に魅力的な学校です。附属大学への進学を見据えながら、幅広い教育環境の中で主体的に成長できる点は、家庭にとっても大きな安心材料となります。
おもな国立大学附属校3選
国立大学附属校は、教育実験校としての性格を持ち、自由で多様な学びを重視しています。内部進学の仕組みは基本的にないため、多くの生徒が難関大学を目指して主体的に努力しています。学力面での刺激を受けながら成長できるのが特徴です。
筑波大学附属高等学校 (東京都)
筑波大学附属高等学校は、全国トップレベルの学力を持つ生徒が集まる進学校です。多様なバックグラウンドを持つ生徒たちが互いに切磋琢磨できる環境が整っており、学力面での刺激を受けながら成長できます。制服がなく校則も比較的緩やかで、自主性を重んじる校風も大きな特徴です。
- 学力水準:全国トップレベルの生徒が集まる
- 校風:制服なし、自由度の高い自主性尊重の環境
- 進学実績:最難関大や医学部への豊富な進学実績
高いレベルでの学習環境を望み、自由な校風の中で主体的に取り組みたい生徒に向いています。難関大学を目指す強い意欲を持つご家庭にとって、有力な選択肢となる学校です。
東京学芸大学附属高等学校 (東京都)
東京学芸大学附属高等学校は、生徒の主体性を徹底的に尊重する校風で知られています。自由度が高く、課題研究やレポート提出など大学のゼミさながらの学びを高校段階から経験できる点が大きな特徴です。探究活動が重視されることで、自分でテーマを設定し、仲間と議論しながら深めていく力を養えます。帰国生も多く、多様性に富んだ国際的な環境で学べるのも魅力です。
- 校風:自由度が高く、生徒の主体性を最大限尊重
- 学び:レポートや探究活動を重視、大学ゼミ的な学び
- 環境:帰国生が多く国際的で多様性に富む
自由な環境で自らの関心を追究し、多様な仲間から刺激を受けたい生徒に適しています。学習の枠にとらわれず、自律的に取り組む力を養いたいご家庭にとって、有力な選択肢となるでしょう。
お茶の水女子大学附属高等学校 (東京都)
お茶の水女子大学附属高等学校は、伝統ある国立女子校として落ち着いた学習環境を提供しています。少人数制の授業を重視しており、生徒一人ひとりにきめ細かい指導を行える点が強みです。また、高大連携プログラムやスーパーグローバルハイスクール(SGH)としての活動も盛んで、グローバルな視野を広げながら学習を深めることができます。
- 校風:伝統ある女子校として落ち着いた雰囲気
- 学び:少人数制による丁寧な指導
- プログラム:高大連携・SGH活動で国際的な視野を養成
落ち着いた環境で基礎からじっくり学びたい生徒や、国際的な学びを通じて視野を広げたいと考えるご家庭に適しています。学習習慣を大切にしながら、将来を見据えて着実に力を伸ばしていける学校です。
特定分野に強みをもつ大学附属校2選
一部の大学附属校は、国際教育や理数教育など特定分野に特化した教育を実践しています。自分の興味や将来の進路を早くから深めたい生徒にとって大きな魅力があります。
国際基督教大学高等学校 (ICUHS) (東京都)
国際基督教大学高等学校(ICUHS)は、圧倒的な国際性と多様性を誇る環境が魅力です。帰国生が多く在籍しており、異なる文化や価値観を持つ仲間と共に学ぶことで、国際社会で必要なコミュニケーション力や柔軟な思考を自然に身につけられます。
- 環境:多国籍な生徒が集う国際的な学習環境
- 教育方針:対話を重視するリベラルアーツ教育
- 進学:内部進学・外部受験の双方に強い
国際的な環境で学びたいお子さまや、多様な価値観を尊重しながら自分の考えを深めたい家庭に適しています。進学の柔軟性と国際性を同時に重視する場合に、有力な選択肢となるでしょう。
芝浦工業大学附属中学高等学校 (東京都)
芝浦工業大学附属中学高等学校は、理数教育と国際教育を柱にした先進的な学びが特徴です。STEAM教育を重視しており、ものづくりや探究を通じて課題解決力を育成します。授業では「考える力」「創造する力」を養うことに重点が置かれ、研究活動や実験、プロジェクト型学習が豊富に取り入れられています。
- 教育方針:本格的なSTEAM教育を展開
- 学び:探究的授業・プロジェクト型学習が充実
- 設備:最新設備を備えた近代的キャンパス
理数系や工学系に強い興味を持つお子さまに特に適しています。大学進学を見据えながら、実践的な学びを通して自らの関心を深めたい家庭にとって、有力な選択肢となる学校です。
学習環境と大学進学の条件・学部情報をチェックして性格にあう大学附属校を選ぼう
最終的に大切なのは、日々の学び方と進路の仕組みが、お子さんの気質と家庭の優先順位にあっているかどうかです。
中学・高校での授業の進め方や探究の位置づけ、部活動や行事や附属大学にどの学部・学科があり、どのような学び方や進路傾向があるかまで重ねて確認すると、入学後の生活を現実的に思い描けます。
迷いが残るときは、候補を2〜3校に絞り、家庭で「続けやすい生活リズム」「伸ばしたい力」「学びたい分野」の3点を重視しておくと、説明や案内の情報に振り回されず、自分たちの軸で判断できます。
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。