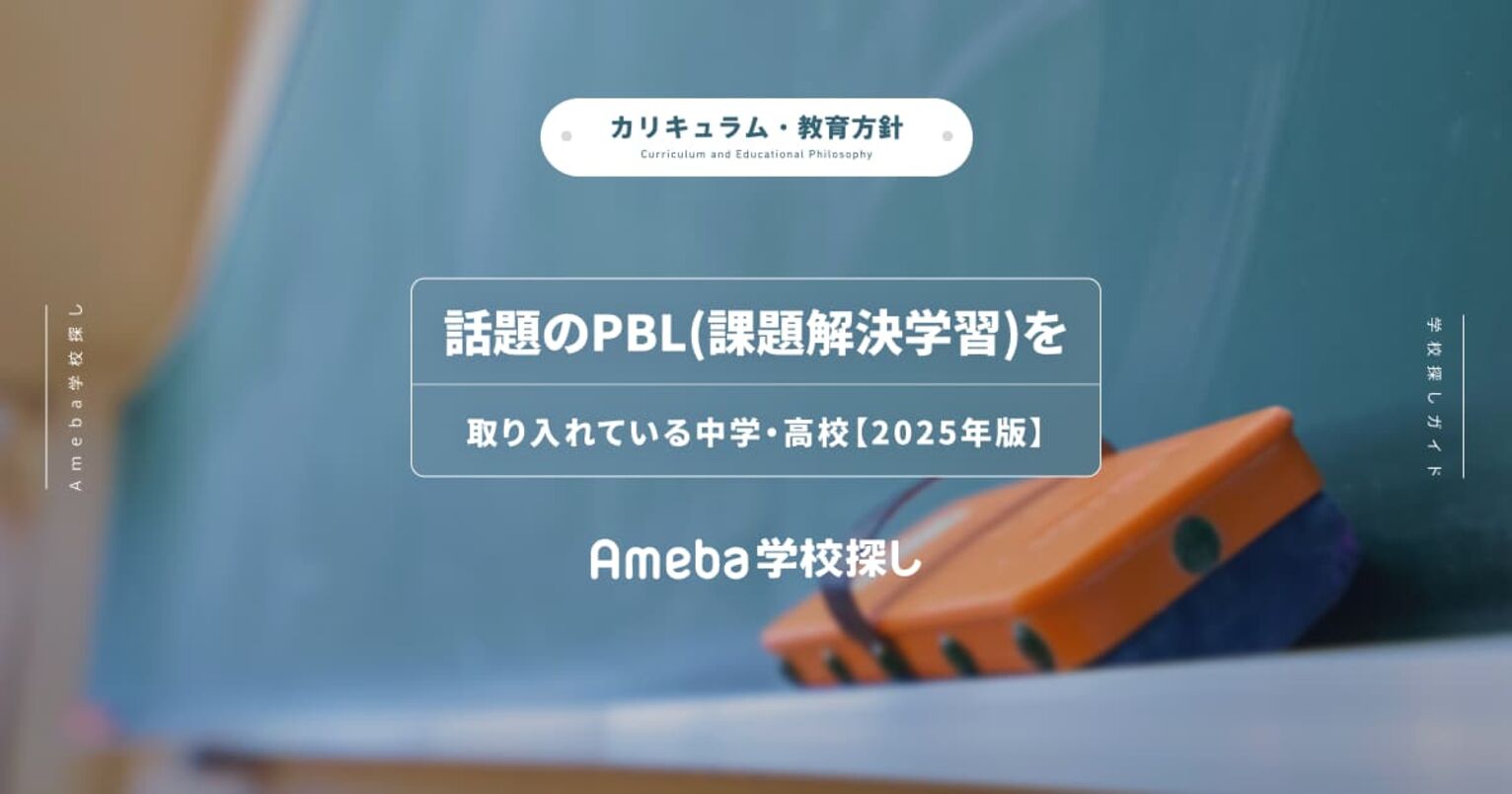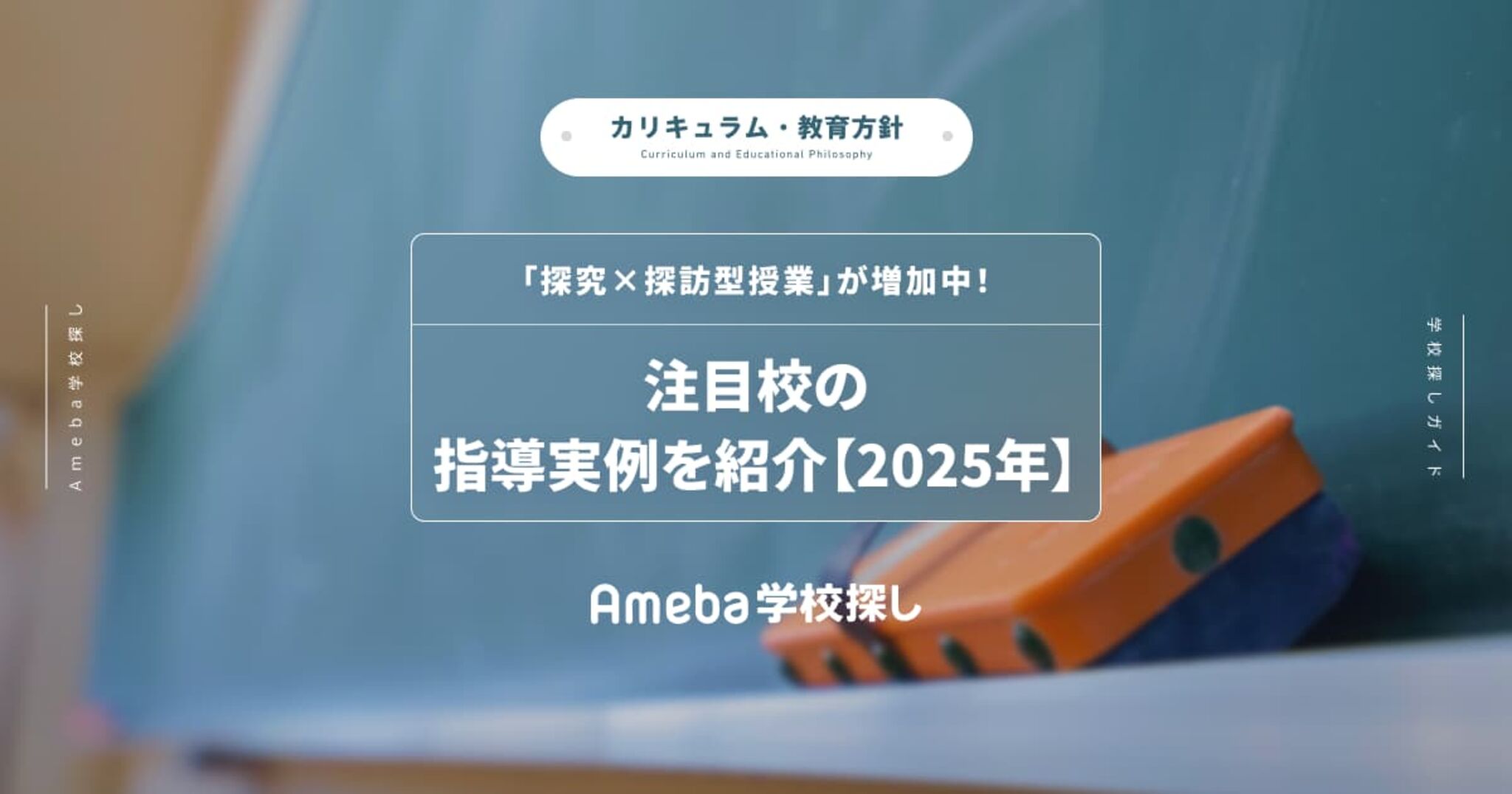近年の教育現場は、「暗記中心の受動的な学習」からの脱却を目指し、生徒が自ら考え、主体的に取り組む「探究型の学び」へのシフトが進んでいます。なかでも注目を集めているのが、「PBL(Project Based Learning/プロジェクト学習)」です。
近年はPBL(課題解決学習)を取り入れている中学・高校も増え、多彩な学びができるとして注目されています。
今回は、話題のPBL(課題解決学習)を取り入れている中学・高校について解説します。PBLを積極的に導入し、成果を上げている注目校の事例も紹介しますので、最後までご覧ください。
- PBLとは?その特徴と教育的意義
- PBLの基本と狙い
- 教育現場における導入の背景
- PBLを導入している注目の中学・高校を紹介
- 広尾学園中学校・高等学校(東京都)
- 和洋九段女子中学校・高等学校(東京都)
- 工学院大学附属中学校・高等学校(東京都)
- 湘南学園中学校・高等学校(神奈川県)
- 千葉県立千葉中学校・千葉高等学校(千葉県)
- 埼玉県立浦和第一女子高等学校(埼玉県)
- 松蔭中学校・高等学校(兵庫県)
- 京都文教中学・高等学校(京都府)
- 大谷中学校・高等学校(大阪府)
- PBLを導入する学校選びのポイント
- 年間プログラムが設計されているか
- ICT整備と教員のファシリテーション体制
- 発表機会や外部連携があるか
- PBLによって子どもの主体性や課題解決力が培われる
PBLとは?その特徴と教育的意義

PBL(Project Based Learning/課題解決型学習)とは、実社会の課題やテーマを出発点に子ども自身が問いを立て、調査・協働・発表を通じて解決策を導き出す探究型の学習手法です。
単なる知識の習得ではなく、自ら考えて他者と協働し、アウトプットにつなげるというプロセスを重視する手法として確立しました。
PBLでは、「正解が1つではない問い」に向き合うことを前提としているのがポイントです。思考力・判断力・表現力に加え、リーダーシップ・チームワーク・プレゼンテーション力など、社会で求められる実践的なスキルを育む教育法として注目されています。
PBLの基本と狙い
PBLの基本は、「正解のない問いに挑戦すること」にあります。情報収集・分析・仮説検証・発表を通じて解決策を探る学び方であり、必ずしも正解・不正解が決まっているとは限りません。教員は「指導者」ではなく、生徒の思考や協働を支える「ファシリテーター」として伴走する点もポイントです。
PBLの狙いは論理的思考力や創造力の向上にあり、これからの社会を生き抜くために必要な力を総合的に育む教育方法として注目されています。
協働的に学ぶ力(チームワーク・対話力)の育成や社会とのつながりを意識した課題解決力の醸成なども目的に、日本の教育現場で導入が進んでいます。
教育現場における導入の背景
近年、教育現場でPBL(課題解決型学習)の導入が進んでいる背景には、社会と教育を取り巻く大きな変化があります。
2022年度に学習指導要領が改定されて以降、「探究的な学び」が必修化し、多くの学校がPBL型授業を導入するようになりました。課題発見力・判断能力・協働力を育む教育として小中高のみならず大学でも注目され、探究プログラムのひとつとして全国展開が進んでいます。
昨今はグローバル化やAIが進展し、単に知識を覚えるだけでは対応できない時代に突入しています。PBL(課題解決型学習)は時代にあった教育法として導入され、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の一環としても活用されています。
PBLを導入している注目の中学・高校を紹介
ここでは、PBLを導入している注目の中学・高校を紹介します。具体的にどんな学習カリキュラムになっているか、チェックしてみてください。
広尾学園中学校・高等学校(東京都)
広尾学園中学校・高等学校ではPBLを教育の中心に据えたカリキュラムを採用し、英語でのプレゼンも標準化されています。
- 探究型学習・PBLを重視したカリキュラムを全コースで展開
実社会や国際課題をテーマに、生徒が主体的に調査・分析・発表をおこなう - 「探究」「グローバル探究」「サイエンス探究」など専門性の高いPBL科目を設置
学問横断的な視点で学ぶ力や創造的思考を育成 - 少人数制でのディスカッション・プレゼンテーションが日常的におこなわれる
意見を言語化し、他者と対話する力を実践的に身につける - 社会人や大学研究者と連携した実践型プロジェクトも実施
実社会との接点がある課題に取り組みながら、思考と行動を結びつける
AI×医療、起業×SDGsなど、近年注目されている複合的なテーマに基づいた課題解決型学習を実施しているのが特徴です。学年末には全校プレゼン大会が開かれ、生徒が探究成果を発信しています。
和洋九段女子中学校・高等学校(東京都)
和洋九段女子中学校・高等学校では、中学1年から探究プログラムがスタートします。地域課題や環境問題をテーマに、仮説→調査→発表までおこなうグループ型プロジェクトを実施しているのが特徴です。
- 中高一貫でPBL型授業・探究学習を体系的に導入
学年が上がるごとに探究の難易度・自由度が増し、自ら課題設定する力を育む - 「クロスカリキュラム」で教科横断型の学びを実施
国語×社会、理科×英語など複数教科を組み合わせたテーマ学習を展開 - 企業や大学との連携によるプロジェクト型学習も充実
大学の研究者や社会人の協力を得て、現実的な課題に向き合う経験を提供 - プレゼンテーション・ディスカッションを重視した授業設計
グループ発表や意見交換を通じて、表現力・傾聴力を養う
また、「PBL型入試」でも全国的に注目されています。与えられた課題やテーマに対して受験生が自分の考えをまとめ、論理的に説明・提案・発表する形式の入試は、できたことを積み重ねていく加点法で採点されています。
工学院大学附属中学校・高等学校(東京都)
工学院大学附属中学校・高等学校では、探究・STEAM教育・ICT活用を3本柱に、全学年でPBLを展開しています。国際バカロレア(IB)中等教育プログラムも導入するなど、国際的な特色も強いです。
- 中高6年間を通じて探究型・PBL型授業を体系的に導入
1年次からプレゼン・グループワーク・フィールドワークを重視 - 「グローバル教育」や「リベラルアーツ探究」など多様なPBL科目が充実
社会課題・テクノロジー・文化など横断的に学ぶカリキュラム構成 - ICT端末を1人1台活用、EdTechと融合した学びを実践
情報収集、資料作成、オンライン協働、動画プレゼンなどが授業内で定着 - K-STEAM教育に注力し、理数系だけでなく創造的思考を育てる
グローバル・リベラルアーツと数理情報工学の融合を実現
「未来都市を設計せよ」「多文化共生を促進せよ」など社会的なテーマに取り組むことが多く、協働的な課題解決に挑戦する姿勢を育みます。探究活動を活かした総合型選抜(旧AO入試)対策にも対応しているので、大学受験対策を万全にしたい方にもおすすめです。
湘南学園中学校・高等学校(神奈川県)
湘南学園中学校・高等学校は全学年で「総合学習」にPBLを導入し、地域の課題や社会問題をテーマに探究活動を実施しています。企業や自治体と連携したプロジェクトも多く、プレゼン・ディスカッション力の育成に注力しているのが特徴です。
- 中高6年間を通じて探究型学習(PBL)を段階的に実施
中1〜高2までの「総合探究」の時間で、課題発見・調査・発表の力を育成 - 社会課題(SDGs・地域課題)をテーマにした実践的プロジェクト
地元・藤沢市やNPO、地域企業と連携して実社会の問題に取り組む - 「ESD(持続可能な開発のための教育)」に基づいたカリキュラム
環境・人権・国際理解など、地球規模の視点をもつ探究学習 - フィールドワーク・インタビューなどの実地調査も重視
教室の外に出て学ぶことで、学びと現実社会の接続を実感
地元商店街の活性化案づくり、海洋環境保全プロジェクト、SDGsをテーマとした探究フェアなど独自性の高い学習をしているのがポイント。生徒一人ひとりの個性や関心を尊重する校風で、少人数クラスでの密な指導を徹底しています。
千葉県立千葉中学校・千葉高等学校(千葉県)
千葉県立千葉中学校・千葉高等学校はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校であり、とくに科学技術や社会課題をテーマにしたPBLを推進しています。
- 中学段階から探究型学習「知の探究」を実施
各学年で独自のテーマ設定→調査→まとめ→発表をおこなう - 高校ではSSHの取り組みとして本格的な課題研究を実施
理系に限らず、文系テーマや社会課題を扱う自由研究も可能 - 大学・研究機関・企業と連携した高レベルなPBLに参加可能
実験・調査・論文作成・英語によるプレゼンなども経験できる - 高3では課題研究発表会を開催し、成果を公開プレゼン
教員・外部講師・同級生との相互フィードバックで完成度を高める
大学・研究機関との共同研究、地域企業との商品開発プロジェクト、国際会議での英語プレゼン発表など実践的な学習が多いのがポイント。探究活動は中高一貫で段階的にレベルアップし、理系分野だけでなく地域福祉や環境保全など幅広いテーマで探究できます。
埼玉県立浦和第一女子高等学校(埼玉県)
埼玉県立浦和第一女子高等学校では、スーパーグローバルハイスクール(SGH)指定校の経験を活かし、「未来のための『女性学』探究プロジェクト」というプログラムを実施しています。全生徒が主体的に取り組む探究活動として、PBLの学びが推進されているのが特徴です。
- 1・2年生で「課題研究(探究活動)」を必修化
各自でテーマを設定し、調査・考察・プレゼンテーションをおこなう - 「総合的な探究の時間」における個別・グループ型PBLが充実
社会課題・ジェンダー・科学技術・文化など、自由度の高いテーマに挑戦 - 「SGH指定校」としてグローバルリーダーを育成
海外校との交流、英語での課題解決型ディスカッションも実施 - 大学や研究機関と連携した「高大連携プログラム」
大学教員の講義・研究室訪問・専門的な資料調査などを体験
国際協力をテーマにした課題研究、SDGsに基づく地域課題提案、英語でのディベートやプレゼンなど学習のバリエーションも豊富。文部科学省「SGHネットワーク参加校」や「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)拠点校」にも選ばれ、グローバル課題への探究や英語での発表活動も重視しています。
松蔭中学校・高等学校(兵庫県)
松蔭中学校・高等学校は「英語力」「国語力」「課題解決能力」「ICT」の4つを軸に、国際交流も充実している学校です。実用的な「話せる英語」を身につけられるほか、高校卒業時には英検準1級・TOEFL iBT80以上を目指せるコースも設置されています。
- 中学・高校で段階的に深まる探究型授業を実施
自分でテーマを見つけ、調査・分析・プレゼンまで主体的におこなう - ICTを活用した調査・発表ツールの活用が充実
タブレット端末やオンラインリサーチを積極的に活用 - 英語による探究活動や国際交流プログラムを推進
海外研修や留学生との交流を通じ、グローバル視野を養う - ICTグループワーク中心のPBLで協働力・コミュニケーション力を強化
実社会の課題を模したプロジェクトにチームで取り組む機会多数
伝統を大切にしつつも、未来志向の探究型教育を積極的に取り入れる学校としても知られていて、「自分で考え、解決し、発信する」能力を養います。全学年でポートフォリオを作成し、成長を可視化しているのもポイントです。
京都文教中学・高等学校(京都府)
京都文教中学・高等学校は、「文教京都学」の考え方のもと、「考え方」を養う学びを重視しています。京都屈指の文化・芸術エリアにある強みを活かし、文化面でも「答えのない問題をどのように解決するのか」「得た知識をどう課題解決に役立てていくのか」を考えられる環境です。
- 中高一貫で段階的に深める探究型学習プログラムを実施
自己テーマ設定から調査・分析・発表までを一貫しておこなう - ICTを活用した調査・資料作成・プレゼンテーションを推進
タブレット端末やデジタルツールを使い効果的に学びを進める - 英語でのディスカッションやプレゼンテーション授業を導入
海外研修や国際交流も取り入れ、英語力と探究力を同時に育成 - 地域課題やSDGsをテーマにした実践的なPBLプロジェクト
社会問題に対して解決策を考え、実際に行動する機会を提供
仏教系の教育理念を活かしているのが特徴で、思いやりや持続可能性への意識を探究に反映しています。地域社会や国際社会を視野に入れたテーマ設定も多く、グローバルに活躍したい生徒や実践的な学びを求める生徒におすすめの学校です。
大谷中学校・高等学校(大阪府)
大谷中学校・高等学校は「探究プログラム」に力を入れており、全生徒が年間を通じてPBL型授業に取り組んでいます。
- 中学・高校で段階的に探究力を育むPBL授業を実施
実社会の課題や校内テーマを生徒が主体的に解決 - 宗教教育と探究活動を融合した独自のカリキュラム
精神性を重視し、倫理観や人間力を高める探究テーマも設定 - ICTを活用した調査・発表ツールの利用が活発
タブレットやオンラインリソースを用いたリサーチが可能 - 英語でのプレゼンやディスカッションを通じた国際理解教育
海外研修や留学生との交流プログラムも充実
「まちづくり」「防災」「福祉」「アート」など多様なテーマに着手でき、インタビュー・企画提案・プレゼンなど手法も多様です。地域イベントや外部コンテストにも積極的に参加する学校で、アウトプットの機会も豊富です。
PBLを導入する学校選びのポイント

PBLを導入している中学・高校が増えているとはいえ、実際の年間プログラムやICT教育との連携度合いは学校によりさまざまです。偏差値・学校との距離・進学実績なども加味しつつ、理想的な学校を探したいときは以下のポイントも確認してください。
年間プログラムが設計されているか
本格的なPBLを期待するときは、単発の体験ではなく「テーマ設定→調査→発表→振り返り」まで体系化している学校が望ましいです。年間を通じて計画的に段階を踏みながら進められれば、PBLの本来の効果を十分に引き出せるでしょう。
- 学年ごとに探究のテーマや難易度が体系的に設定されているか
- 調査・討議・発表などのプロセスが段階的に組み込まれているか
- 教科横断的な学びやキャリア教育と連携しているか
- 評価方法やフィードバック体制が整っているか
子どもが継続的に探究力や課題解決力を育める環境になっているか確認しておくのがポイントです。
ICT整備と教員のファシリテーション体制
PBL授業には、iPadなどICTデバイスやオンライン交流ツールなどの活用が欠かせません。また、教員が学びの支援者として伴走できるスキル・研修体制が整っているかも重要です。
ICT整備
- タブレットやPC、オンライン調査ツールが十分に用意されているか
- デジタル資料の作成や共有がスムーズにできる環境が整っているか
- 授業やグループワークでの活用事例が豊富か
教員のファシリテーション体制
- PBLの進行を支援するための専門的な研修を受けた教員がいるか
- 生徒の意見を引き出し、議論を深めるスキルを持った教員がいるか
- 生徒の主体的な学びを促すためのフィードバックがおこなわれているか
上記が整っている学校であれば、生徒がICTを駆使して調査・分析を進めやすく、教員の適切なサポートによりチームの議論が活性化されます。
発表機会や外部連携があるか
PBLでは、学んだことをまとめて発表し、フィードバックを受ける機会が重要です。地域企業・大学・NGO連携、国際交流、コンテスト出場など学外発信の機会がある学校では、探究成果をアウトプットできます。
- 校内での定期的な発表会やプレゼンテーションの場が設けられているか
- ポスターセッションやワークショップなど多様な発表形式があるか
- 地域社会や企業、大学など外部との連携プログラムがあるか
- 外部コンテストや課題解決プロジェクトに参加できる機会があるか
PBLの成果を社会や他者に共有できる経験は、子どもの学びを深めることにつながります。生徒が他者に伝える力や説得力を磨くことができるだけでなく、実社会との接点をもつことで学びのリアリティとモチベーションも高まるでしょう。
PBLによって子どもの主体性や課題解決力が培われる

PBLは、将来に必要な「課題を解決する力」「主体的に考える態度」「協働して発信するスキル」を育む質の高い学びです。探究的な学習を日常化する学校を選ぶことで、学びが実社会につながり、子ども自身の意欲と自信を育てられるのがポイントです。
本記事で紹介した注目校や選び方のポイントを参考に、子どもの未来につながる学校選びを進めてください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。