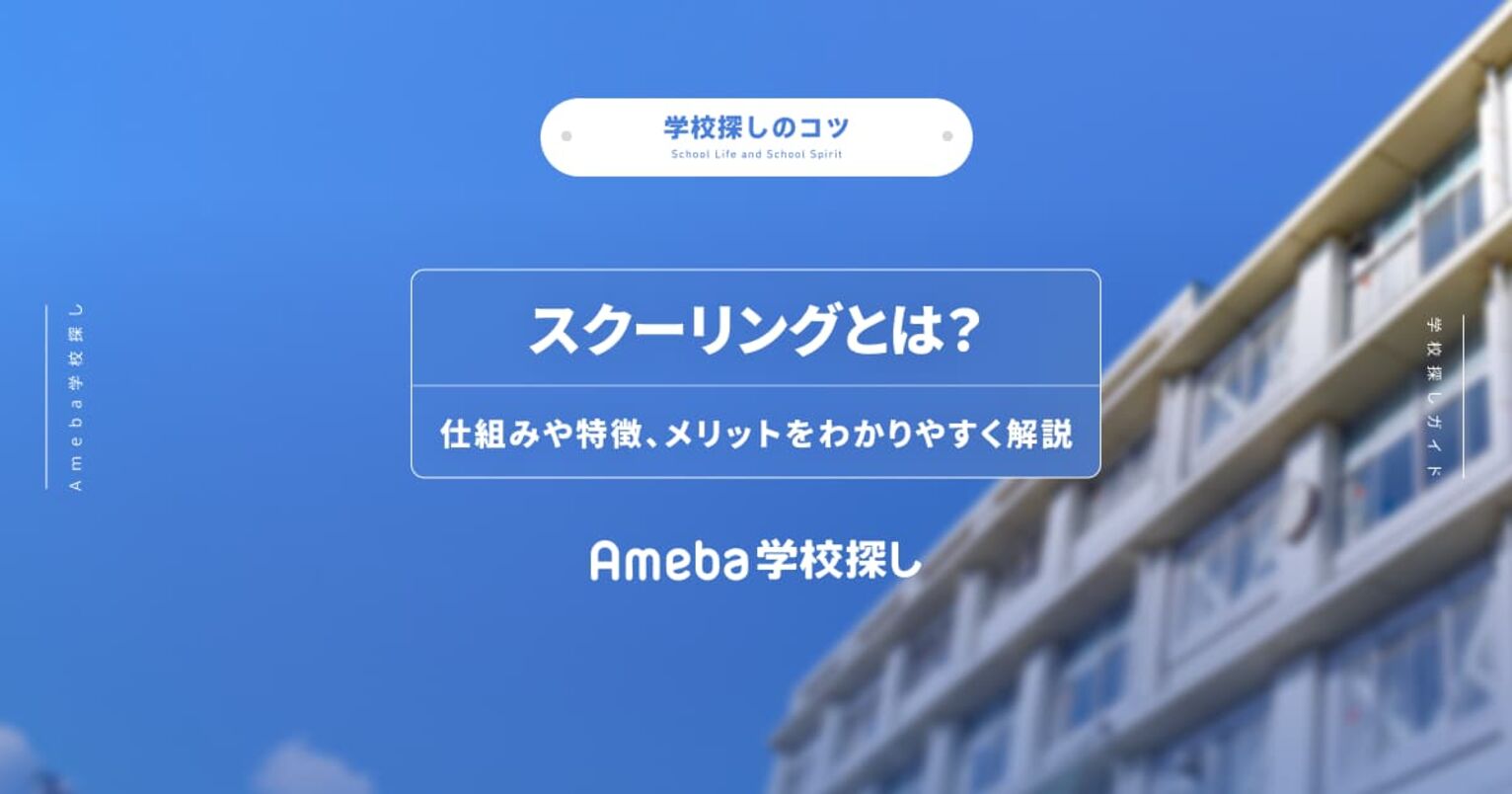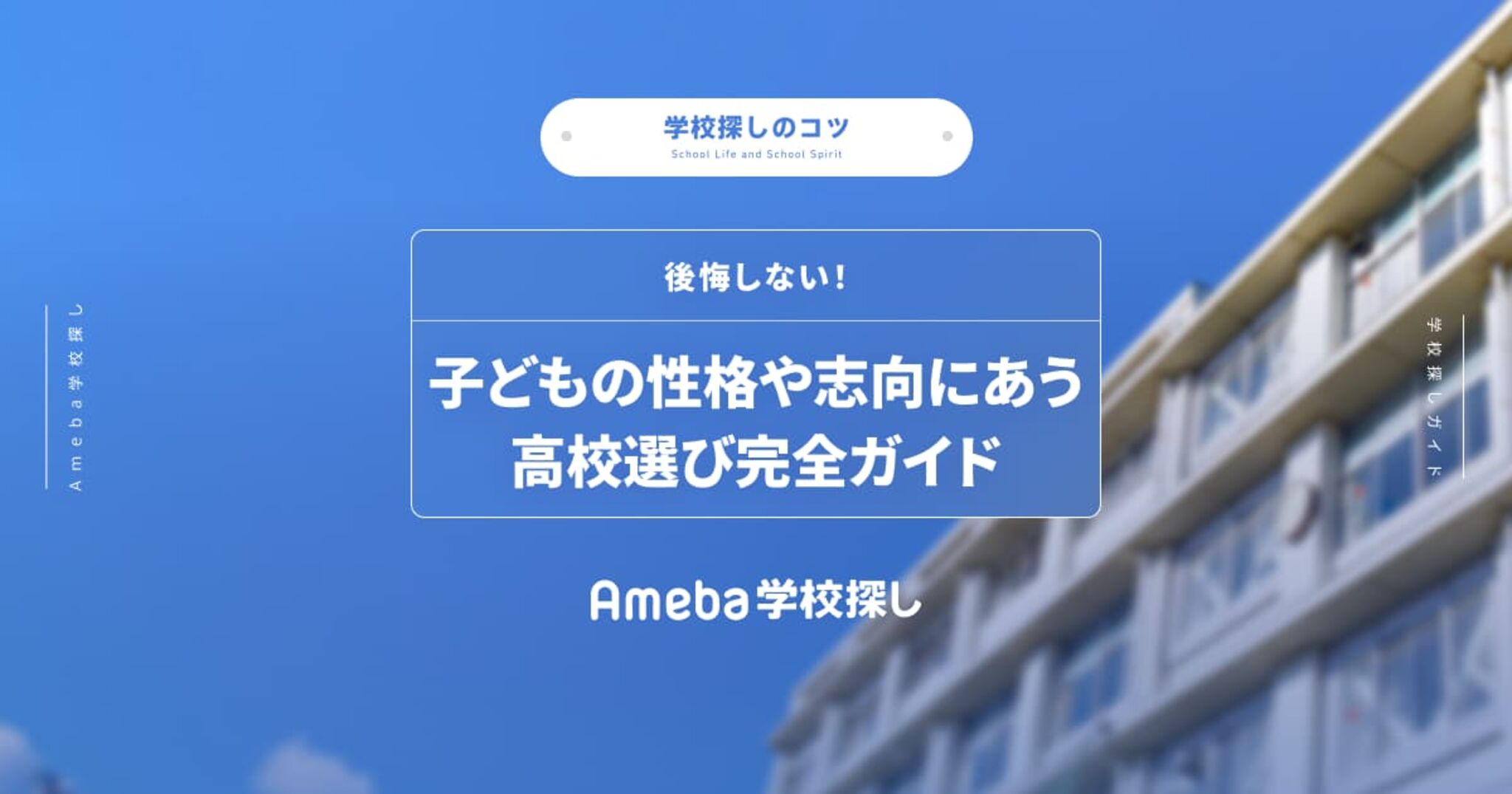「スクーリング」という言葉を耳にするものの、具体的にどのような制度なのかご存じない保護者の方も多いのではないでしょうか。
通信制高校や一部の高等教育機関を検討する際に重要な要素となるのが「スクーリング」です。
本記事では、スクーリングの基本的な仕組みや日程の特徴、子どもにとってのメリットや注意点を詳しく解説します。学校選びの参考になる情報をお届けしますので、ぜひご一読ください。
スクーリングとは?基本の仕組みを解説

スクーリングは、通信制教育の重要な構成要素として、生徒の学習理解を深める役割を担っています。
普段は自宅で学習を進める通信制において、実際に学校へ登校して直接指導を受ける貴重な機会となります。
保護者のなかには「通信制なのになぜ登校する必要があるのか」と疑問に思われる方もいるかもしれませんが、スクーリングには通信教育だけでは補えない重要な役割があります。
レポート学習だけでは理解しきれない内容を教師が直接指導したり、実験や実習など体験を通して学ぶ機会を提供したりするのです。
スクーリングの定義
スクーリングとは、通信制高校や大学などで学ぶ生徒が、実際に学校へ登校して授業や面接指導を受ける仕組みのことです。
普段は自宅で学習する通信制ですが、一定期間は学校に通い、教師から直接指導を受けたり、仲間と一緒に学んだりする時間が設けられています。
通信制の基本的な学習は、「レポート(添削指導)」「テスト(試験)」「スクーリング(面接指導)」の3つの要素で構成されており、すべてを満たすことで単位認定がおこなわれます。
なかでもスクーリングは、教師と生徒が直接顔をあわせておこなう授業として、とくに重要な位置づけがされています。
※学校教育法施行規則に「面接指導1単位」という直接的な規定はありませんが、「1単位時間」は通常、小学校で45分、中学校・高校で50分とされ、この授業時数で1単位を計算することを標準としています。面接指導も教育課程の一環としておこなわれる場合、この「1単位時間」の考え方に基づいて所要時間が定められることになります。
スクーリングの実施方法と日程の特徴

各学校によって実施方法や頻度は異なりますが、生徒や保護者の負担に配慮した柔軟な仕組みが整えられています。
学習スタイルや家庭環境にあわせて選択できる多様な形態があることも特徴のひとつです。
働きながら学ぶ生徒や子育て中の保護者、遠方に住む家庭など、さまざまな事情を抱える生徒に配慮して、各学校では創意工夫を凝らしたスクーリング形態を提供しています。
通学日数の目安
スクーリングの回数は学校によって異なりますが、一般的に年間5日〜20日程度が多いです。全日制に比べると通学日数は少なく、柔軟に学習を進められるのが特徴です。
スクーリングの通学日数は、法令で一律に決められているわけではなく、文部科学省が定める基準表に基づき、各学校が必要な単位時間数を確保します。
そのため、実際の通学頻度は年間の指導計画や履修している科目数によって変わります。
集中スクーリングと分散型
スクーリングには、「集中スクーリング(数日間まとめて通学する方式)」と「分散型スクーリング(週1回程度通う方式)」があり、家庭の事情や子どもの性格に応じて、通いやすいスタイルを選べます。
集中スクーリングは、夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用して、3〜5日間連続で授業を実施。短期間で集中的に学習できるため、普段はアルバイトなどで忙しい生徒にとって効率的な学習方法といえます。
一方、分散型スクーリングは定期的に登校することで学習リズムを維持しやすく、友人関係も築きやすいという利点があります。
校舎以外でのスクーリング
一部の通信制高校では、提携施設や地方会場を利用したスクーリングを実施しており、遠方に住んでいる生徒でも通いやすい仕組みが整えられています。
広域通信制高校では、全国各地にサテライト校舎や協力校を設置し、本校まで通うことが困難な生徒への配慮をおこなっています。また、リゾート地や研修施設を利用した合宿型スクーリングでは、学習と同時に自然体験や集団生活を通して豊かな体験を積むことができます。
最近では、新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業とスクーリングを組み合わせたハイブリッド型の学習形態も登場しており、より柔軟な学習環境が提供されています。
スクーリングのメリット
- 教師から直接指導が受けられる
- 友人や仲間との交流の場になる
- 規則正しい生活リズムがつくれる
スクーリングは学習面だけでなく、子どもの成長に大きな影響をもたらします。通信制という学習形態だからこそ得られる貴重な機会として位置づけられています。
とくに、普段はひとりで学習することが多い通信制の生徒にとって、スクーリングは学習意欲の向上や心理的な安定につながる重要な場面となります。また、将来の進学や就職に向けた社会性の育成という観点からも、スクーリングの果たす役割は非常に大きいといえるでしょう。
教師から直接指導が受けられる
普段の通信学習では自宅で、ひとりで勉強することが多いですが、スクーリングでは教員から直接指導を受けられ、理解不足を解消できる点が大きなメリットです。
レポート学習だけでは理解が難しい内容について、教師が具体例を示しながら説明したり、生徒一人ひとりの理解度にあわせて個別指導をおこなったりします。また、理科の実験や体育の実技など、実際に体験することで理解が深まる科目においては、スクーリングがとくに重要な役割を果たします。
疑問点をその場で質問できる環境があることで、学習のつまずきを早期に解決でき、学習効果が大幅に向上します。
友人や仲間との交流の場になる
スクーリングは、生徒同士が交流できる数少ない機会です。人間関係を築くことで、学校生活への安心感や学習意欲が高まるというメリットがあります。
通信制高校に通う生徒の多くは、さまざまな背景や事情を抱えています。不登校を経験した生徒、働きながら学ぶ生徒など、多様な仲間との出会いは、お子さんにとって大きな励みとなることでしょう。
学校に友だちができることで「ひとりじゃない」という安心感を得られ、学習への意欲も高まります。また、グループワークや共同学習を通して、協調性やコミュニケーション能力も自然と身についていきます。
規則正しい生活リズムがつくれる
定期的に登校することで、生活リズムを整えやすくなり、社会性を養う効果も期待できます。
通信制の学習は基本的に自分のペースで進められる反面、生活リズムが乱れやすいという側面もあります。スクーリングがあることで、決まった時間に起床し、身支度を整えて外出するという基本的な生活習慣が身につきます。
また、集団のなかで行動することで、時間を守る、協調性をもつ、マナーを身につけるなど、社会生活に必要なスキルも自然と習得できます。これらの経験は、将来の進学や就職活動において大きな財産となるでしょう。
スクーリングの注意点と保護者が確認すべきこと
スクーリングを含む学校選びでは、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。
入学後に「こんなはずではなかった」という状況を避けるためにも、事前の情報収集と確認を丁寧におこないましょう。
通学場所・日数を確認する
学校によってはスクーリング会場が遠方の場合もあります。「自宅から通えるか」「無理なく参加できる日数か」を必ず確認しましょう。
とくに広域通信制高校の場合、本校が他県にあることも多く、スクーリングのために長距離移動が必要になる場合があります。電車やバスでの移動時間、乗り換えの回数、最終的な交通手段なども含めて、現実的に通学可能かどうかを検討することが重要です。
また、年間のスクーリング日数だけでなく、実施時期や曜日、時間帯についても確認しておきましょう。家族の仕事の都合やほかの予定との兼ね合いも考慮して判断することが大切です。
費用面の負担を把握する
スクーリングには交通費や宿泊費がかかる場合もあるため、学費以外に必要となる費用を把握しておくと安心です。
遠方でのスクーリングや合宿型の場合、宿泊費がかかってきます。スクーリングにかかる費用は、学校や会場、そして居住地によって大きく変わります。
学費以外に必要となる交通費や宿泊費については、各校の案内で事前に確認できます。学校によっては、遠方からの生徒に対する交通費補助制度や、分割払いに対応している場合もありますので、経済的な負担が心配な場合は遠慮なく学校に相談してみましょう。
子どもの性格にあうスタイルかを検討
人との交流が得意な子には交流型のスクーリングが向いていますが、集団が苦手な子には少人数や短期集中型のほうが適している場合もあります。
お子さんの性格や特性を十分に理解した上で、最適なスクーリング形態を選択することが大切です。また、不登校経験がある場合は、そうした生徒への理解とサポート体制が整っている学校を選ぶようにしましょう。
通信制高校では、不登校経験者への配慮やカウンセリング体制が充実しているところもありますので、事前に相談してみることをおすすめします。
スクーリングは通信制教育において欠かせない登校型授業
スクーリングは、通信制教育において欠かせない登校型授業です。
子どもの理解度を高め、仲間や教師とつながる機会になる一方で、通学日数や費用など確認すべき点もあります。
学校を選ぶ際には、スクーリングの頻度・形式・会場をしっかり比較検討し、子どもにとって安心して通える環境を整えてあげましょう。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。