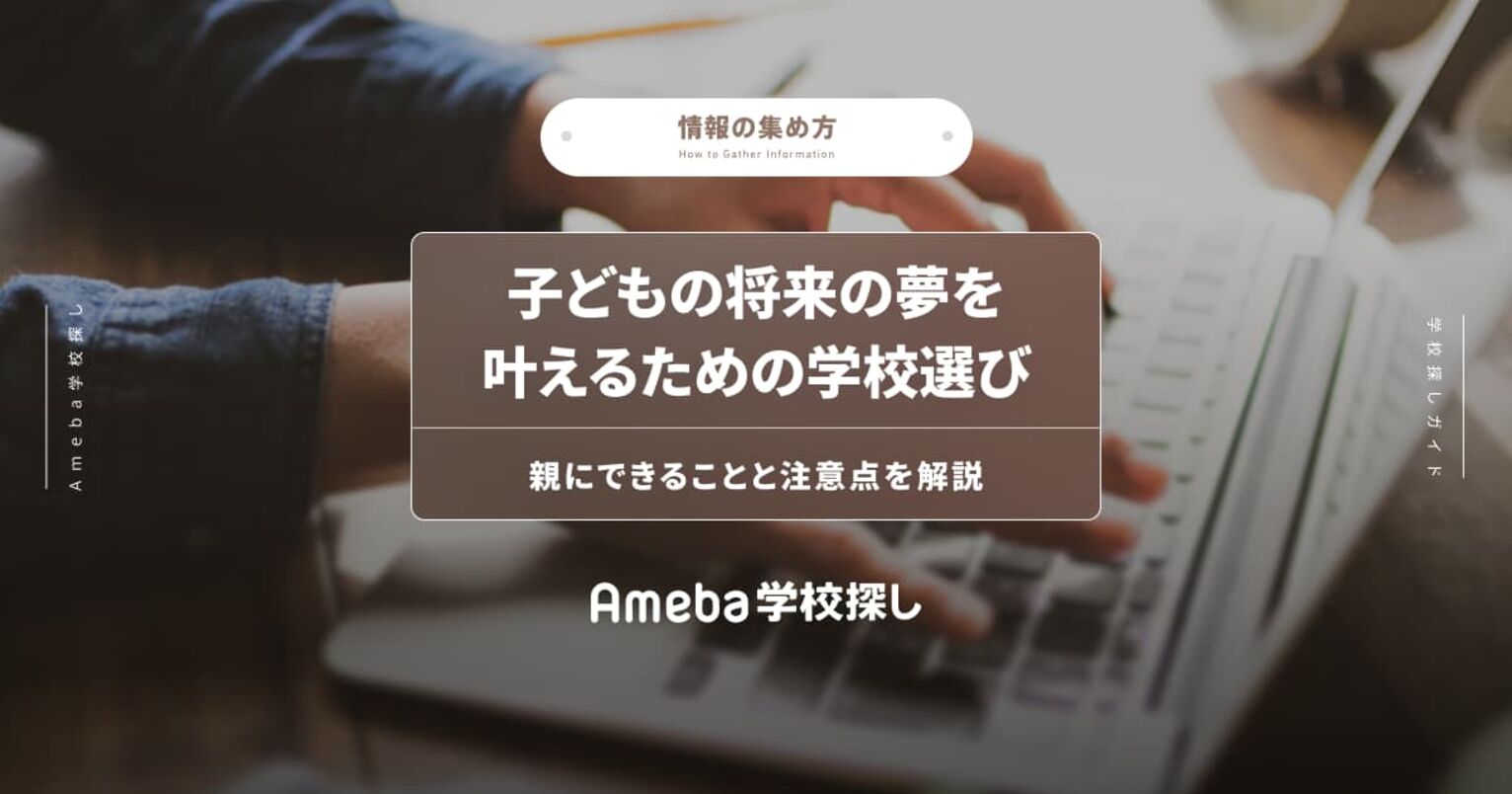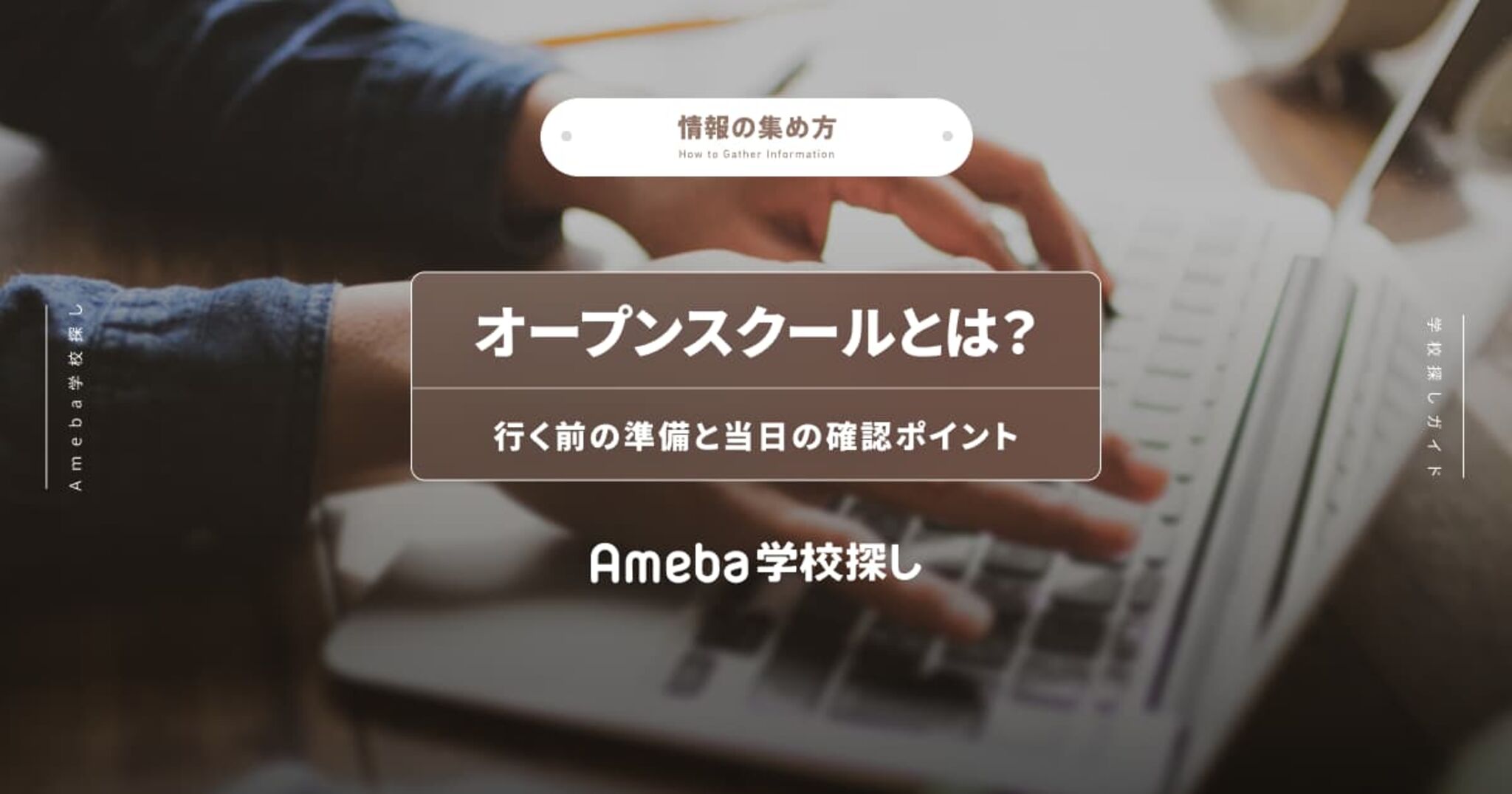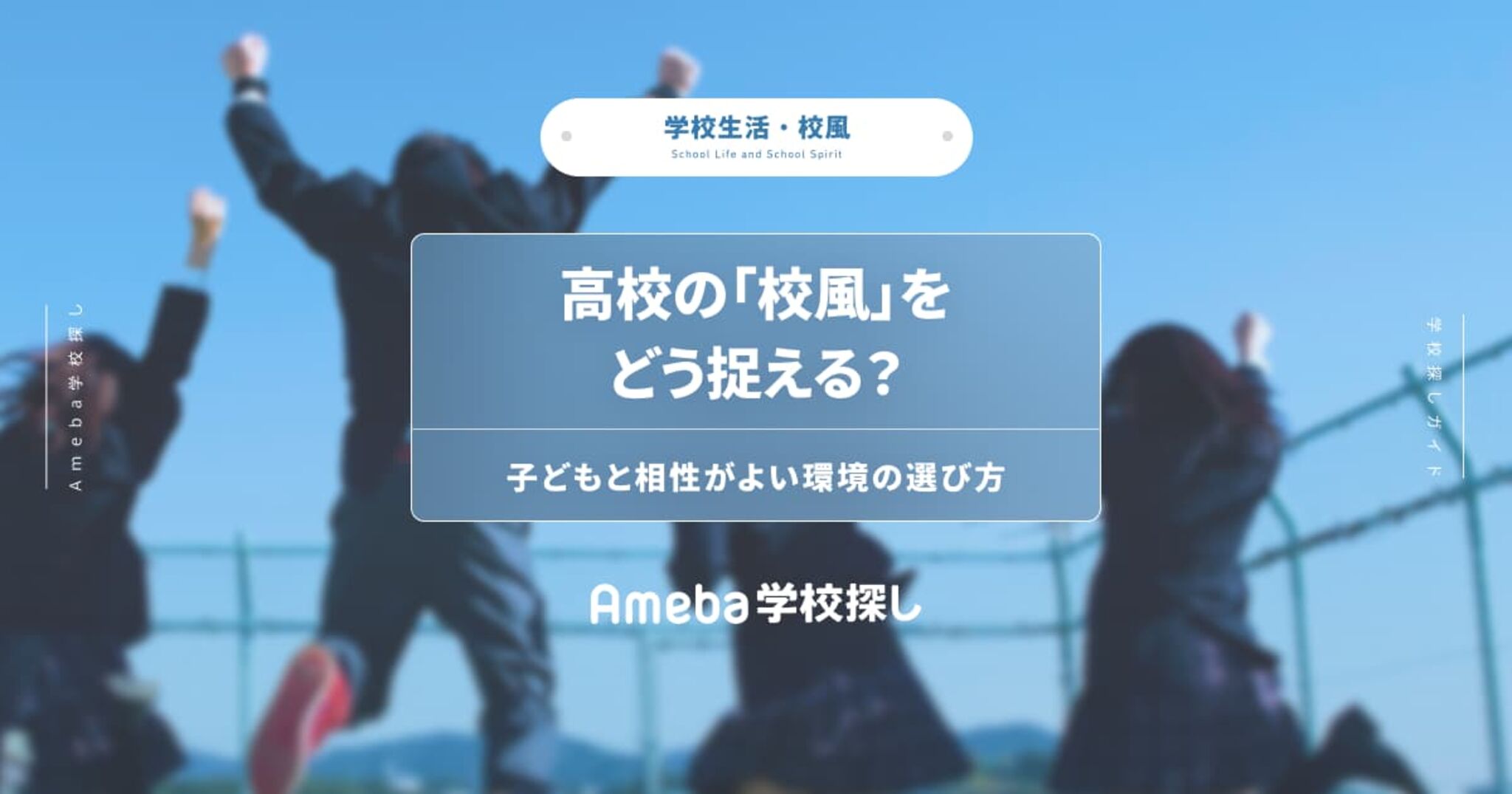子どもの将来の夢を叶えてあげたいと願うのは、多くの保護者にとって自然なことです。しかし「どの学校を選べば夢に近づけるのか」「夢がまだ定まっていない場合はどうすればよいのか」と悩む方も少なくありません。
進路には普通科や専門学科、高校卒業後の大学や専門学校など、多様な選択肢が存在します。
本記事では、お子さんの夢を応援するために親ができるサポートや、学校選びの際に押さえておきたい注意点を解説します。日常の関わりからできる工夫も紹介し、安心して子どもの未来を支えられるようにまとめました。
お子さんはどんな将来の夢を抱いていますか?

これまでに子どもと将来の夢について話したことがある方も多いでしょう。とはいえ、昨今は「とくに夢がない」と答える子どもも少なくありません。夢を語っていても、まだ限られた選択肢の中から何となく選んだり、兄姉や友人の影響を受けたりと、現実味が薄い場合もあります。
しかし、中学・高校進学を考える時期に、子どもが抱いている夢や目標を改めて確認することはとても大切です。たとえ曖昧なものであっても「今どのようなことに関心があるのか」「何に楽しさを感じるのか」を親子で共有することで、進路の選択がしやすくなります。
そのうえで、学校選びがどれほど重要かを一緒に考え、最良の選択肢を探っていきましょう。
子どもが抱く「将来の夢」を叶えるために親ができること
子どもが将来の夢を持ち始めたとき、保護者にとって最も気になるのは「どうすればその夢を応援できるのか」という点ではないでしょうか。進学には普通科や専門学科、高専など多様な選択肢があり、それぞれに特徴があります。
夢を実現するために学校選びが重要だと感じたとき、親がどのように関わるかが大切になります。これから紹介するのは、親が子どもの夢を支えるためにできる具体的な取り組みです。
親ができるサポート
前半では、夢や目標がまだはっきりしていない子どもに向けて、体験や「好き・得意」を深める工夫を紹介します。後半では、夢が定まったときに必要なスキルや資格の調べ方、進学先の探し方、受験に向けた情報収集について解説していきます。
将来の夢や目標を見つけるサポート
「まだ夢が見つからない」「やりたいことがわからない」と悩む子どもは少なくありません。中高生の時期は進路を考える大切な時期ですが、必ずしも明確な夢を持っている必要はありません。むしろ、さまざまな体験や関わりを通じて少しずつ興味を広げていく過程が、将来の目標を見つける土台となります。
保護者にできるのは、子どもの興味の芽を大切にし、体験の機会を作ったり「好き」「得意」を深める声かけをしたりすることです。焦らせず、子どものペースで考えを育む姿勢が安心につながります。
これからは具体的に、次のような視点から子どもの夢や目標を見つける方法を紹介していきます。
子どもの夢を見つける方法
- 物事を体験する機会をつくる
- 子どもの「好き」や「得意」を深める
物事を体験する機会をつくる
子どもが将来の夢を見つけるためには、実際に多くの物事を体験することが欠かせません。学校や家庭だけでは得られない新しい刺激に触れることで、自分の興味や関心を意識できるようになります。
地域のイベントに参加したり、さまざまな職業の人の話を聞いたり、本や映画などから新しい世界に触れたりすることは、夢や目標を考えるきっかけになります。保護者がこうした体験の場を意識的に用意してあげることで、子どもは「自分にもこんな可能性があるのか」と気づき、将来を描く第一歩につなげられます。
子どもの「好き」や「得意」を深める
子どもが小さなころから示している「好き」や「得意」は、将来の夢や目標を考えるうえで大切な手がかりになります。絵を描くのが好き、工作が得意、人と話すのが楽しいなど、些細に思えることも成長の方向性につながる可能性があります。
保護者にできるのは、それを否定せず受け止め、一緒に深めていく姿勢を持つことです。たとえば「どうして好きなの?」「どんなときに楽しいと感じる?」と問いかけることで、子ども自身が自分の気持ちを言葉にしやすくなります。その積み重ねが、興味を自覚し、自分の強みに気づくきっかけになります。
こうした親子のやり取りは、将来の進路選択で迷ったときにも「自分はこういうことが得意だった」と振り返る材料になります。安心して夢を描けるように、日常の会話から「好き」や「得意」を育んでいきましょう。
子どもにあった学校選びのサポート
将来の夢や目標が少しずつ見えてきたら、それを実現するためにどのような学校を選ぶかを考えることが大切です。保護者が積極的に情報を集め、子どもと共有しながら話し合うことで、進路の選択に安心感を持たせられます。
親ができる具体的な関わり方
このようにステップごとに整理して考えることで、「どんな環境が子どもにあっているか」を判断しやすくなります。資格やスキルだけに目を向けるのではなく、子どもが意欲的に学べるかどうかという観点も忘れずに意識しましょう。
必要なスキルや資格を調べる
子どもが将来の夢を実現するためには、その職業や分野にどのようなスキルや資格が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
たとえば、IT分野を目指すならプログラミングやデザインの知識、公認会計士や税理士を目指すなら簿記や会計の知識が欠かせません。こうした情報は学校の公式サイトや説明会、業界団体の公式サイトなどから調べることができます。
また、資格は高校在学中に取得できるものもあれば、大学や専門学校での学びが前提となるものもあります。保護者があらかじめ調べておくことで「今はどこまで学んでおけばよいのか」「高校ではどの分野を重点的に選ぶべきか」を整理しやすくなります。
調べた情報を子どもと共有し、「この資格はどのタイミングで取るのが良いかな?」と話し合うことが、進路選択に安心感をもたらします。
スキルを身につけられる学校を探す
将来の夢が定まってきたら、その夢を実現するために必要なスキルを学べる学校を調べることが重要です。
特定の学科やコースに進むことで、専門的な知識や資格を高校在学中から身につけることができます。また、普通科の学校であっても選択科目や課外活動によってスキルを磨ける場合があります。
【分野ごとの代表的な学校の例】
- IT・プログラミング(Webデザイナー、ゲームクリエイターなど)
工業高校「情報技術科」「デザイン工学科」、普通科+情報系選択科目 - 商業・ビジネス(公認会計士、税理士など)
商業高校「商業科」「国際経済科」、普通科+商業系部活動 - 工業・ものづくり(建築士、自動車整備士など)
工業高校「機械科」「建築科」「デザイン科」、普通科+専門講座
※学校のカリキュラムや取得可能な資格は、2025年度以降変更される可能性があります。最新の内容は必ず公式情報を確認してください。
入学・受験のために情報を集め共有する
学校を選ぶ際には、公式サイトや学校説明会、パンフレットなどから情報を集めることが欠かせません。とくにカリキュラムや取得可能な資格、学校生活の雰囲気などは、外からの印象だけではわかりにくいため、実際に足を運んで確認することが安心につながります。
集めた情報は、子どもと共有しながら一緒に検討することが大切です。「この学校ではどんなことを学べるのか」「自分の興味にあっているか」といった視点を話し合うことで、子ども自身も主体的に進路を考えるきっかけを得られます。
また、入試の方式や募集要項は年度ごとに変わる可能性があります。必ず最新の情報を公式サイトから確認し、家族で見落としがないようにしましょう。
将来の夢(目標)につながる学校を選ぶときの注意点

子どもの夢や目標にあわせて学校を選ぶことは大切ですが、実際には気をつけておきたいポイントもあります。
夢が途中で変わる可能性もあれば、スキルや資格の習得を急ぐ必要がないケースもあります。さらに、普通科で得られる経験や校風・教育方針との相性も見逃せません。
学校選びで特に意識しておきたい注意点
これらを理解しておけば、「選択肢を狭めすぎて後悔する」といったリスクを減らすことができ、子どもにあった最適な進路を選びやすくなります。
将来の夢や目標が変わる可能性がある
中高生の時期は心身ともに大きく成長するため、興味や関心が変化しやすく、今思い描いている夢が将来も続くとは限りません。憧れや身近な人の影響で選んだ道も、学びを深めたり新しい経験を重ねたりするなかで「本当に自分にあっているのか」と迷い始めることは珍しくありません。
そのため、学校選びをするときには「夢が変わる可能性」を前提にしておくことが重要です。たとえば、入学後に新たな分野へ関心を持った場合でも、コース変更や転科、あるいは転校といった選択肢が取れる学校なら柔軟に対応できます。そうした制度が整っているかどうかを、入学前に確認しておくことは安心につながります。
保護者としては「せっかく選んだ学校で夢が変わったらどうしよう」と不安に思うかもしれません。しかし、その変化は子どもが成長している証でもあります。
大切なのは「夢が変わってもやり直せる環境を用意してあげること」です。事前に複数の選択肢を把握し、子どもと一緒に「万が一方向転換した場合はどうするか」を話し合っておくことで、安心して進路を選ぶことができます。
大学や専門学校でのスキル・資格取得も可能である
「できるだけ早く資格やスキルを取らせたい」と考える保護者の方もいますが、中学や高校の段階で無理に専門スキルを身につける必要はありません。
高校卒業後に進む大学や専門学校には、専門的なカリキュラムや実習環境が整っており、そこで基礎から学んで資格を取得する道も十分にあります。
中高生の時期は、むしろ幅広い分野を学びながら自分の関心や適性を見つけていくことが大切です。早くから専門分野を絞り込みすぎると、夢や目標が変わったときに方向転換が難しくなるリスクがあります。
保護者は「どの時期に専門性を深めるのが子どもにあっているか」を一緒に考え、選択肢を提示してあげることが安心につながります。
普通科の高校に通うメリットもおさえておく
専門学科や工業・商業高校は、資格や専門スキルを高校在学中から学べる点が魅力です。しかし、普通科の高校にも見逃せないメリットがあります。普通科では幅広い教科を学ぶことができるため、自分の関心を探しながら将来の進路を柔軟に考え直すことが可能です。
たとえば、理系や文系の進路変更がしやすいこと、大学や専門学校に進む際に多様な選択肢を確保できることは普通科ならではの強みです。進学後に「やっぱり違う分野に挑戦したい」と思ったときに、進路を制限されにくいのは大きな安心材料となります。
早いうちに専門性を身につけさせたいと思う保護者の方にとっては不安に感じるかもしれませんが、普通科はむしろ子どもの可能性を広く残しておける環境です。夢が定まっていない段階では、普通科で基礎学力を培いながら進学の幅を広げておくことが将来の選択肢を支える力になります。
校風や教育方針がお子さんにあっているか確認する
学校を選ぶ際に、取得できる資格やカリキュラムの内容に注目するのは当然ですが、それだけでは十分ではありません。実際に子どもが通う環境として大切なのは、その学校の「校風」や「教育方針」が子どもの性格や価値観にあっているかどうかです。
たとえば、競争心を重視する校風は意欲を高める一方で、のびのびとした環境を望む子どもにはあわないかもしれません。反対に、自由度が高い校風は自発的に学ぶ姿勢を育てますが、自己管理が苦手な子にとっては不安定な要素になることもあります。
校風や方針を重視せずに学校を選んでしまうと、せっかく入学しても居心地の悪さを感じ、学習意欲の低下や不登校につながるリスクがあります。学校説明会や公開授業に参加し、実際の雰囲気を確かめることで、子どもが安心して学べる環境かどうかを判断しましょう。
お子さんの将来の夢・目標をじっくり話し合い最適な選択肢を見つけよう
子どもの夢や進路を考えるとき、保護者にとって不安は尽きません。「この選択で将来に繋がるのか」「夢が変わったときに対応できるのか」と心配になるのは自然なことです。
大切なのは不安を一人で抱え込まず、子どもと一緒に時間をかけて話し合い、今の段階でできる最良の選択肢を探っていくことです。
お子さんの夢を叶える学校選びのポイント
- 子どもの「好き」や「得意」を伸ばすことが夢の発見につながる
- 学校や学科の違いを理解し、柔軟に選択肢を残しておく
- 校風や教育方針が子どもにあうかを確認する
これらを踏まえて進親子でじっくり話し合う時間の積み重ねが、将来の夢を実現する力へとつながっていくでしょう。
この記事の編集者
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。