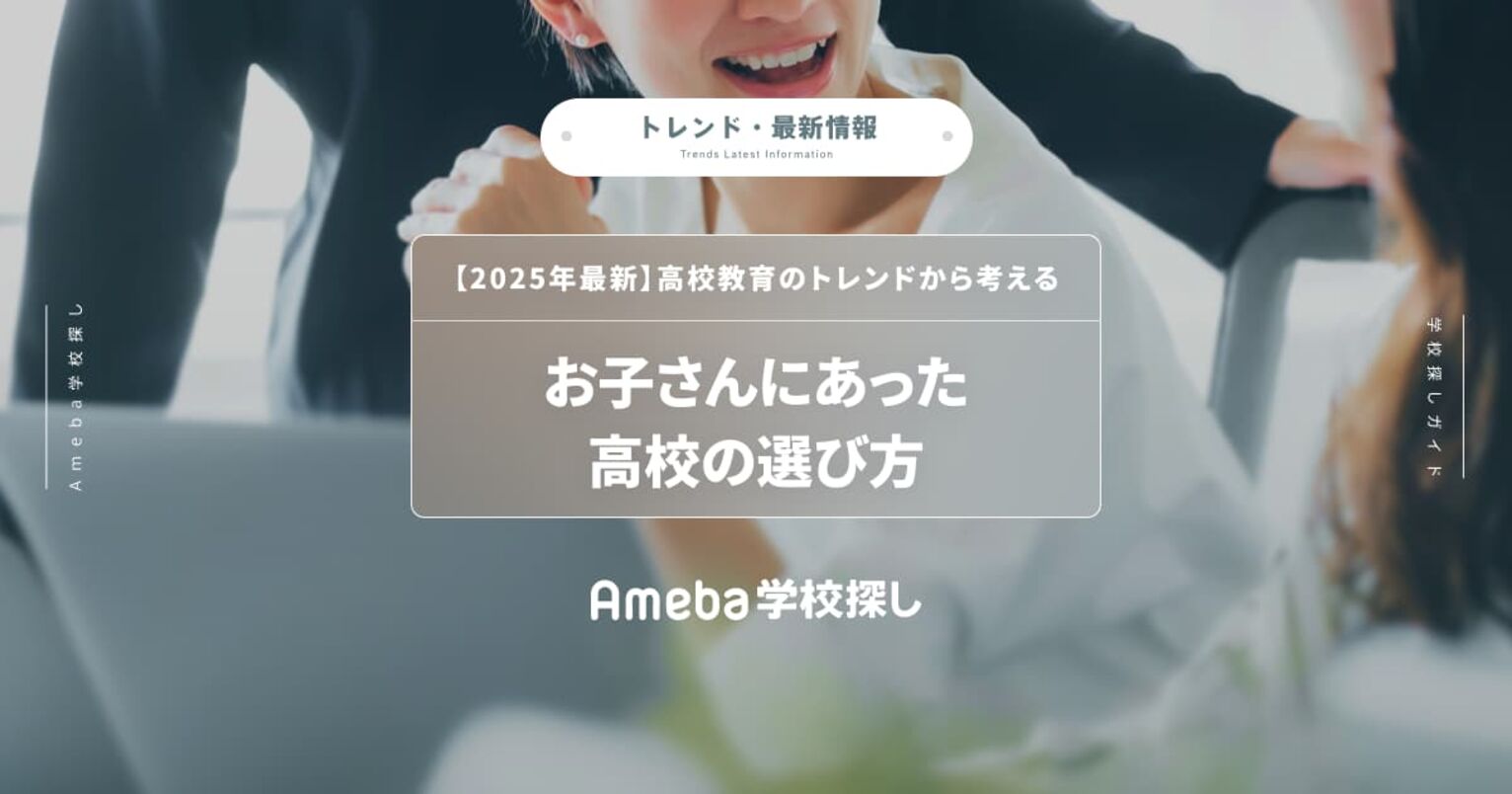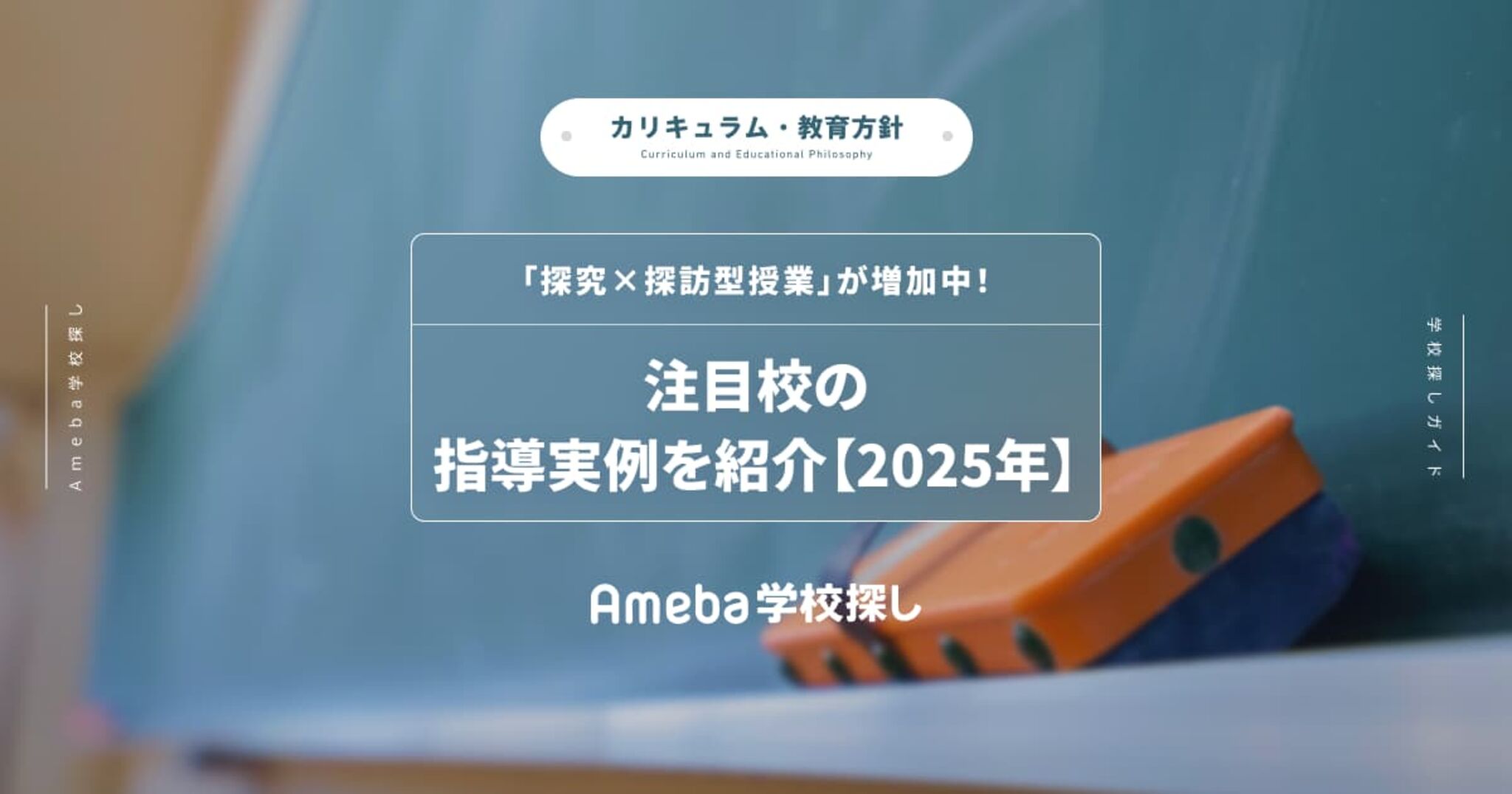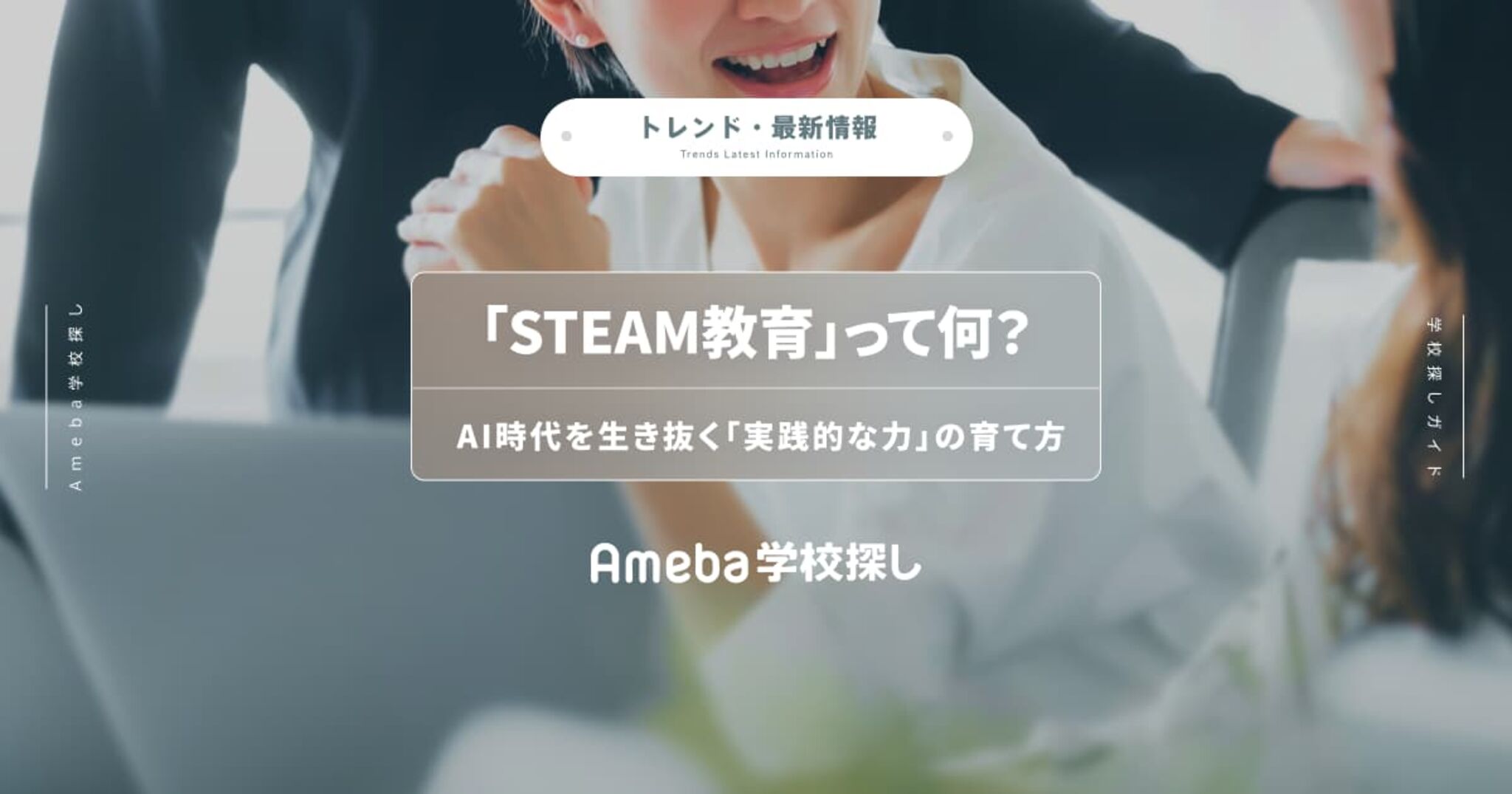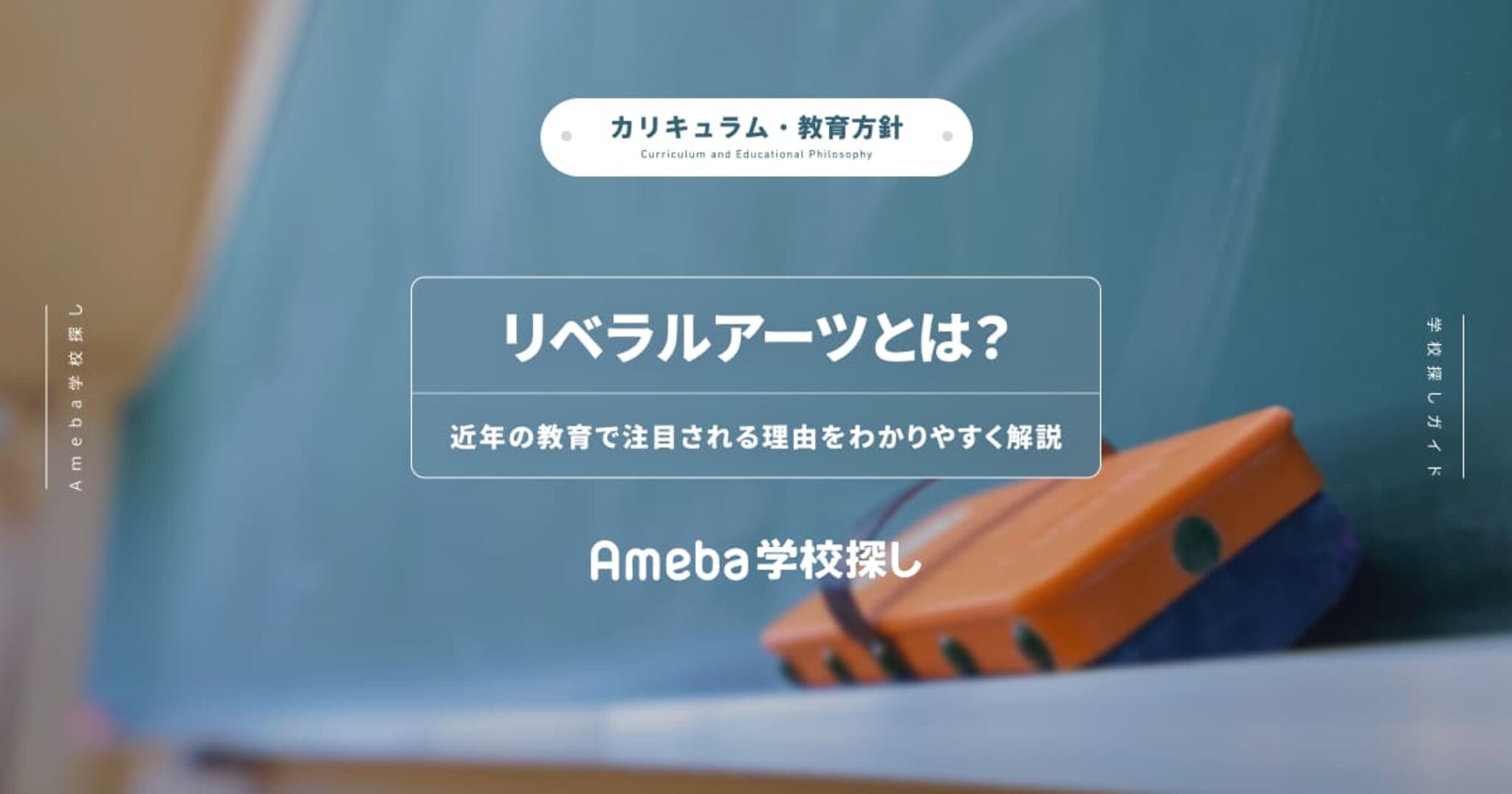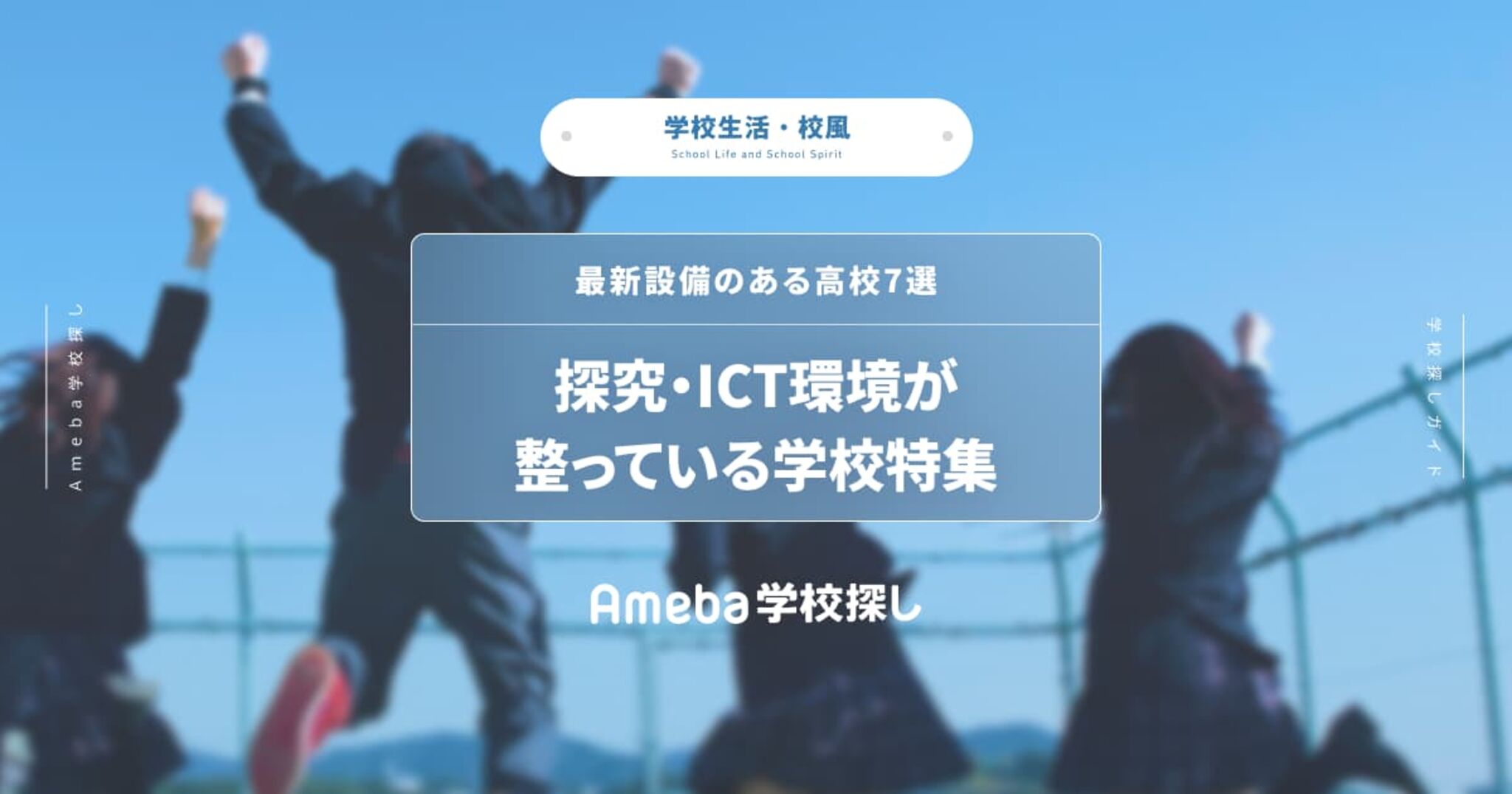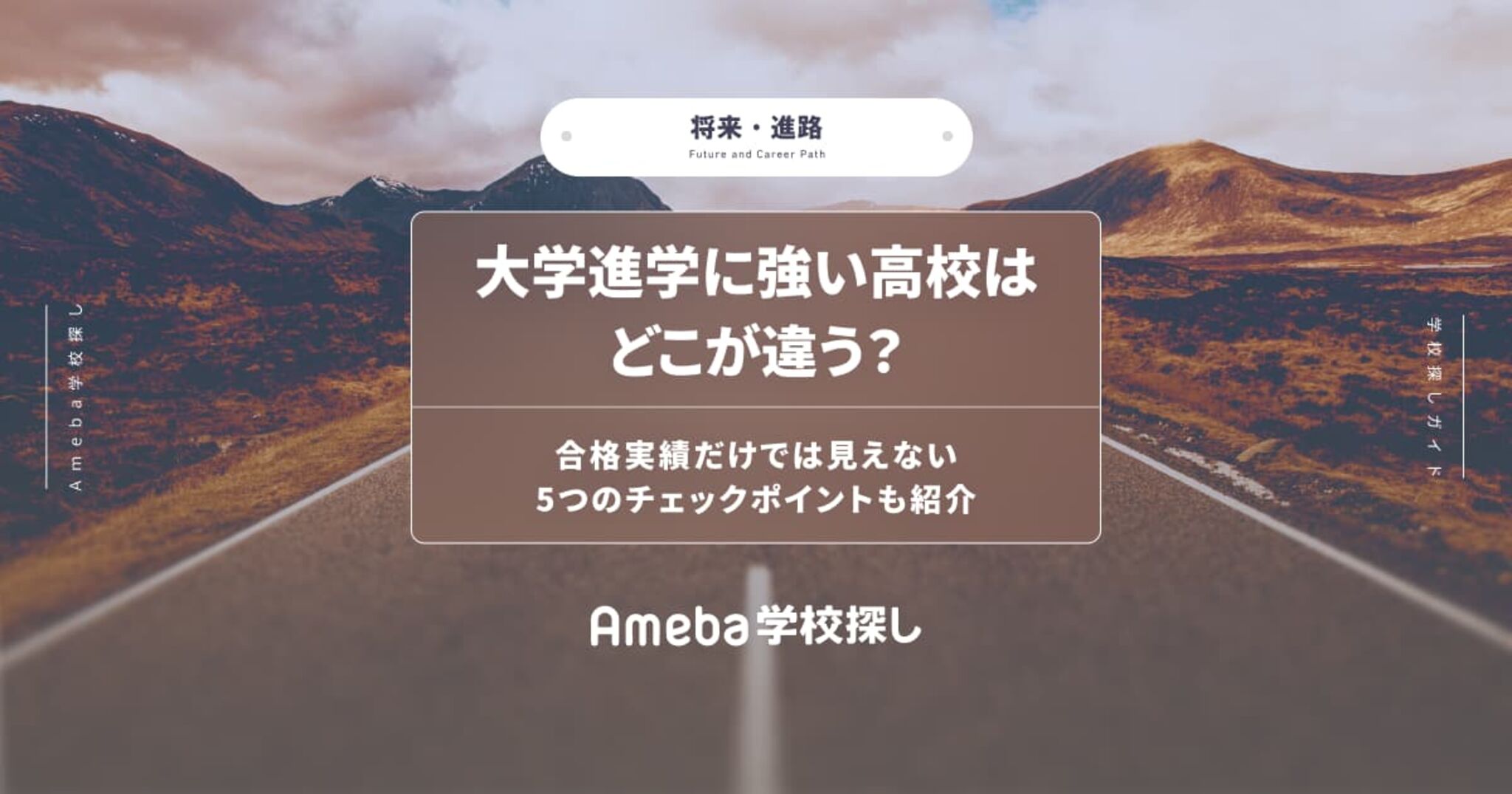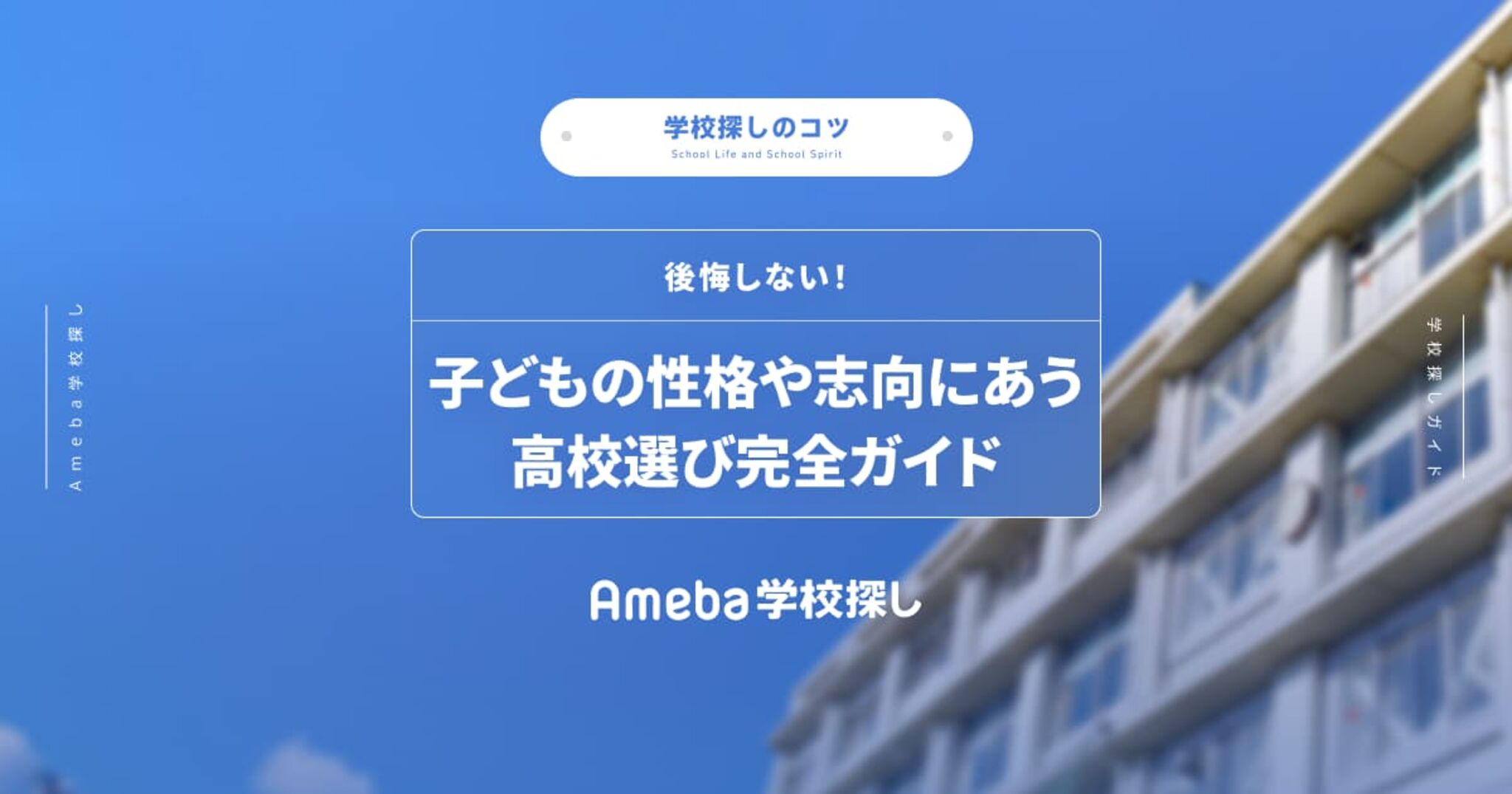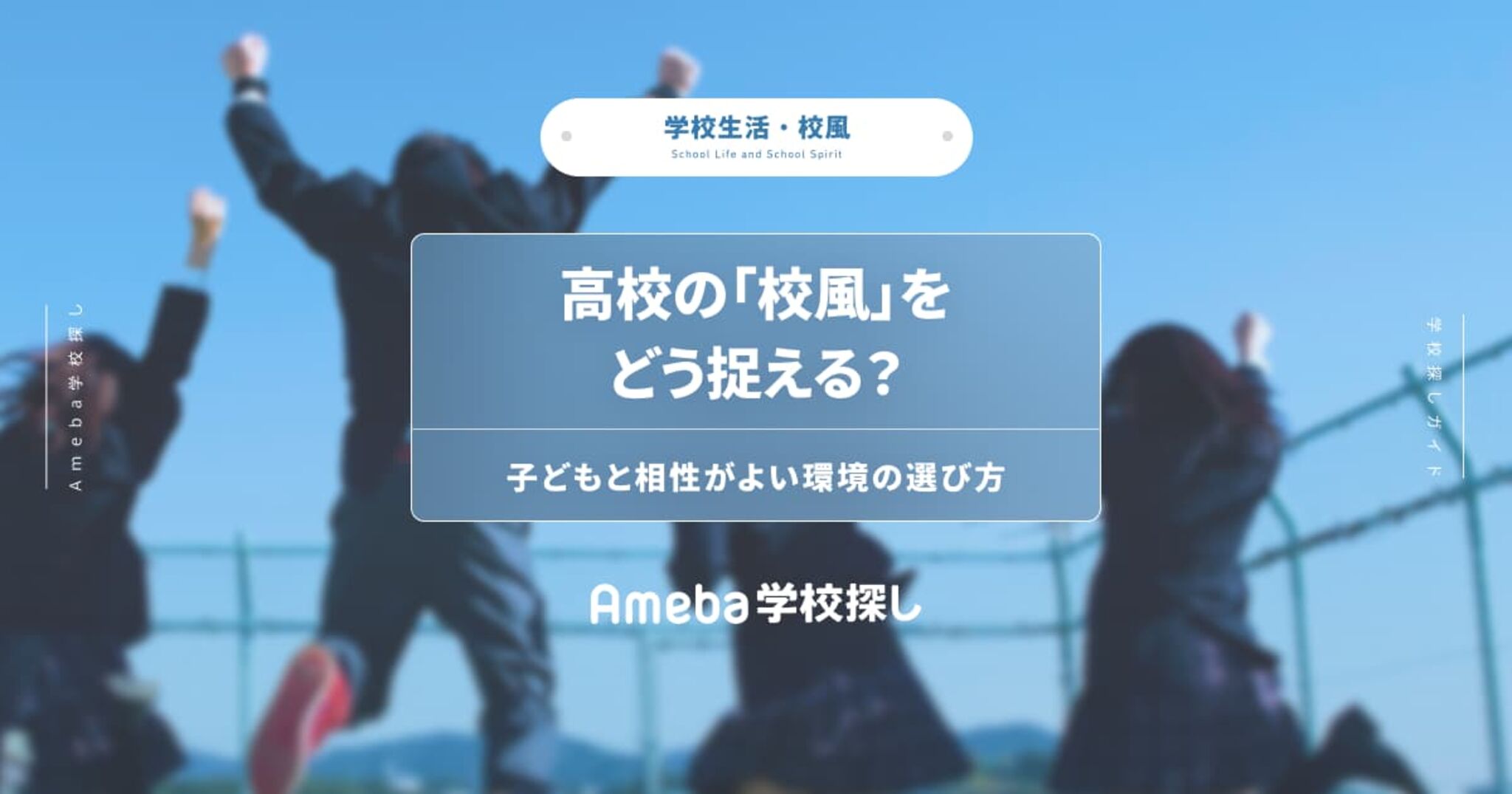高校選びは、偏差値のほかに「この学校なら安心」と思える基準が見えにくく、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。お子さんの将来にあった環境をどう見極めればよいのか、不安を抱える保護者の方は少なくありません。
今の高校教育は大きく変わり、ICT活用・探究学習・STEAM教育・高大接続など、次々と改革が始まっています。こうした変化をしっかりと踏まえることで、お子さんにあった高校の選び方が少しずつ見えてきます。
この記事では、2025年最新の教育トレンドをわかりやすく解説し、高校選びの判断材料となる視点をお届けします。
【2025年現在】高校教育の4つのトレンドと背景

2022年度から、高校では新しい学習指導要領にもとづく教育が本格的に始まっています。
学習指導要領とは、全国の学校で共通する学びの基準で、約10年ごとに見直されるものです。今回の改訂では、これからの社会を生き抜くために必要な力を育むことを目的に、大きな方向転換がおこなわれました。
ポイントとなっているのは、「自分で課題を見つけて考える力」や「人と協力して取り組む姿勢」を育てることです。こうした力は、大学での学びや将来社会で活躍するための土台となります。
そのために「総合的な探究の時間」が必修となり、ICTを活用した学びも広がっています。さらに、理系と文系の枠をこえたSTEAM教育など、新しい授業の取り組みも導入されています。
こうした背景から、現在の高校教育には4つの大きなトレンドが見られます。その具体的な内容を順に見ていきましょう。
「GIGAスクール構想」の深化と「個別最適な学び」の実現
「GIGAスクール構想」とは、すべての生徒に1人1台の学習用端末とインターネット環境を整備する国の取り組みです。
第1期 (~2023年度) は、タブレットなどの端末やネットワークを全国の学校に行き渡らせることが大きな目標でした。つまり、学びの「土台づくり」の段階です。
現在の第2期「NEXT GIGA」では、整備した端末をどのように活用するかがテーマになっています。通信環境の強化に加えて、AIドリルやデジタル教材を使った学びの質の向上が進んでいます。
NEXT GIGAが目指しているのは「一人ひとりにあった学び」と「仲間と協力する学び」の両立です。たとえば、AI教材が理解度にあわせて課題を出したり、先生が学習履歴を見ながら個別にサポートできるようになっています。また、オンライン上で仲間と意見を交わす授業も広がっています。
これまでのように「黒板を前に一斉に聞く」授業から「自分のペースで深め、仲間と一緒に広げる」学習へと進化しているのです。お子さんにとっても、無理なく学びを深められる安心感と、将来に生かせる力を育む環境が整いつつあります。
事例①埼玉県立春日部高等学校(埼玉)
大学入学共通テストの科目となった「情報Ⅰ」の対策に、デジタル教材「Life is Tech! Lesson」が導入されました。AIが生徒一人ひとりの解答状況を分析し、弱点や理解度にあわせて最適な学習プランを自動生成してくれる仕組みです。生徒が自分で学習状況を把握し、みずから学びを調整していく「自己管理力」を育てる点でも大きな意義があります。
事例②神奈川県立希望ケ丘高等学校(神奈川)
全県立高校に付与されているGoogle Workspaceのほかに、Microsoft 365のアカウントが導入されました。授業の最初に意見を集めたり、最後に振り返りを入力したりと、端末を使った学びの可視化が進んでいます。生徒たちが意見を交わし合うだけでなく、先生たちもICTの活用方法を共有し合い、学校全体で新しい学び方を広げています。
このように、GIGAスクール構想は高校教育の基盤を変えつつあります。生徒一人ひとりの理解度やペースにあわせた学びを支えると同時に、仲間と協力する力を育てる大きな原動力になるでしょう。
課題解決能力や表現力を養う「探究学習」が本格化
2022年度から必修になった「総合的な探究の時間」は、今の高校教育を代表する大きなトレンドのひとつです。この科目の狙いは、単なる知識の習得にとどまるものではありません。
生徒が自分で課題を見つけ、情報を集め、整理して考える力を伸ばしていくことです。その積み重ねが、社会で必要とされる問題解決力や表現力につながっていきます。
こうした学びの背景には、変化の激しい社会で「正解のない問い」に挑む力を育てたいという考えがあります。
また、仲間と協力しながら自分の答えを導き出す経験を重ねることで、将来社会で役立つ姿勢や力を養っているのです。
事例①東京都立竹早高等学校(東京)
「Tタイム」と呼ばれる探究学習を1年から3年まで実施しています。大学研究室を訪問するなど校外との連携も積極的に取り入れており、学びを社会と結びつける実践的な探究活動が展開されています。
事例②成蹊高等学校(東京)
全員参加型の探究活動に加え、希望者向けのPBL型(課題解決型学習)を実施しています。
高校1年では学習旅行のプランをグループで企画します。旅行先の文化や歴史を学ぶだけでなく、仲間と協力して企画を形にすることで、創造力や協働力を育みます。
このように、学校ごとに異なりますが、探究学習では生徒がテーマを決める・調べる・考える・発表するという流れを体験できます。その過程を通して、知識を活用して考える力や仲間と協力する姿勢、自分の考えを表現する力が少しずつ身についていきます。
「総合的な探究の時間」は、まさにこれからの社会を生きるお子さんにとって欠かせない力を育てる学びと言えます。
文理の枠組みを超えた「STEAM教育」と「リベラルアーツ」
AIやIoTなど技術の進化が社会のあらゆる分野に影響を与える今、学び方そのものも大きく変化しています。
これまでのように文系・理系をわけて学ぶだけでは、複雑な社会の課題に十分に対応できません。そのため高校教育では「文理の枠組みを超えた学び」がますます重要になっています。その代表例がSTEAM教育です。科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の頭文字をあわせたものです。
これらを総合的に学ぶことで、論理的に考える力と創造的な発想を生み出す力を同時に育てます。プログラミングやデータサイエンスの授業もこの流れのひとつです。
また、リベラルアーツも注目されています。幅広い分野を横断して学ぶことで、ものごとを多面的にとらえ、本質を見抜く力を育てます。哲学や歴史、人文学の学びは、理系分野の研究や国際社会での対話にも役立つ基盤となります。
事例① 渋谷教育学園幕張高等学校(千葉)
探究活動としてプログラミングやデータサイエンスを取り入れ、課題の発見から解決までを実践的に学べる環境を整えています。たとえば、生成AIをテーマにしたセミナーでは、デジタル技術を使った思考の磨き方を学んでいます。
事例② 中央大学附属高等学校(東京)
「教養総合」を柱とする、社会科学・人文科学・芸術文化を融合した分野横断型のリベラルアーツ教育を展開しています。問題発見と解決を重視し、文理の枠を超えた学びを通じて、論理的思考や総合力を深めていくカリキュラムが整えられています。
こうした各校の取り組みは、分野を横断して考える柔軟さや、協力して課題に取り組む姿勢を伸ばすものです。将来にわたって「新しい価値をつくる力」として生かされていくでしょう。
大学入試改革と連動した「高大接続」の強化
「高大接続」とは、高校での学びと大学での学びをつなぎ、高校生活で得た力を大学進学後にもいかせるようにする仕組みです。
これまでの入試は知識の多さが重視される傾向があり、高校での学びが十分に評価されにくい面がありました。そのため文部科学省は、高校・大学・大学入試を一体で見直す改革を進めています。
背景にあるのは、社会の急激な変化に対応できる力を育てる必要性です。暗記に頼る学習だけでなく、自分で課題を見つけて考え、表現する力がより重視されるようになっています。高校でその力を育み、入試や大学の学びにつなげていくことが狙いです。
入試の方法も多様になり、学力試験だけでなく総合型選抜や学校推薦型選抜が拡大しています。探究活動や課外活動、小論文やプレゼンテーションといった取り組みも評価の対象になっています。
事例① 桐蔭学園高等学校(神奈川)
麻布大学と連携協定を通じて、高校生が大学の研究者から直接講義を受けたり、模擬的な研究活動を体験したりできます。大学レベルの学びに触れることで、知識を深めるだけでなく「自分の興味をどう探究していくか」という姿勢も自然に育まれます。
事例② 早稲田大学本庄高等学院(埼玉)
日本医科大学との「高大接続連携協定」を活用し、医学部への推薦枠を設けています。高校での学びや活動の成果が、大学進学へとしっかり結びつく仕組みです。生徒は「学ぶこと」と「将来の夢」を自然につなげて考えることができます。
このように、高大接続の改革は「高校での学びをどう深めるか」がポイントとなります。保護者の方にとっては、進学実績だけではなく、探究活動や表現力育成への取り組みを確認することが大切な視点となるでしょう。
教育トレンドを受けて考えるこれからの高校選び

これからの高校選びは「偏差値が高いかどうか」や「進学実績」だけでは判断できない時代になっています。大切なのは、お子さんが高校生活を通してどんな学びを体験し、どんな成長を重ねられるかという視点です。
すでに解説してきたように、高校教育はICTの活用・探究学習・STEAM教育・高大接続といった改革が同時に進んでいます。
高校選びでは、こうした取り組みを通じて「お子さんが未来に向けて力を伸ばしていける環境」を確認することが大切になります。
高校選びのチェックポイント
- 高校の教育理念と目指している生徒像
学校が育てたい人物像が家庭の教育方針と一致しているか - 探究学習の充実度
テーマ設定の自由度や外部との連携体制はどうか - カリキュラムの特色
STEAMやリベラルアーツなど、多様な学びの機会があるか - ICT環境や活用レベル
1人1台端末をどの程度活用し、授業に組み込んでいるか - 進路指導の内容と大学入試への対応力
一般選抜に加え、総合型・推薦型にも対応しているか - 校風や教師の雰囲気
お子さんの個性にあった環境で安心して学べるか
こうした視点を持つことで、「数字だけにとらわれない、お子さんにあった学校選び」が見えてきます。高校教育のトレンドを理解しておくことは、迷いがちな学校選びにおいて、保護者にとって大きな指針になるはずです。
高校の教育理念と目指している生徒像
高校を選ぶ際には、学力や進学実績だけでなく、その学校が掲げる教育理念に注目することが大切です。教育理念とは「どんな大人になってほしいか」という学校の願いであり、生徒像を示す指針になります。
たとえば「自律した学習者」や「国際社会で活躍できる人材の育成」など、学校によって表現は異なります。その理念が家庭の教育方針やお子さんの将来像と一致しているかを確認しましょう。
学校説明会やパンフレットには、校長メッセージや育成したい人物像が具体的に記載されている場合があります。こうした情報を丁寧に読み取り、お子さんにふさわしい環境かどうかを考えることが第一歩となります。
探究学習の充実度
高校教育の中心に位置づけられている「総合的な探究の時間」は、いまや学校選びの大きなポイントです。思考力や主体性などの「生きる力」を育むだけでなく、総合型選抜や学校推薦型選抜などの大学入試で評価される場合もあります。
探究学習では、生徒がみずから課題を見つけ、情報を集めて分析し結論を導きます。テーマは「地域の課題」「環境問題」「国際交流」など幅広く、社会と結びついた実践的な学びが広がっています。
また、外部の大学や企業、地域団体と連携したプログラムがあるかどうかも確認したい点です。学校によっては、大学の研究室でのフィールドワークや企業との共同研究に取り組める場合もあります。
さらに、学校側のサポート体制も大切なポイントです。専任の先生が探究活動を支えてくれるか、発表の場や指導の仕組みがあるかを確認することで、その学校の学びの質をより具体的にイメージできます。
カリキュラムの特色
高校を選ぶうえで見逃せないのが、どんな授業や科目を学べるかという「カリキュラムの特色」です。
とくにSTEAM教育やリベラルアーツが重視されるなか、一人ひとりの興味や関心にあわせた選択肢があるかどうかがポイントです。以下の点を確認しましょう。
- 文理の枠を越えた学びがあるかどうか
- 特色ある選択科目が充実しているか
- 理解度にあわせた授業体制になっているか
たとえば、データサイエンスの先端的な科目を選べる学校もあれば、哲学などの教養科目を設けている学校もあります。こうした学びは、将来の進路を考えるうえで新しい可能性を広げるきっかけになります。
また、習熟度にあわせた授業や少人数制の授業を取り入れている学校では、生徒の理解度にあわせて学習を深めやすくなります。得意な分野をさらに伸ばしたり、苦手を克服したりと、自分にあったペースで学べるのは大きな魅力です。
このように、学校ごとに用意されているカリキュラムは大きく異なります。説明会や学校案内で、どんな科目や学びの機会があるのかを具体的に確認してみましょう。
ICT環境や活用レベル
ICT(Information and Communication Technology)は「情報通信技術」を意味します。GIGAスクール構想のもと、高校でも学びの効率を高めるため、1人1台端末の導入が進んでいます。端末を自宅学習にも活用できるか、Wi-Fi環境やセキュリティ体制が整っているかを確認しましょう。
授業では、オンライン教材を使った個別学習やグループでの協働作業など、さまざまな形でICTが取り入れられています。さらに探究活動では、情報収集・アンケート調査・海外とのオンライン交流などにも活用され、学びの幅を広げています。
ICT環境の整備状況や活用の幅は学校によって異なるため、学校説明会や資料で確認することが安心につながります。
進路指導の内容と多様化する大学入試への対応力
近年の大学入試は、一般選抜(学力試験)だけでなく、総合型選抜や学校推薦型選抜といった多様な方式が広がっています。そのため、高校には幅広い入試形態に対応できる進路指導が求められています。
進路指導が充実している学校では、面接や小論文の指導、探究活動を入試に活かすサポートなどがおこなわれています。また、一人ひとりの適性や将来像にあわせたキャリアカウンセリングも重視されており、進路に向けた安心感を高めています。
進路実績の数値だけでは見えにくい部分こそ、高校選びで注目したいポイントです。
校風や教師の雰囲気
高校選びにおいて、学習内容や進路実績と同じくらい重要なのが校風や教師の雰囲気です。日々の学校生活をお子さんが安心して送れるかどうかは、学習意欲や成長にも大きな影響を与えます。
確認のポイントとしては以下のような点があります。
- 学校全体の雰囲気が落ち着いているか、活気があるか
- 教師が生徒に寄り添い、対話を重視する姿勢を持っているか
- 生徒同士の関係性や協調性を育む取り組みがおこなわれているか
こうした校風や教師の関わり方は、実際に学校説明会や公開授業に参加しなければわからない部分も多いでしょう。資料だけに頼らず、直接学校を訪れて体感することで、お子さんにあう環境かどうかを確かめることができます。
高校教育のトレンドを理解しお子さんにあった高校選びに活かそう

高校教育は今、大きな変化のなかにあります。GIGAスクール・探究学習・STEAM教育・高大接続の強化など、これまでにない学びの枠組みが次々と整備されつつあります。
こうした動きを踏まえることは、お子さんにあった進路を考えるうえで大切な視点になります。数字や進学実績だけでは見えてこない、その学校ならではの教育の魅力に気づけるからです。
高校選びは、保護者にとっても大きな決断であり、不安や迷いが伴うのは当然のことです。教育の最新トレンドを理解しておくことで「ここなら安心できる」という手がかりが見つかり、判断に自信が持てるようになります。
ぜひ説明会や学校見学にも足を運び、教室の雰囲気や先生・生徒の表情を直接感じてみてください。そのうえで、どうか安心して、一緒に歩んでいける学校を見つけてくださいね。
- 葉玉 詩帆
Ameba学校探し 編集者
幼少期から高校卒業までに、ピアノやリトミック、新体操、水泳、公文式、塾に通う日々を過ごす。私立中高一貫校を卒業後、都内の大学に進学。東洋史学を専攻し、中東の歴史研究に打ち込む。卒業後、旅行会社の営業を経て2021年より株式会社CyberOwlに入社。オウンドメディア事業部で3年半の業務経験を経て、Ameba塾探しの編集を担当。「Ameba学校探し」では、お子さんにぴったりの学校選びにつなげられる有益な記事づくりを目指しています。