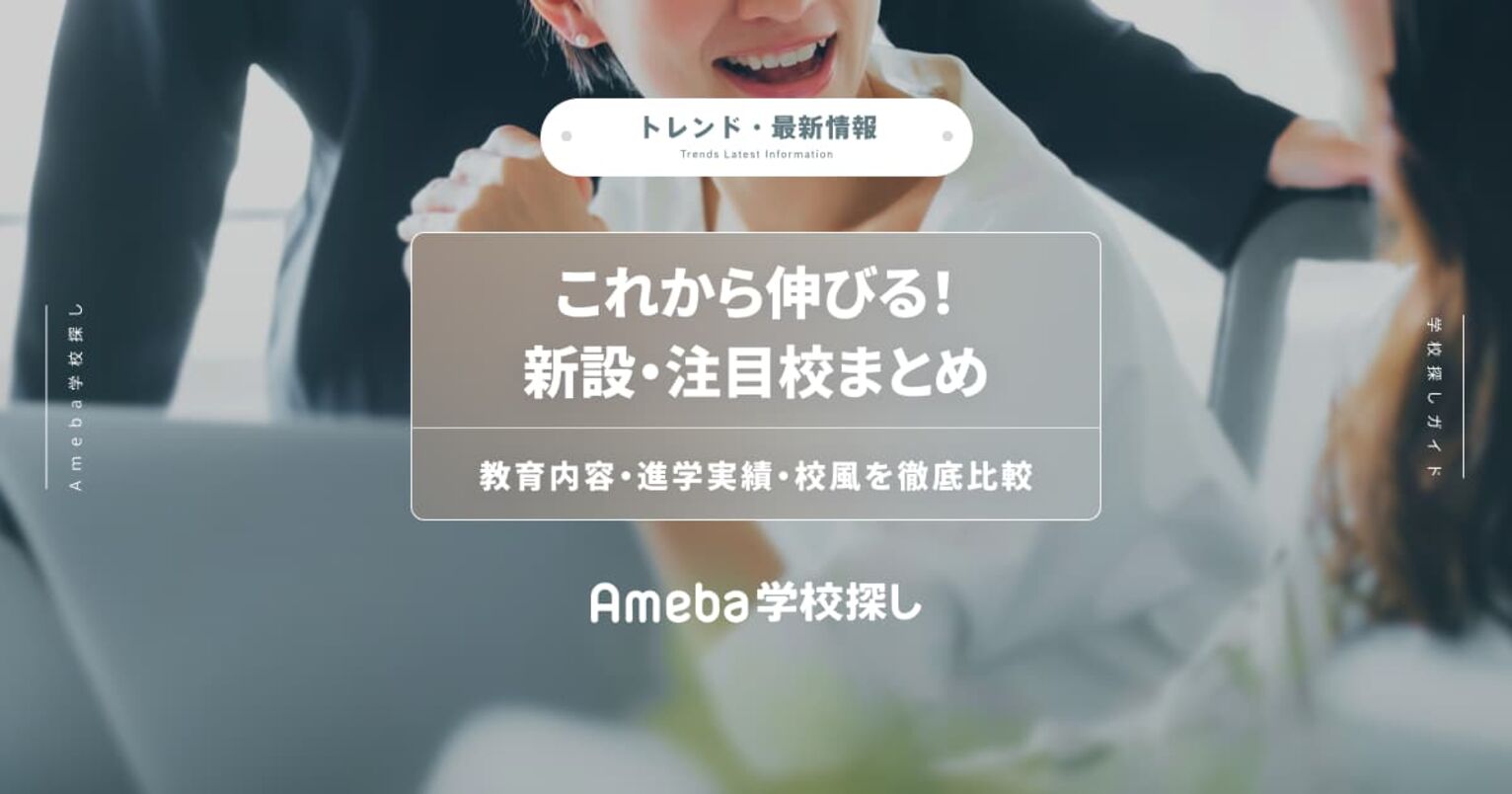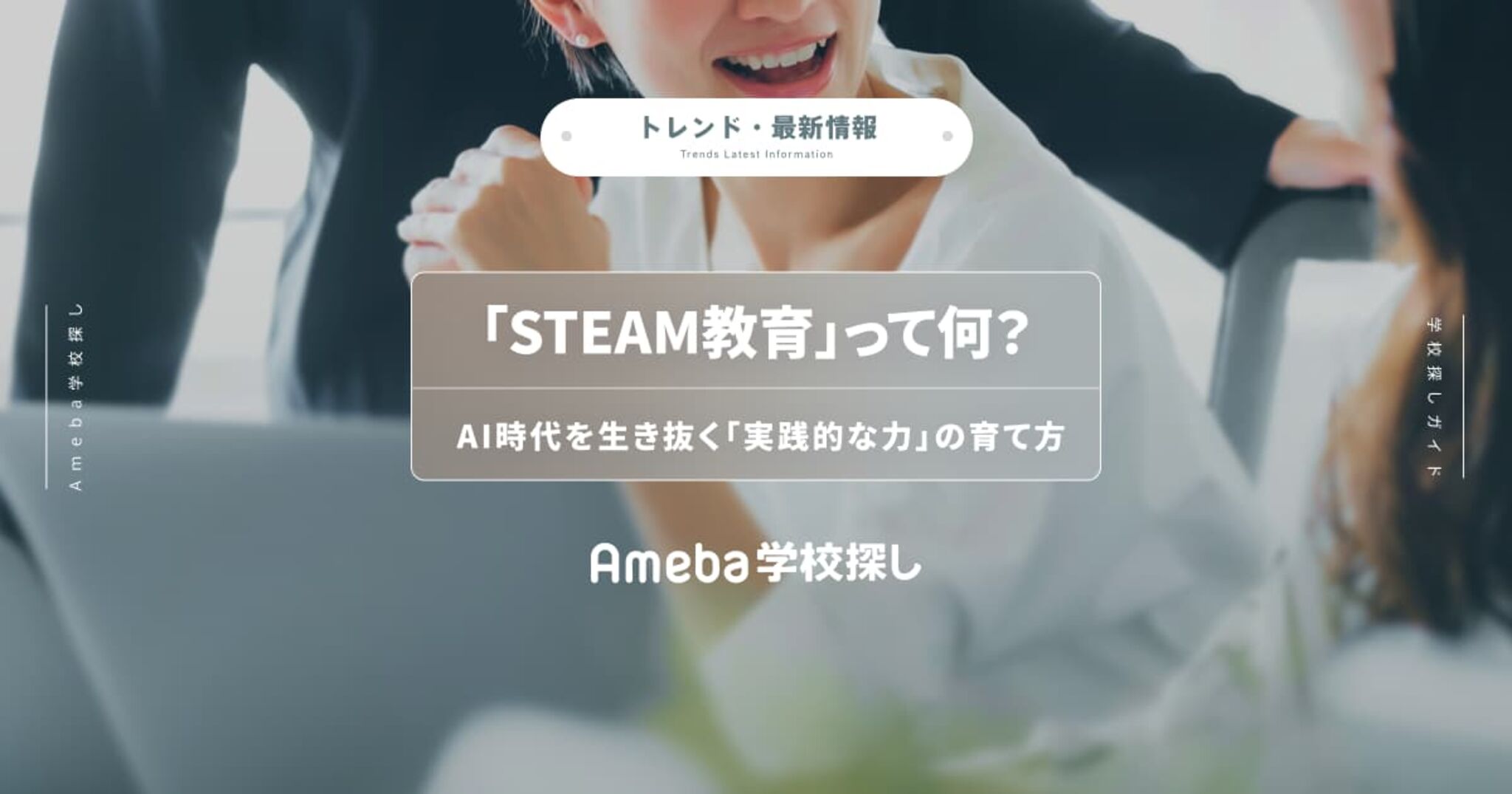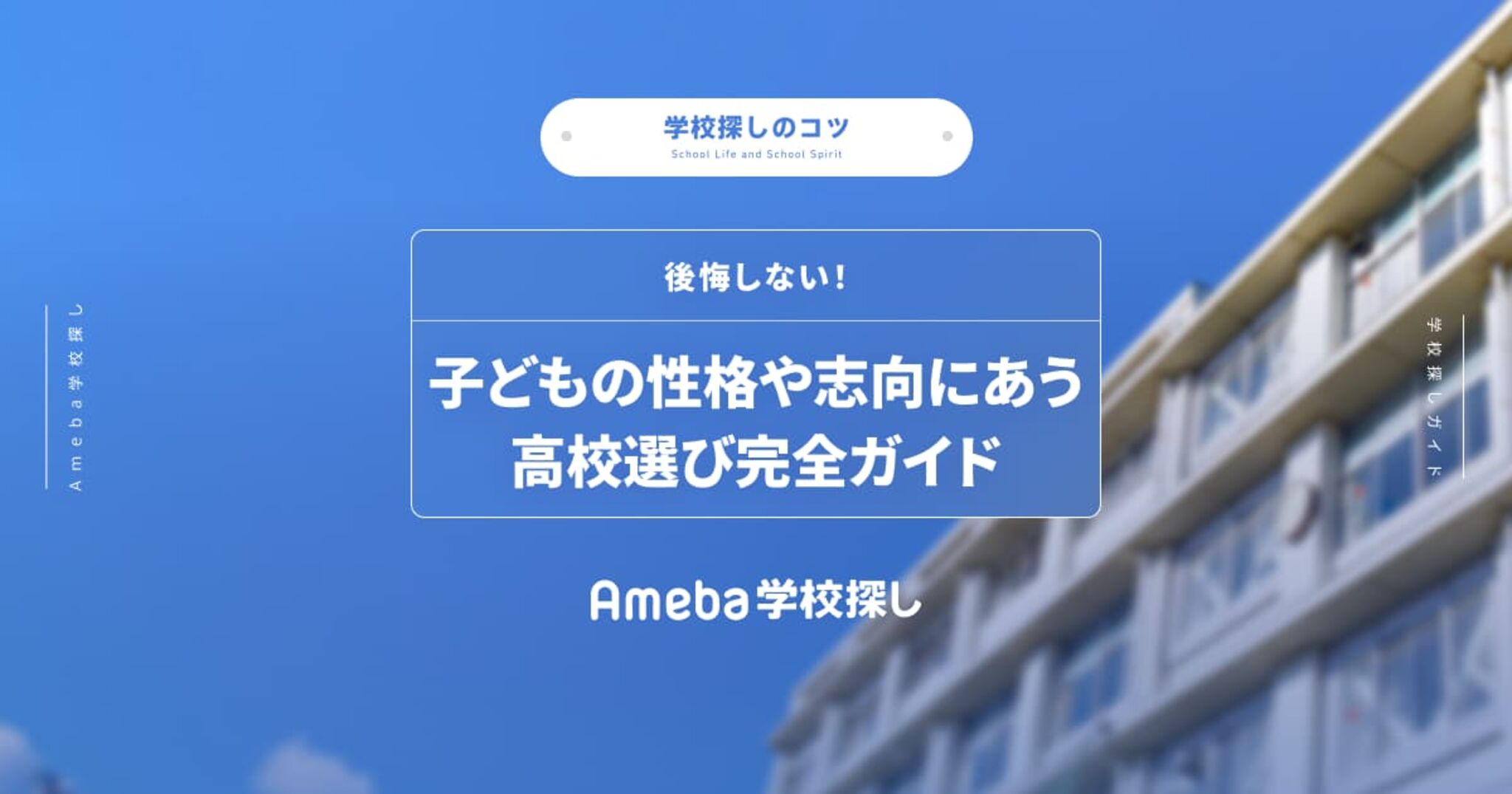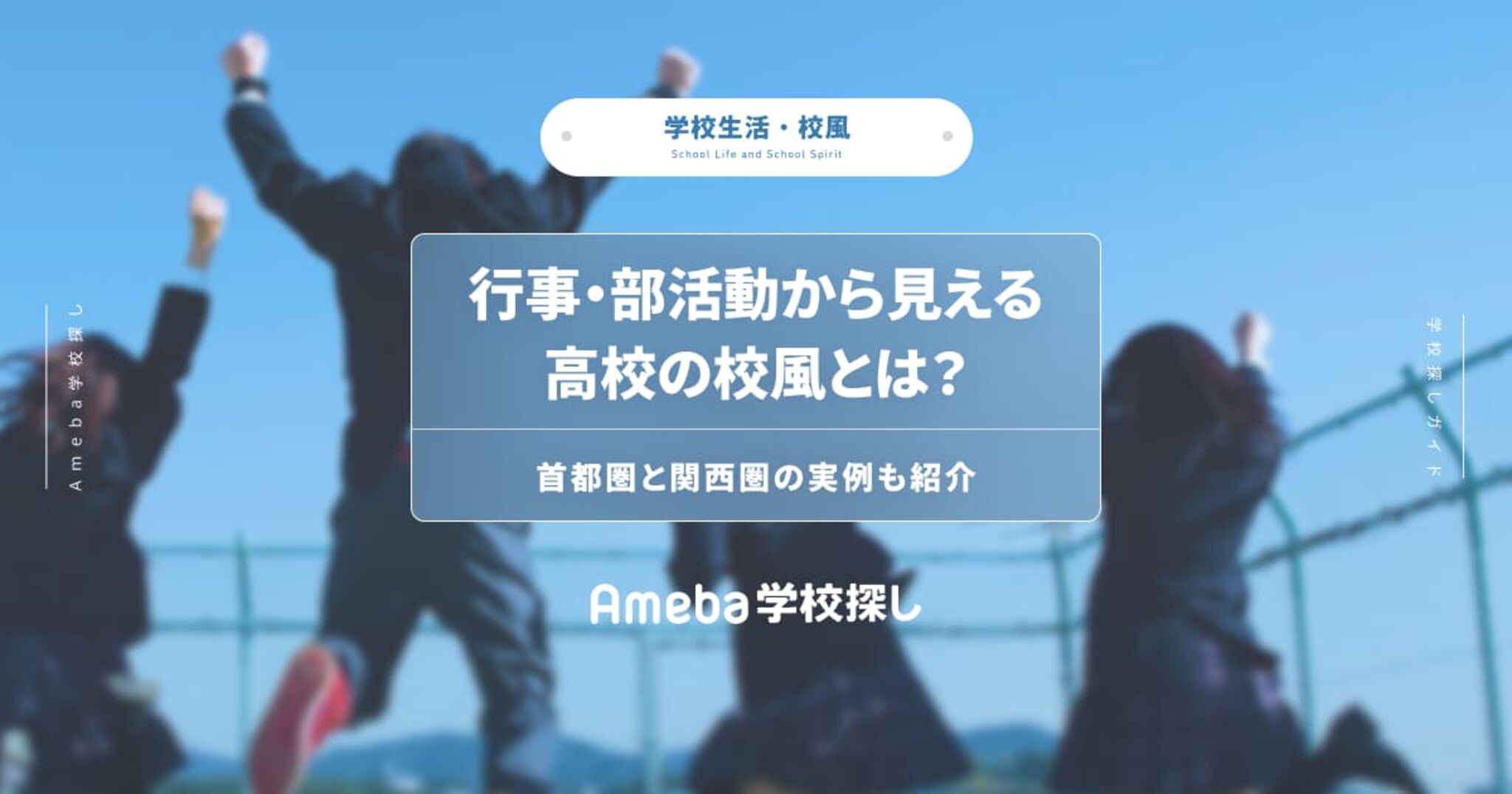お子さんの学校選びで悩まれている保護者の方は多いのではないでしょうか。近年、中学・高校では新設校やリニューアル校が相次いで誕生し、従来とは異なる魅力的な教育を展開しています。
探究活動や国際交流、STEAM教育といった新しい学びのスタイルを通じて、お子さんの可能性を広げる学校が続々と登場しています。偏差値だけでは見えてこない学校独自の特色や教育方針を知ることで、お子さんに最適な学校を見つけることができます。
この記事では、2025年度以降も注目される新設・注目校を首都圏と関西に分けて紹介し、教育内容・進学実績・校風の3つの視点から解説します。
新設校や特色ある学校が増えているのはなぜ?
近年、中学・高校では新設校やリニューアル校が相次いで誕生しています。この背景には大きく2つの要因があります。
2022年度から高等学校で新しい学習指導要領がスタートし、教育の現場が大きく変わりました。従来の暗記中心の学習から、自分で課題を見つけて解決する「探究型学習」や、生徒同士で協力しながら深く考える「アクティブラーニング」が重視されるようになりました。
新しい教育では「総合的な探究の時間」という科目が必修となり、お子さんが主体的に学び、考える力を育てることを目指しています。また、英語では「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランス良く身につけることが重要視され、より実践的なコミュニケーション能力の育成が求められています。
こうした新時代に求められる学びに対応するため、探究活動やSTEAM教育、国際交流などの特色あるカリキュラムを整備する学校が増えているのです。新設校やリニューアル校は、こうした教育改革にいち早く対応できる環境を整えやすく、お子さんの未来に必要な力を育てる教育を実践しています。
もうひとつの大きな要因は、少子化時代における学校の生き残り戦略です。18歳人口は1992年の約205万人をピークに減少を続け、2023年には約110万人まで減少しています。
このような状況のなかで、私立学校は独自の魅力を打ち出さなければ、お子さんや保護者に選んでもらえなくなりました。
そこで、多くの学校が学校ブランドの刷新や独自の教育プログラムの導入を進めています。具体的には、校名変更による国際的なイメージアップ、共学化による間口拡大、最新のICT環境整備などです。
また、地域との連携を深めた探究活動や、大学・企業との連携プログラムなど、従来の学校では体験できない特色ある教育を展開する学校も増えています。
2025年注目の新設・リニューアル校【首都圏編】
首都圏では、教育改革の流れを受けて魅力的な新設校やリニューアル校が続々と誕生しています。ここからは、お子さんの個性や将来の夢にあわせて選べる、特色豊かな学校を紹介します。
ドルトン東京学園中等部・高等部(東京都)
2019年に開校したドルトン東京学園は、アメリカで100年以上前に生まれた「ドルトンプラン」という学習者中心の教育法を実践している中高一貫校です。調布市に位置し、成城学園前駅からバスで約6分という立地にあります。
この学校の最大の特徴は、生徒一人ひとりの興味や探究心を大切にした「自由と協働」の教育理念です。従来の一律な授業スタイルではなく、「ハウス」「アサインメント」「ラボラトリー」という3つの柱で構成される独自教育システムを採用しています。
定期テストがない代わりに、生徒が自分で作成するポートフォリオで学習を評価するため、主体的な学習姿勢が自然に身につきます。
英語教育にも力を入れており、スタンダード・アドバンスド・アカデミックの3クラス編成で、生徒のレベルに応じた学習が可能。
最上位のアカデミッククラスでは、英語圏の大学入学に必要な高度なレベル(CEFR C1相当)を目標とした授業をおこない、海外大学進学も視野に入れたアカデミックライティングや本格的なディスカッションに取り組みます。
2025年3月には開校以来初となる卒業生を輩出し、シドニー大学への進学者も輩出するなど、国内外への多様な進路を実現。
さらに、同校はサンフランシスコ州立大学をはじめとした海外大学と連携協定を結んでおり、海外進学を希望する生徒への充実したサポート体制が整っています。大手予備校の河合塾グループが運営しているという安心感もあり、従来とは異なる教育アプローチに関心のある保護者から高い人気を集めています。
開智日本橋学園中学・高等学校(東京都)
東京23区内での国際バカロレア認定校として注目を集める開智日本橋学園は、都心の浅草橋駅から徒歩約3分という立地にあります。PBL(課題解決型学習)と探究学習、ICT活用に強く、都市型の国際教育に特化した学校として人気が高まっています。
同校では中学1年から高校1年まで、リーディングコース(LC)、デュアルランゲージコース(DLC)、グローバル・リーディングコース(GLC)の3つのコースに分かれて学びます。
2022年度入学生からは、全コースで国際バカロレアのMYP(ミドル・イヤーズ・プログラム)を導入。MYPは11歳から16歳を対象とした探究型学習プログラムで、生徒が主体的に考え、課題を発見・解決する力を育てることを目的としており、より充実した国際教育環境が整っています。
教員の約4分の1が英語で授業をおこなうことができ、美術や技術・家庭科の授業はすべて英語で実施されます。ホームルームも英語でおこなわれ、休み時間にも英語を積極的に使う生徒が多く、「英語で学ぶ」環境が日常的に整っています。
帰国生にとっては、英語力を維持・向上させながら学校生活を送れる環境が用意されており、高校2年からのディプロマ・プログラムでは、6科目中3科目を英語で学ぶバイリンガルDPの取得も可能です。
国内外を問わず幅広い進路選択ができるため、国際感覚を育てたいとお考えの保護者から注目されています。
千葉県立松戸国際高等学校(千葉県)
2024年度から千葉県教育委員会によりグローバルスクールに指定され、カリキュラムを一新してさらなる国際教育の充実を図っている千葉県立松戸国際高等学校は、公立校でありながら国際教育に力を入れている注目の学校です。
ユネスコスクールにも加盟し、SDGs(持続可能な開発目標)を意識した探究活動などにも取り組んでいます。
同校は普通科と国際教養科を設置し、外国人・帰国生の受け入れも積極的におこなっています。校訓である「希望」のもと、「松国力」と呼ばれる心情・智能・体軀の3つの力を高め、社会力豊かなグローバル人材の育成を目指しています。
グローバルスクール指定に伴い、海外留学制度の拡充や国際理解教育のさらなる推進が図られており、生徒の国際的な視野を広げる多様な機会を用意。加えて、公立校ならではの学費の負担軽減も大きなメリットで、質の高い国際教育を受けやすい環境が整っています。
同校は松戸市に位置し、JR武蔵野線・新八柱駅や新京成線・五香駅からアクセス可能。都心からの通学も比較的便利です。国際教育に興味があるものの、私立校の学費が気になるという保護者にとって、検討価値の高い学校となっています。
2025年注目の新設・リニューアル校【関西編】
関西地域でも、時代の変化に対応した新設校・リニューアル校が多数誕生しており、それぞれが独自の教育方針で注目を集めています。
関西ならではの教育風土を活かしながら、お子さんの未来を見据えた特色ある教育を展開する学校を紹介します。
大阪公立大学工業高等専門学校(大阪府)
2022年に名称変更した大阪公立大学工業高等専門学校は、大阪府立大学と大阪市立大学の統合により誕生した大阪公立大学のもとで、新たな歩みを始めました。寝屋川市に位置し、全国でわずか3校しかない公立高等専門学校のひとつとして貴重な存在です。
同校の大きな特徴は、実践重視のPBL(課題解決型学習)カリキュラムと充実した産学官連携です。ものづくりの街・大阪の特性を活かし、専門分野の知識と技術を深く学びながら、創造力と高い倫理観を兼ね備えた実践的技術者の育成を目指し、技術力だけでなく、現代社会で求められる問題発見・解決能力も重視した教育が注目されています。
2022年度からは、総合工学システム学科として、エネルギー機械コース、プロダクトデザインコース、エレクトロニクスコース、知能情報コースの4コース制に再編。AIやIoTなどのデジタル技術が進化する社会に対応したDX人材の育成を目的とした質的転換が図られており、現代に求められる教育内容が充実しています。
就職面では、毎年数百社からの求人があり、本科の求人倍率は20倍を超える高い数値を保っています。公立校ならではの学費の安さに加えて、高い技術力と優れた就職実績を誇る同校は、技術系への進路をお考えの生徒にとって魅力的な選択肢となっています。
2027年度には大阪公立大学中百舌鳥キャンパスへの移転も予定されており、さらに充実した教育環境が期待されています。
※移転計画については学校公式サイトまたは最新の公式情報をご確認ください。
関西学院千里国際中等部・高等部(大阪府)
関西学院千里国際中等部・高等部は、日本で唯一インターナショナルスクールと協働運営する中高一貫校として、本格的な国際教育を実現している注目の学校です。箕面市に位置し、35以上の国籍をもつ生徒・教員が集う多様性に富んだキャンパスが特徴です。
同校の最大の魅力は、関西学院大阪インターナショナルスクール(OIS)との同一キャンパス内で日本の一条校とインターナショナルスクールが連携した独特な教育環境のもと、校舎・授業・課外活動・理念を共有していることです。
2013年からは、OISが創立以来実施してきた国際バカロレアのディプロマ・プログラムを共有授業として履修できるようになり、海外大学への進学の道も大きく開かれました。
教育面では、開校当初から国際バカロレアの理念を取り入れた対話型・思考型の学習を重視し、中高6年間にわたって「探究型」の授業を展開しています。中学1年生では「知の探検隊」という授業で探究型学習の基本を身につけ、高校生全員がフィールドワークに参加して課題研究論文に取り組みます。
文部科学省のスーパーグローバルハイスクール(SGH)に指定された実績もあり、「高い国際通用性を有するレジリエンスに富むグローバルリーダー育成」をテーマとした教育が実践されています。
帰国生の受け入れを主な目的としながらも、一般生も含めた国際的な学習環境は、生徒の国際感覚と多様な価値観を育む貴重な機会となっています。
京都先端科学大学附属高等学校(京都府)
京都先端科学大学附属高等学校は、STEAM教育に特化した先進的な教育で注目を集めている学校です。1925年創立の約100年の歴史を持ちながら、ニデック株式会社創業者の永守重信氏が理事長を務める革新的な教育環境が整備されています。
STEAM教育の例として、環境問題を科学的に分析し、技術で解決策を考え、デザイン性も重視した製品をつくるといった、複数の分野を組み合わせた学習に取り組みます。同校ではこうした体験を通じて、将来社会で役立つ問題解決力や創造力を育てています。
文部科学省からスーパーグローバルハイスクール(SGH)とワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業(WWL)に指定された実績があり、その教育プログラムは対外的にも高く評価されています。とくに「世界で活躍できるグローバル人材の育成」を掲げ、グローバル教育と探究型プログラムを融合させた独自の教育を展開。
同校の大きな特徴は、大学進学を最終目標とするのではなく、「社会に出たときに何を果たしたいか」という目的意識を持たせることに重点を置いていることです。STEAM教育を通じて自分の興味を発見した生徒たちが、明確な目標を持って進路選択をしており、将来への意欲を育てたいと考える保護者からも関心を集めています。
学校選びで注目すべき4つのポイント
新設校や注目校について詳しく知るほど、「どの学校がわが子にあっているんだろうか…」と迷いが深まることもあります。
ここでは、お子さんにぴったりの学校を見つけるために、とくに注目したい4つのポイントを紹介します。
- 教育方針とカリキュラムの特徴
- 学習支援体制と進路サポート
- 学校行事・部活動の充実度
- 通学環境とアクセスの利便性
教育方針とカリキュラムの特徴
学校ごとに学習方針は大きく異なり、お子さんの将来に与える影響も変わってきます。大学進学を重視する進学校は授業進度が速く、演習や模試が多めに設定されており、確実な学力向上を図っています。
一方、探究学習やPBL(課題解決型学習)を重視する学校では、プレゼンテーションやフィールドワークが多く取り入れられ、知識の応用力や課題発見力が自然に養われていきます。
国際志向の強い学校を検討される場合は、英語授業の割合や留学制度の充実度、国際バカロレア対応の有無などが重要な確認ポイントとなります。
たとえば、将来的に海外大学への進学をお考えであれば、IBディプロマが取得できる学校や、英語でほかの教科を学ぶイマージョン教育を実施している学校が適しています。
お子さんの将来像に沿った学び方ができるかどうかを、学校案内や説明会でしっかりとチェックしてみてください。学習スタイルに迷ったときは、お子さん自身の興味や性格、将来の夢について改めて話し合ってみることをおすすめします。
学習支援体制と進路サポート
生徒一人ひとりの能力や志望に応じた学習フォローと進路指導の手厚さは、学校の教育力を測る非常に重要な指標です。
とくに新設校や変革期にある学校では、少人数制を活かしたきめ細やかなサポート体制が整っており、お子さんの成長を丁寧に見守ってもらえる安心感があります。
具体的には、週末や長期休暇中の補習・講習の充実度、チューター制度の有無、オンライン学習環境の整備状況などを確認してみてください。
これらは直接的な成績向上につながる重要な要素です。また、質問しやすい雰囲気づくりや、個別面談の頻度なども、安心して学習に取り組める環境かどうかを判断する材料になります。
進路サポートの面では、大学・専門学校・海外大学とのパイプの太さ、推薦・総合型選抜入試への対応力、キャリア教育の早期実施などが注目ポイントです。
近年はICTを活用した学習分析や、進路決定を支えるポートフォリオ管理も広がっています。「ただ授業を受けるだけ」で終わらない学習支援があるかどうかが重要です。
学校行事・部活動の充実度
学校生活の満足度を大きく左右するのが、行事や部活動の充実度です。
文化祭・体育祭・修学旅行といった伝統的な行事に加えて、海外研修や地域との連携イベント、探究発表会など、生徒の自主性や創造性を伸ばす機会がどれだけ用意されているかも学校選びの判断材料となります。
とくに新設校では、従来の枠にとらわれない新しい行事やプログラムが企画されており、「初めての体験」を通じて大きく成長できる機会に恵まれています。また、生徒主体で企画・運営される行事があるかどうかも、リーダーシップや協調性を育むという観点から注目したいポイントです。
部活動については、全国大会を目指す強化部があるのか、初心者でも楽しめる文化部が充実しているのかなど、興味や性格にあう選択肢があるかを確認しましょう。
公式サイトやSNSの写真・動画を見ることで、生徒たちの表情や活動の様子から実際の充実度を把握しやすくなります。何より、お子さんが「この学校で学校生活を過ごしたい」と感じられるかどうかがもっとも重要です。
通学環境とアクセスの利便性
通学時間は毎日の生活に直結する重要な要素です。お子さんの体力面や部活動との両立にも大きく影響します。
多くの教育機関では片道1時間程度を通学時間の目安としており、それを超えると体力面や学習時間の確保に影響が出る可能性があると考えられています。そのため、現実的な通学プランを立てることが大切です。
電車・バスの乗り換え回数、混雑具合、遅延の頻度なども、実際の通学を想定して確認しておきましょう。朝の通勤ラッシュ時間帯と重なる場合は、負担になりすぎないかどうか慎重に検討する必要があります。また、帰宅時の安全性も重要な確認ポイントです。
学校の立地によっては、自然豊かな環境で学べる一方で、アクセスが不便な場合もあります。その際は、スクールバスの運行状況や、最寄り駅からのバス便の充実度なども調べてみてください。
オープンスクールや説明会の際には、実際の通学ルートを試してみることで、日々の負担感をより具体的にイメージできます。
「通学が大変そうだけれど、この学校の教育に魅力を感じる」という場合は、お子さん自身の体力や意欲も含めて、家族でよく話し合って決めることをおすすめします。「毎日通いたい!」と感じた学校を選ぶことが、充実した学校生活につながります。
新設・注目校は新時代に求められる学びや魅力がたくさん!
新設・注目校は、大学入試制度の多様化に伴い、従来の学力指標だけでは測れない21世紀型スキルを重視した教育アプローチと教育の可能性を持っています。共通しているのは、生徒一人ひとりの個性や興味を大切にし、従来の枠にとらわれない新しい学びの形を提供していることです。
探究活動やSTEAM教育、国際バカロレア、ICT活用など、一見難しそうに聞こえる教育手法も、実際は「知りたい」「やってみたい」という自然な気持ちを引き出し、学ぶ喜びを実感できるように工夫されています。
新設校だからこそできる革新的な取り組みや、リニューアル校がもつ伝統と革新の両立など、それぞれの学校が時代の変化に対応しながら、未来に必要な力を育てようと努力しています。
近年、教育界では基礎学力の習得に加え、思考力・協働力・問題解決力といった汎用的スキルの重要性が注目されています。
ぜひ、教育内容・進学実績・校風の3つの視点から各校を比較検討しながら、興味や将来像にあわせて、お子さんにとって最適な学校を見つけてください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。