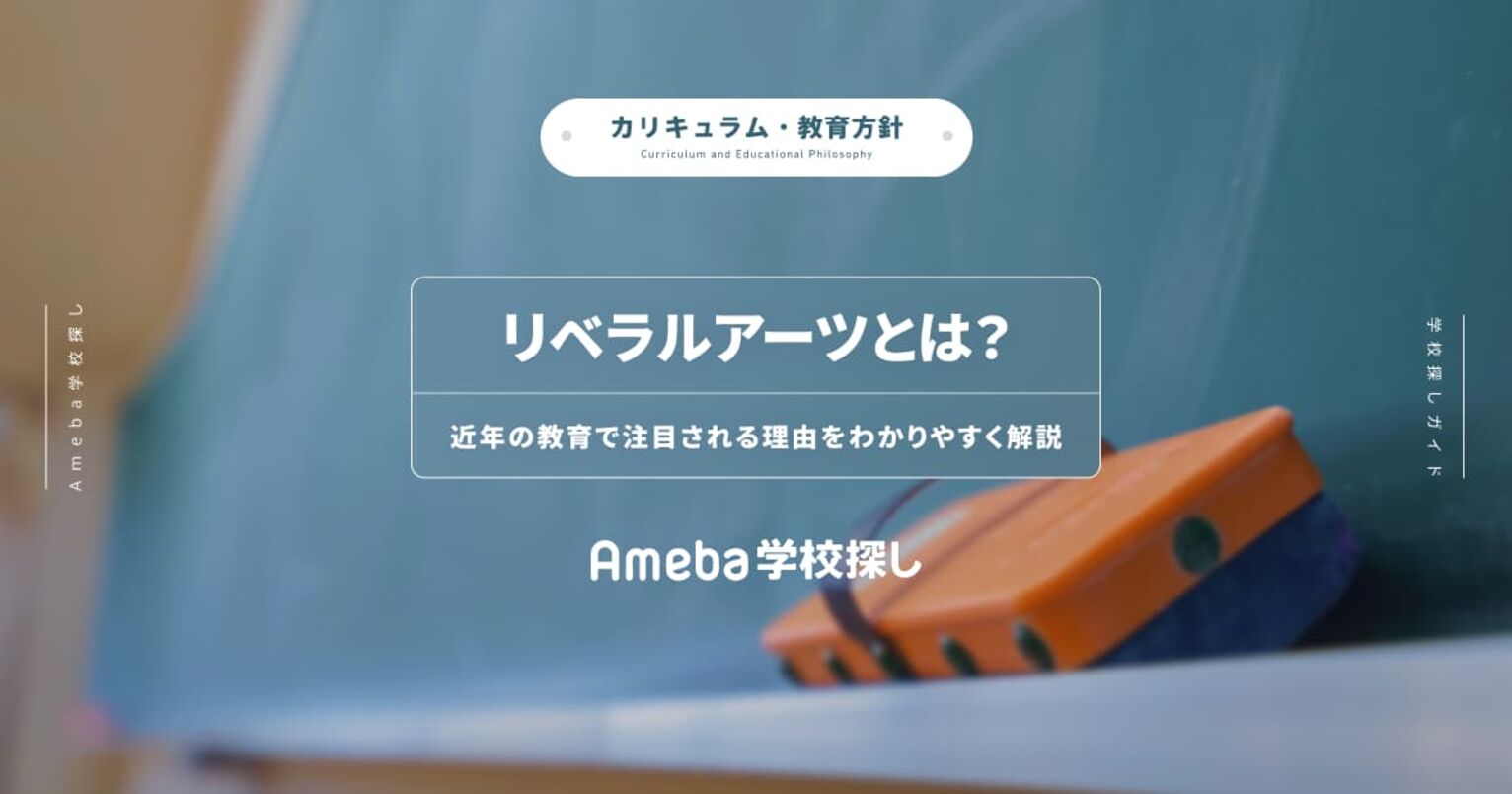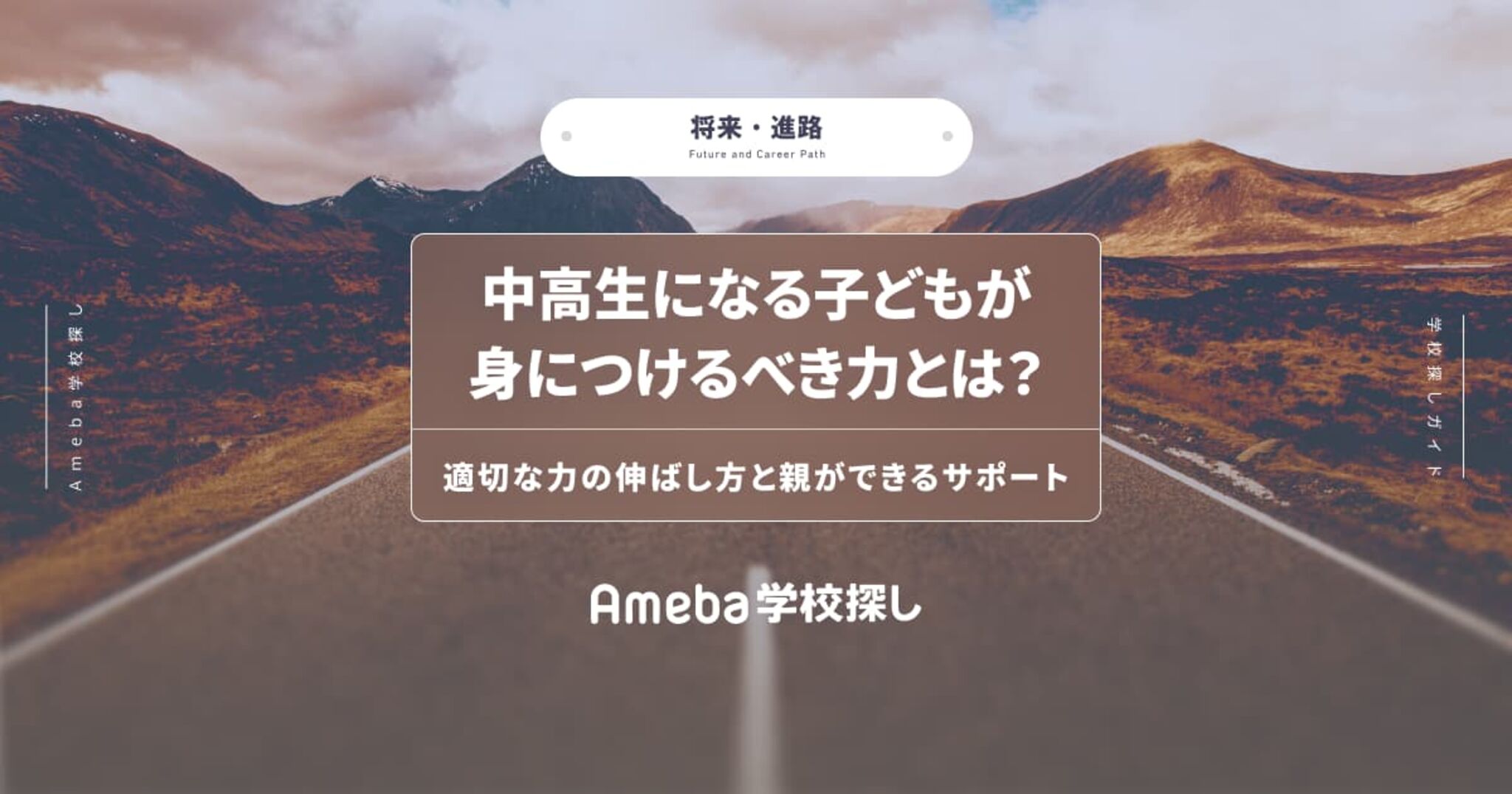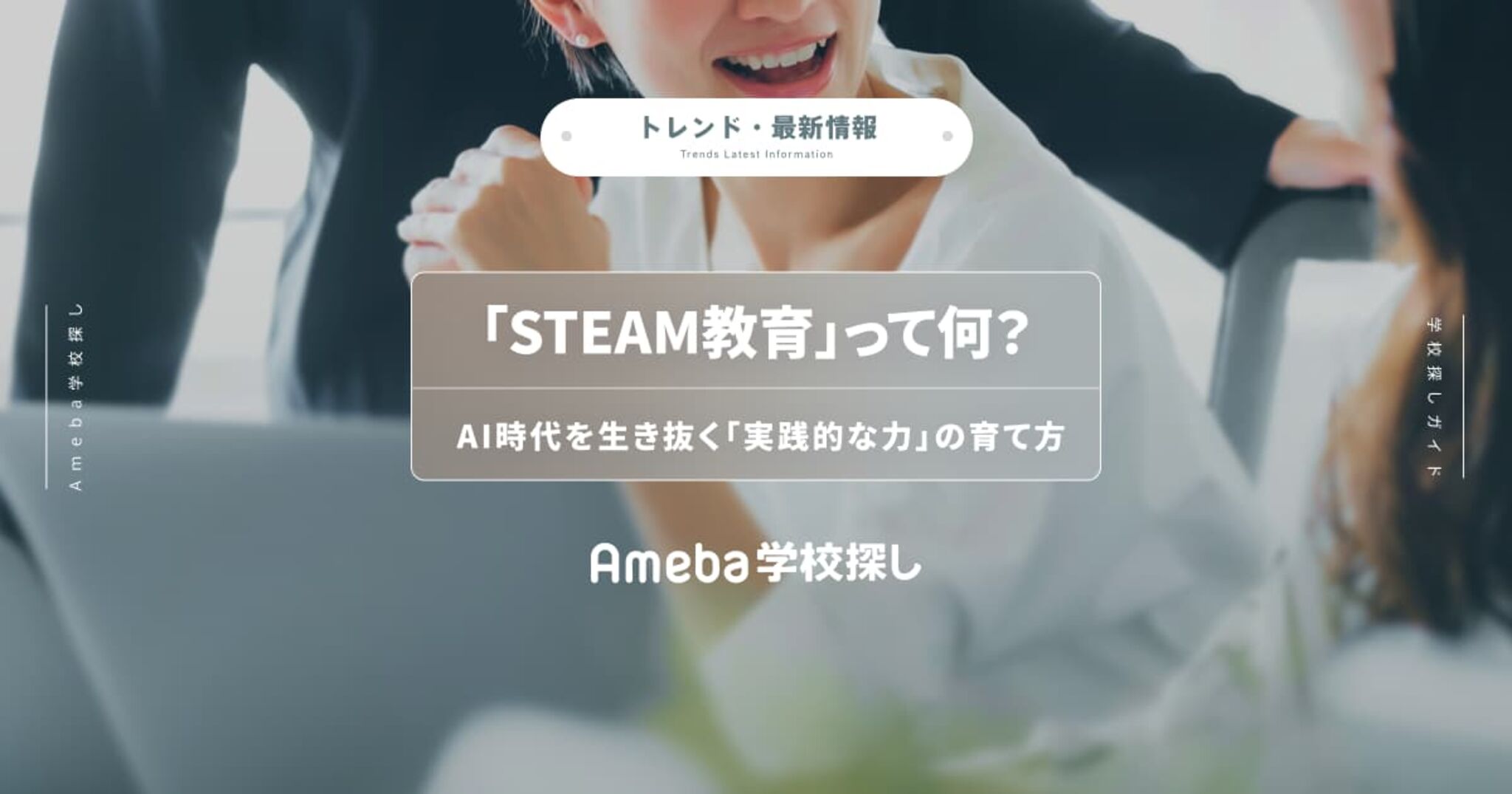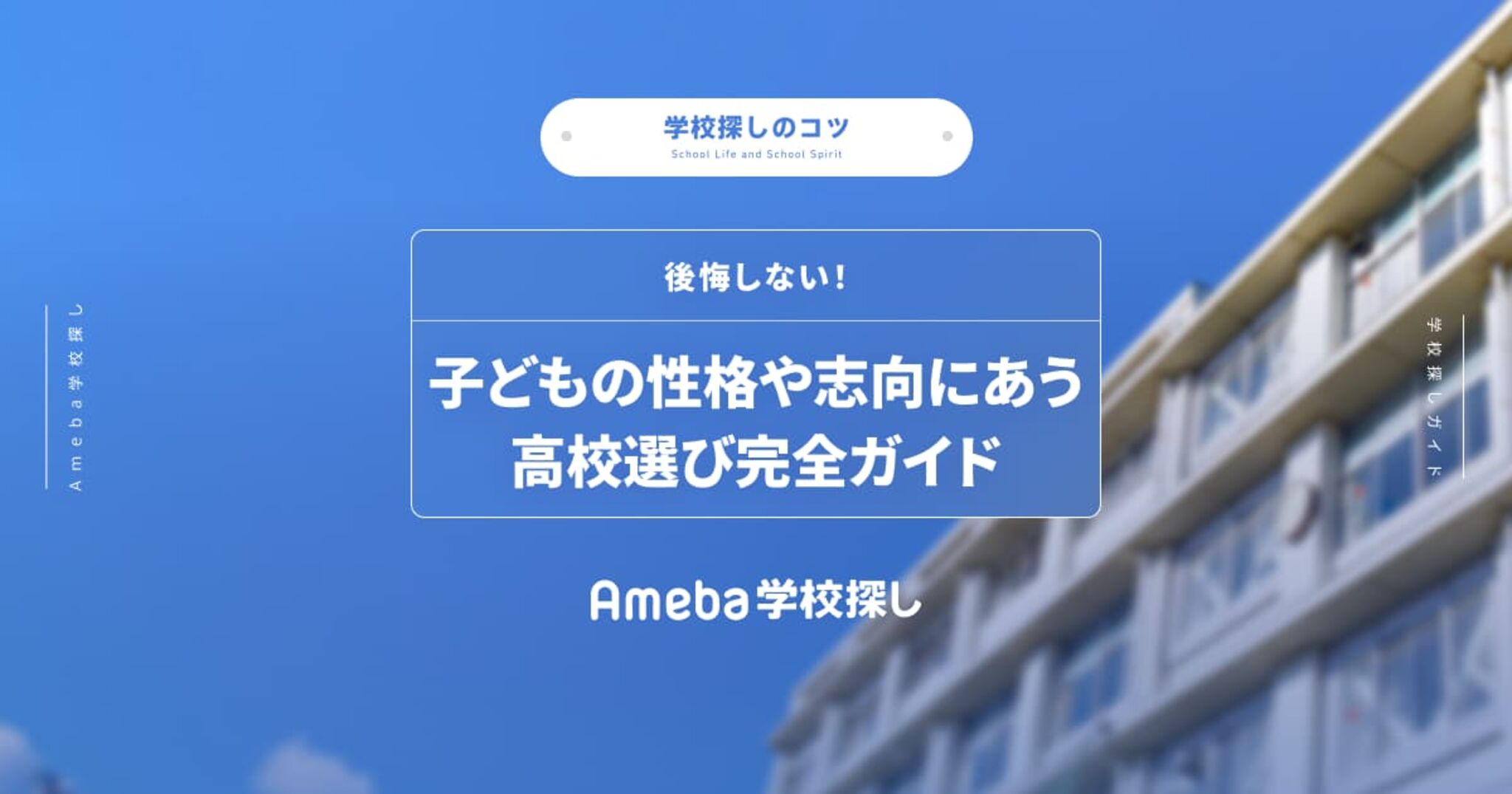近年、教育現場や大学で注目されている「リベラルアーツ」。専門的な知識だけでなく、幅広い分野の学びを通じて「自ら考え、社会で活躍できる人材」を育成することを目的としています。
しかし、「リベラルアーツ教育とは具体的に何を学ぶのか?」「日本の教育制度でどのように取り入れられているのか?」と疑問に感じる保護者も多いでしょう。
そこで本記事では、リベラルアーツの意味や特徴、お子さんの進路選びに役立つ情報を詳しく解説します。変化の激しい現代社会で求められる力や、実際に日本の大学でどのような取り組みがおこなわれているのかを知ることで、お子さんの将来を考える際の参考にしてください。
リベラルアーツとは?
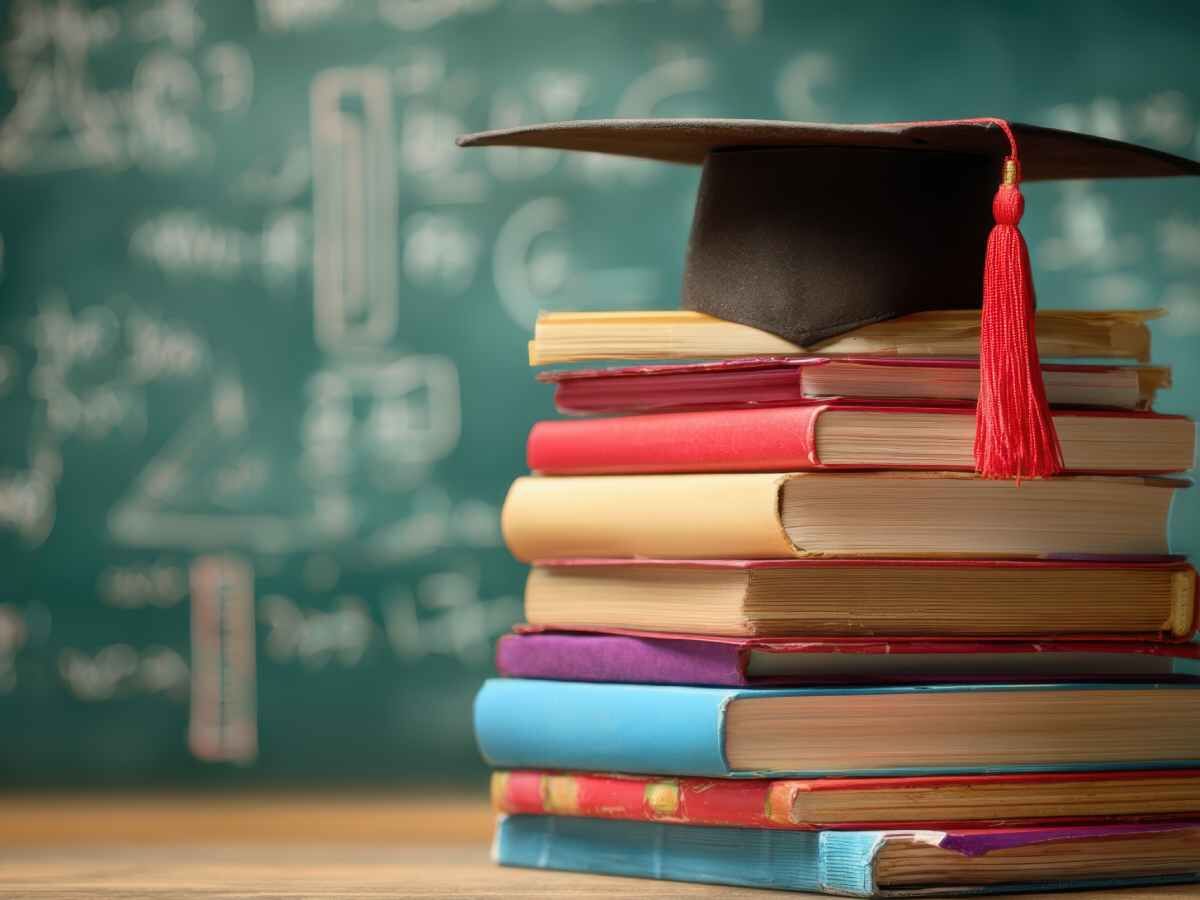
リベラルアーツ(Liberal Arts)とは、古代ギリシャ・ローマ時代にさかのぼる教育概念で、「自由人にふさわしい学問」と訳されます。
単なる知識の習得ではなく、哲学・文学・歴史・数学・自然科学など幅広い分野を学ぶことで、思考力や表現力、そして社会を多角的に理解する力を養うのが特徴です。現代では「一般教養」と呼ばれることもありますが、リベラルアーツはそれよりも深い意味を持っています。
文部科学省も「新しい時代にふさわしい教養」として、知識のみならず規範意識や倫理性、バランス感覚などを含めた包括的な人格形成の重要性を示しており、これからの社会で求められる人材育成にとって欠かせない教育となっています。
リベラルアーツの歴史的背景
リベラルアーツの起源は、古代ローマの教育制度にあります。当時の自由市民に必要とされた「自由七科」(文法・修辞・論理・算術・幾何・天文・音楽)が基礎となり、ヨーロッパ中世の大学教育にも受け継がれました。
この「自由七科」は、言語に関する3学(文法・修辞・論理)と数理に関する4科(算術・幾何・天文・音楽)で構成されています。
これらを学ぶことで、自由市民として社会で生きていくための基礎的な素養を身につけることができると考えられていたのです。中世ヨーロッパでは、これらの科目を修了した者だけが、神学・法学・医学といった専門分野に進むことが許されていました。
つまり、リベラルアーツは専門教育の土台となる重要な学習だったのです。現代でも「幅広い知識による人格形成教育」として世界中の大学で重視されています。
リベラルアーツが現代で注目される理由
AIやグローバル化が進む現代社会では、専門知識だけでは不十分です。リベラルアーツ教育は「課題解決力」や「コミュニケーション力」といった汎用的スキルを養うため、多様なキャリアで役立ちます。
文部科学省も「混迷した社会状況を乗り越え、一人ひとりが自らにふさわしい生き方を実現する」ために、新しい時代にふさわしい教養を再構築することの必要性を指摘しています。
AIや環境問題、多様性への対応など、答えのない課題に直面する現代では、「なぜそうなるのか?」「ほかにも解決方法はないか?」と多角的に考え、異なる価値観を持つ人々と協働して答えを見つけられる人材が求められています。
そのため、日本の大学でもリベラルアーツ学部や全学共通教育として導入が進んでいます。自然科学、社会科学、人文科学など幅広い分野に触れることで、自分の興味を発見したり、将来の進路選択に役立てたりすることができます。
これは中高生にとっても大きなメリットといえるでしょう。
リベラルアーツ教育の特徴
リベラルアーツ教育は、「多角的に物事を考える力」と「社会で応用できる力」を育む点が特徴です。従来の日本の教育とは異なり、ひとつの専門分野だけでなく、文系・理系の枠を超えた幅広い学習を通じて、お子さんが将来どの分野に進んでも活かせる学びを提供します。
そのため、進路選びにも大きな意味を持つ教育といえるでしょう。お子さんがこれからの変化の激しい社会で活躍するために必要な能力を身につけられるよう、リベラルアーツ教育の具体的な特徴を紹介していきます。
幅広い分野を横断的に学ぶ
リベラルアーツ教育では、文系・理系を分けず、哲学からデータサイエンスまで幅広く学びます。人文科学(文学、歴史、哲学など)、社会科学(経済学、政治学、心理学など)、自然科学(数学、物理学、生物学など)の3つの分野を横断的に学習することで、ひとつの問題に対してもさまざまな角度からアプローチできる力が養われます。
たとえば、環境問題について考える際も、科学的な知識だけでなく、歴史的な背景や経済的な影響、そして人間の価値観や行動といった多面的な視点から理解できるようになります。
これにより、お子さんが専門分野に進んだときも他分野とのつながりを理解できるため、社会課題に取り組む視点が広がります。
この横断的な学習は、現代社会で求められる「複合的な問題解決能力」を育てることにもつながります。ひとつの答えではなく、多様な解決策を考えられる柔軟な思考力は、どのような進路を選んでも役立つ力となるでしょう。
批判的思考力と表現力の育成
リベラルアーツ教育では、一方的に知識を覚えるのではなく、「なぜそうなるのか」「本当にそれで正しいのか」といった疑問を持ちながら学びます。
情報をそのまま受け入れるのではなく、分析し、評価し、自分なりの意見を組み立てる批判的思考力を養うことを重視しています。
授業では、ディスカッションやプレゼンテーションが多く取り入れられ、自分の考えを論理的に説明したり、ほかの人の意見を聞いて自分の考えを深めたりする機会が豊富にあります。
これにより、お子さんは単に知識を持っているだけでなく、その知識を使って考え、伝える力を身につけることができます。
この能力は、社会に出てからも非常に重要です。正解のない課題に向き合ったり、チームで協力して問題を解決したりする場面で、批判的思考力や表現力は大きな強みとなります。
また、さまざまな価値観を持つ人々とコミュニケーションを取る際にも、相手の立場を理解し、自分の意見を適切に伝える力は欠かせません。
将来の進路に広がりを持たせる
リベラルアーツ教育で得た力は、特定の職業に限定されることなく、どの進路にも活かせるのが大きな特徴です。
研究職やビジネスの世界はもちろん、国際機関、NPO、起業など、多様なキャリアパスに柔軟に対応できる基礎力を身につけることができます。
従来の日本の教育では、早い段階で文系・理系にわかれ、専門性を重視する傾向がありました。しかし、リベラルアーツ教育では、幅広い教養をベースに「考える力」そのものを鍛えるため、社会情勢の変化や技術の進歩に柔軟に対応できる人材を育てることができます。
お子さんにとっても、将来の選択肢を狭めることなく、自分の興味や社会の変化にあわせて進路を選択できる柔軟性を身につけられるのは大きなメリットといえるでしょう。
日本の学校教育におけるリベラルアーツ教育

日本でも近年、多くの学校がリベラルアーツ教育を導入しています。大学では専門学部として設置するところもあれば、全学共通科目として幅広く取り入れる大学もあります。また、中学・高校でも「総合的な探究の時間」を活用して、リベラルアーツ的な学びが広がりつつあります。
お子さんの進路を考える際に、どのような学校でリベラルアーツ教育が受けられるのか具体的に知っておくと、選択肢が広がります。ここでは、日本の教育現場での実際の取り組みをご紹介します。
リベラルアーツ学部を持つ大学
日本でリベラルアーツ教育を本格的に提供する代表的な大学として、国際基督教大学(ICU)が挙げられます。
ICUは日本初の4年制リベラルアーツ・カレッジとして1953年に設立され、1学部1学科制で入学後に31の専修分野から専門を選択できるシステムを採用しています。
ICUでは「文系、理系の区別なく幅広い知識を得た後に、専門性を深めることで、豊富な知識に裏打ちされた創造的な発想力を養う」ことを目指しており、多様な背景を持つ学生や教員と共に学ぶ環境が整っています。
上智大学では、国際教養学部が1949年の創設以来、日本の国際教育の先駆者として半世紀以上にわたり、幅広い教養と論理的思考力を育むリベラル・アーツ教育を英語で提供してきました。
同学部ではすべての授業が英語でおこなわれ、教員の50%以上が海外出身者という国際的な環境のもと、比較文化、国際ビジネス・経済、社会科学の3つの専門分野から選択して学ぶことができます。
そのほかにも、桜美林大学のリベラルアーツ学群では32の学問分野からメジャー(主専攻)とマイナー(副専攻)を組み合わせて学ぶことができ、玉川大学リベラルアーツ学部では2023年度から「ダブルフィールド制」を導入するなど、各大学が独自の取り組みを展開しています。
立命館大学では2025年にグローバル教養学部を新設し、オーストラリア国立大学との共同プログラムにより、4年間で2つの学位取得を可能にするなど、国際的な視野を持った人材育成にも力を入れています。
全学共通教育でのリベラルアーツ
東京大学では前期課程(1・2年次)において、文系・理系の枠を超えた教養教育を重視し、3年次から専門課程に進む制度を採用しています。京都大学でも全学共通科目として、人文・社会科学系、自然科学系など幅広い分野の科目履修が可能となっています。
とくに、東京大学の教養学部では、専門課程に進む前の前期課程で文科・理科の区別を超えた幅広い学習がおこなわれ、学生が自分の興味や適性を発見する機会が提供されています。
青山学院大学では全学共通教育システム「青山スタンダード」を導入し、5つの教養領域(キリスト教理解・人間理解・社会理解・自然理解・歴史理解)と4つの技能領域から幅広く学習できる制度を整えています。
グローバル教育との連携
多くの大学で、リベラルアーツ教育と国際教育を結びつける取り組みが広がっています。英語での授業や海外大学との交換留学を通じて、学生は「世界で活躍できる力」を身につけることができます。
ICUでは世界31カ国・地域84校の大学と協定を結び、学生が現地の学生と同じ授業で学んで単位を取得できるシステムが整っています。日英バイリンガル教育を実践し、多様な文化背景を持つ学生が共に学ぶ環境を提供しています。
中学・高校でも広がる探究学習との関係
中高一貫校や一部の公立高校では、2022年度から本格的に導入された「総合的な探究の時間」のなかにリベラルアーツの要素を取り入れる取り組みが広がっています。
立命館中学・高等学校では、STEAM(Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics)の「A」にリベラルアーツを含めた探究学習を実施し、生徒が複数の教科を横断して課題を探究する学びを展開しています。また、長岡京市との連携により、実際の地域課題に取り組む実践的な学習もおこなわれています。
実践学園中学・高等学校では「リベラルアーツ&サイエンス教育」として、大学教授を招いた模擬授業や多彩な校外学習を通じて、幅広い視野を育む教育を実践しています。
文部科学省も「総合的な探究の時間」について、「探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習をおこなうことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する」ことを目標に掲げており、これはリベラルアーツ教育の理念と非常に親和性があります。
保護者が知っておくべきポイント
リベラルアーツ教育は、将来の進路選択に大きな意味を持ちます。保護者がリベラルアーツについて正しく理解しておくことで、お子さんの志望校選びや進学の方向性を考える際に、より適切な判断ができるようになるでしょう。
リベラルアーツは「遠回り」ではない
リベラルアーツのような幅広い学びは一見遠回りに見えますが、実際は社会に出たときにもっとも役立つ力を育てる教育です。「専門性がないと就職に不利なのでは?」と心配する方がいるかもしれませんが、これは誤解です。
ICUが2022年に実施した卒業生調査の分析によると、2008年の教学改革以降の入学者において、「日英両語で学ぶ力」「世界の人々と対話できる言語運用能力」「自他に対する批判的思考力」「文章記述力以外のコミュニケーション力」などの項目で、教学改革前の入学者と比べて有意に高い修得度が認められました。
リベラルアーツで身につけた総合的な力は、むしろ将来の可能性を広げる「土台」となる教育と捉えることが大切です。とくに、変化の激しい現代社会では、ひとつの専門分野だけでは対応できない複雑な問題が増えています。
デジタル化や技術革新により職業の形も変化していくなかで、お子さんが大人になるころには新しい分野の職業が生まれている可能性もあり、未来に対応できる柔軟性と適応力を育てるのがリベラルアーツ教育の大きな価値といえます。
出典:国際基督教大学 大森佐和・エスキルドセン ロバート「卒業生調査を用いたリベラルアーツ教育の持続的効果の分析」
大学選びの視点が広がる
大学を選ぶ際、従来は「偏差値」や「就職率」を重視する傾向がありましたが、リベラルアーツ教育を理解すると「どのような学びの環境が用意されているか」「お子さんの成長にどう寄与するか」という視点を持てるようになります。
たとえば、入学時に専攻を決めずに幅広く学んでから専門分野を選択できるシステムや、少人数制でディスカッション中心の授業、文系・理系の枠を超えた学際的なカリキュラムなどは、お子さんが自分の可能性を発見し、本当に興味のある分野を見つけるのに役立ちます。
また、リベラルアーツ教育に力を入れている大学では、教員と学生の距離が近く、一人ひとりに対するきめ細かな指導が受けられることが多いです。
このような教育環境を知ることで、お子さんの性格や学習スタイルにあった大学選びができるようになり、結果的により充実した大学生活を送ることにつながるでしょう。
社会で必要とされる力を理解する
現代社会で求められているのは、単なる知識よりも「考える力」「伝える力」「協働する力」です。リベラルアーツ教育がこれらを育むことを理解しておくと、お子さんの将来への投資として教育の意義がより深く見えてきます。
文部科学省も「新しい時代にふさわしい教養」として、知識のみならず規範意識や倫理性、バランス感覚などを含めた包括的な人格形成の重要性を示しており、これからの社会で求められる人材育成にとって欠かせない教育と位置づけています。
お子さんがどのような進路を選んでも、これらの基礎的な力があることで、専門分野での学びがより深まり、社会で活躍できる幅も広がります。保護者として、長期的な視点でお子さんの教育を考えることが、将来への最良の投資となるでしょう。
リベラルアーツに関するよくある質問
ここからはリベラルアーツに関するよくある質問をまとめて紹介します。
- リベラルアーツとは、文系・理系を超えて幅広い学問を学び、人間としての教養や思考力を養う教育のことです。古代ギリシャ・ローマ時代の「自由七科」(文法・修辞・論理・算術・幾何・天文・音楽)が起源となっており、「自由人にふさわしい学問」という意味を持っています。
- リベラルアーツ教育を受けることで、将来、お子さんがどのような分野に進んでも活かせる基礎的な力を身につけることができます。具体的なメリットとしては、まず幅広い知識を持つことで、変化の激しい社会でも柔軟に対応できる適応力が身につきます。
また、論理的思考やコミュニケーション力が鍛えられるため、将来的に進路を選ぶ際の可能性も広がります。ひとつの専門分野だけでなく、複数の分野にまたがる問題を解決する力も養われるため、現代社会で求められる「総合力」を持った人材として成長できます。
さらに、入学時に専攻を決めずに幅広く学んでから専門を選択できるシステムを採用している大学も多く、お子さんが本当に興味のある分野を見つけてから深く学べるという利点もあります。
- 専門教育はひとつの分野を深く学ぶのに対し、リベラルアーツは幅広い分野を学ぶことに重きを置いています。従来の日本の大学教育では、早い段階で専門分野を決めてその分野を集中的に学ぶことが一般的でした。
一方、リベラルアーツ教育では、まず文系・理系の枠を超えた幅広い教養を身につけ、その土台の上に専門性を築いていきます。リベラルアーツで身につけた思考力や表現力は、その後専門分野を深める際の基盤としても役立ちます。
- リベラルアーツ教育は、とくに、「ひとつの分野にまだ絞れない」「幅広い知識を学んで将来を考えたい」と考えるお子さんに向いています。好奇心が旺盛で、さまざまなことに興味を持ち、多様な価値観に触れることを大切にするお子さんには理想的な教育環境といえるでしょう。
また、「決められた答え」よりも「なぜそうなるのか」を考えることを好み、ディスカッションや表現活動に積極的に取り組めるお子さんにも適しています。将来の職業がまだはっきりと決まっていなくても、じっくりと自分の興味を探求したいお子さんには、リベラルアーツ教育が持つ柔軟性が大きなメリットとなります
リベラルアーツは思考力や表現力、教養を養うことができる
お子さんの将来を考える保護者として、リベラルアーツ教育の本質を理解することで、進路選択の際によりよい判断ができるようになるでしょう。
変化の激しい現代社会では、ひとつの専門分野だけでは対応できない複雑な問題が増えています。だからこそ、幅広い教養と柔軟な思考力を身につけるリベラルアーツ教育の価値は今後も高まっていくでしょう。
文部科学省も「新しい時代にふさわしい教養」として、知識だけでなく倫理性やバランス感覚を含めた包括的な人格形成の重要性を示しており、日本の多くの大学でリベラルアーツ教育の導入が進んでいます。
もっとも大切なのは、リベラルアーツ教育が決して「遠回り」ではなく、お子さんの将来の可能性を最大限に広げる「投資」であるということです。論理的思考力、表現力、多角的な視点、そして生涯にわたって学び続ける力。これらはどのような進路を選んでも必ず役立つ、人生の基盤となる力です。
お子さんが自分らしい人生を歩んでいけるよう、リベラルアーツ教育という選択肢についても、ぜひ親子でじっくりと話し合ってみてください。
この記事の編集者
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。