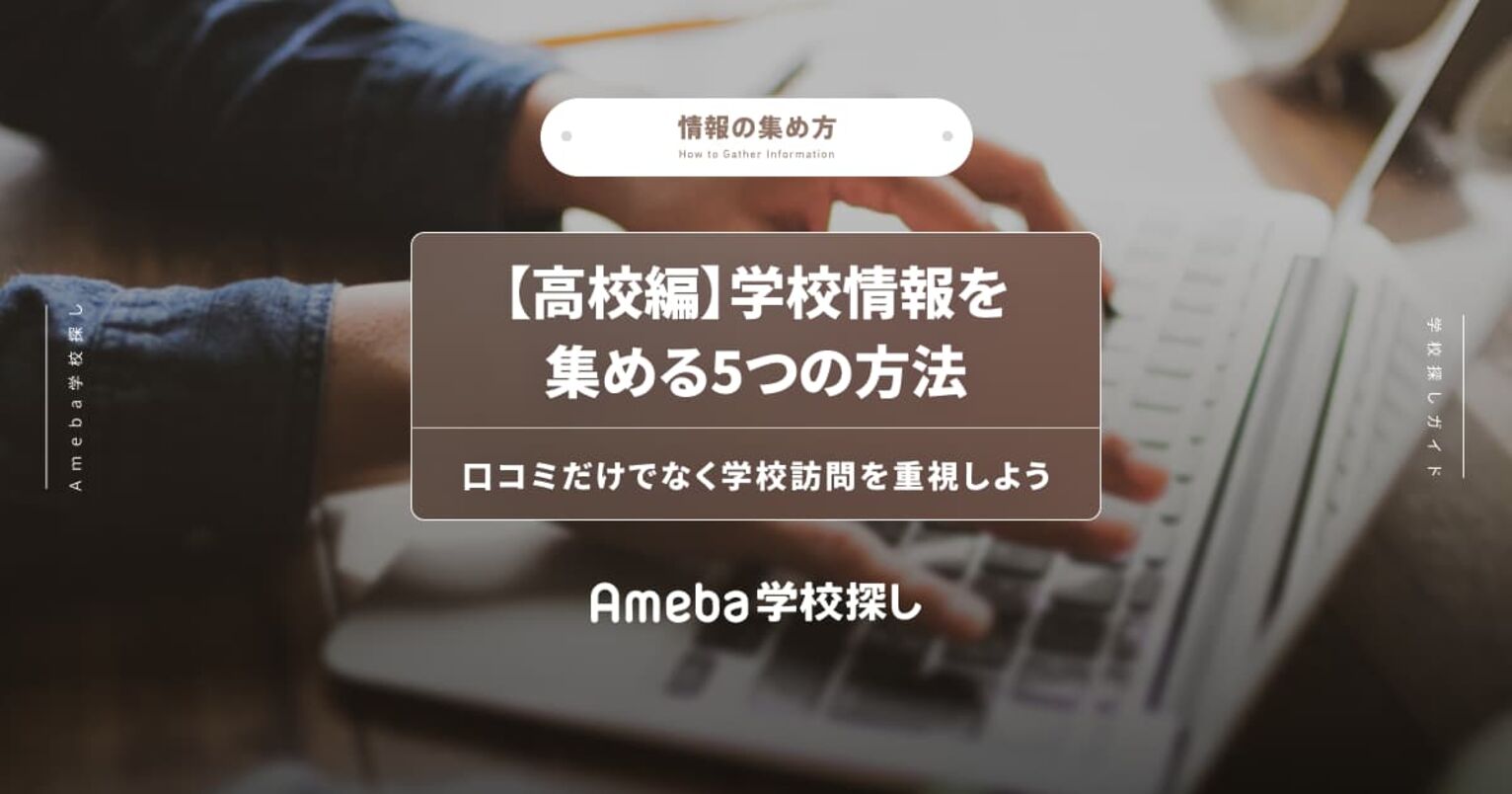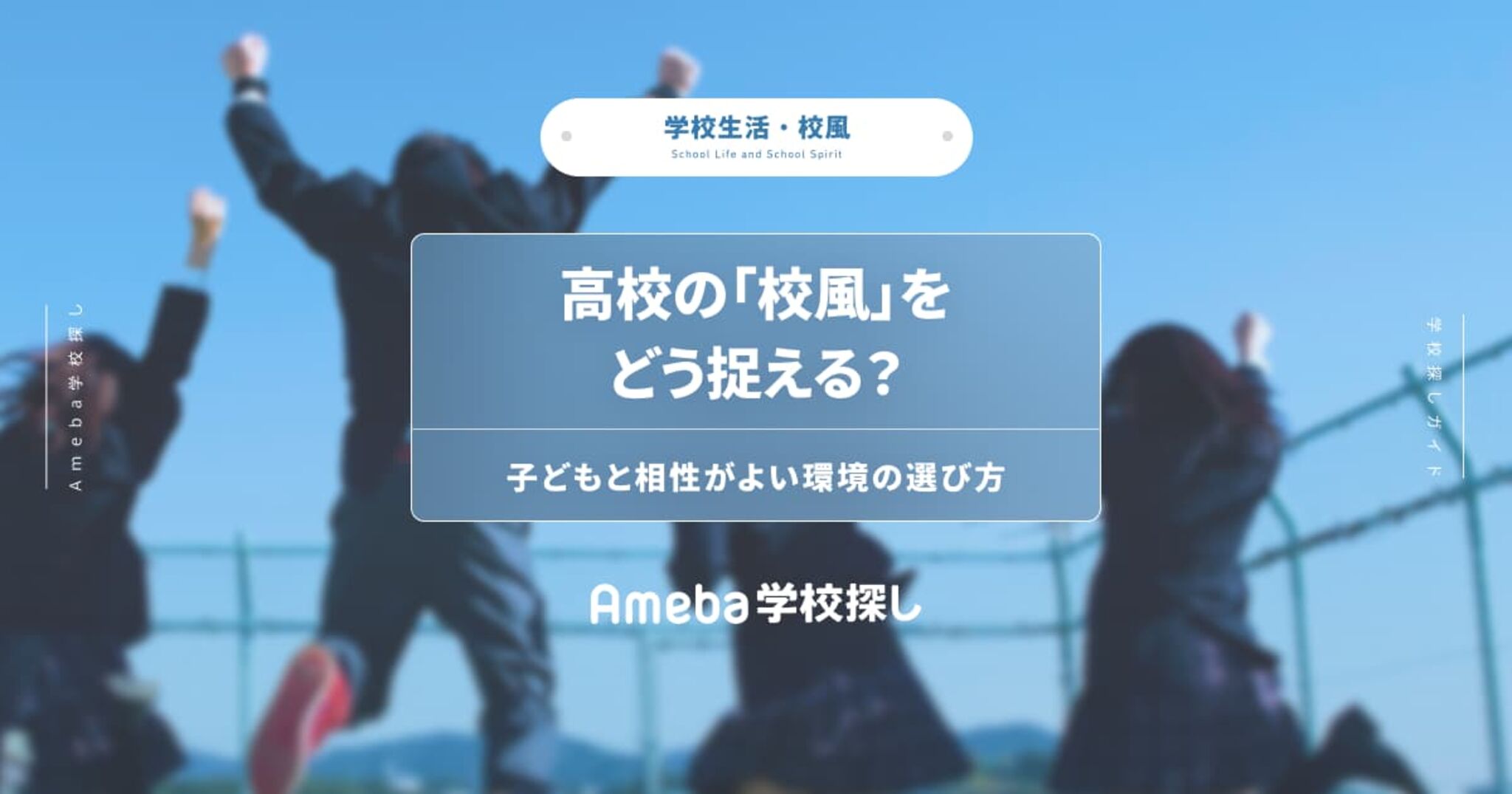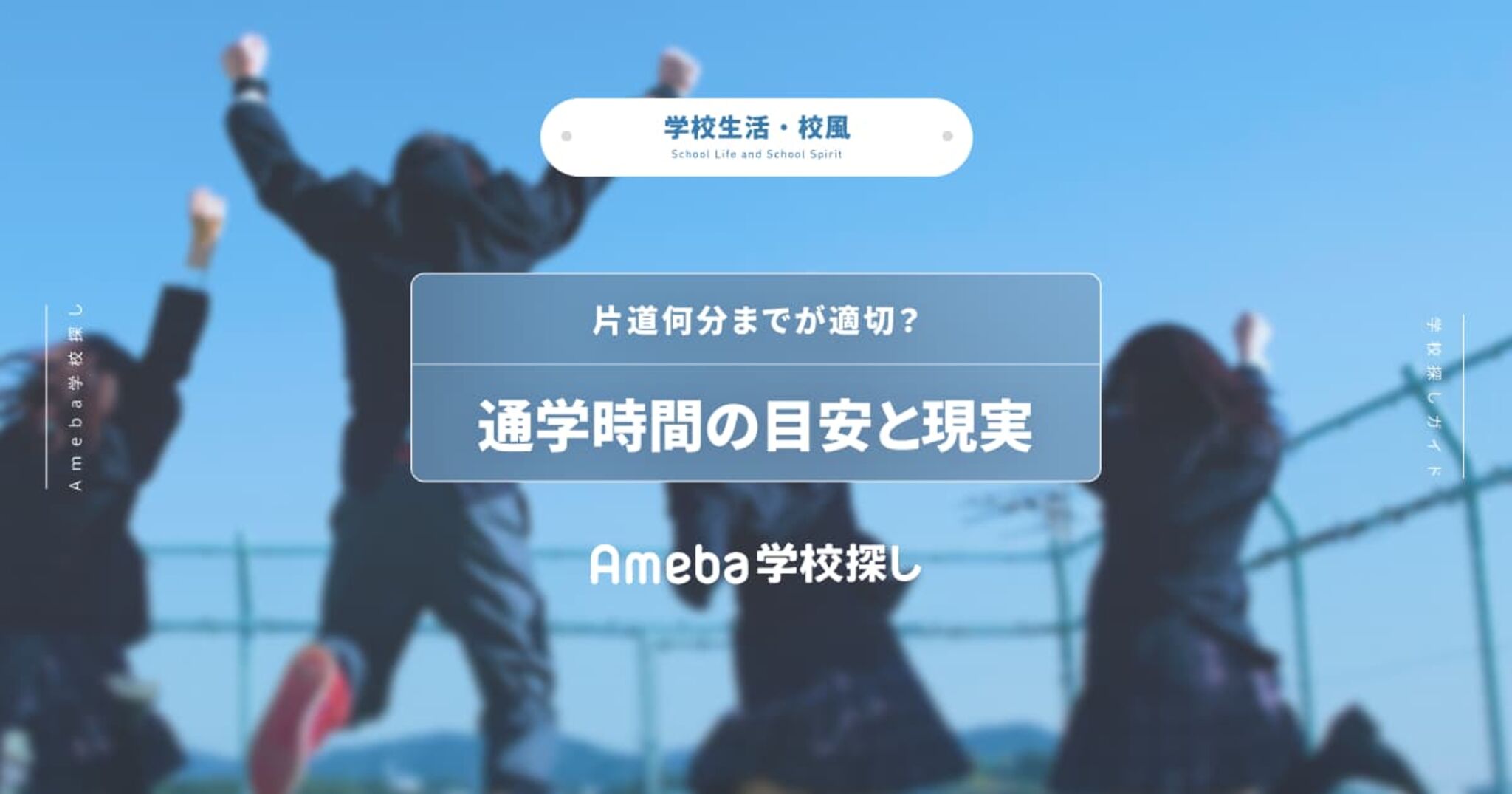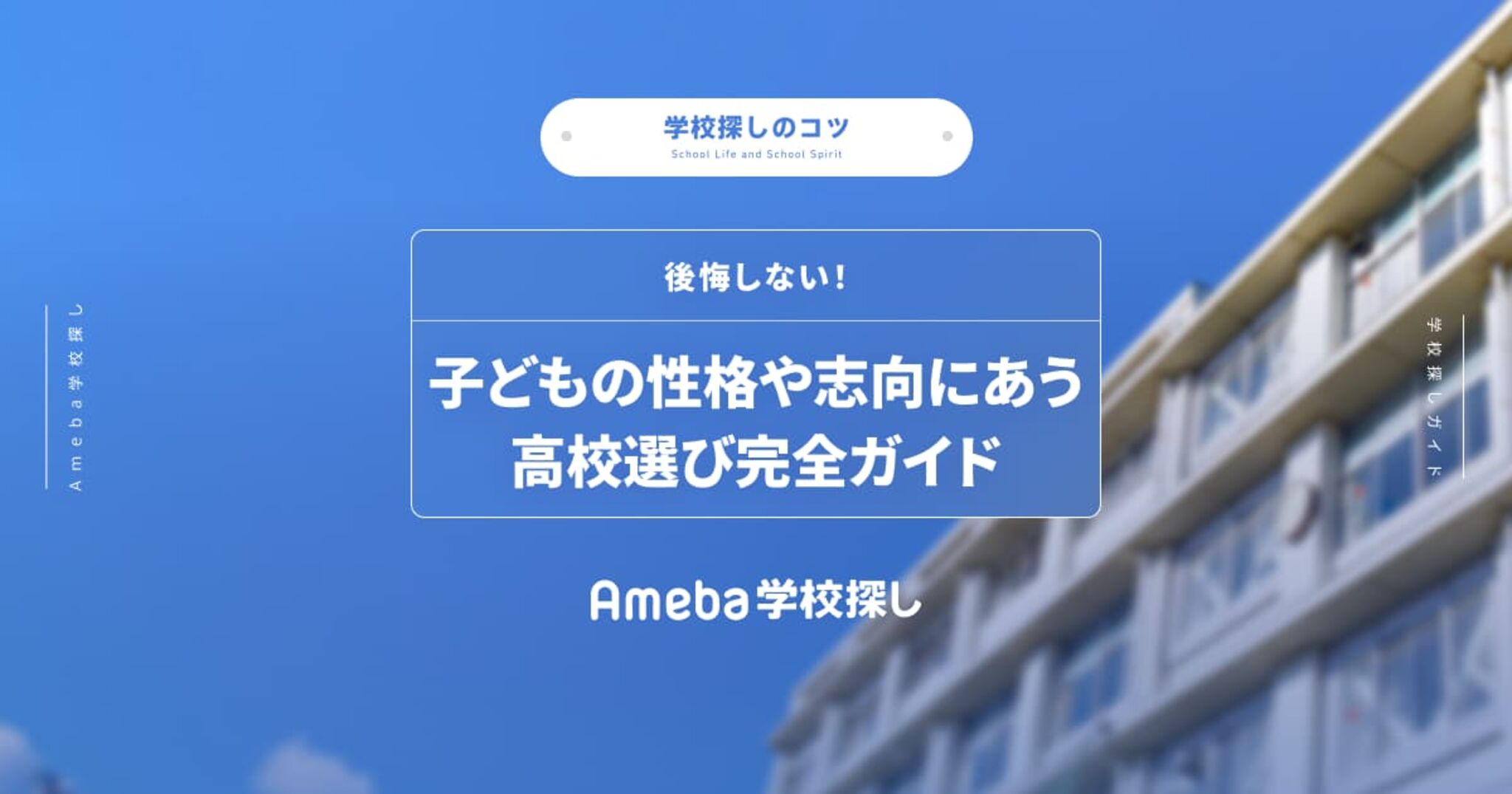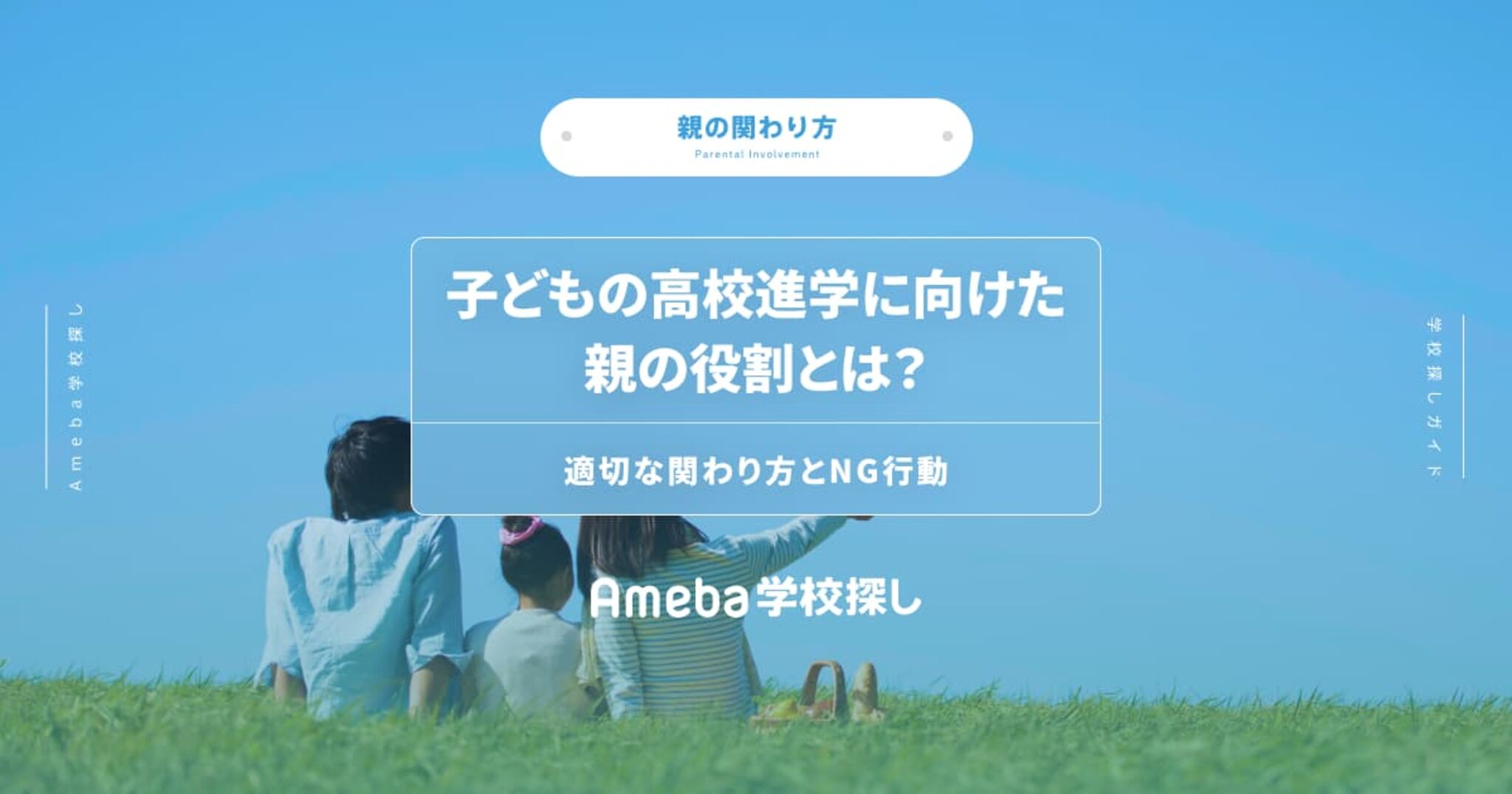高校受験における学校選びは、お子さんの将来に直結する大切な選択です。偏差値や立地だけでなく、学校の雰囲気や教育方針、通学のしやすさなど、多面的に情報を集めることが重要になります。
この記事では、保護者の方が実際に役立てやすい「学校情報の収集法」を5つに整理し、それぞれのメリット・注意点とともに詳しく解説します。口コミだけに頼らず、客観的な視点で判断するためのヒントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
学校選びで集めたい情報とは

高校選びで重要な情報は多岐にわたります。学力レベルや進学実績はもちろんですが、それ以外にも校風、教育方針、部活動の充実度、進路指導の手厚さ、施設の充実度なども大切な判断材料となります。
また、通学の利便性や安全性、学費や諸費用についても、3年間通い続けることを考えると現実的に検討しておく必要があります。
学力レベルや進学実績だけでなく校風も重要
学校によって教育方針や生徒の雰囲気は大きく異なります。同じような偏差値帯の学校でも、自由な校風を重視する学校もあれば、規律を大切にする管理型の学校もあります。
特進コースがある学校でも、部活動との両立ができるのか、自主性を重んじる環境なのか、それとも厳格な指導でサポートしてくれるのかなども重要な判断材料となります。
性格や価値観にあった環境を選び、のびのびと学校生活を送るためにも、お子さんが自ら積極的に学習に取り組めるタイプなのか、ある程度の管理があったほうが安心なのかを見極めることが大切です。
進学実績を見る際は、国公立大学や有名私立大学への合格者数だけでなく、どのような進路サポートがあるのか、推薦入試への対応はどうなのかなども確認しておきましょう。
通学・安全面・費用のリアルもチェック
自宅からの通学時間や経路、交通費、指定品の購入費用、模試・補習費なども家庭にとっては現実的な検討項目です。
通学時間が長すぎると、部活動や勉強時間に影響が出る可能性があります。一般的に片道1時間以内が理想的とされていますが、お子さんの体力や生活リズムも考慮して判断しましょう。
安全面では、最寄り駅から学校までの道のりや、帰宅時間帯の人通り、街灯の設置状況なども実際に確認しておくと安心です。
費用面では、入学金や授業料以外にも、制服代、教材費、部活動にかかる費用、修学旅行費用などを事前に把握しておくことが重要です。私立高校の場合はとくに、年間でどの程度の費用がかかるのかを詳しく確認しておきましょう。
学校情報を集める5つの方法【高校編】

効果的な情報収集のためには、複数の方法を組み合わせることが大切です。ひとつの情報源だけに頼らず、さまざまな角度から学校の実態を把握しましょう。
ここでは、保護者の方におすすめの情報収集方法について紹介します。それぞれに特徴やメリットがありますので、お子さんの志望校に応じて活用してください。
- 学校説明会・個別相談に参加する
- 学校訪問・文化祭・体育祭を見学する
- SNSや公式サイトで日々の様子をチェックする
- 卒業生・在校生・保護者の口コミを活用する
①学校説明会・個別相談に参加する
学校説明会や個別相談は、最新のカリキュラムや進路サポートの詳細を直接聞ける貴重な機会です。近年はオンライン説明会が増加し、遠方の学校の情報も得やすくなっています。
学校説明会では、校長先生や教頭先生から直接学校の教育方針を聞くことができます。また、進路指導部の先生からは具体的な進学実績や就職状況について詳しい説明を受けられるでしょう。
個別相談では、お子さんの現在の学力や志望進路について具体的に相談できます。「うちの子の成績でも大丈夫でしょうか?」「部活と勉強の両立はできますか?」など、気になることを直接質問できるのが大きなメリットです。
オンライン説明会の場合は、移動時間がかからず、複数の学校の説明会に参加しやすいという利点があります。ただし、学校の雰囲気や施設の様子は実際に訪問しないとわからない部分もあるため、可能であれば現地での説明会にも参加することをおすすめします。
なお、説明会に参加する際は、事前に質問したいことをまとめておくと効率的です。配布される資料は後で比較検討する際に役立つので、しっかりと保管しておきましょう。
②学校訪問・文化祭・体育祭を見学する
各学校の行事では、在校生の様子や教師との距離感など、「パンフレットではわからない情報」が得られます。とくに文化祭や体育祭では、学校の雰囲気や生徒の主体性を感じやすく、多くの保護者の方が重視するポイントです。
文化祭では、生徒たちがどのような取り組みをしているのか、クラスや部活動の団結力はどうなのか、先生と生徒の関係性はどうなのかを肌で感じることができます。
体育祭では、生徒たちの元気さや学校全体の活気を確認できるでしょう。応援の様子や競技への取り組み方から、学校の校風を読み取ることができます。
普段の学校見学では、授業の様子や休み時間の生徒の過ごし方、校舎や施設の状況などを詳しく見ることができるでしょう。図書館の蔵書数や自習スペースの充実度、理科実験室やパソコン室などの設備も確認しておきましょう。
見学の際は、お子さんと一緒に参加することをおすすめします。保護者の方が感じることと、お子さんが感じることは異なる場合があるからです。「この学校で3年間過ごしたい」とお子さん自身が思えるかどうかが重要になります。
③SNSや公式サイトで日々の様子をチェックする
学校のInstagramやYouTube公式チャンネルでは、日常の活動や校内行事を動画で確認できます。近年はICTを活用した情報発信を重視する学校が増えており、リアルな学校像が掴めます。
公式サイトでは、最新のお知らせや学校行事の様子、部活動の成績、進路実績などが定期的に更新されています。とくに「学校生活」や「在校生の声」といったコンテンツは、学校の日常を知るのに役立ちます。
Instagramでは、学校行事や部活動の様子が写真付きで投稿されており、生徒たちの表情や学校の雰囲気を感じ取ることができます。制服の着こなしや校内の様子なども確認できるでしょう。
また、YouTubeの学校公式チャンネルでは、学校紹介動画や授業風景、部活動の様子などが配信されています。実際に学校を訪問する前に、ある程度の雰囲気を掴んでおくことができます。
ただし、SNSや公式サイトの情報は学校側が発信するものなので、よい面が強調されている可能性があります。これらの情報を参考にしつつ、実際の学校訪問や説明会での情報と照らし合わせて判断することが大切です。
④卒業生・在校生・保護者の口コミを活用する
気になる学校をリサーチする際、実際に通っている人の声は参考になります。ただし、個人の体験談であることを踏まえ、複数の情報源とあわせて判断しましょう。
卒業生からは、実際に3年間通ってみての感想や、進路実現に向けてどのようなサポートを受けたのか、学校生活でよかった点や改善してほしい点などを聞くことができます。
在校生の保護者の方からは、入学後の様子や、保護者会の雰囲気、学校からの連絡体制、実際の費用面などを聞けるでしょう。
口コミサイトやSNSでの情報も参考になりますが、匿名の情報については信頼性を慎重に判断する必要があります。極端によい評価や悪い評価だけでなく、バランスの取れた意見を重視しましょう。
また、地域の保護者ネットワークや、中学校の先輩保護者の方からの情報も貴重です。同じ地域から通学している先輩の体験談は、通学面での参考にもなります。
⑤塾や教育関係者から第三者的な意見を聞く
塾講師や進路指導の専門家は、複数の学校に通う生徒を見ているため、比較・分析が得意です。とくに模試後の面談などで学校との相性や合格可能性を確認するのに有効です。
塾の先生は、お子さんの学習状況や性格を把握した上で、適切な学校を提案してくれます。「この子にはこういう環境が向いている」という客観的なアドバイスをもらえるでしょう。
進路指導の経験豊富な先生からは、各学校の教育方針の違いや、大学進学に向けた取り組みの特色などを詳しく聞くことができます。
もちろん、中学校の進路指導の先生も重要な相談相手です。これまでの進路実績や、お子さんの成績を踏まえた適切な志望校選びについてアドバイスをもらえるため、個人面談などで相談するようにしましょう。
ただし、塾や教育関係者の意見も、あくまで参考のひとつとして捉えることが大切です。最終的には、お子さんと保護者の方が納得できる選択をすることが重要です。
集めた情報はどのように活用する?
各学校の情報を集めても、それを適切に整理・活用しなければ意味がありません。ここからは、収集した情報をもとに、お子さんにとって最適な学校選びをするためのポイントを紹介します。
情報の整理方法や、家族での話し合いの進め方について具体的に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
家庭の方針・子どもの性格と照らし合わせて整理する
まず、お子さんの性格や学習スタイルを改めて整理してみてください。自分で計画を立てて学習を進められるタイプなのか、ある程度の指導やサポートがあったほうが力を発揮できるタイプなのかを見極めることが重要です。
その上で家庭の教育方針についても話し合っておきましょう。「のびのびと自分らしさを大切にしてほしい」「しっかりとした規律のなかで成長してほしい」「将来の進路を重視したい」など、家庭によって重視するポイントは異なります。
収集した学校情報を、これらの観点から整理してみてください。学校の特色とお子さんの特性、家庭の方針がマッチしているかどうかを客観的に判断することが大切です。
また、お子さんの将来の夢や興味のある分野についても考慮しましょう。文系・理系の選択、芸術系やスポーツ系への進路希望、将来就きたい職業などを踏まえて、それに適した教育環境を提供している学校を選ぶことが重要です。
オープンな会話で子どもの気持ちを引き出す
保護者の期待を一方的に押しつけるのではなく、お子さんの言葉を受け止めながら、一緒に情報を見て話し合うことが進路選びの第一歩です。
お子さんとの話し合いでは、まず「どんな高校生活を送りたいか」を聞いてみましょう。勉強に集中したいのか、部活動も頑張りたいのか、友だちとの時間を大切にしたいのかなど、お子さんなりの希望があるはずです。
学校見学や説明会に参加した後は、お子さんの率直な感想を聞いてみてください。「どんなところがよいと思った?」「気になることはある?」など、オープンな質問を投げかけることで、お子さんの本音を引き出すことができます。
保護者の方が感じた学校の印象と、お子さんが感じた印象を比較してみることも大切です。同じ学校を見ても、感じ方は人それぞれ異なります。その違いについて話し合うことで、より深い理解につながるでしょう。
プレッシャーを与えすぎないよう注意しながら、お子さんが自分の意見を安心して話せる雰囲気をつくることを心がけてください。「間違った選択をしたらどうしよう」という不安を抱えているお子さんも多いので、「一緒に考えよう」という姿勢で接することが大切です。
情報を多角的に集め、納得のいく高校選びを

高校受験は、お子さんの将来を大きく左右する重要な分岐点です。偏差値だけにとらわれず、校風・教育方針・部活動・進路実績・通学時間など、さまざまな観点から学校を比較検討することが求められます。
情報収集では、学校の公式サイトやパンフレットに加え、口コミ・説明会・学校訪問・卒業生の声・SNSや動画サイトでの発信など、保護者や生徒自身がリアルな視点で得られる情報源をバランスよく活用することがポイントです。
とくに近年は、学校の発信力や広報の工夫が進み、InstagramやYouTubeを活用した動画説明、体験授業や「オンライン個別相談」など、直接足を運ばなくても雰囲気を知る手段が増えています。これらのツールを上手に活用することで、効率的に情報収集をおこなうことができるでしょう。
ただし、オンラインでの情報収集だけでは限界があります。可能な限り実際に学校を訪問し、子ども自身の目で見て、肌で感じることが大切です。パンフレットや動画では伝わらない、生徒たちの表情や校内の空気感、先生の人柄などを直接確認することで、より確信をもって学校選びができるでしょう。
もっとも大切なのは、「子どもにあう学校かどうか」という保護者の視点だけでなく、お子さん本人の目で見て、感じることです。3年間という大切な時期を過ごす場所だからこそ、お子さんが「この学校で頑張りたい」と心から思える環境を選ぶことが何より重要です。
ぜひ、親子でじっくりと情報を集めながら、お子さんの個性や将来の目標にもっとも適した学校を見つけて、納得のいく進路選択を進めていってください。
- 中山 朋子
Ameba学校探し 編集者
幼少期からピアノ、書道、そろばん、テニス、英会話、塾と習い事の日々を送る。地方の高校から都内の大学に進学し、卒業後は出版社に勤務。ワーキングホリデーを利用して渡仏後、ILPGAに進学し、Phonétiqueについて学ぶ。帰国後は広告代理店勤務を経て、再びメディア業界に。高校受験を控える子を持つ親として、「Ameba学校探し」では保護者目線の有益な情報をお届けする記事づくりを目指しています。